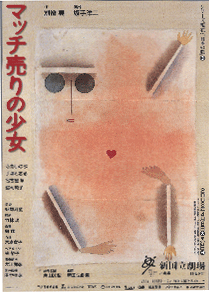
|
題名: |
マッチ売りの少女 |
|
観劇日: |
03/4/11 |
|
劇場: |
新国立劇場 |
|
主催: |
新国立劇場 |
|
期間: |
2003年4月8日〜27日 |
|
作: |
別役実 |
|
演出: |
坂手洋二 |
|
美術: |
妹尾河童 |
|
照明: |
竹林功 |
|
衣装: |
宮本宣子 |
|
音楽・音響: |
島猛 |
|
出演者: |
寺島しのぶ
手塚とおる 猪熊恒和 富司純子 早船聡 |
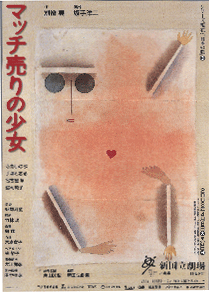

「マッチ売りの少女」
劇場に入ると正面の背景に昔の木造民家が二軒ならんで建っている。(図参照)その前に客席があり、矩形の台である舞台をはさんで、もう一つの客席がある。長い左右の壁には民家の延長のように昔風の家屋がはりついていて、劇場全体が、日本がまだ貧しかったころのなつかしい風情がただよう下町というしつらえである。両わきには電柱が立っていて、一条の光のなかを、しきりに小雪が降りてくる。観客である僕らはその街並にすっぽりと包まれたような気にさせられる。
僕は、入り口でこの情景を見た途端に少したじろいだ。その理由は後にしよう。
開幕を待っている間、壁の家の前を何度か拍子木をたたいて「火の用心」を告げる夜回りがとおった。僕らにも何かに用心しろというばかりに。
この戯曲は、「大みそかの寒い夜」という設定以外に、いつともどこともいっていない。とすれば、坂手洋二は、今回この芝居を取り上げるに当たって、背景をおそらく初演のころ、つまり六十年代の日本の街においていると考えられる。
その初演の時につくられたパンフレットに坂手洋二はこだわっている。そこにはこう書かれていた。
「その頃、人々は飢えていた。毎日毎日がくらい夜であった。街は、沼沢地の上に生臭く広がり、ところどころ、ハジケタおできのように、市場が開かれた。物陰でいくつかの小さなものが殺され、ひそかに食べられた。人々は忘れられた犯罪者のように歩き、時に思いがけなく、何かスバシコイものが闇をくぐり抜けて走ったりした。(略)
と、そんな時代からいまは、どれほど遠いのだろうか?本当にそれは、遠い昔の語りぐさになったのだろうか?・・・」(公演パンフレットより)
このテキストは、終幕近くナレーションとして読み上げられるが、戯曲にはなかったものを坂手がわざわざ挿入したのは、観客に語るべき何かを含んでいると考えたからだろう。この現代詩の響きを持つみごとな広告コピーは別役実が書いたものか、当時の演出、鈴木忠志の手になるものか知らないが、これは戦争の惨禍と戦争による飢餓の陰喩ではないかと思われる。もちろん他の解釈も成立するだろうが、何か陰惨な時代があってそれを忘れようとしているものあるいはその記憶が薄れていくことに警鐘を鳴らしていることはほぼ確実である。
しかし、この芝居には直接的にそれらを示唆するような言葉も会話もでてこない。ではなぜ坂手洋二は、劇場全体を四十年前に引き戻すという大掛かりな背景をつくり、その中で起こる出来事として、この芝居をやろうとしたのだろうか?
その前に、どういう話なのか、そしてどのように演じられたのかを知っていただく必要があろう。とりあえず舞台上で展開する話は以下のようなものである。
ある年の大みそか、雪の舞う寒い夜に、初老の夫婦が「お茶にしよう」とテーブルに道具をそろえているところへ「市役所の方から」やって来たという若い女が訪ねてくる。
女は、この夫婦の娘だと告げる。そしてかつて自分は「マッチ売り」をしていたという。マッチが燃えているつかの間、男達にスカートの中を見せる「マッチ売り」である。
女は七歳の少女にそれを教えたのは誰か知りたいというのである。
夫婦に娘はいたが、子供のころ電車に引かれて死んでしまった。しかし、女は娘であると言い張る。初老の男は、女が娘と主張するのに抗しきれず、「いやそうかもしれない、そうだ、あなたは私の娘だ。」この場が治まるのなら、いたしかたがないと肯定してしまう。
すると今度は外で弟が待っているという。弟などいるはずが無いが、寒い外に放っておくわけにもいかず家の中に招じ入れる。この弟は父親にせっかんされ続けたといって、身体は痣だらけの上に、片腕が曲がってしまっている。まともに見られない夫婦は、ビスケットを与え、とりあえず弟と認める。その上で何をして欲しいのかとたずねるが、「私たちは、あなたの娘と息子なのです。」と繰り返すばかりである。
埒が明かないと見て、夫婦は帰ってもらおうとする。その時疲れたのか姉はテーブルに突っ伏して寝ている。「もっといただいていいですか?」という弟にビスケットをやって、もう遅いから今夜は泊まってもらおうと言い出したとき、突然女が起きて、弟はビスケットを食べ過ぎたと怒りだす。
「お父様とお母様にごめんなさいといいなさい。さあ、お詫びをするのです。お前のしたことで、私がどんなに恥ずかしい思いをしたか、分かりますか?・・・」謝りなさい、謝りなさいといいながら、女は弟を引きずり倒し激しく打擲する。「お前の食べたビスケットは誰の分だったのです。お前のために今夜誰が飢えなくてはいけないのです。」
男は「やめなさい。・・・あんなもの、いっぱいあるのです。」といって止める。すると、女は急に態度を変え「許してください、お母様。私はいけないことをしました。許して下さい。・・・許して、お父様。許して下さい。マッチを、マッチをすらないで・・・」とすがる。何がどうなっているか夫婦は呆然と見ているだけである。弟は女を抱いて「お姉さまに触らないで下さい。お姉さまは卑しい女です。だからお姉さまは触られたくないのです。」といい、そして、つぶやく。
「お父様はマッチをお買いになった。お父様はマッチをお買いになった。毎夜毎夜。お姉さまのために・・・。毎夜毎夜お姉さまのために・・・。」「でも、僕は責めません。でもどうしても、僕は責めるわけにいきません。お姉さまがおっしゃったからです。責めてはいけない。責めてはいけません。・・・」
そして、童話「マッチ売りの少女」の最後のシーンが読み上げられる。
「お母様は少女を腕に抱きかかえ、光と喜びに包まれて、高く高く上っていきました。そこにはもう、寒いことも、おなかのすくことも、こわいこともありません。二人は神様のみもとに召されたのです。」
場面は既に朝、初老の男と妻は、朝のお茶の準備をしている。
「新しい年の朝が、小さな亡きがらの上に上りました。その亡きがらは、ほとんど燃えつくした一束のマッチを持っておりました。人々は言いました。この子は、暖まろうとしたんだね。そうです、この子は、とても寒かったのです。」
この女は、寺島しのぶが演じた。弟は手塚とおる。これが適役だった。妹尾河童の作った矩形の台の外に手塚が立ったとき、一瞬異形と思ったのは曲がった片腕のせいではない。その雰囲気であった。実在と非実在の中間あるいは現実と彼岸の交錯する場に屹立するものとでもいえばいいのか、そういう両義的でしかも確固たる存在感を作りだしていた。別役の芝居ではこういう人物がしばしば登場するが、演じるほうは加減が難しい。
寺島しのぶもまた、この加減に苦労したふしがあって、弟を打擲する場面での豹変は、誰もが驚いて、しかも心を揺さぶられるシーンになったが、前半の娘だと言い張るところでは、この人の地なのか少し誠実さが出過ぎてしまった。父親に迫るでもなく、緊張感を秘めて、淡々と本当のところを追求するというある種の軽さが欲しかった。もっとも演出の坂手洋二の要求だったのなら仕方ないが。
富司純子の妻は、あまり期待していなかったが、明りが入って、テーブルの脇にたっているのを見て、あっと思った。よほど稽古をしたと見えて、しっかりと初老の男の妻を演じていた。静かなお茶の時間を楽しめる夫婦の典型的な妻を、いやみなく演じきるのはむづかしいものだが、この妻役は舞台の経験が少ないはずなのにかなり高い水準で成功していたと思う。(もちろん僕らが通ったあの「緋牡丹博徒」の面影などみじんもない。)
初老の男は、名古屋章の予定だったが、病気で倒れたことは知っていた。それが近石真介になり、猪熊恒和に落ち着いた背景には、近石真介と演出の坂手洋二の間に演技をめぐる見解の相違があったという、うわさをWebのなかに見つけた。
本当だとすれば珍しいことである。うわさをしていた人は匿名で誰だかわからないが、いっそ、初老の男を菊五郎が、弟役を菊之助がやったらよかったのではないかとからかっていた。 そういわれれば、そもそも寺島しのぶと富司純子の母子というキャスティングも妙なものである。意図的にやったとしてもその意味はまったくわからないが。
それはともかく、猪熊恒和の初老の男を見れば、坂手洋二が何をもくろんでいたか推量できる。坂手はおそらく大きな演技をして欲しくなかったのであろう。初老の男は、娘だと言い張られて、その場を取り繕うために妥協をした。さらに弟の存在も意に反して認めることになった。これはすべて自分の穏やかな暮らしを守るためにしたことである。逆に言えば、理不尽な主張をあいまいな形で受け入れる普通の夫婦とは、善意の人であり、親切の人である。だが、実際にこんなことはあり得ない。夫婦の態度もまた虚構だということは、開幕のシーンでさまざまの置物をルールにしたがってならべ、儀式めいて行われる「お茶の時間」に表れている。それは。虚空の中に浮かぶ寓話のような時間であり夫婦であり生活なのだ。だから、初老の男をあまりリアルに演じるのは、この虚空と寓話性という二重構造を壊すことになる。
しかし、徹底的にリアルにする方法もある。父親と娘を対峙させるやりかたである。夜中の闖入者と戦っているうちに、虚実がわからなくなって、夫婦の日常性が危機に瀕するという演出もありうるのではないか。名古屋章も近石真介もだまっていたら、後者を選択するような気がする。
猪熊恒和の初老の男は、台詞の抑揚を抑え、精神の高揚もなく淡々と演じた。女の主張にもあまり抵抗を示さず、その場をしのぐような気の弱さと、時折見せる怒りで存在感の薄い小市民を見せた。巡り巡ってきた役柄だけに、ノリがわるいというのも気の毒なことだが、僕にはこの初老の男ははじめから不満があった。富司純子のリアルな演技の水準とかみあっていなかったというのがひとつである。もう一つは稽古不足だったのか、この男に存在しなければならない理不尽なものに対する抵抗、その内的な緊張感が感じられなかったという点である。坂手洋二がこれを許したとすれば、問題だと僕は思う。
僕がいった「リアルにする方法」をいったん通過したうえで、坂手が考えたような、たかぶりを押さえた演技に引き戻すという作業があれば、内的充実が生まれ、猪熊恒和への不満は解消されたかもしれないし、むしろ近石真介でやれたような気がする。
この虚空に展開される寓話という構造は、舞台装置にも仕掛けられていて、テーブルの置かれている台に描かれた白と黒の同心円は椅子と卓がのっている中心が回り、さらにその外側がドーナツ状に独立していて、回転するようになっている。テーブルは微妙なスピードで回転して、四方から見ている観客の視点を気づかないうちに変化させる。そして、ドーナツ状の外側の円と組み合わせて、人間の移動あるいは距離のリアリティを消してしまうということをやるのだ。
このあたりはなかなかみせるのだが、背景になっている非常にリアルな家や家並には疑問を感じた。最初に、「入り口でこの情景を見た途端に少したじろいだ。」と書いたが、そのことである。それは、この芝居を上演する今日的な意味という、演出上の根幹にかかわる問題で、長くなるが、その点について言及したいと思う。
公演パンフレットに寄せた別役と清水邦夫の作品タイトルに関する面白いエッセーの中で大笹吉雄が書いている。
「これは、はやくに別役実の『戦後論』だと理解されていた。ここに登場する飢えた姉弟と少女の無残な生き方は、間違いなく戦後の子供の「記憶」に他ならないからである。が単にそれだけにとどまらず、もうひとまわり大きな『日本論』であり『日本人論』だということをかつて指摘したことがある。(80年、拙稿「マッチ売りの少女と『天皇』」)。この考えは今も変わらないが・・・」
この文脈から、天皇と関係付けられた「日本人論」についてある程度類推できるが、、ここでそれを確かめておきたい。80年に書かれた大笹のエセーから引用する。
ビスケットを食べ過ぎた弟を「そのためにだれかが飢えることになる」と打擲する女に向かって「やめなさい。・・・あんなもの、いっぱいあるのです。」というのを男の無責任なやさしさだと指摘して、
「作者はこういう「やさしさ」を、ここでは実にさりげなく、しかも深いところから告発しているといってよく、マッチ売りの少女の「寒さ」は、いわば情況的なのである。我々は果てしなく責任を避ける柔構造の中にあり、それを作者は家族の関係を介して示した。重要なのはこの点である。
我々は長く天皇を親とする家族関係の中にあったが、そこから生まれる生あたたかさとやさしさが、責任をとらない「親」の属性であるとすれば、ここに描かれた関係は、丸山真男的な意味における「天皇制」に他ならない。
責任を回避するかぎり、あらゆる関係ははっきりせず、変化もまたない。一夜開ければ、男と妻がいつものように、まるで何事もなかったごとく、朝のお茶を飲む所以である。」
大笹がこれを書いたのは初演から十四年後の昭和五十五年のことである。そしていまでもその考えにかわりはないという。
また別の見方もある。別役実は、一時期共産党の早稲田における重要な細胞であった自由舞台の政治的なリーダーをやっていた。六十年安保の前後、組織としての左翼に属していたことになる。この戯曲が書かれたのは、池田勇人が所得倍増を唱えて、日本が高度成長の入口にさしかかっていたころで、市民の生活は豊になりつつあり、それにつれて革命への道は遠ざかっていくように見えていた。社会の変革にとって、その生ぬるい湯に浸かったような日常性を打破して、豊かさの裏にある矛盾をあらわに、見せなければならない。その焦りのようなものが当時の知識人の心情にあったとと思う。(その延長上に七十年安保がある)「マッチ売りの少女」は日本人論の前に、変革への意志が経済的豊かさにからめとられようとしている時代の中で生まれたのであり、少なくとも別役実の中に、作品を通してそういう「情況」を、「惰性態としての日常性」として告発しようという意図はあったと思う。
今回坂手洋二が背景として考えた時代設定が初演当時のものとすれば、日常性を撃つという意図はもちろん、大笹の戦後論にしたがえば、この姉弟は、戦後上野の地下道にいた戦災孤児などのイメージに重なるという意味の指摘は有効であろう。そこから日本論、日本人論、天皇制という議論も至近距離にある。
しかし、ここからが僕の疑問なのだが、四十年近くたった今、この芝居を観て、僕らはまだ戦後論も天皇もわかるが、若い観客は、いうところの「その頃、人々は飢えていた。毎日毎日がくらい夜であった。・・・と、そんな時代からいまは、どれほど遠いのだろうか?本当にそれは、遠い昔の語りぐさになったのだろうか?・・・」という問いかけに、どうこたえればいいのか?丸山真男的な「天皇」の無責任の連鎖がわれわれのDNAに組み込まれているといわれても、この時代にどこを探せばその根拠が見つかるのか?
別役実は坂手洋二との対談(講演パンフレット)でこう発言している。
「いま僕がいちばんやりにくいのはね、八十年代くらいまでは、それぞれの時代があるテーマを持っていたのだけれど、それが無くなってしまったこと。時代の問題点についての共有感覚みたいなのがあって、その中で芝居が観客の琴線に触れて、ある振動を作り上げることが出来た。・・・ところが八十年代以降、時代が持つテーマがほとんど見えない。今回のイラク戦争もそう。六十年安保反対の時のように我々が肌で感じた「うねり」のような意味での時代性があるかというと、「イラク戦争反対」からは感じないわけね。」
これに対して坂手洋二も同意している。
別役の発言は、いたいほど分かるし同感でもある。しかし、これを違う角度で見れば、我々が戦後一貫して考え議論してきた方法論で世界を了解することがいつの間にかできなくなった、そういうことであろう。
それは八十年代の終わりに何があったのかを考えてみれば見えてくる。ひとつは昭和天皇がなくなったことである。もう一つは、ベルリンの壁が壊れ、ソ連が崩壊したことである。我々は、「天皇」と「革命」の二つをほぼ同じ時期に失ったのである。
いま大笹吉雄が、八十年に書いた「マッチ売りの少女」と天皇に関するエセーの有効性を言うのはかまわない。文学としての戯曲を研究する立場では間違っていないのだから。
しかし、今日上演される「マッチ売りの少女」を見る若い観客に、このような説明が果たして通じるだろうか?日常性の中に潜む虚偽や矛盾をあらわにすることが社会の構造変革や何かの意味のあることだと主張できるだろうか?
僕はそれはほとんど絶望的に無理だと考えていた。
だから、「少年H」の妹尾河童がもっとも得意そうな、古い時代のなつかしい日本家屋の背景をみたとき、直感的に違和感を覚えたのであった。もはやあの時代に引きずり込むことは不可能だ、これでは何も新しいことは始まらないじゃないか・・・そういう思いが実は劇場の入り口で、僕をたじろがせた。
坂手洋二は、「いやこういう時代もあったのだ」ということを見せようとしたのだろうか?いや、はっきりと言おう。坂手は、戦後論も天皇論もわかっていて、そのような論理にしたがって、つまり「マッチ売りの少女」を焼け跡闇市の片隅にしゃがんでいた戦災孤児とみたてて、そういう時代の背景の前で、物語を作ろうとしたのである。それならそれでよい。
しかし、この企画が目的にしていたものはどうなるのだ。
「このシリーズが、というよりは現代演劇の再演という試み自体が初演当時の時代背景や戯曲のテーマを検証することではない。今日的な視点で新しい息吹を戯曲に吹き込むことで、戯曲が再生し、舞台は同時代的な意味を持つ。と同時に60年代演劇の読み直しで世代の橋渡しという役割を持つ。」(新国立劇場のシリーズ企画)
この戯曲は、最初にいったように、何時とも何処とも設定していない。大みそかの夜に初老の男夫婦の家に見知らぬ女が訪ねてくるという話である。不条理に違いないがいたってニュートラルな物語である。「今日的な視点で新しい息吹を戯曲に吹き込むこと」は可能ではないか?大笹の言い方を借りると、「マッチ売りの少女」に戦後論や天皇という補助線を当ててみなくても、見えてくる何かがありそうなものだ。
矩形の台にいくすじもの同心円が描かれた舞台はモダンであり抽象的でシンプルである。台詞は不条理とも形而上的ともとれる。だが、背景にはまるで臍帯でつながっているようにあの時代の風景が常に見えていて、そこへ回帰せよとせまるのである。
ここでいう「今日的な視点」といっているものを取り戻すためには、八十年代をすぎて時代はどういう様相を示しているのか、そこにある大きな断層も含めて、ここらで冷静に考えてみる必要がある。。
(2003.4.16)
