

|
題名: |
AMERIKA |
|
観劇日: |
03/3/7 |
|
劇場: |
シアタートラム |
|
主催: |
MODE+世田谷パブリックシアター |
|
期間: |
2003年3月1日〜16日 |
|
作: |
フランツ・カフカ |
|
翻訳: |
{翻案・構成}松本 修(振付) 井手茂太 |
|
演出: |
松本 修 |
|
美術: |
伊藤雅子 |
|
照明: |
斉藤茂男 |
|
衣装: |
半田悦子 |
|
音楽: |
市来邦比古 |
|
出演者: |
井口千寿留
石井ひとみ 石村実伽 占部房子 大崎由利子 来栖礼子 小崎有里衣 佐藤沙恵 裕木奈江 石母田史朗 笠木誠 粕谷吉洋
小嶋尚樹 斎藤歩 佐藤淳 高田恵篤 得丸伸二 福士惠ニ 星野貴紀 宮島健 |
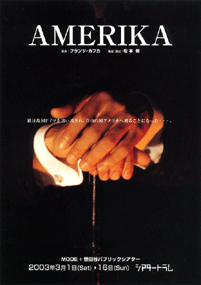
「AMERIKA」
朝日新聞に劇評が出ているのを見て「いけない。また見逃してしまった。」と思った。松本修の芝居にはこれまでそういうことが続いていたからだ。ところが今回は間に合うと連れ合いに言われて、「会社の人事」以来じつに十年?ぶりに見ることになった。
MODEの動向については、松本修が札幌にいったあたりからなんとなく疎遠になっていたが、今回のアンケート用紙に『「MODE」のファンだから(観た)』と言う文言があるのを見ると、その活動が一定の観客層を獲得するまでに、思想(コンセプト)やテーマ性の充実、何よりも面白さの水準を高めてきたことをものがたっているようで、頼もしく感じられた。もっとも、僕らの業界(マーケティング)用語でスローガン−「○○のMODE」の○○に何が入るのか僕はまだ知らない。
すくなくともこの芝居のスケールといい、実験的な(といえば怒られそうだが)手法、テーマといい、「柄」がすっかり大きくなって、この時点から見ると「会社の人事」などははるか遠いところに点景としてあるだけだと思った。初演は二年も前のことらしいから、遅ればせながら認識を新たにしたというわけである。
それにしても、カフカである。
ちょうどこのとき、カフカの短編「断食芸人」の紹介をまくらにした少し長めのエセーを読んだばかりであった。去年の秋には斉藤憐の「ミレナ」(佐藤信演出)を見た。「ミレナ」はドイツの収容所でなくなった、カフカの恋人であり、彼を世に出した編集者、ジャーナリストである。
僕はカフカは小説的すぎると思っていて、彼のいい読み手ではないが、最近目に付くことが多いのをみると、どうもいまがシュンなのかもしれない。
なぜカフカかということについて、松本修は初演の時にこう書いている。 「原作の小説をどう身体化、舞台化していくか、その結果が作品となる。この作業にカフカの『アメリカ(失踪者)』はうってつけである。その整合性のなさ、唐突な展開、中断、そして未完であること。現代演劇の必要十分条件を備えている。まさに二十世紀の世界、我々が知っている人生そのもののように思える。」
「小説」をいったん解体し演劇的な方法で舞台上に再構築するというのは劇作のひとつの考え方である。その素材としてカフカは好都合だったというのである。もっとも現代演劇の必要十分条件云々は少し口が滑った感がある。整合性のなさや、唐突な展開、未完成など、もともとカフカの小説にひろく見られる特徴で、よく言えば無邪気、不条理、悪く言えば非合理的、未熟の物語を舞台で表現するとすればどうなるか?という問題意識が最初にあったのだろう。その課題をオーディション、ワークショップと長い時間をかけて練り上げていった結果、原作の妙な部分を「演劇的」に克服して、これほど完成度の高い作品に仕上げることができたのだと思う。
原作を刈り込む手腕や「演劇的」表現感覚の鋭利さは随所に見られたが、とりわけていえば、主人公カール・ロスマンを女性を含む複数の俳優によってリレーする方法は「カール・ロスマンはアメリカにいながら、アメリカにはいない。カール・ロスマンはカフカでないが、カフカである。そして彼はなにものでもあり、なにものでもない。」さらに作品にかかる両義的なものの全体を示していて説得力がある。また各プロットの間を俳優による群舞(ダンス)で繋ぐやり方には展開にスピード感があって、時空間をワープする劇的なダイナミズムを感じさせる。結果、一種の寓話を見るように、原作を知らない観客にも、ものがたりがどんな唐突な展開を見せようと違和感を感じることなく十分楽しむことができたのである。
こうして小説「アメリカ(失踪者)」の世界は舞台上に再構築されたのだが、一方この芝居はもう一つのテーマを伏流水のように抱えていたのであり、それは終幕近くになって噴出する。 この点について、まえに作品を作るうえで「アメリカ(失踪者)」は好都合だったと言う松本の発言を紹介したが、このとき、彼はカフカについては何も言及しなかった。「まさに二十世紀の世界、我々が知っている人生そのもの」と言う言葉でこの作品世界を示唆したにすぎなかった。 しかし、この芝居には始めからカフカの影は登場していたのであり、カフカという地下水脈は時おり地上にしみてきてものがたりの複層的な構造をあらわにした。そして、連続性を断ち切って挿入されるスライドの警句が観客の意識に積み上げられその存在は次第に大きくなっていく。
明らかにカフカという実存を意識して作り上げられているのである。一見、原作が唐突に中断していることを補うために仕組まれた伏線のように見えるが、「カフカとはなにものか?」という、ある種めまいをさそう問いかけが、劇作の前にいわば先験的にあった。それがカフカの魔力というものだろう。
それに応えようとして、ついに「変身」の冒頭部分が挿入され、カフカを取り巻く実世界が表にあらわれる。二十世紀初頭の東欧にユダヤ人の事務屋として小説を書きながら孤独に生きた男。カフカとおぼしき山高帽の男が、他の乗客に交じって列車に乗り、どこかへ運ばれていく暗示的なシーンで終幕となるが、ここで俳優たちは素に戻り、衣装を舞台において立ち去る。
このようにして芝居は「いまカフカをやることの意味」を留保したのだ。
僕はそれで十分だったと思う。実際、終わってみれば楽しい大人のメルヘンを見たようないい気分であった。「だって、あれは人生そのものでしょう」と俵万智が感想に書いている。(パンフレット)人生はあのようにして理不尽なものを必然と受け止めて生きて行かねばならないもの、というのだ。 それを読んで僕は、安心した。僕らの世代の文学(元)青年なら数倍冗舌になるところだが、カフカについてはもっともふさわしい感想のように思う。
ところで、開幕直後の客船のシーンで、罐焚き(宮島健)が恐ろしく怒り狂って大声をあげるのが不思議で、えらく戸惑ってしまった。意味がわからないのでこっちがパニックになってどうなるかと思ったが、唐突に上院議員が出てきて話が変わったので安心した。あれはあんなに怒るものなのか?原作は「火夫」と言う短編として書かれ、この小説の第一章になったもののようだが、そのせいで力が入りすぎたのか?
船室を「のぞき込む」という設定だからもう少し個室らしくできていたら、事情は変わっていたかもしれない。しかし、全体として伊藤雅子の装置は素晴らしい出来であった。工場の中にある金属製の渡り廊下のような構造を正面に三段に組み上げ、その二階部分を舞台から袖、客席へと回廊のように延長した。それは、NYに着く客船のデッキであり、ウエストサイドのアパートの裏窓であり、郊外の広大な屋敷の迷宮になる。秀逸は、舞台中央を客席の下に潜り込むようにしつらえ、ここから群衆を出し入れしたことである。袖から出すよりは数段迫力に勝っている。こういう立体的でダイナミックな構造と「アメリカ」というイメージを融合させたデザイン力には並々ならぬものを感じる。欲をいえば、船室とか邸宅、アパートの狭い部屋、そこに並べる小道具類などディティールの処理に工夫があればと思った。
振り付けの井手茂太は、俳優は筋肉のつき方が専門のダンサーとはまるで違うことをよく知っていて、そういう前提のもとに非常にスピードのある面白い群舞を作り出した。俳優はかなり稽古を積んだものと見えて、自信に満ちて嬉々として踊っていたのが印象的だった。このダンスは新世界のものではあったが、音楽は、ボヘミヤ的な民族世界にとどまり、決してアメリカの領域に踏み込もうとしなかった。市来邦比古の仕事は目立たないが、この芝居の骨格を考えた場合極めて大事なことであった。
俳優では、石村実伽のカール・ロスマンが、身体の切れも良く、少年らしい役柄の雰囲気がでていて強く印象に残った。倒錯的で官能的な松本演出の意図をよく表出していたが、ほんの少し堅さが見えたのは気のせいか?これから大きく開く才能と見えた。
裕木奈江の長ぜりふは困ったものである。母親の死に様を語るシーンの少しあとに、斉藤歩の長いモノローグがあるが、これと比較すると無残というよりほかない。斉藤のせりふは、歯切れの良さ、抑揚、リズムいずれも申し分がなく、決して力を込めていないが語る心境がリアルタイムで伝わってくる。はじめて舞台で見たが、みごとなせりふまわしだった。いつかこの人のイヤーゴを見てみたいと思う。
カール・ロスマンを演じた若い役者達はそれぞれ個性の違いはあるが「行き暮れて一人」といった哀愁を漂わせて皆、役柄の造形に成功していたと思う。笠木誠だけは一人薹が立っていたが、結局このカール・ロスマンがカフカを投影された人物を演じることによって芝居の構造である両義性は強調されたのであり、それを印象づけるに足る存在感であった。
大崎由利子の貫録も目立った。
こんなに一人で何役もやれるのはめずらしいことで、役者冥利に尽きるのではないかと思ったが、衣装の半田悦子の苦労を考えるとそうばかりも言っていられない。オクラホマ劇場の場面で、脚立を使うアイディアは誰のものか別にして、少々息切れがした印象だった。ついでに言うと、失業者の斉藤歩のズボンの前が開いているのは不自然だ。普通あれでは脱げてしまうのではないか?僕は、カフカについてあまり自信のあることを言えないが、気になっていることを言っておくと、時々挿入されるカフカのアフォリズム(だと思うが)が良く分からなかった。最初の「傘を忘れた」シーンに挿入されるニーチェの「私は自分の雨傘を忘れた。」と言うテクストからして理解不能であった。あのままでは単なるごろ合わせと思われかねない。カフカがニチェについて言及している可能性は高いが、いったいどういう関係になっているのか?
カフカは自分の書いたものから百ほどのテクストを取り出して、アフォリズムとして編集したらしいが、あのスライドはそれから採ったものか?だとしても、場面と照らし合わせてビンゴ!と言うほどのものは無かったように思う。意図的に大きくずらしたのでなければ、翻訳も含めて、ここは再考の余地があるのではないか。最後に、これほどやれるなら(というのは失礼!)演出家としての松本修をプロモートする方法を提案しておきたい。
まず、この芝居を新国立劇場にもっていき、もっと多くの国内の観客に紹介すると同時に海外のプロデューサーに見せる機会を作る。 次にイギリスかフランス、その両方で公演を企てる。その成功を逆輸入する。 (業界人だからすぐそういう発想する!)
それほど、 この芝居は、世界に知らせるだけの価値があると断言していい。(2003/3/15)