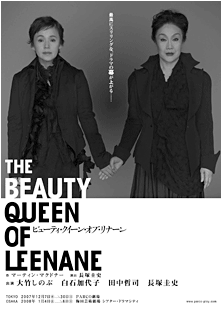
「ビューティー・クイーン・オブリナーン」
この時代に民族の気質というものに何程の意味があるか怪しむムキがあるのは承知で言うのだが、アイルランド人かたぎについてだけはどうも濃厚に存在するという気がしている。
突然Yに手を引かれて劇場に行くことになって、気がついたら何を見るのかもわからないまま席に着いていた。幕が開くと、下手のキッチンの横にある勝手口から買い物バッグを持った女が入ってくる。流しの前には台所用のテーブルがあって、その横、舞台中央にソファ、上手は玄関に通じる廊下が奥に続いている。そしてソファの前のロッキングチェアに座ったままの老女がいて、入ってきた女の様子を窺っている。
四十才になる、いかず後家の娘とその母親が、小高い丘の上にある家で暮らしているということらしい。そこまではわかったが、最後列の端っこだったので女優が誰であるか判別できない。母親は足腰が弱く座ったきりで、娘に口やかましくあれこれ命じている。買ってきた食い物の銘柄にけちをつけ、買い忘れたことをなじってバカだのちょんだの言いたい放題である。自分の面倒を見るのは娘としての義務だといわんばかりで、身内とはいえ人の気持ちなど忖度することなどまるでない。娘も親に対してどうかと思われるようなひどい悪態をつきながら、体が動かなくなっている老人に当てつけるように動き回る。エゴむき出しのぶつかり合いである。
この開幕からの数分間のやり取りを見て、これを書いたのはアイルランド人に違いないと直感した。
親には娘に対する情というものがあり、一方娘には年老いた親に対するいたわりの気持ちがあると考えるのが僕らの常識である。ここにそれがないと断言するつもりはないが、「ある」という常識でみれば、この二人は母娘でありながら赤の他人よりももっと遠い存在である。いっそ赤の他人同士で悪態をつきあっているなら分かりやすいが、ふたりが本気でいがみ合い憎み合っているのか、それとも常識の通り深いところで情が通じ合っているのか判然としないというのがいかにもアイルランド人らしい感覚だと思うのである。その剣呑な、しかし乾燥したやり取りにはそこはかとなく「ユーモア」が漂っている。たとえば母親は、娘の目を盗んで毎朝おまるの中身をキッチンの流しに捨てる。洗い物の皿がおいてあろうとお構いなしである。水で流してもにおいは残る。娘は自分が仕事をする場所を汚されて激怒するが、後の祭である。何という酷薄で残酷で汚らしく滑稽なことか。しかも、そうしたいがみ合いはいつまでも実に執拗に続けられる。こういうその「おかしさ」はどこから来るのであろうか?おそらくこの二人の関係が、「親子の情」なる「甘っちょろい」ものに対する批評になっているからである。それがちょうど「人間」というものに対する辛辣で毒のある風刺になっているのだ。あの北海に面した過酷な風土の中にいかにもぴったりの情景で、こういうものはアイルランド人にしか紡ぎ出せない物語だと思うのである。同じヨーロッパといえいったいなぜ彼らにだけそのような感覚が備わったのか不思議である。シーザーも来なかったローマ帝国の辺境であったことが独特の歴史を形成したのであろうか?ともあれ、そのあたりのことについて書いていると話が停滞するばかりだから、先へ進もう。
話の舞台になっているのはアイルランドの片田舎、リーナンという村である。この家のある丘に登ってくる道はぬかるんでいると言うせりふがあるところから、湿っぽく荒涼とした痩せた土地に違いないと思った。
母親マグ(白石加代子)は七十才、つかまり立ちをしなければ歩けないほど足腰が衰え、四十才になる娘のモーリーン(大竹しのぶ)がいなければ日々の暮らしもままならない。(娘が大竹しのぶなのには、まもなく気付いたが、母親役は誰かわからなかった。よたよた歩く割には張りのある大声で、その姿には場を圧する存在感がある。白石加代子と気付いたのは休憩時間になってからだった。)
モーリーンには二人の妹がいるが、さっさと結婚して家を出ている。モーリーンは男も知らず、二十年以上も母親の面倒を見るために自分の人生を犠牲にしてきた。なぜモーリーンがこの家に縛りつけられてきたのかその隠された理由の一つがやがて明らかになる。モーリーンは若い頃、アイルランドの若者がまともな仕事にありつこうと思ったら海を渡って英国に行かねばならないというごく当たり前の事情によって、英国で職を得ていた。そこにはアイリッシュに対する差別と偏見がある。あるとき何かに耐えきれなくなってモーリーンは、精神を病んだらしい。長い間入院して、病気から回復するとやがて故郷の母の元に帰ったがその理由は伏せられた。しかし、この秘密は母親が娘をこの家に縛りつける口実になった。言うことを聞かなければ、村中にばらしてしまうという脅しである。モーリーンはこのことがあって、村を出て一人で暮らして行くことには自信が持てなかった。
ある日、近所に住む若者レイ(長塚圭史)がやってきて、伯父がボストンに移住することになった、ついては細やかな送別パーティを開くのでモーリーンにも出席を賜りたいというのである。これにはロンドンで働いているレイの兄パド(田中哲史)も一時帰郷するというので、モーリーンはひそかに心をときめかせる。パドは、若い頃モーリーンがあこがれた対象であった。
パーティは盛り上がった。その夜おそく、モーリーンは母親が寝てしまった家へパドを誘う。パドは酔っていたが久しぶりに会ったモーリーンが意外に魅力的だったことに気がついていた。モーリーンはベッドに誘いこむことに成功した。しかし、翌朝の二人の会話から、パドの首尾はうまくいかなかったことがわかる。しかし、互いに好意を持ったことだけは確信したようだった。起きてきた母親はこれを敏感に察知し、パドもまた二人の折り合いが悪いことに気がついた。
パドはロンドンに帰った。モーリーンには再び口うるさい母親との生活が戻る。しかし、今度はなんの保証もあるわけではないが、パドとの暮らしを夢見ることができた。そうはさせじと母親がいっそう娘につらく当たり、娘は娘で母親に敵意をむき出しにする。二人の関係はパドの出現により、次第にのっぴきならないところへ追いつめられていくのである。
そんなとき、実はロンドンのパドもまた、偏見と差別の中、今の暮らしを捨てて伯父のいるボストンに移住しようと決意している。パドは、ボストンにモーリーンが来てくれることを願っているが、彼女が自分をどう思っているかそれほど自信がない。手紙を送ればマグが気付くに違いないと思って、レイ宛の封書の中に、くれぐれも直接モーリーンに手渡すようにと念をおして、手紙を同封した。そこには、自分は先にボストンに行っているから、もしよかったら一緒に暮らさないかということを慎重に誠意が伝わる言葉を選んで書いてあった。これをモーリーンが読んでいれば一も二もなくボストンに向かっていたはずだった。運の悪いことに、レイがこれを届けたとき家にはマグしかいなかった。躊躇した揚げ句、手紙をマグに渡してしまう。マグは封を切って読んだ。そして当然それを隠した。
しばらくしてそれに気付いたモーリーンはがく然とした。パドの誘いに乗るには時が経ちすぎていたのだ。
エピローグで、レイがモーリーンに「・・・それで刑事さんは納得したの?・・・」と訪ねると、モーリーンは軽くうなづいて「・・・すべて終わった・・・」とつぶやく。家を出た母親はぬかるみに足をとられ転倒して頭を打ったというのである。
何という結末か。母親を殺してしまうとは。しかし、そこはアイルランド人である。人間というものをどう見ているか、そのアングルが独特で、これはアイリッシュにしか書けない始末の付け方である。つまり我々が持っている常識というものを痛烈なやり方で覆してしまうシニカルな視点を彼らは持っている。それは、あの風土がはぐくんできた感性なのだろうか。
書いたマーティン・マクドナーは実は英国人らしい。父親が典型的なアイリッシュで、幼い頃から父親の故郷の話を散々聞かされて育った。気質としてはアイリッシュといってもいいのだろう。ついでに言えば、ジョナサン・スウィフトも出自はイングランドにある。しかし、彼は狂信的とも言える愛国者であり、その厭人主義といい、痛烈な毒のある風刺といい、典型的なアイリッシュ気質といっていい。
この戯曲はマクドナーの処女作である。この後書いた「ロンサムウエスト−神の忘れたまいし土地」を2002年五月に見ている。(兵庫県芸術文化協会主催、世田谷パブリックシアター、鵜山仁演出、辻萬長、磯部勉、小島聖、横堀悦夫出演)これは兄弟があい争う話であるが、我欲をむき出しに親兄弟、肉親同士が強烈な激しさでいがみ合う様は見ていてそのやり切れなさに胸が塞がれる思いがしたものだ。痩せて実り少ない土地に対する憎悪、貧しさゆえの人間不信、親殺し、ついにはカトリックの神父でさえも自ら命を絶つという絶望的な情況。陰鬱で暗く、バイオレンスが渦巻いている舞台であった。
身内が争うというのはマクドナーの特徴かもしれないが、そのシニカルな筆致において共通するものがあると感じた芝居に、フランク・マクギネスの「サムワン」(2006年一月、ホリプロ主催、俳優座劇場、松本祐子演出、高橋和也、大石継太、千葉哲也出演)がある。
僕はこの劇評においてもアイルランド人に言及せざるを得なかったと見えて、自分のロンドン、カムデンタウン(先日マーケットが火事で焼けた)で出会った物乞いのアイリッシュとの体験談を交えて縷々書いている。このときも、書いたのはアイルランド人だと直感したのであった。なぜか独特のにおいでわかるのだ。
それは僕にとっては好ましいにおいである。正直に言うとあの執拗さにはいささか閉口するが、現実的で情け容赦のない人間関係、説教臭さや理想主義をかざさない率直さは、なにか遠い時代の古武士の姿を思い起こさせるのだ。厳しい自然やイングランドによる絶えざる圧力に、屈してなるものかという意気地が、絵画や音楽といったやわな表現には向かわず、ただ一点言葉による創造活動に向けて噴出したのがこの国の文学だと僕には思われる。
もう一つ、この劇にも言えるが、物語全体に宗教の影が薄いことにも僕は共感を覚えている。マクドナーは、「ロンサムウエスト」で、神は無力ではないかと神父を攻め自殺に追いやっている。キリスト教社会では考えられないことだと思ったが、それには事情があったと推定できる。アイルランドという辺境には欧州でも最も遅くカソリック教会がやってきたのであった。そのために土着の宗教に対して寛容にならざるを得なかった。どのようにして融合したのかあの国の歴史を調べたわけではないから詳しいことはわからない。八百万の神々をあがめていたところへ仏教が入ってきた我が国のようなものだったのか。この国の道を走っていると、「静かに走れ!妖精が横切る道だ」という看板が大まじめで立っているというが、この「妖精」が古代からこの国に住み着いている神だったのではないか。「妖精」という古層の上に一神教の神が乗っかっている。それがどんな風景なのか興味は尽きない。
昔、旅番組のスポンサー側のプロデュースをやっていたとき「アラン島のオートバイレース」を取材する企画が提案されたことがあった。バイクレースはともかく、このアラン島の風景にはいささか驚いた。日本の畔で仕切った田んぼのような広さの畑が続いている。ただし、畔は腰の高さほどに石を積み上げたもので、東アジアの気候につかっているものにとっては異様である。泥炭質の地面をわずかに覆った表土を大洋から吹きつける強烈な風がさらっていかないように粗末な石垣でかこっているのである。その中でジャガ芋が育つ。番組は確かそのとき取材したものに昔のレースのフィルムを交えて構成しオンエアした。畑を取材しようなどという酔狂なことを言い出すものはいなかった。
百五十年前、そのジャガ芋が立ち枯れ病の流行で壊滅状態になった。餓死するもの百万余、国を出るもの数百万、わずか数年でアイルランドの人口は半減した。「いいアイルランド人は、皆外国にいる」とアイルランド人は言う。北海道ぐらいの大きさの国に人口三百五十万人あまり。しかし、米国だけでもアイルランド系はすでに四千万人を超えている。この国の運命がいかに過酷であったかを物語る数字である。かたくなで妥協することを知らない孤高の人が生きる、とはそういうことだったのかという思いに駆られる。
モーリーンは、ぬかるんだ道を小高い丘にある家に向かっている。空はどんよりと重く、海なりの咆哮があたりに響き、冷たい雨混じりの風が頬をさすように吹きすさんでいる。どんな希望があるというのだ、この神の忘れたまいし土地に・・・。
僕は、リーナンという寒村がどんなところか知りたくなった。いまは幸いGoogleで空から近づくことができる。そこは、ブリテン島に向き合った首都ダブリンの緯度をそのまま真西に追って、この島国の北大西洋沿岸に達するあたりになる。氷河が削ったU字谷が、入り江になって細長く入り込んでいる、その奥にリーナンはあった。クリックすると町のホームページになる。そこには普通の民家のように見える小さな建物が明るい青空をバックにたたずんでいた。想像とは大違いである。
トップニュースとして、2007年7月に町の真ん中にある橋が壊れて車が通れなくなったために、観光バスが百キロメートルも迂回しなければならなくなった記事が掲示されている。その後に、マーティン・マクドナーのブラック・コメディ「Beauty Queen of Leenane」の舞台になった旨の記事もあった。
壊れたというのは、石組みのアーチがいくつか連なった重厚な橋で百五十年ほど前に作られたものらしい。それが、七月の鉄砲水で流れてきた木や石の圧力で石組が崩れたというのである。材料はそこに残っているから組み上げれば元に戻りそうである。この国の歴史の強靱さというものを感じさせるエピソードではないかと思った。
また、町の中心には小さなホテルがあり、観光する場所の標識がいくつかみられるところから、実像は存外、「神が見捨てた町」とはほど遠いのかもしれない。入り江ののんびりした風景、小さな家が建ち並ぶ町の様子、そして何よりもそれらの風景の上に広がる、抜けるような青空を見て、僕は、ひょっとしたらマーティン・マクドナーにやられたかなという思いがした。
題名: |
ビューティークイーン オブ リナーン |
観劇日: |
07/12/9 |
劇場: |
パルコ劇場 |
主催: |
パルコ劇場 |
期間: |
2007年12月7日〜12月30日 |
作: |
マーティン・マクドナー |
演出: |
長塚圭史 |
美術: |
二村周作 |
照明: |
佐藤啓 |
衣装: |
前田文子 |
音楽・音響: |
加藤温 |
出演者: |
大竹しのぶ 白石加代子 田中哲司 長塚圭史 |
