 }
}「僕と僕」
さあ、ゲームの始まりです
愚鈍な警察諸君、ボクを止めてみたまえ
ボクは殺しが愉快でたまらない
人の死が見たくてみたくてしょうがない
汚い野菜どもには死の制裁を!!
積年の大怨に流血の裁きを!!
(風車様のマーク)SHOOLL KILL
学校殺死の酒鬼薔薇
平成九年(1997)五月二十七日午前六時半頃、神戸市須磨区にある市立友が丘中学校の正門前に男子児童の生首が置かれているのを出勤してきた用務員が見つけた。上の文は、男の子の口に挟まれていた紙に書かれていたものである。殺されたのは、四日前から行方不明だった十一歳の小学六年生であった。猟奇的なやり方に連続殺人を匂わせる挑発的な犯行声明が加わり周辺地域はいうまでもなく日本中が騒然となった。
当時はテレビのワイドショーを比較的よく見ていたから、記憶はかなり鮮明に残っている。最初は、友が丘中学校の正門前から七八百メートル離れた道に駐車していた不審な車の存在が取りざたされた。まもなく正門を見下ろす小高い丘の上を通る道路脇の薮の中に二十歳台から三十歳台のがっしりした体格の若い男が、黒いビニール袋を手に提げて佇んでいたという目撃情報が報道された。さらに、犯行があった前後に中学校の裏門に黒い小型乗用車が停まっていたとの情報もあり、いよいよ報道の犯人探しは三十歳台の、車で移動出来る非勤め人という方向で加熱していった。
殺された児童の小学校はもちろん周辺の小中学校は集団登下校を始め、父兄は通学路に交代で立って見守った。一方で「黒いビニール袋の男」から捜査に進展はなく、ワイドショーが告げる内容は日に日に薄くなっていった。わずかに、数カ月前に何日間かに渡って猫の惨殺死体が放置されていたことや殺された鳩の死骸が見つかったことなどが住民の証言で明らかになり、事件との関連性が検討された。さらに二ヶ月前、同年三月十六日に、同じ須磨ニュータウン地域にあって友が丘中学校から一キロほど離れている竜が岡北公園で起きた山下彩花ちゃん(当時小学四年、十歳)殺害事件とそれに先立つ女子小学生の連続殴打事件も何か関係があるのではないかと話題に上った。児童を襲った事件としては類似しているが、これは被害者の「お兄ちゃんにやられた」という証言から、犯人は少年ではないかということで、見過ごされた。「黒いビニール袋の男」という先入主がこの事件との関連性を考えにくくしていたともいえる。
そうした膠着状況の中、事件から九日目の六月四日午前十一時、神戸新聞社に犯行声明文が届いた。神戸新聞はこれを捜査本部へ届け、真偽を鑑定することになった。社内では取り扱いを慎重にすべきという意見もあったが、信憑性は高いとして独自に発表しようとした。ところがこれを嗅ぎつけた他社が、神戸新聞に押しかけコピーを入手するという騒ぎになり、ようやく手紙が届いてから二日後に全文が各紙上で一斉に公開された。
「神戸新聞社へ
この前僕がでている時にたまたまテレビがついており、それを見ていたところ、報道陣が僕の名を読み違えて『鬼薔薇』(オニバラ)といっているのを聞いた
人の名を読み違えるなどこの上なく愚弄な行為である。表の紙に書いた文字は、暗号でも謎かけでも当て字でもない、嘘偽りのないボクの本名である。ボクが存在した瞬間からその名がついており、やりたいこともちゃんと決まっていた。しかし悲しいことにボクには国籍がない。今までに自分の名で人から呼ばれたこともない。もしボクが生まれた時からボクのままであれば、わざわざ切断した頭部を中学校の正門に放置するなどという行動は取らないであろう。
やろうと思えば誰にも気づかれずにひっそりと殺人を楽しむことも出来たのである。ボクがわざわざ世間の注目を集めたのは、今でも、そしてこれからも透明な存在であり続けるボクを、せめてあなた達の空想の中でだけでも実在の人間として認めていただきたいのである。それと同時に、透明な存在であるボクを作り出した義務教育と、義務教育を生み出した社会への復讐も忘れていない。
だが単に復讐するだけなら、今まで背負っていた重荷を下ろすだけで、なにも得ることが出来ない。
そこでぼくは、世界でただひとりボクと同じ透明な存在である友人に相談して見たのである。すると彼は、『みじめでなく価値ある復讐をしたいのであれば、君の趣味でもあり存在理由でもありまた目的でもある殺人を交えて復讐をゲームとして楽しみ、君の趣味を殺人から復讐へと変えていけばいいのですよ、そうすれば得るものも失うものもなく、それ以上でもなければそれ以下でもない君だけの新しい世界を作っていけると思いますよ。』その言葉に突き動かされるようにしてボクは今回の殺人ゲームを開始した。
しかし今となっても何故ボクが、殺しが好きなのかは分からない。持って生まれた自然の性としか言いようがないのである。殺しをしている時だけは日頃の憎悪から解放され、安らぎを得ることが出来る。人の痛みのみが、ボクの痛みを和らげることが出来るのである。・・・・・・・・・」
まるでフィクションの世界にいるような気分になったのを覚えている。残虐な快楽殺人を行う者の知性が意外に高いことが文章から見て取れて驚きであった。世間は国籍とか義務教育、社会への復讐という言葉に反応し、それを手がかりに犯人探しを始めようとした。そして何よりも『透明な存在であるボク』という言い方には様々の複合的な意味を感じ取ることができて、この言葉は長く記憶に残った。
しかし、この声明文の後も捜査状況が進展しているのかどうかいっこうに伝わってこなかった。捜査員の口が堅かったなどということは、むろんこちら側にいて分かるはずもない。この当時、朝日新聞は神戸支局に応援を送り、総勢五十人体制で取材に当たったという。すると他の新聞社や週刊誌、TV局などを合せると数百人の記者がこの新興住宅地に入りこんで取材活動をしていたことになる。実際、殺された児童が通っていた多井畑小学校や友が丘中学校の生徒の家と分かれば、夜昼かまわずドアホンが押されたらしい。同じ家がなんども取材の申し込みをされるということがあって、犯人がまだ捕まらずただでさえ不安なところへ踏み込まれて、住民は苛立った。そのため北須磨団地自治会の代表が、マスコミ側に取材自粛を要請するという異常な事態にまでなった。そこまでの騒ぎになっていたことを当のTVが言うはずもないが、報道ぶりを見ていて現場の騒乱と苛立ちを感じることは出来た。
この過熱ぶりがややおさまってきたかと思われた頃、事件から一ヶ月ほど経過した六月二十八日土曜日の午後九時前、民放の旅番組をみていたらそろそろエンディングになろうとしていた矢先にいきなり画面が切り替わり、緊迫したナレーションが重なった。兵庫県警捜査一課長の記者会見が始まろうとしていたのである。
「逮捕は午後七時五分、逮捕場所は須磨署内。被疑者は中学三年生の少年A。男性。十四歳です。」凶悪な事件の犯人は、中学生だったのだ。日本中に衝撃と戸惑いが走った。
この劇は、少年Aの犯行における心の軌跡を描きながら、我々の社会がこれをどう受け止めたらいいかを検証したものといえる。 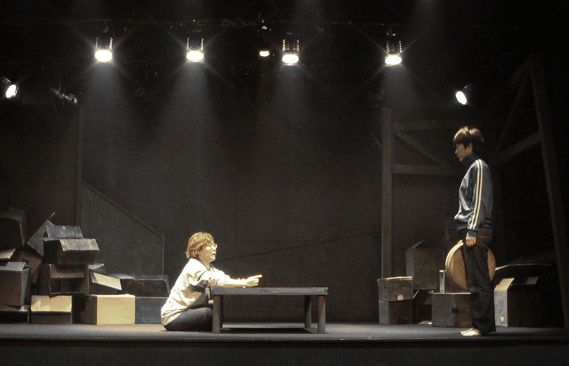
薄暗い部屋には折り畳まれた段ボール箱が散乱している。上手のぼんやりとした灯が、緑色の藻がはり付いた水槽を浮かび上がらせていて、その前で男の子がひざまずいて中をのぞき込んでいる。舞台中央にはこたつの台のようなものをおいて、女が本を広げており、幕が開くとすぐに朗読がはじまる。
「広い土間の真中に涼み台のようなものを据えて、そのまわりに小さい床机が並べてある。台は黒光りに光っている。片隅には四角な膳を前に置いて爺さんが一人で酒を飲んでいる。肴は煮しめらしい。・・・・・・」
小説の一部のようだが、これが延々と続く。爺さんは白髭を生やしているが肌艶は若々しく輝いている。この後かみさんが現れて一言二言言葉を交わすと、やがて爺さんは向こうへ行くといって土間の障子からすうっと表へ通り抜けていく。この様子を見ていた「自分」も、爺さんについて行くと、川の側までやってきて、三四人の子供を前に、懐から手ぬぐいをとり出して肝心絞りのようにねじって見せた。これが今に蛇になるといって、蛇遣いのようなしぐさをする。そうしながら川の中にどんどん入っていって、見えなくなる。今に向こう岸に上がって蛇を見せてくれるものと思ってながめていたが、爺さんは現れなかった、という話である。
爺さんの様子を自分が俯瞰してみているという想定であるが、その話の中に自分も登場人物として参加していることになっている。劇を見ている時は分からなかったが、これは夏目漱石の「夢十話」のうちの第四夜の全編であった。「こんな夢を見た」ではじまるこの小説の形を借りて、自分の夢を映像化したものが、黒澤明のオムニバス映画「夢」である。つまり、これは(漱石がみた)夢の中の出来事だったのだ。煙のように表へ出て行く浮遊感や、蛇が現れるのを待つという想定を、フロイトの「夢判断」に結びつけて考えるむきもあるようだが、この物語が意識下に潜んでいるどんな欲望や衝動を表わしているのかは分からない。
少年はシンジといい、祖母に小説を読んでもらっていたのであった。シンジは、話の中に二人の「自分」がいることに気づいて、祖母にそのことを質すと、これは夢の話で自分の身体からもうひとりの自分が出ていってしまう状態を表わしていると説明する。ひとりの中に二人の違った自分が存在し幽体離脱のように、ひとりが分裂して離れるということをシンジは自分の経験に照らして、あらためて確認する場面は象徴的である。シンジは、本能的な衝動に突き動かされる自分とそれを制御しようとする理性的な自分が同居していることに始めから自覚的であったということを作家は言おうとしているからである。いつの間にかシンジよりは背が高く大人っぽい人影が舞台奥に現れ、寄り添うように動き回る。分裂したシンジの悪を行う片割れである。
この漱石の小説を最初に使ったのは、面白い趣向であった。説明のつかない不条理な出来事なのに、妙に鮮明なイメージが行間にただよっているのである。ただし実際にこういう事実があったかどうかはぼくにはわからない。シンジが大好きだったという祖母が亡くなったのは彼が五年生になったばかりの春である。小学生に漱石を読み聞かせる祖母の感覚もすごいが、それをせがむ少年というのも恐ろしく早熟であると思った。
ただ、そういうものへの関心とは少し違うが、少年には変わった才能があったという。少年Aは中学二年のときに一晩で小倉百人一首を八十首覚えると言う離れ業をやって翌日の対抗戦に備え、周囲を驚かしたということがあったらしい。「見て」覚えたというのである。カメラのシャッターを切るように瞬間的に映像として記憶することが出来る才能をもっていた。「直感像素質者」といって、天才型の芸術家に見られる能力である。後に、ある作文の中でダンテの「神曲」の一節を引用しているが、これは本屋で立ち読みしたページを丸ごと記憶していたものであった。異能の持ち主だったのである。
劇は、犯行が行われている「現在」を写し取りながら、何故犯行に至ったのかという経緯を追い、逮捕された後の父母の回想を交えるという、三つの時制を往来する。作家がもっとも重要視しているのは言うまでもなく「何故」である。
祖母が亡くなったことは、かなり少年にとって衝撃だったらしい。長患いの後というのではなかった。体調を崩したかと思うとあっけなく亡くなったことに人の命のあやふさを感じたのであろうか?その頃から、蛙を殺したり猫に石を投げつけたり、動物虐待の行動が目立つようになったという。
そうなるには何か家庭に問題があったのかといえば、朗読の場面に続いて現れる少年の父親と母親の会話から格別の反抗児というわけではなかったことが分かる。母親は、事件の後、もはや住めなくなった元の自宅に戻って荒れ果てた部屋(段ボールが散乱した舞台はその部屋を表わしていた)から、一枚の絵を拾い出す。シンジから母の日にもらったプレゼントだという。結婚したての頃の母親の写真を見て描いたものだった。母親はそういうやさしい一面がある子なのに何故・・・と絶句。父親は、これは天災にあったようなものだという。散らかった部屋を眺め回して、この事件は先頃経験した震災と同じだというのである。
父親は、沖永良部島で生まれ、集団就職で神戸にやってきた。電気関係の資格を取って神戸でも有数の大企業に転職したサラリーマンである。無口であったが、子煩悩なところがあり、添い寝して昔話を聞かせるとか休日には三人の子供を趣味の釣りに連れていくなど、極く普通の親子関係だった。息子がこのような凶悪な事件を起こすなど思いも寄らなかったであろう。自分では防ぎようのない天災に襲われたようなものというのは実感であった。
近所に住んでいる下の弟ノブオの同級生ハタジュン君が、昨日の午後から帰らないと捜索願がでたということで、雷が鳴る中を団地の住人が総出で付近を探していた。シンジの母親も時々家にきて見知っていたジュン君の捜索に加わった。新興住宅地の割には近所付き合いがあるようで、意外なことにそれぞれの家庭の事情には通じているように見える。様々の人々がこの捜索に加わっていた。少し耄けが入った老人は、労働組合のリーダーだったのか、時ならぬ反権力の演説をはじめて、娘に連れ戻されるというエピソードが挿入されたりする。
シンジが緑亀を見せるといってジュン君をタンク山に誘い出し殺害する場面は幻想的である。既に死んで横たわっているジュン君と会話を交わしているところへ、シンジの分身である男が現れる。これはガルボスという犬だと紹介するが。男は俺は犬かと不満そうである。しかし、中学校の前に首を置くという大胆な行為にでる時には、このガルボスが主導権を握っている。バモイドオキ神の洗礼を受けさせるといってジュン君の瞼に傷を付けるのはガルボスである。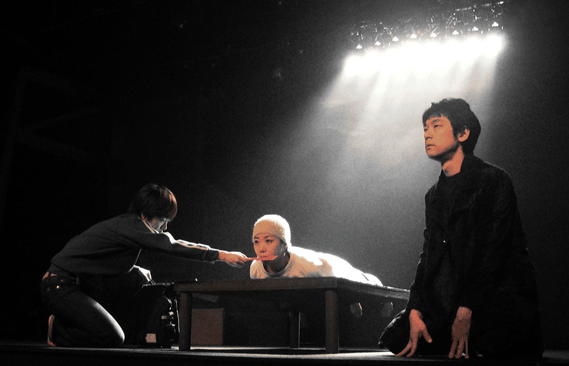
お前は死んでいるとシンジに向かってガルボスが言う。
「死んでるから生きてるもんに興味あんねん。生きてるもん殺して、どうなってんのや思 うて、からだん中あちこち研究したくなるねん……。」
お前は十四年前に生まれて、ゆっくりゆっくり時間をかけて死んでいったのだ。
「殺された」とお前はいったではないか。「サカキバラいうんは暗号や謎かけやない、ぼ くの本名や、ぼくが存在した瞬間からその名前ついてて、ぼくのやりたいこともちゃんと 決まってたいうて……、そう書いて送ったんやねん。」犯行声明文の一つの解釈である。
シンジは、それはみんなお前がやったことではないかというが、ガルボスはただ犬のように吠えて退場する。分身が遠ざかり、統一されたシンジが現れる予兆である。
少年Aは、児童の首を絞めてもなかなか死なないことに困惑しながら、しかし明らかに性的に興奮していたと供述している。首を切り落とす時も快感を抑え切れなかった。二ヶ月前に、少女を襲った時も性的な高揚感を感じていたという。この欲望と衝動に身をまかせながら、一方でどうにかしなければならないという葛藤を声明文に読み取ることも可能である。
シンジは犯行の前日、同級生を殴ってけがを負わせたことで、当日は児童相談所にいくように言われていた。人間は蟻やゴキブリと同じだとこの同級生に言ったことを咎められた。父親に何故殴ったと問い詰められると、自分には人間は野菜に見える、この野菜をどのぐらい殴ったら壊れるのか試したかったという。野菜という言葉は父親が口にしたとシンジは主張した。二年前の神戸の震災の折り、長田町のおばのところへ父親と一緒に様子を見に行ったことがあった。途中広場や寺の境内にたくさんの焼けた遺体が並べられているのを見て、父親が「これではまるで人間、野菜やな」といったことを記憶していた。父親は死んだ人がかわいそうだからそういったのだと説明すると、シンジは、それならムラヤマは何故スイスからきた救助犬を断ったのだ、あれがいればもっと助かった人はいたはずではないかと怒りに震える。時の村山首相が地震直後の対応を誤ったことに殺意さえこめられた強い憤りを感じていたのである。「何故なにも悪いことをしてない人が、あんなふうに死ななければならないのか?」と自問して、シンジはその答えは一つしかないという。それは「この世の中のものはぜんぶ作り物」だからだ。人間も蟻もゴキブリも、この家もみんな・・・だから神戸だって壊れたのだというのである。みんな作り物だから壊してもいいのだというのがシンジの主張であった。
祖母の死から二年、阪神淡路大震災があって六千余の人が亡くなった。少年Aは街も人間もあっという間に壊れてしまう、焼け焦げた死体と瓦礫の山になってしまうことを目の当たりにしたのである。猫や鳩などの小動物を「壊して見よう」と言う衝動が湧き上がってきたのは祖母の死をきっかけにしているとしても、震災は、それがさらに亢進していくトリガーになっていたのではないかというのが作家の見解のようだ。
劇はこの後、死んだ祖母が母親の前に現れ、シンジの子宮回帰願望のようなものに言及する。しかし息子は既に母親の手の届かないところへ行っているようだった。まもなく刑事が家にやって来る。父親が声をかける。「シンジ、あの人が、何やお前に聞きたいことがあるそうや。」この両親にとって、息子は本当に手が届かないところへいこうとしていた。
その朝七時半頃、家を訪ねた数人の刑事に少年Aは素直に従ったという。連続少女殺傷事件についてはすぐに認めた。児童殺害についてはあいまいな供述が続いたが、証拠を突きつけられてついには泣きながら自供を始めたという。
実は、事件の後すぐに県警は極秘裏に専従班九名を選んで捜査を続けていた。友が丘中学の全校生徒の作文や答案用紙を借り出して筆跡鑑定を行ったのは事件後すぐのことであった。捜査本部は比較的早い時期に少年Aをマークしていたが、十四歳という年齢を考慮して、ことを慎重に運ぶ方針であった。
劇はシンジが極く普通の家庭に育ち、親にも住民にもこのような凶悪殺人を犯すような子供には見えなかったことを描いている。しかし、人の死を目の当たりにしたことが契機となって、離人症や「ジキル博士とハイド」のような二重人格という極端な形ではないにしろ二つの人格が一つの身体の中に生まれ、正と邪とが戦っていた。それはそれで納得のいく話である。では、この自己分裂的な心身の状態が、劇でもいっているように「思春期だから」誰にも起き得ることなのか、あるいはたまたま少年Aの心にだけ起きた特殊な事態だったのか、気になるところである。
もちろん、この劇がその回答を用意すべきだというつもりはない。事件以来、少年法の厚いベールに包まれているにも関わらず、たびたびこの犯罪、というよりは「少年A」について言及した出版が見られるのは、そこへの興味があるからであろう。
逮捕から七ヶ月経った頃、名文で知られるノンフィクション作家、高山文彦はアルチュール・ランボオの詩集「地獄の季節」から借りた同名のドキュメンタリーの冒頭でこのようなことを書いている。
「・・・自慰を覚え、のど仏が突出し、陰毛が生え、髭が生えた。からだばかりが容赦なく先に、大人になろうとしていた。秘密が生まれ、自分だけが疎外されていると言う暴風雨のような自意識にさいなまれた。寡黙と暴力とが、兄弟みたいに反目しあいながら寄り添っていた。何故自分は自分なのか突然分からなくなり、頭の中が真っ白になった。幼い頃のことが、懐かしくてたまらなかった。生まれてこの方ずっと大人であるかのような顔をしている大人たちのことを軽蔑していた。二十歳になれば痛みとともに突然、大人というものになり、少年期の記憶はきれいさっぱり消えてなくなるのだと信じて疑わなかった。・・・」このような自分の思春期における苦しみを語り、それがランボオの「地獄の季節」に出会って救われたというのである。
「・・・強いて言うならば、外へ外へと向かう粗暴で凶暴な力を鏡のごとくこちら側へ映し返し、おのれの内面をはじめて深くのぞき込ませるきっかけになったといえるかもしれない。・・・ひさびさに読みすすむうち、自分自身のかつての嵐のような衝動がみうちを駆け抜け、それとともに少年Aの心の風景までが、驚くほど明快に語られているように思われてきて、胸の奥がざわめきはじめた。」
また、ジャーナリストで小説家の勝谷誠彦は、少年Aに呼びかけるある文集の中で、「一つ間違えばボクであったかもしれない君に」という言い方で次のように語りかけている。「君のやった犯罪は許されるものではないが、いつか必ず手記を出してくれ。君は自分の思うところを自分の言葉で書ける人だ。だから事件のことを書いて欲しい。あの事件は一体何だったのか書くことが君の責務だ。そうすることが殺された子供たちへの責務である。」
むろん山崎哲はこういう資料にも目を通しているだろう。高山の説は一般的に思春期特有の生理と心的状況が存在することを建前にして進められる。しかし、それが正しいとしても、何故少年Aだけが突出して凶暴な犯罪に向かったのか説明することは困難に違いない。(だから一冊の本になった。) 勝谷もまた似た様な仮説を前提にしている。少年Aもやがて思春期における自分の行為を対象化して語れる日が来るであろう。だが、それがいかに分析的で説得力を持っていても所詮は記憶を元に再構成される過去の幻影のようなものである。死んだ細胞を観察しても、それが生きていた時と同じものとはいえないように、過去を理解しようとすればするほどかえって知りたいと思う真実から遠ざかるのである。
この事件を扱う困難さは、少年犯罪というデリケートな問題ということにもあるが、むしろ上に述べたような思春期特有の生理にともなう心的状況とは何か?その心の中でどんな出来事が進行していたか?ということを、精神医学の領野に踏み込むのを避けて(つまり、正常であるという前提で)ありのままに描こうとすることにあるのだと思う。その点でこの作品は、ためらいなく出来事の真ん中へあるいは少年の心の中に入りこみ、何が起きていたか、その真実に肉迫しているといえる。
この作品を書くまでに事件から十年という歳月がたっていることを意外に思ったが、おそらく資料を集めることにそんなに時間はかからなかったはずだ。視点を変えながら克明に出来事を描いていることでそれは分かる。何を取り上げ、何を捨てるか、そのことで全体がどのように見えるかということに腐心していたのではないだろうか。シンジとその分身の葛藤、既に死んでいるジュン君との会話、北須磨団地の人々の様子、母親との関係、その工夫の仕方に僕は詩人としての山崎哲をみる。
僕はこの事件に興味はあったが、その後書かれたものはほとんど読んでいない。したがって、事実関係について多少の周辺情報を含め、知っている程度であったが、この劇ではじめて知って感心したことがいくかある。その中から一つだけ書いておこう。実は事件の最初から犯行声明文にある「腐った野菜ども」という言葉に違和感を持っていた。人間を野菜と見なすのは少し無理があるのではないかと思ったのだ。この劇で、父親との会話の中にそれが出てくる。神戸の震災のときにおばさんの様子を見に父親と長田町に出かけたことがあった。途中の道端や寺の境内で焼け焦げた死体が並んでいるのを見て、父親が「これではまるで野菜やな」といったことを覚えていたのだ。八百屋の台の上に並べられた野菜を連想したのだろう。そういうことがあったとは知らなかった。シンジの犯行には神戸の震災における経験が影を落としていたのだ。これは、こんど新たに分かったことであった。
舞台の細かいところに記憶違いがあってはいけないと思って戯曲を取り寄せて見たのだが、それで少し驚いたことがある。舞台の印象とはまるで違って、むしろ生き生きとして明るいタッチで描かれていると感じたのだ。言い過ぎかも知れないが、舞台よりも明晰であり、しかも詩的で分かりやすく、何よりも完成度が高い。戯曲賞をとっても不思議ではないようなレベルだと思った。
舞台は、作者としてのテレがあるのか、抑揚を押さえ込んで一本調子のようなところが多い。北須磨団地の人々など、もっと日常的でさりげない雰囲気でよさそうなものだが、やはりどこかに力がはいっている。
この戯曲を他の演出家でやって見たらどうなるか?違った芝居に見えるかもしれないと思う。
題名: |
僕と僕 |
観劇日: |
07/11/24 |
劇場: |
シアターイワト |
主催: |
新転位21 |
期間: |
2007年11月22日〜25 |
作: |
山崎哲 |
演出: |
山崎哲 |
美術: |
濃野壮一 |
照明: |
海藤春樹 |
衣装: |
蟹江杏 |
音楽・音響: |
半田充 |
出演者: |
石川真希 久保井研 辻孝彦 村山好文 伊藤悦子 杉祐三 おかのみか 大畑早苗 小畑明岩川藍 神戸誠治 岩崎智紀 永岡沙江 神谷由紀子 ヒザイミズキ 日下義浩 吉田男爵 荒川智広 松井亜紗美 澤頭直美 笹本賀子 三浦秀典 田村尚久 粟野南 |
