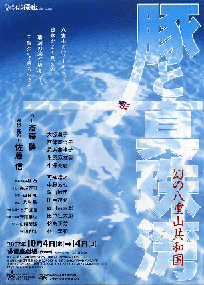
「豚と真珠湾」
まったく斉藤憐にも困ったものだ。一つの歴史観に凝り固まっているのは仕方がないとしても、そこから繰り出す文明批評の射程が今生きている時代に届いていないどころか、その批判精神は滑稽なほど無意味な想念に充ち満ちている。この劇は、終戦前後の八重山諸島の人々の暮らしに取材して、その時期、独立運動があったことをかなり克明に描いている。そのこと自体はあまり知られていない面白い出来事であり、その顛末がどうなったのか興味もかき立てられるのだが、それを描く視点が、「弾圧される庶民」という相変わらずのパターンからでていないために、そこが八重山である必要もなかったろうという気にさせられる。僕は琉球が日本から独立する理由はいくらも見つかると思っているので、むしろそれに焦点を当てた議論を紹介してくれた方が、意味があったと思っている。旧日本軍が沖縄戦で非戦闘員に集団自決を強いたことを教科書から削除したことに抗議して県民十万人が集結したことがあったばかりで、その怒りの根底には琉球の長い歴史が横たわっていることを認識する機会でもあった。しかし、庶民対権力という視点ではそれ以上のものが見えてこない。地主と農民の対立を取り上げた「春、忍び難きを」(2005年5月俳優座)に比較すれば、生な権力批判は影を潜めたので、その分いらいらはおさまったが、ときどきせりふの中にバカなことを仕込んでいたので驚き、あきれた。一端を紹介すると、日本が朝鮮を植民地にしたから朝鮮戦争が起きて南北が分断されたのだ、というのがある。朝鮮戦争の原因は日本の併合にあったというのはいくら何でも飛躍だろう。あれは共産中国と国連軍が戦った戦争で、ためにする言いがかりに聞こえる。また、米兵捕虜を殺害した罪で告発され巣鴨に収監された若い兵士に死刑判決がでると、何で若い者を殺す必要がある、放っておいても五十年も経てば皆死ぬではないか、というのがあった。確かに国家の名においてわざわざ殺さなくてもいずれ人間は死ぬ。戦時犯罪には微妙なところはあるが、そんなことをいうなら法はなくてもいいことになる。東條英機も広田弘毅も放っておけば十年もしないうちに、はかなくなっていたにちがいない。勝手な言い分というよりは、庶民感覚と偽装した権力批判のつもりだろう。普通の人間はそんな哲学的な発想をしないものだ。
硫黄島を取った米軍が沖縄に向かって進軍する時途中にあった先島諸島、八重山諸島は無視された。当たり前のことだ。そんな島に何の戦略的価値もない。そのまま終戦となったが、しばらく占領軍がやって来なかったために無政府状態になった。それをいいことに八重山諸島では独立して共和国になろうという動きがあった。そういうことを昔、風の噂で聞いたことがあったが、その時はやればよかったのにと思ったものだ。国が観念の産物あるいは共同幻想だった時代はいいが、経済のグローバル化ということを考えれば、今は無責任に、あるいは不用意にそんなことはいえないと思う。その石垣島での話である。
サカナヤー(料理屋)の「オモト」を営む女主人南風原ナベ(大塚道子)の家。娘のタマ(小澤英恵)戦災孤児の大城キクノ(生原麻友美)その弟の珍吉(林宏和)それに戦災で身内を亡くして孤老となった安谷屋マイツ(阿部百合子)と一緒に孤児を養いながら暮らしている。そこへ台湾人の元軍属で輸送船を操っていたが今は密貿易をしている林国明(可知靖之)、沖縄本島の糸満で漁船を所有して漁をしている喜舎場アサコ(長浜奈津子)、中学校の歴史の教師比嘉長輝(中野誠也)とその教え子で小学校の教員をしている桃原用立(松島正芳)らが出入りしている。ある日、喜舎場アサコが南風原ナベの長男英文(田中壮太郎)を沖縄本島から自分の船に乗せて連れ帰る。英文は、出征して沖縄の式部隊にいたところ生き残ったもので、ナベたち家族は狂喜して迎える。
終戦で役場も学校も機能しなくなった。なにしろ日本帝国が無くなったわけだからその末端であった行政機関も消えたわけである。占領軍は何も言ってこなければ誰もやってこない。小学校の教師、桃原は同級生であった英文に、とりあえず新聞「海南新報」を復刊させて島民から意見を収集すると同時に情報発信しようと持ちかける。賛成した英文は、教師であった比嘉長輝に相談し、顧問になってもらう。「八重山新報」と名をあらためてスタートしたが、最初は記者である英文たちが営業をして回った。貴重品だった紙は林国明が台湾から運んでくれた。次第に読者も増え、住民の意見も集まってきた。大方は行政機能がマヒ状態になっているのはいろいろ不都合だという。そこで比嘉長輝がかつての同志と語り合って自分たちの共和国を作ったらどうかといいはじめる。戦前は赤だといわれていた比嘉とその教え子たちを警戒していた住民も賛成に回る。そこで、共和国設立の準備に一同張り切るが、ある日突然来るべきものがやってきた。
ダン・南風原(西川竜太郎)は日系二世の二十三歳、ハワイで生まれ育った。占領軍からの通達をもって派遣されてきた部隊の兵士で通訳である。ナベを訪ねてきたのには訳があった。実はダンの父親はその姓が示している通り、ナベの元の連れ合いで、下の子が生まれたあと、ひとりでハワイに渡ったものだった。ダンは父親に石垣に行ったら訪ねて元気でいると伝えてくれといわれていたのだ。つまり、英文とタマの腹違いの兄弟というわけである。ナベはあえて名乗らなくてもいいだろうと判断して、子供たちにはこのことを伏せた。
遅ればせながら島にも占領政策が浸透してきて、警察官の新屋敷静男(田中茂弘)は共和国設立の動きを察知した進駐軍の手先となって、これを阻止しようと動き回る。ダンも事情が分かってくるにつけ、英文たちに警告をはじめるが聞き入れない。ところが、進駐軍の意向も働いて、むしろ住民のあいだで意見が分かれ、比嘉長輝や英文たちは少数派として追いつめられる。共和国構想は一敗地にまみえるのだ。
そうこうしているうちに、英文が連合国から戦犯として召喚されるという事態を迎える。沖縄本島で米国軍捕虜の始末に困り、これを刺殺した嫌疑をかけられた。新兵の度胸試しで無理やりそういうことが行われていたことは知られている。英文は、それをやらされたひとりとして訴追されることになったのだ。かくて英文は巣鴨プリズンに収監される。ダンによりその様子は伝えられるが、しばらくして死刑の判決が出たと知らされる。五十年もしたら放っておいても死ぬとナベが嘆いたのはこの時である。しかし、まもなくダンが英文は判決が出た後減刑されたという事実を伝えにやって来る。
共和国の構想といっても、財源はどうするか、政府をどう構成するかなど具体的な話がまったく出てこないところを見ると、果たして本気だったのか怪しいのではないかと思ってしまう。一瞬訪れた無風状態の中で牧歌的な夢を見ていたのではなかろうか。むしろ、漁船を持っている喜舎場アサコが、漁をするよりは密輸まがいの物資を運んで大もうけをするエピソードや、やはり無政府状態になった台湾と八重山の間で商売する林国明の存在の方に、この時代の権力も支配もない自由な気分が溢れていて、共和国のイメージにリアリティを与えている。
特攻隊の生き残り、桑原収(塩山誠司)が島に現れ、かくまわれることになるが、これは劇に緊張感を演出する、といっても唐突で主筋に関わりが薄い。ただし、ナベと林国明、ダンとキクノに並んでタマとの恋愛模様を描いて花を添えたともいえる。復員した桑原が商社マンとして再び島を訪れる終幕もほほ笑ましい。こういう脇の話を用意するところなど、劇の作りはさすがにうまい。
舞台美術は、演出の佐藤信が兼任している。佐藤はこのところ自分の演出では自分が装置を考えることにしているようだが、それには少し疑問を感じている。この間見た再演の「夜明けのマンハッタン」でもこの劇でも、全体はともかく細部の処理が美しくない。寸法を間違えているのではないかとか、位置関係が正しくないのではないかと感じることが多い。サカナヤーの店というものがどんな様子か知らないのだが、この舞台ではおよそ南国らしからぬ白い薄っぺらな板張りの壁で窓もなく風通しもすこぶる悪いのではないかと思わせる。料亭のようなものならそういう豪奢なところはみじんもない。かといって、客に料理を出す雰囲気でもない。八重山なのだから、それらしい植栽があってもおかしくないのにまるで歌舞伎の書き割り見たいなそっけない舞台だった。こんなみすぼらしい舞台しか出来ないなら専門家にまかせた方がいいのではないか?
ところで最初に、一体斉藤憐の問題意識はどうなっているのかと書いた。「八重山共和国」とは確かに目の付け所は面白かったが、占領軍に押しつぶされて終ったのは権力による庶民の弾圧ではないかというのが彼の主張である。一般的に独立自尊の精神を封殺する権力という図式を表現するのに格好の材料と思ったのだろう。しかし、現代の観客は必ずしも彼と「怒り」を共有しない。強いものが弱いものを支配するのは間違っているという考えで、劇中様々の歴史観を披瀝したことを最初に示しておいたが、まだある。登場する台湾人にかこつけて、台湾五十年の支配があったから戦後の三国人などという彼らにとってははなはだ迷惑な扱いがあったという。また、平和に暮らしていた琉球の人々を薩摩がやってきて支配した。自然の恵みの中でまどろんでいたハワイに、あるとき米国が乗り込んできて自分の国にした。他国に踏み入って支配しようとするのはいつの時代もたしかにいいこととはいえない。しかし、それで歴史を裁こうとしたら、人類の歴史はすべて悪いことだらけになってしまう。十五世紀からスペインが南米に対して「ミッション」と称してやった行為はどう裁かれるべきなのか?真面目に考えたら怒りで狂い死にするほどであろう。ただし、そう見えるのは現代に立って過去を見ているからに他ならない。こんな単純なことが斉藤憐には分からないらしい。その理由は彼の中で「大きな物語」がいまだに生きているからなのだ。権力に弾圧される庶民を描けば条件反射的に観客が反応するといまだに思い込んでいる。「大きな物語」とは権力の弾圧に耐えて、いつかそれをくつがえして自分たちの理想の社会を作り出そうという壮大な構想を持つ物語である。このあいだ「アルゴス坂の白い家」(2007年9月、新国立劇場)劇評でも書いたが、この世界全体の共通語ともいうべき「大きな物語」がソ連や東欧諸国の体制崩壊とともに崩れ去って、人々は個別の現実に即した「小さな物語」に閉じこもってしまっているのが今日のポストモダン社会なのである。にもかかわらず斉藤憐は、権力対庶民とか善と悪、資本対労働とか大きく問題を二つの対立概念に還元してしまう「大きな物語」がまだ有効だと思い込んでいる。そういう単純な物差しで今目の前で起きていることを判断するには、あまりにも問題が複雑なことを現代の観客は既に知っている。こういう現実をまともに捉えることが出来ないから、半世紀も前の出来事をほじくり返して、こぶしを上げよと迫るのである。
歴史の勉強をしようというのなら教科書として適当な劇ではあったが、時代錯誤な主張にははなはだ戸惑いを覚えてしまうものだった。
大塚道子は若い頃は表情に切れ味の鋭そうな知性が表れていて、張りつめた感じがしたものだった。この劇を見ると、年を取って少しとぼけた味が出てきたと思う。台湾人の林国明となにかあったような気配だったが、その関係をさりげなく感じさせるなど達者なところを随所に見せた。中野誠也は久し振りにみたと思う。四十年前に近所に住んでいたことがあったが、見かけはあまり変っていない。しかし、滑舌というよりは発語に力みがあってがせりふが聞き辛くなってしまった。それに比べると若手の存在感が今一つである。斉藤憐の作品を佐藤信の演出でやっているようでは、俳優座の前途も多難だな。
題名: |
豚と真珠湾/幻の八重山協和国 |
観劇日: |
07/10/5 |
劇場: |
俳優座劇場 |
主催: |
俳優座 |
期間: |
2007年10月4日〜14日 |
作: |
斉藤憐 |
演出: |
佐藤信 |
美術: |
佐藤信 |
照明: |
中村透 |
衣装: |
黒尾芳昭 |
音楽・音響: |
若生昌 ・田村悳 |
出演者: |
大塚道子 阿部百合子 長浜奈津子 生原麻友美 小澤英恵 可知靖之 中野誠也 塩山誠司 田中茂弘 西川竜太郎 田中壮太郎 松島正芳 林宏和 |
