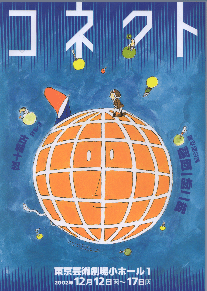
|
題名: |
「コネクト」 |
|
観劇日: |
02/12/13 |
|
劇場: |
;東京芸術劇場 |
|
主催: |
劇団一跡二跳 |
|
期間: |
2002年12月12日〜17日 |
|
作: |
古城十忍 |
|
演出: |
古城十忍 |
|
美術: |
礒田央 |
|
照明: |
礒野眞也 |
|
衣装: |
豊田まゆみ |
|
音楽・音響: |
黒沢靖博 |
|
出演者: |
奥村洋治 小林立樹 山下夕佳 重藤良紹 関谷美香子 福留律子 他 |
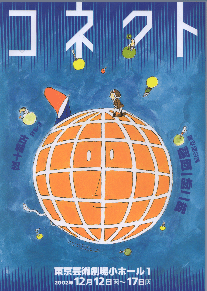
「コネクト」
遊園地のブランコや砂場の隣によくある、よじ登ったり、回したりして幼児が遊ぶ球形の遊具とおぼしきものが舞台中央にある。その前にはダイニングテーブルと椅子。本やティッシュ、珈琲メーカー、その他の小道具は、なぜか手の届かない高さにつるされた三つの棚にわけて置かれている。あと一つ、時計が描かれた風船が空中高く浮かんでいるという、どちらかといえばシンプルな舞台である。
冒頭、大勢の出演者がそろって奇妙なダンスをはじめる。足をあげ、二度ほど前にふって下ろし、そしてまわる。ほぼその繰り返しで、顔は無表情、無言、だんだんと前に迫ってくるような気がする。それはとても気障りで印象的な動作で、その意味では、振り付けはとりあえず成功しているといえるだろう。 いったいこの踊りは何を意味しているのか?僕は懸命に考えていた。しかし、とうとう、なんの手がかりもつかめないまま、彼らは溶暗の中に消えてしまった。
次に、暗やみから中年のサラリーマンが歩いてきて、ダイニングテーブルの前に座る。酔っぱらっているらしい。動き回って、ぶつくさ言って、仕舞には突っ伏して寝てしまったようだ。この男は一体なんだ。夜中に酔って帰ってきて誰も出てこないところをみると一人暮らしなのか?それともこれは幻想なのか、象徴的な表現なのか? このあたりから僕は、思考能力が衰えてきて、目の前で展開されている状況をまともに考えることができなくなってしまった。
そんな霞がかかった様な状態で、ようやく僕が理解したのは、次のような設定である。 中年男はこの家のお父さんで、この父親は、ここ四五年、記憶喪失だったらしい。24才になる息子は就職したがまもなく会社を辞めて、自宅の二階の自室にこもってしまっている。この息子は、時々やってやってくる引きこもりカウンセラーと話をする以外、インターネットのチャットを通じて、唯一社会と「コネクト」している。妹は家を出て暮らしているが、たまに帰ってくる。そしていまは妊娠している。母親(なかなかうまい役者である。)は家の外で何か活動的にやっているらしい。しかし、家族のことについては全く能天気である。
引きこもりの息子は、チャットで、「レゾンデートル」さんとか「アイデンティティ」さん「匿名」さんとか呼びあって、同じ境遇の仲間と意見交換をしている。この場面は、球体の遊具(二階の閉じこもりの部屋を表現している)のなかにいる息子を中心に、原色系の衣装をまとったチャットの相手たちが現れ、バーチャルな世界を実際に展開してみせて、現実である家族とのシーンとわけている。(この次元の違いを、照明や役者の位置によってもっと画然とさせたほうが、よりわかりやすかった。) ここでは、主として引きこもりの社会病理に関する議論が飛び交う。チャット上のニックネームに託した作者の意図が読み取れる。
一方、他の家族については、娘の結婚妊娠も知らなかった父親と、娘の出産の心配に気がつかない母親というように、バラバラの思いを抱いているようで、僕らにはこの家族の一種やり切れなさが伝わってくる。 このように、「引きこもり」の息子とそれを取り巻く「バーチャルな場」、そしてバラバラの「家族」という三つの軸をどのようにまとめあげるのかがこの芝居のテーマだと気がつくのだが、正直な話、最後のどんでん返しをみるまでは、僕にはその論理構造がさっぱりわからなかった。
息子と父親が実はバーチャルな世界でつながっていたというラストシーンにしても、驚きはあっても「あざやかな結末」というには少し違うような気がしている。 ではなぜ僕は最後のシーンを見て、この芝居の構造を理解で来たのか? それは、作者がまさにこのラストを見せたかったために、この芝居を書き始めたのだと気がついたからだ。
作者はバーチャルリアリティの可能性を明るく信じているように思える。心を閉ざした息子と家族から記憶喪失という形で取り残された父親が、唯一本音を語れる場として偶然ふたりともインターネットを選んだ。途中でバーチャルな世界に登場する酔っ払いは、実は父親だった。お互いの存在を理解しあったと感じた相手は結局、家族だったのだ。 いうまでもなく、こういう結論を導きだすための伏線が、この芝居の構造になっている。
そう考えると、かなりご都合主義のところがあって、その一つの典型は、父親の記憶喪失である。父親の存在を書き込めば、バーチャルな世界というよりは家族崩壊のテーマが立ってくるので、不在、あるいは希薄な存在にとどめたかったのであろう。あるいは、息子の引きこもりの原因を父親との関係で説明する必要が生じる煩わしさを考えたのかもしれない。いずれにしても、記憶喪失という設定は、誰が見ても現実味に欠けるし、いい加減といえばいえる。
もう一つは、「星の王子様」である。突然なぜか「星の王子様」が引用され、長々とこの物語が説明される。そして、まるで「この話はわかっていただいたと思うので、これからはそれを前提にします。」といわんばかりに、このお話とバーチャルな世界の人々がなぜか、いつの間にか同化してしまう。それどころか、息子のカウンセラーのひとり〈現実世界の存在〉が「星の王子様」に登場する悪い動物になってしまうのである。ラストシーンに導く重要なプロットであるが、何しろ唐突に現れるものだから、ご都合主義といわれても仕方がないのではないか。
引用は構わないが、こういう形で利用するには、「要約」がよほどうまくいかないと、そのあとの説得力がなくなる。この童話(とあえていう)は、さまざまの寓意に満ちていて、一筋縄ではいかないとサン=テクジュペリ本人がいっているし、それが文学者の間の定説である。この場合、息子の口から要約はされるのだが、、単に作者自身の解釈を聞かされることになる。しかも、かなり理屈ぽいから注意して聞いていても残念ながら納得できたとはいえそうもない。(このあたりの演出は不親切きわまりない。) かくて、観客は取り残されて、あとに続く大騒ぎをぼう然として眺めなくてはならないのだ。
とここまで書いて、この劇団は、これまでも、童話を劇中に取り上げて〈たとえば「青い鳥」〉全体を構成するというやり方をしてきたことを知った。それならば、最初に「星の王子様」を下敷きにしていることを知らせるほうが親切であった。
ご都合主義のほかにもいくつか感じるところがあったので、指摘しておこう。 まず、息子が、なぜいったん就職して、それから何がきっかけで会社をやめ、引きこもったのか?説明がないことである。明確な理由などないかも知れないが、状況説明がないと、この息子のこの芝居における「レゾンデートル」がはっきりしない。 もっとはっきり言えば、「引きこもりは、本人にとっては個別の理由があってのことであり、精神医学的にはアイデンティティクライシスの一種であり、社会病理学的には高度に発達した資本主義社会における新たな疎外の問題だと言える。」と、いってしまえば身もふたもないが、息子の人物造形はこのようなステレオタイプの視点から出ていない。
父親は、記憶喪失にもかかわらず会社(あるいはどこかに)にかばんをもって出かけ酔っぱらって帰ってくるのはなぜか?その間の生活はどうなっていたのか?なんの説明もない。 こういうことが重なって、極めて生活感のない、観念的な芝居という印象を受けるのである。
また、バーチャルリアリティについても、作者には考え違いがあるのではないかと思っている。 チャット上のニックネームに現れているように、ここでの存在はノミナル〈唯名的〉なものである。したがって、自分のアイデンティティは傷つけられることもなければ、浸潤されることもない。いつでも身を引くことができる安全な場所だ。
しかし、現実は匿名で過ごすことはできない。 バーチャルな世界で、実は息子と父親がつながっていたというのは、このノミナルな関係でのことであり、現実の父と子がつながっていたわけではない。 ここで描かれたように、親と子がインターネットを通じて理解しあえたとしても、実際に、息子は引きこもりから立ち直れるのか、親は、家族のために父親らしく振る舞えるのかという問題はまた別の話である。
僕が、あざやかな結末と感じなかったのは、こんなことでは何も解決しないという思いがあったからだ。 作者のインターネット社会の未来に対する明るい見通しが少し気掛かりである。
