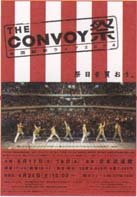 }
}|
題名: |
ザコンボイ祭り04 |
|
観劇日: |
04/8/18 |
|
劇場: |
武道館 |
|
主催: |
ザ・コンボイショウ |
|
期間: |
2004年6月26日 〜9月5日全国 |
|
作: |
構成:今村ねずみ |
|
演出: |
今村ねずみ |
|
美術: |
堀尾幸男 |
|
照明: |
豊島信幸 |
|
衣装: |
高橋智加江 |
|
音楽・音響: |
宮永治郎 |
|
出演者: |
今村ねずみ 瀬下尚人 石坂勇 右近良之 徳永邦治 館形比呂 橋本拓也 黒須洋壬 |
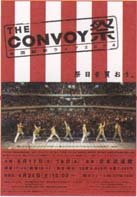 }
}
「ザ・コンボイ祭り04」
武道館の明かりが落ち薄暗いブルーのサスペンションが差し込むステージに大きなオブジェが浮かび上がるとやがて声が、今村ねずみの声だけがどこからか降ってくる。
「じつぞん(実存)」といって言葉が途切れる。僕は耳を疑った。お祭りの幕開けにはそぐわない哲学用語である。「自分が生きているという実感・・・」と続くモノローグはザ・コンボイショウがたどってきた長い道のりを自省し現在を確かめるためにおかれた祈りの時間のようだ。彼らは祭りを始める前に、これまでを支えてきた人々に、あるいは僥倖をもたらした神々に感謝の気持ちを捧げるように静かに言葉を重ねる。
1986年5月、横浜上大岡、滝沢化粧品店二階の喫茶店で旗揚げしたザ・コンボイショウ。観客動員5人、出演者のほうが多かったという。このときは全員二十歳台だった。あれから二十年近くたち、メンバーのほとんどは不惑を超えた。
この祭りのツアーには武道館(二日間)だけで一万四千人が集まった。発売と同時に売りきれる貴重なチケットを手に入れた幸運の人々である。僕らの隣には髪をきりりと結い上げてねじり鉢巻きに祭り袢纏を羽織ったの女の子が数人陣取っていた。ペンライトをかざす女性達の年齢は母娘以上に離れている。まるで自分達の祝祭のようにその顔は喜びに輝いて見える。
「これはみんなの祭りだ!」とだれかが言った。観客は素直に言葉通り受け止めて楽しんでいるように思えた。
開幕からもっとも得意なダンスそして和太鼓、タップと続いて後半はほとんど歌で通した。「雲のゆくへ」のようにストーリー性があって激しいパフォーマンスが加わるというものではなく、もっと気軽な、歌によってメッセージを手渡すショウに仕立てられている。
歌は、何しろ武道館だから、歌詞は大音響のために聞き取れない、声はわれるで評価しようがない。これは祭りなのだと思えばそれでいいのかもしれない。出演者たちがあの広い客席を駆け足で一周するというサービスにファンは間近に見られることであるいはタッチできたといって大喜びだった。
この人気の要因は言うまでもなく彼らのパフォーマンスの質の高さ、オリジナリティにあるのだが、実はそのキャラクターによるところも大きいのではないかと思う。
今村ねずみはステージでこう語った。
「ショウが終わると腹が減っていることに気がつく。家に帰る前に渋谷の富士そばで一杯食べて、サウナに寄って疲れをとる・・・」
ほんとうかどうかはともかく、この言葉が違和感なく聞こえるところが彼のキャラクターなのだ。
また、パンフレットの「つれづれなるままご挨拶」では次のような書き出しで真情を明らかにしている。
「今年開けてから夜は本も読まず、映画も見ず、CDを買ったのは3枚、レンタルビデオで借りたのは3本、芝居は2本、あまり人にも会うこともなく、別に避けているのではなく、祭りに向けて『何かしなくては・・・』と感じつつ、そんな使命感も持たずに実際過ごしていた。・・・だけど僕は動いていた。何かアイディアやネタ探しのために動いていたのではなく、自分に向かって動いていたような気がする。・・・」
出演者それぞれもまたパンフレットの中で発言している。これはインタビューしたものをライターの田中あずさが記事にまとめた文章だと思う。トーンは一貫しているが読んでいてやや隔靴掻痒のところがあると感じたが、紹介しよう。
石塚勇「・・・自分を突き詰めて舞台に集中していても、どこかで客観的にみている自分がいる。皆で舞台に立っていても、ひとりをずっしりと感じることがある。助け合うことはあっても、舞台に立つ自分を作り上げるのは、結局個人ですから。・・・勿論余裕なんてない。毎日必死ですよ。でも、ただ突き進むっていうんじゃなく、楽しみながら進めるようになったというか。若いころは、大勢の人や都会の中にいても、いまよりもっと孤独でした。・・・」
橋本拓也「2年間コンボイを離れたことは、僕にとっての反逆でもありました。離れて、外からコンボイショウをみたとき、『コンボイショウはすごい。でも誰かが突き破らないと、先に行かないだろうな』と思ったんです。・・・ずっと都会で育った中で、個性や強さって何だろうと考えたとき、"周りと共存しながら、きらりと光る反逆性を持つ"ことだと思いますね。・・・最近『好感が持てる』とか『共感できる』ことって、すごく薄っぺらに見えるんです。そういうものを軽々しく提供する大人たちに、すごく腹が立つ。『よく考えろよ』って。都会の人たちって、皆『右向け右』な気がする。そういうのが、本当にイヤなんです。・・・」
右近良之「去年くらいから、自分の存在理由とか生きていく意味とか、死に逝く事とか、ずっと考えてきたんです。その答えが最近わかりました。大袈裟なことではないんだけど、自分の中で、はっきりとした答えが出たんです。答えが出たことで、以前は頭ではわかっていても日々の生活の中で自然にできなかった事とかが、少しづつだけどスッと出来るようになってきました。タクヤが作った"雲のゆくえ"の歌詞に『いろいろなことがわかるんだ』って言う下りがあるんですけど、その言葉がいまの気持ちと重なるんです。以前に比べて、ほんの少しだけど、周りのこと、自分のことがわかるようになってきました。・・・」
徳永邦治「この世界で生きていく不安や孤独は、いつでもつきまといますよ。だからこそ、一歩ひいた視点から自分を見る、第三者の俺として『まんざらじゃないぜ』『お前、結構やってるよ』って自分に言いたいですね。」
瀬下尚人「ねずみさんが『曲づくりは全部感覚でやった』っていっていたんです。・・・曲を聴くと感じるのが『何故コンボイを続けているんだろう』『どうしてここにいるんだろう』って言う葛藤のような言葉がちりばめられていること。でもそれがネガティブなイメージではなく『それでも続けていこう、やってやろう』って言う強い筋が全体に通っているんです。・・・」
黒須洋壬「コンボイが結成されてから20年近く経ちますが、その間、自分がいた7〜8年というのは、8人のメンバーが一番濃く、密につきあっていた時期です。コンボイを出たり入ったり、いろいろなストーリーを共有しながら皆が関わっていた。そんな時期を一緒に過ごした8人だからこそ、ねずみさんのメッセージとそれぞれの想いとがリンクするんじゃないかな。・・・」
館形比呂「たくさんの価値観がある世の中で生きるとき、誰もが孤独を感じるシーンってあると思うんです。僕も、年末で周りが慌ただしいときなんかは妙に孤独な気分になってしまいますが・・・。孤独を感じたり寂しい気持ちになるからこそ頑張ろうと思うことってありますよね。それを積み重ねて強くなった人は、寄り添ったときの暖かさも人一倍感じていけるような気がします。・・・」
今村ねずみ「・・・東京に来て僕は、"ねずみ"と呼ばれるようになり、いまのメンバーと、この東京で知りあいました。別に僕らは、街頭でストリートダンサーをやっていたわけでもない。街角で大声を出して歌っていたわけでもない。いわゆるこの世界にいて、何かを主張しまくって生きてきたわけでもない。そんな僕らがコンボイをはじめた。その偶然の出会いが、続けていくうちに必然的な意味を持ちはじめたんです。・・・」
彼らは今村の影響を強く受けているに違いないが、自分達の来し方行く末をよく考えている。それは現在の成功が決してハッピーな道のりばかりでなかったからであろう。だからこそこれほどまでにストイックになれるのである。テレビ画面に現れる空虚なエンターティメントと称するものとは無縁に、彼らは自分達がやりたいこと、表現すべきものを考えに考え抜いて舞台にあげる。観客は彼らの実存を掛けて創造した世界に強い共感を覚えるのである。
今村はいまの自分を「夢みるオヤジ」だと表現した。
「ねずみさんは四捨五入するともう五十歳だ。」と若いタクヤがからかった。実際は1958年生まれだからまだ四十歳台である。しかし、彼らが年齢のことを気にし出しているように感じるのは確かだ。
この先彼らがどうなるかは誰にもわからない。ただ、この世界第一級のエンターティメントをいつまでもみたいという願いだけは届いているに違いない。
それにしても「実存」。
山崎正和が「柔らかい個人主義の誕生」を書いて久しいが、日本人の心の中に、西欧的なものとは関係なく我が国特有の『個人』(他者との相対的関係性において)が根づきつつあるのではないか?そういう事が想起された言葉であった。(8/30/04)

Since
Jan. 2003