

|
題名: |
クリスマスキャロル |
|
観劇日: |
02/12/17 |
|
劇場: |
三百人劇場 |
|
主催: |
劇団昴 |
|
期間: |
2002年12月17日〜25日 |
|
作: |
チャールズ・ディケンズ |
|
翻訳: |
河田園子・菊池准 |
|
演出: |
河田園子 |
|
美術: |
加藤ちか |
|
照明: |
石島奈津子 |
|
衣装: |
岩倉めぐみ
|
|
音楽: |
上田亨 |
|
出演者: |
金尾哲男 田中正彦 北川勝博
宮本充 西村武純 田島康成 金沢君光 奥田隆仁 竹村淑子 大坂史子 田村真紀 矢島祐果 新喜ゆかり 喜田ゆかり |
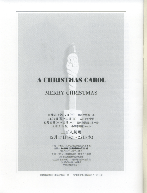
「クリスマスキャロル」毎年恒例の公演だということだが、何度かみているというつれあいにさそわれていい年をしてと思ったが、はじめてみた。 音楽劇に仕上げてあって、担当した上田亨は手慣れた様子でこの話に、曲想や演奏、タイミングという点で過不足のない、いい曲を書いていた。 問題は脚本で、全体に甘い。 スクルージが冷酷でけちで、不信心のひねくれもの、情というものをいっさい解さないという男であればあるほど、この話は面白くなる。つまり、最初に、弱い者いじめを徹底的にみせて観客の憤激をかき立て、精霊に懲らしめられる場面で観客の怒りを解き放ち、最後の改心によって観るものがカタルシス得るという構造である。 この点で、河田園子の脚本は、スクルージに手心を加えてしまった。
前半の描き方は、スクルージの悪意に焦点がなければならなかったが、いじめられているものが、家族愛によって耐えている様子の方が強調されているように見えた。ここは踏ん張って、スクルージがいかに悪いやつかを徹底的に描くべきだった。 金尾哲夫のスクルージも、意地の悪さや吝嗇ぶりを示すのに身体全体を使うよりは、主として顔の表情だけで表現しようとしたために悪役ぶりが薄められて、脚本の甘さを助長した。子供が見ていたら、憎悪が湧くというよりは少しこわい学校の先生ぐらいにしか見えないのではないか。僕にも人の悪い上司が部下をにらみつけている程度にしか感じられなかった。
この話をひとつの寓話とみなして脚色するなら書くものの自由である。しかし、河田園子がディケンズの「クリスマスキャロル」を描こうとしたのなら、決定的に見逃したものがある。 それは宗教的な背景である。「神は見ている。」という怖さを日本人の感覚では、理解しにくいと思うが、この「恐れ」(=超越的な存在に対する)が物語の土台を作り、通奏低音のように存在していることを河田はおそらくほとんど意識していなかった。(そこを外すと、単なる勧善懲悪のお話になってしまう。) その結果、人間の悪意と不信心の象徴と「神」〈新教における〉との対峙という深刻な課題としてスクルージをとらえることが出来なかったために、この主人公が単なる意地悪人間のように描かれてよしとしたのではないか?僕はそうにらんでいる。
こういう認識の甘さがあったので、各プロットの描き方に締まりが無く、全体にお子様向けのお手軽な印象を与えてしまった。 この印象は美術にも表れていた。加藤ちかは、大きなクリスマスツリーを舞台中央において、背景の板に開けた同じ形の空間を通して、必要に応じて出し入れしたが、この空間がメルヘンというよりは便宜的で安っぽい漫画のように見えた。街の様子が雑然としているのは、ねらいだったかもしれない。しかし、その主な原因は、パステルカラー調の色使いにあって、褪めたような色の装置や小道具が作り物であることと寓話性を強調したことが、かえって舞台全体のビジュアルコンセプトを焦点ぼけさせたところにあった。衣装も同じような発想にみえたのは、河田演出の注文だったのであろう。
こういう舞台美術の表現感覚は、才能もあるが、体験すること、多くの舞台を見ることで養われるものだと僕は思っている。同じメルヘンタッチでも、色や形の採用によって暖かくもシャープにもなりうる。研究してもらいたい。 それにしても北川勝博は怪優である。どんな役でもやってのけるが、いつでも北川勝博をさらけだしている。今度の舞台も何役やったか数えてなかったがずうずうしいくらいの存在感は、いったい特やら損やらわからない。もっと目を大きく開いて演ったら、「特」の方に少し傾くかもしれないと思うが。 ついでによけいなことだが少しダイエットをしたらどうか。
オルガン弾きの新喜ゆかりがよくやっていたと思ったら初舞台とのこと、今後も自信をもってやってほしい。 田村真紀の精霊ぶりもよかった。 河田園子は、今度の舞台は「家族」をテーマにしようと考えたようだが、その演出意図はよく出ていたと思う。その点では満足していいと思う。 しかし、観客の方から眺めると、ドラマとして面白いことが第一義的関心である。スクルージが悪の権化で、それを懲らしめ改心させるというドラマの起伏が激しければ激しいほど面白いし、その振幅がリアリティを欠くほど大きくなったときに観客は引いてしまう。この物語の場合、その臨界点を押さえるのがディケンズの時代の宗教的な倫理である。 こうしたことを十分に吟味し立体的なものとして構築したうえで、その背後に「家族」というテーマが透けて見えてくるようにつくれたら観客の満足度はもっと上がっただろう。 何しろ、このところ会社人間だったことをやめたお父さん達が家庭に帰ってきて、日本中が「家族って何だったんだっけ?」と考えはじめている。 河田の関心は、問題意識という程のものではないが、ずばり時代の核心をついていて、この人の演出家としての感度のよさを間違いなく示している。 (2/12/03)