

|
題名: |
リタの教育 |
|
観劇日: |
05/12/9 |
|
劇場: |
下北沢OFF/OFFシアター |
|
主催: |
佐藤正隆事務所 |
|
期間: |
2005年12月5日〜12月25日 |
|
作: |
ウイリー・ラッセル |
|
翻訳: |
吉岩 正晴・芦沢 みどり |
|
演出: |
高瀬久男 |
|
美術: |
倉本政典 |
|
照明: |
奥畑康夫 |
|
衣装: |
宮本宣子
|
|
音楽: |
山北史郎 |
|
出演者:
|
有川 博 富本牧子
|
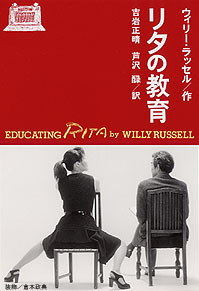
「リタの教育」
小劇場でロングランという実績のある舞台の再演である。大学の社会人向け講座にやってきた美容師と教授の二人芝居で、『マイ・フェア・レディ』の現代版を思わせる内容だ。
それにしても英国人は、労働者階級の女を中産階級あるいは貴族の男が教育して成功するというお話が好きである。いやひょっとしたら、英国だけではないかも知れない。ただし、そういう階級社会がある国は他に見当たらない。(フランスもドイツも隠れていて見えにくいが)これが男と女、逆の場合はこの後で観た『セパレート・テーブル』(自転車キンクリート公演)のように悲惨なことになる。男が誇りを傷つけられるとか何とか屈折してしまうからだ。いずれにしても、イギリスがそういう社会だということを念頭において見ないと心の機微、ディテールが分かりにくいかも知れない。
この芝居は、構成が非常にしっかりしていて、いかにも英国の戯曲らしい。それも人気の因になっていると僕は思う。構成はいいが、最後は気に入らなかった。それはあとにしよう。
1980年の初演が大ヒットして、イギリス中が「Educating RITA」を知った。翻訳した芦沢みどりがいっている。イングランドのある町の成人教育講座の白い送迎バンにピンクの文字で劇のタイトルが書いてあるそうだ。ヒットにあやかったものだろうが、向こうの自治体はなかなか粋なことをやるものである。
下北沢駅前のビルの二階には入り口がひとつで同じように狭い劇場が二つある。そのうちの一つに入ると階段状の客席が70あまり、半分は舞台が占めている。上手にドアがあり本棚が壁一面を覆っている。正面に小さな出窓、前にソファとティテーブル。下手手前には古ぼけた机と椅子が置いてある。いかにも田舎町の大学の煙草の煙で煤けたような文学部教授の部屋である。倉本政典の装置は劇場の狭さに合わせてこじんまりとリアルで、緯度の高い英国の日差しや外の寒々しい風景まで感じさせて雰囲気がある。
教授のフランク(有川博)は一杯引っかけて講義するほどの酒飲みでしかも気難しくかんしゃく持ちである。
明かりが入るとフランクが如何にもそれらしい人物像をスケッチしたあと、ドアがノックされて、リタ(富本牧子)が勢い込んで入ってくる。フランクは何事かと驚くが、社会人講座をいやいや引き受けさせられたことを思い出した。とんでもない(下層の)言葉遣いとがさつな態度に文学どころではないと見て取ったフランクは、自分には教えることが出来ないと断る。ところが、リタはもう少しましな人生にしたいから英文学を学ぶのだといって引き下がろうとしない。リタの正直で率直な物言いに興味を覚えたクランクは、ついに引き受けることにする。
リタには、読むべき小説が言い渡され、講座はそれについて感想と批評を述べ、さらに議論と指導という方法で行われる。
最初の講座では個人的で主観的な感想は慎み、批評すなわちクリティークという態度で臨むべきだと教えられる。それには、誰かが書いた批評を参照し引用することも必要だとフランクはいう。なるほど、Literature とはそういうものか。久しく小説を読んでいなかったから忘れていた。
ある日深刻な顔で現れたリタが、フォースター(「眺めのいい部屋」「インドへの道」の作者)の「ハワーズ・エンド」を読んでいるうち「我々はこの話について貧乏人には用がない。」という記述に出くわして先が読めなくなったと訴える。自分が貧乏人だからというのである。フランクは苦笑しながら、それは重要なことではない、むしろ主人公がいう「オンリー・コネクト」つまり「関係性こそが大事なのだ」という言葉に注目すべきだというのである。違う価値観、思想あるいは文化をその関係性で見ていくという態度、それが「オンリー・コネクト」であり、文学にも人生にもあてはまることだというのである。丁寧な解説でどうやらリタは小説と実人生との接点を理解したようだ。
モームや毒舌と皮肉で有名なバーナード・ショー、才人オスカーワイルド、女流作家ヴァージニア・ウルフ、そして詩人のT・Sエリオット、ディラン・トマス、イェーツなどが取り上げられ、英文学専攻の学生ならずとも、僕までフランクの個人教授をうらやましく思う。
また、この戯曲が発表された七十年代初めの風俗も取り入れられていて、ファラ・フォーセット・メジャーズの名前が出てきたのには苦笑させられた。美容師であるリタが、お客に似合いもしないファラのようなスタイルを頼まれて困ったというエピソードである。米国のテレビシリーズ「チャーリーズ・エンジェルズ」のヒロインで、ブロンドのよくカールした狼ヘアーが魅力だった。イギリスでも、うけたのだ。すぐに映画に進出するほどヒットしたが、イメージが固まってしまって、芝居が恐ろしく下手だったからあっという間にブームは去った。
他にTVネタでアル・カポネ、エリオット・ネス、カムバックしたフランク・シナトラの話などがちりばめられていて世代の違い、階層の違いが表わされる。
「マクベス」を劇場で観たと聞いて、自分の生徒の成長ぶりに喜んだフランクが感想を聞くと、あれは少し変だという。三人の魔女に破滅すると予言されて、その通りになる馬鹿はいないというのである。それに対してフランクは「いや、それが悲劇というものなのだ。」と説明する。ロメオもジュリエットと出会う場面で、何か恐ろしいことが起きると感じている。ジュリアス・シーザーも自分の運命を予感していた。つまり、主人公が抗いがたい運命の糸に操られ、やがて悲しむべき結末を迎えるように描かれているのが悲劇だというのである。「いいかいリタ、誰かが交通事故で死ぬというのは悲しい出来事ではあるが、それは偶然起きたことで、悲劇とはいわないのだ。」その物語の一部始終を見終わって、私たち観客はカタルシス(感情の浄化)を覚えることが出来る。これはアリストテレスの「詩学」ではないか。なるほど、このようにして「悲劇」を論ずるものかと、感心した。リタも多分感心したと思う。
この当たりから、フランクは自分の学生からは受けたことのない教えることの喜びを感じており、リタもまたより多く学ぶ意欲をかき立てられている。
しかし、リタの家庭では運命の歯車が狂い始めている。夫が嫉妬しているのだ。おそらく妻の向学心と、明らかに、会ったこともない教授に対して。
フランクはそれを察知して、夫ともどもわが家のティパーティに招待しようと提案する。リタは快諾する。が、その日になって連絡もなしに彼女は現れなかった。リタによると、出かけようとして夫とケンカになり、ようやく一人で家を出たのはいいが道に迷ってだいぶ遅れてしまった。家の前まで来ると、窓越しにフランク夫妻とその友人たちが談笑しているのが見えた。この人たちと対等に話すことは出来ないと感じ、惨めな気持ちでその場を去ったというのだ。
次第に夫の暴力沙汰がエスカレートしていた。ある日、リタはトランクをもって部屋に現れた。ついに別居を決心したのだ。修復は不能らしい。リタが、社会人講座をやめる気が無いからだ。友人の部屋に転がり込むことになった。
季節は移ろい、あるときにはリタが部屋に入るなり、キャンパスの芝生の上で学生たち何人かと議論してきたという。そのうちの一人に注目しているらしいが、対等に渡り合ったという自信がみなぎっていた。
ところで、フランクが大酒を飲んで、少し屈折していることが気になっていたリタが過去に何かあったのではないかとときどき詮索する。その度にはぐらかされていたのだが、どうやらフランクは若い頃創作をしていたらしい。詩集も発表していた。ある日何もいわずに二冊の詩集を手渡して、感想を書くよう求める。リタは素晴らしいと絶賛するが、何故かフランクは機嫌が悪い。詩人であることあるいは小説を書くことに挫折した時期があったのだろう。文学研究者としての道を選んだことに納得出来ないものを感じているのかも知れない。その挫折感、喪失感が浮き上がってくるたびに酒でごまかしてきたのではないか。
そしてこの悪癖がついに彼の運命を変える事態を引き起こす。学生の前で、講義の途中酔っぱらったあげく、教壇から転げ落ちたのだ。
処分は、オーストラリアの姉妹校に二年間出講という比較的軽いもので済んだ。しかし、教え子だった妻は一緒に行かないという。教壇で泥酔するという行為にあきれ果てたのだろう。
夕暮れ時、荷物をまとめようと段ボール箱を運び込み、棚から本を詰め込んでいる。すると本のうしろから夥しい酒瓶が現れる。鬱屈した日々の挫折感やら喪失感が飲み干した空き瓶である。そこへリタが入ってきてパリへ行くかも知れないなどと言い出す。若い学生の誘いがあるらしい。
フランクは、とりとめない話を続けるが、ついにおずおずと申し出る。「一緒にオーストラリアに行かないか?」フランクは、いつの間にかリタに恋していたのである。窓から差す夕日を見ながら二人は無言で立っている。
英国文学を渉猟しながら、若い向上心旺盛な女の生活を浮き彫りにし、それに惹かれて行く老教授の物語は、柄が大きいとは決していえないが心温まる佳品として十分に面白い。小劇場ロングランはこの芝居に対する首肯ける評価である。
ただ、僕としては最初に書いたように、締めくくりが気に入らない。オーストラリアに誘うのはいい。しかし、ここで、あっさりとリタが承知してしまうのでは大甘の結末だと思う。しかし、あいまいな態度なのは承知したとほとんど同じである。ここは踏ん張って、リタには一緒に行かないという選択をさせるべきだった。リタは、フランクに対して教師又は人間としての興味あるいは好意を持っているように見えたが、男として見ていたという瞬間はなかったような気がするからだ。
さて、富本牧子については何も知識がない。はじめてみたが、なかなか味わいのあるリタであった。衣装を換え、ヘアスタイルを変える大忙しの舞台裏だったろうが、最初に現れたがさつで無教養な姿と最後のリタがそれほど落差のないことが少し残念だった。何もないところへイギリス文学の精粋が教授の正しい指導によって注ぎこまれたのだから、一皮むけたような様子が欲しかったというのはぜいたくな望みだったか?それとも演出がそこまで気を配らなかったせいか。
衣装の宮本宣子は、如何にもロンドン郊外の町の美容師のファッションといった風情を作り出した。何着用意したか知らないが大変だったことは容易に想像出来る。
有川博は、もともと器用な役者だと思わないがこの役ははまっていた。最初のイギリス人らしいしぐさが如何にも新劇で、それが持続するのかと思って、「やれやれ」だったが、途中からなくなった。ただ、年は少し作りすぎではなかったか。あれでは爺過ぎる。もっと色気がなければ、単なる老いらくの恋になってしまう。
また、再演があるかも知れない。その時はもう少し英国文学の知識を持ってみたらさらに味わい深いものになるかも知れないと思う。
それにしても階級社会とは、厄介なものである。