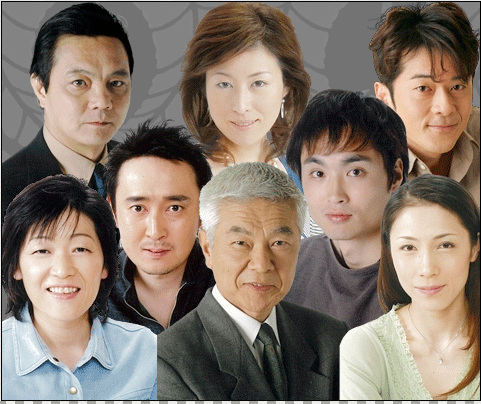
「フユヒコ」
物理学者寺田寅彦、晩年の家庭生活を描いたもので「東京原子核クラブ」に続いて97年に書かれた戯曲である。「東京・・・」は、理化学研究所を舞台にした群像劇、いわゆるグランドホテル形式の芝居であったが、寺田も理研に関係していたからその時想を得たものと思われる。この戯曲は「赤シャツ」(=漱石)「MOTHER」(=与謝野晶子)と合わせてマキノノゾミ三部作といっている。あとの二つは見ていない。「東京・・・」は、後半の特に戦後の場面がうまく書き込まれていなくて、へなへなと腰が折れてしまった感があった。(劇評参照)
それに比べると、この芝居は家庭という狭いところにフォーカスした分うまくまとまっていて、複数の戯曲賞をとったことは諾える。何よりもユーモアの質が知的で上質、構成がしっかりまとまっていて、非常によくできた芝居である。反面、学者としてあるいは文章家としての寅彦については独白、暗転時のナレーションとしてあっさりと描かれるだけである。後妻と子供たちの間で右往左往する父親像がやや喜劇的に描かれるが、これを評伝劇としてみるならば、寺田寅彦の何であるかはさっぱり浮かんでこない。後妻が「悪妻であった」という噂を確かめるという作家の意図は分かるが、この三人目の妻の像が必ずしも鮮明に描かれいないところには不満が残る。
もっとも、タイトルが「フユヒコ」であるところをみると、必ずしも評伝劇を目ざしたものではないといっているようだ。 寺田寅彦は吉村冬彦のペンネームを持っている。「冬彦」をさらにカタカナにしたのは、史実をフィクションの方に寄せようとした意思のあらわれであろう。寺田家のわずか一週間あまりの出来事を切り取ったのは、おそらく寺田の人物像よりも「家族」というものを見せようとしたのである。それが作家にとっても、時代にとっても気になるからに違いない。
寺田家の居間。座卓に座布団、正面のガラスの嵌まった障子がいかにも昭和初期である。ガラス越しに二階に通ずる階段が見えている。下手に一間のふすまがあって、その向こうは妻寺田りん(津田真澄)の部屋。上手はいちだん下がった応接間でティテーブルにピアノとチェロがおいてある。ピアノの上に大きな招き猫が鎮座しているところがおかしい。
この招き猫は、妻のりんがいらだった時に決まって五十銭銅貨を何枚か投じるといういわば欲求不満のはけ口である。夫の理学博士寺田冬彦氏(山野史人)は困惑し追いつめられるとこれを懐に抱いて頭をなでると安心を得るというなんとも便利な置物である。
りんは、博士の三人目の妻で子供たちと血のつながりはない。子供は長男康一(太田佳伸)を筆頭に、 次男秀一(五十嵐明 )次女早月(椿真由美)三女秋子(加茂美穂子)。
小さな旅行かばんを持った夫妻が家に戻ってくる。妻のりんはかなり怒っている様子で、居間の戸を開けると憤然として自分の部屋に駆け込むなり、ぴしゃりとふすまを閉めてしまう。
伊香保温泉に出かけるつもりで家をでる時、冬彦は玄関先で電報を受け取った。札幌の康一からで「折り入って話があるので、年越しには早いが明日帰る」というのであった。電報までよこしたところを見るとよほど大事なことに違いない。しかし、自分はその明日には温泉である。電報の件は言い出しにくくて、ともかく上野にむかった。ところが、それが気になって行くべきか止めるべきか迷いながら半日上野の街をうろうろした揚げ句、最後の汽車を見送ると、すごすごと家に戻ってきたのであった。
久しぶりに夫婦水入らずで温泉旅行のはずが、夫の優柔不断のために台無しになってしまった。妻の怒りももっとものことである。りんはこの怒りを隠そうともしない。わがままと非難されると「どうせこの家では私だけ他人なんだから」と辛辣である。
翌日、康一が帰ってくるというのに芝居見物と称して妻は朝から出かけている。よほどへそを曲げてしまったらしい。康一の折りいっての話というのは、この度、中谷宇吉郎(寺田の教え子)教授の推挙により、北海道帝国大学講師嘱託に決まったというのであった。それはめでたいことではあるが、何も旅行の予定を変更してまで聞かねばならない話でもなかった。しかし、後の祭りである。
温泉旅行で女姉妹だけになる間、次男の秀一が都内のアパートから留守居にやってきている。秀一はドイツ文学を専攻して今や翻訳家の卵である。家族が揃ったのでちょうど時期だし、ひとつ欧米で行われているクリスマスの祝いというものをやってみようということになるが、りんはそんなものはごめんだと帰ってこない。長男が帰省したというのに、母親は不在というのもなんだか妙なものである。りんの頑なな性格が現れている。
りんはまた江戸っ子らしいユーモアのセンスも見せる。冬彦がタバコの置き場所をしょっちゅう忘れるので、和服の袖にタバコとマッチを縫い込んでしまった。このおかしな格好は子供たちにすこぶる不評であったが、家の中だけなら誰にもみられやしないといって平気であった。
翌日、康一の講師就任の祝いが、理研の総帥大河内正親(佐藤祐四)を招いて行われる。この人は爵位のある殿様だが神経こまやかで、後妻のりんと寺田家の子供たちの仲がうまくいくように常々気配りを見せているのであった。いける口のりんと互いに酒を酌み交わすという粋なところもあったりする。
康一は大河内政親に、自分は父親と同じ物理を専攻したが、これでいいのかという疑問を感じているという。今や物理といえば相対性原理や量子論という時代に、自分のやっていることは身近な自然現象を物理的に解き明かすという地道なことばかりで、華々しい理論物理の発展ぶりを見ていると、焦りを感じるというのである。大河内は、研究対象の重要性に差があるはずはない、ただ時代のはやり廃りがあることは認めざるを得ない。研究者がそれに左右されてはいけないのではないかと、康一を諭す。大河内は、話の中にさりげなくりんが作ったはぜの佃煮のうまさをさし挟んで、康一と母親との仲を取り持とうと気を使う。二人は折り合いが悪いと思われているのだ。
宴もたけなわになって康一がバイオリン、 秀一がピアノ、冬彦がチェロと三人で合奏を披露しようという時、玄関に人の気配がする。冬彦がけげんな顔で戻ってくるといきなりまねき猫を抱いて頭をなで始める。何か心配事があるらしい。
客を帰したあと、冬彦のいうには、訪ねてきたのは「帝都日日新聞」の記者で、最近三女の秋子をめぐって二人の学生が喫茶店で取っ組み合いの喧嘩をするという事件があった由、この記事が明日の朝刊に載るが、今なら間に合うというのだ。つまり金でもみ消してもいいといっているのだが、冬彦はこれを即刻断った。断ったことが果たして正しかったかどうか、娘の将来を考えると暗澹たる気持ちになっていた。
どうも文化学院に入ったばかりの秋子の周辺で何かが起きているらしい。。文化学院は、西村伊作(大逆事件で連座したいわゆる紀州新宮グループの大石誠之助の甥)が与謝野鉄幹・晶子夫妻らと作った学校で、リベラルを標榜し当時としては珍しい男女共学であった。主旨に賛同した寺田も設立に協力している。専修学校(文部省令による規制をさけるためあえて大学にしなかった)だったが、佐藤春夫文学部長始め、教授陣もそうそうたる顔ぶれで、学生もどこにも受け入れてもらえないような個性的な若者が集まって、独特の校風があった。
翌日朝から、康一と秀二は手分けして近所の販売所から新聞を根こそぎ買い集めてまわった。秋子の目に触れないようにとの配慮である。新聞の束の置き場所に困っていた兄弟に、りんが自分の部屋に隠すように手招きする。りんにはりんなりの家族への気遣いはあるのだ。
その日、沢木が事情を説明したいと冬彦を訪ねてくるが、断固として交際は許さないと追い返し、秋子にも今後沢木に会ってはならないと厳命する。秋子は沢木に好意はあっても結婚したいという気は無い。父親の頭ごなしの言い方に言葉を失い、母の招き猫を抱えると玄関のたたきに打ちつけて割ってしまう。この時入っていた銅貨が意外に少ないことに皆頭をかしげている。秋子はそのまま家を飛びだした。
りんは「そのうち帰ってくるさ」と平気である。次女の早月は電話をかけまくって行方を追っている。暮れの寒空から雪が落ちてきた。いたずらに時が過ぎていく。
すると、夜中に突然沢木が飛び込んでくる。秋子の行き先がわかったというのだ。沢木は雪にまみれ凍傷にかかりかけていた。秋子が友人から金を借りて、軽井沢にむかったことまで突き止めたというのである。沢木はそのまま倒れ込んでしまう。
次の日秋子から「これから帰ります」という電話が入る。夕方には家に帰りつくだろうと皆安堵した。外出から帰った早月が包みを広げると中から招き猫が現れる。そこへちょうど秋子が帰ってきた。やはり大きな包みを持っている。招き猫であった。二人は顔を見合わせる。
秋子が持ってでた旅行かばんはりんのものだったが、中に「冬彦様」と書かれた箱があったという。二人で開けてみると、五十円もする舶来の銀時計であった。上野から戻ってきたあの日、旅行先で渡すはずのものだったに違いない。秋子が招き猫を割った時中のお金が意外に少なかったというのは、このせいだったのだ。二人は包みをかばんに戻してりんの部屋にそっと返しておいた。
康一が戻る。新聞を買い集めるのにお金を使ってしまったのでこれで勘弁と小さな包みを開けると出てきたのは招き猫。秀二が買ってきたのは福助人形でこれはご愛嬌。冬彦も招き猫をもって現れる。そしてとうとうりんが帰ってくると、本命が登場とばかりに巨大な招き猫が包みから取り出されピアノの上に置かれることに。「今度割ったら弁償してもらいます」。
冬彦は沢木が誠意のあるところを見せたことに感じ入って、秋子との交際を認めてもいいという気になっていた。 見舞いの電話で、編集者志望と聞いていたが就職先はあるのか?零細な出版社では家族を養っていくこともできないぞなどと心配している。岩波書店なら何とかなるから紹介状を書こうというところをみると一緒にしなければなるまいと思い始めているようだ。早月も結婚したら?とすすめるのだが、秋子はもう少しこのままでいたいと曖昧な態度である。
明けて昭和十年の正月、伊香保温泉行きをやり直そうと冬彦とりんは出かけようとしている。思い出したように、りんが「講師になったお祝いだ」といって時計の箱を康一に渡す。「冬彦様」の上に紙を貼って上から「康一へ」とかいてある。二人が出かけたあと「兄さんがもらうべきじゃない」と兄弟に言われるが、たしかに康一も複雑な気持ちである。
そこへ、不意に夫婦が戻ってくる。何があったのか、りんはかんかんに怒っている。後に続く冬彦はおろおろするばかりだ。開幕の時と同じようにりんは憤然と自分の部屋に飛び込むとふすまをぴしゃりと閉めた。
一同唖然として眺めているところへ、大河内先生が訪ねてきて今日はお土産があるなどといいながら包みを開ける。出てきたのはなんと招き猫。大河内先生、一同の視線の先を追うとそこには大小の招き猫がきちんと並んでいる。「これは失敬」と大河内先生が退散するところで幕、というわけである。
評伝劇としてはともかく、芝居としては非常によくできていて、面白かった。マキノノゾミの作品を全部見たわけではないが、秀逸といってよいのではないか。
りんの剛直な態度、多少自己主張が強くてわがままなところが悪妻たるゆえんであろうが、亭主の足を引っ張るわけでもないからこの程度ならご愛嬌というものだ。それよりも、なぜ寺田寅彦はこの妻と一緒になったのかそもそもの発端に興味を持った。しかも、この妻は三人目である。前の二人はどうしたのだろう?
そう思うと矢も立てもたまらなくなって、それを知りうる適当な本はないか探してみた。全集に当たるほど時間もない。うまい具合に2006年、岩波からでた山田一郎「寺田寅彦ー妻たちの歳月」があった。
劇評は一応締めくくって、この本でわかった寺田寅彦の妻たちについて書いておこうと思う。
最初の妻は夏子といった。明治三十年(1898)七月、親同士の話し合いで寅彦が満十九歳、熊本の第五高等学校在学中に結婚した。土佐の土地柄、早婚が習いであったらしい。とは言え花嫁は満十四歳、現在なら中学生である。祝言を挙げたが寅彦は熊本へ、夏子は高知の寺田家に残った。寅彦のたっての願いで、夏子は県立高等女学校に通うことになる。寅彦の方にも学業に差し支えがあっては困るという理由で、熊本から一度も帰郷することがなかった。あるいは熊本の気風を思えば、高等学校の生徒が幼妻と暮らすことがはばかられたのかもしれない。夏子は二年の間花婿不在のまま婚家で過ごしたことになる。ちなみに、女学校の受験勉強を見てやったのは寅彦がもっともかわいがったという甥(次姉の子)の別役亮(のちに東京帝大農学部卒業)であった。この人は劇作家別役実の祖父に当たる。また、もう一人の甥(長姉の子)である章の子に作家の安岡章太郎がいる。
やがて、寅彦が東京帝国大学理科大学に入学すると、はじめて二人きりで暮らすことになる。
夏子は「器量のよい方で、目の大きな、ぱっちりした黒い目で、背のすらっと高い人で、評判の美人でした。」(女学校時代の同級生の談)「夏子さんがいれば夜中に明かりはいらぬ。目が良う光るから。」(親類の子の談) などともいわれた。
山田一郎は、漱石の初期の短編小説「趣味の遺伝」の一節、「・・・滴るばかり深い竹の前にすっくりと立った。背景が北側の日陰で、黒い中に女の顔が浮き出したように白く映る。目の大きな頬の緊まった領(えり=首のこと)の長い女である。」をひいて、これが漱石の見た夏子の印象ではなかったかと推量している。
明治三十三年の暮れも押し詰まったある日、二人で出かけた縁日からもどると、突然夏子が大量の血を吐いた。結核であった。その時夏子はすでに妊娠していた。郷里の父利正は迅速に動いた。すぐに夏子を高知に戻して療養させる準備をはじめたのだ。
ー火鉢の上にて夏子と指相撲ー
まもなく別れ別れになるという二月の日記の中に現れる記述を発見して、寅彦の全集を編んでいた友人の小宮豊隆が涙ぐんだという。
高知に戻った夏子は、海岸の村々を転々としながら療養する。そして五月に長女貞子を生んだ。子供はすぐに母親から遠ざけられ、祖父母の手で育てられる。
六月の日記の中には、唯一ともいうべき夏子の心情が現れている。
「郷里より書留来る。また夏よりも手紙来る。乳の張るたび、この乳を飲ますようならば、いかに嬉しからんと思うなどといい越せり。」
寅彦はこの年の秋、帰郷している。感染を恐れた利正が夏子と会うのを禁じたが、内緒で会っていた。そのうち寅彦も体調を崩したので震撼としたが、診断はマラリアであった。この療養のために翌明治三十五年の夏まで寅彦は高知にとどまっている。
秋、十一月十六日の日記。寅彦はすでに復学して東京にいる。
「午前四時、夏危篤の報あり。次いで六時絶息の報あり。十二時新橋発急行。阪井両上送り来る。昨夜会より帰りて床に就かんとする頃、胸騒ぎひとしきりしたるが恰も夏の臨終の刻なりしと思合わされたり。この朝、第二の電報いまだ来ぬ前、暁の鴉夥しく屋根に鳴き騒ぎたり。」
ああ、夏がもうこの世にいない・・・・・胸騒ぎの中で寅彦はそう思ったに違いない。不思議なことだが、たとえ離れていても、愛するものの死はなぜかわかるものなのである。夏子、享年十九。一子を残したとは言え、美しくはかない人生であった。
それから三年後、明治三十八年、寅彦は寛子と再婚する。寛子は土佐高等女学校の第一期生で、この時数えの十九歳であった。兄昶二郎(山内家顧問弁護士)は寅彦と東大時代に親交があり、その妻万寿の兄上村直親(東大医学部卒)とも親しかった。さらに、夏子の親もそうだったが、親同士は戊辰戦争の戦友であった。そういう縁で、二人は見合いのようなことをして結婚することになった。
山田一郎はこれ以上ない簡潔な言い方で、寛子の人となりをまとめている。
「その生涯を見ると寛子は良妻賢母の典型といえた。学者としての夫は、理学博士、東大教授、外国留学、学士院恩賜賞受賞というように物理学界の最高峰に登った。一方で漱石門下の文人として「薮柑子集」で文壇の注目を引いた。妻としての寛子もその栄光の中にいたが、この女性はあくまで寅彦の影の人であった。そして優秀な二男二女を残して、一夜のうちに肺を侵されて急死した。三十一歳であった。」
明治四十年、長男が誕生。東京で初めて生まれたという意味で 東一と名付けられた。次いで明治四十二年、二男正二が生まれる。一年と数ヶ月の欧米留学のあと、明治四十五年に次女弥生が誕生。大正四年には三女雪子が生まれている。その兄弟がこの芝居の康一、秀二、早月、秋子に対応している。
大正二年には父利正が亡くなり、母親の亀子と長女貞子を東京に引き取って同居を始めた。
大正六年の夏ごろから寛子は体調を崩して、寝たり起きたりの生活になっている。下痢がひどく微熱も続いた。しかもこのとき五人目を懐妊していたのである。病状は一進一退を続けたが、結核菌はすでにリンパ腺にはいって全身にまわっていた。十月十八日の日記に「一夜の中に右肺全部を侵されしとのこと」とある。「酸素吸入、カンフル三回。呼吸切迫、一時永眠。」と続く。振り返ってみれば、わずか十二年の結婚生活であった。
このとき、東一と正二はまだ小学生、弥生は幼稚園、雪子は二歳であった。
その状態を誰もが心配した。
再婚話は翌大正七年の年初から始まっている。 寅彦としてはまだ早いという気もあったが、子育てについてはまるで野放しの状態だったので、 来てくれるものがあればともかく検討しようという気であった。相手を選んでいる場合ではない。 六月になって、話が具体的になってきた。寅彦は慎重に親戚中の意見を聴いてまわっている。
そうしてこの年の八月、酒井志んと三度目の結婚をすることになった。酒井家は江戸時代には浅草蔵前で札差をしていた富商で、当時志んの父親は日本橋で数軒の家作を持って豊かに暮らしていたという。志んは、戸籍上の名、紳を嫌って自分では志んまたはしんと書いた。年齢は三十三歳、寛子より一歳年長になる。
志んは「額の広い、落ち着いた賢そうな女だった」と寅彦の友人がいっている。できたばかりの府立第一高女に入った(推定)が、東大医学部を卒業し、故郷岐阜に戻って開業するという医者に乞われて東京を出た。二男をもうけたが、夫が若死にをしたために実家に戻っていたのである。寺田との再婚にあたって、この先岐阜に残してきた二人の男子と会わない約束をさせられたという。
二人の前妻が土佐の人脈の中にあったのに対して、志んは正真正銘の江戸っ子である。互いに微妙なところで生活感の違いを感じても不思議ではない取り合わせであった。しかも、寅彦はすでに四十歳に近く、二人は互いの趣味も考え方も確認するまもなく一緒になったのである。寅彦は土佐の軍人の家の出であるが、志んは東京の商家に生まれ育った。志んが歌舞伎や新派、旅行が大好きで、一方寅彦は多趣味ではあったが妻と共通するところはほとんどなかった。寅彦は気付いていないが、さまざまな齟齬が積み重なって志んは何度も黙って実家に戻っていたことがあったという。また、寅彦も名指しで書いてはいないが、志んに対する不満と思える言葉をなんどか日記に書きつけている。
ただ、いつの間にか寅彦も劇場に同行するようになり、志んが演劇雑誌に投稿した劇評に目を通すなどするようになっていったのは、志んに対する理解が進んだせいであろう。
また、一緒になってまもない頃の寅彦のメモに、志んの鋭い批評眼について書かれている。
「志ん、いわく『あなたは馬鹿にハイカラで西洋かぶれがしていると、また馬鹿に日本流の昔気質なところがありますね』またいわく『つまり勝手な人ですね。自分の都合のいい方に・・・・・・』。実際そうかもしれない。朝飯を食いながら、西洋の野菜の話をしていたのがこんな話になったのであった。」
また、寅彦が志んについて言ったことを志んがメモとして残している。
「志ん子について、寅彦の言ったこと。非常に頭が早いね。動作はスロモーだけれど。だれに似たんだろう。酒井のおじいさん(志んの父親清兵衛)が頭がいいから似たんだろう。学者のような素質がある。何しても大きいかからいいよ。何でもあまり小さくてはね。映画俳優のようなところがある、とちょっと舌を出した。」
少しづつでも共通の何かを探し、尊敬できる部分を見つけていこうとすることが賢明な生き方だと思っているようだ。互いに不満はあっても、、この芝居の昭和九年、明けて昭和十年という年まで二十年近くを一緒に過ごしたことを思えば、これもまたひとつの夫婦のあり方かもしれないという思いがする。
志んが寺田の家に入った時、三女雪子はまだ幼児であった。志んはこの子をとりわけかわいがったようである。芝居の後半は、この雪子の話である。沢木とは僕らが、辛口の評論家として知っている青地晨(本名青木滋)のことである。
青木滋は、旧制佐賀高等学校でストライキをやって放校処分にあい、上京して日大芸術科に潜り込んだが前歴がバレてここも除籍される。仕方なく、西村伊作に頼んで文化学院に入れてもらったものだが、ここで雪子と出会っている。次男正二によると雪子もまた軽度のアンファンテリブルであった。
劇中の喫茶店の騒動はフィクションで、青地によると実際は、雪子と二人で銀座の竹葉の隣にあった喫茶店で話をしているところを写真に撮られたらしい。にわかに騒々しくなったので気付いた。横恋慕した友人が新聞社にスキャンダル話としてを売り込んだのだ。その写真で寅彦がゆすられたことはほんとうのことである。
青地晨はインタビューの中で「寺田寅彦の娘と駆け落ちする」という話をしている。
「同級生の中に寺田寅彦の娘がいた。吉村冬彦というペンネームですから、三文文士の娘かなと思っていた。これと恋愛おっぱじめましてね。(笑)。親父は東大理学部の教授で、なかなかお偉方だと分かってきた。これはいかん、正式に申し込まねばダメになると思い、私の親類の工学博士に頼んで話してもらったが、全然ダメなんです。・・・・・・それでそれから三年ぐらい経ってから、「しょうがない、駆け落ちしよう」ということになって彼女が家に逃げてきた。僕はあの頃妙な道徳観があってね。一緒の家に寝るのはいかんと思い(笑)となりに親父の友達の陸軍中将がいて、僕はその監督下にあったので、その家に泊めてもらった。そのうちにもうきずものだからと(笑)親父さんが折れちゃった。・・・・・・ しかし、この女房はそれから四年しか生きなかった。脊椎カリエスで、長女を残して死んじゃった。」
読んでいてあまり愉快でないものを感じるが、青地晨という男の「含羞の裏返しの露悪趣味」だと山田一郎が擁護している。
ともかくこの騒ぎに志んと弥生が奔走して二人の結婚までこぎ着けたのであった。しかしその雪子は、終戦を待たずになくなっていた。
芝居は、昭和九年の暮れから十年の元旦までのわずか一週間の出来事を描いたものだ。もちろん「フユヒコ」一家の物語で、寺田寅彦は劇中に存在しない。しかし、りんの「悪妻ぶり」を見ているとなぜこの男はりんのような強情で激しい性格の女と結婚する羽目になったのか知りたいと思うようになった。秋子の恋愛事件の顛末もどうなったのか気になる。この物語には、フィクションとして完成していながらそういう広範な背景に誘うようなさまざまな疑問符が仕掛けられているような気がした。そういう意味でも面白く書けた戯曲だといえる。
随筆家としての寅彦を物語に取り込むことは比較的容易だったと思うが、一方物理学者としての側面も、やはり気になるところであった。いうまでもなく寺田寅彦の仕事にはさまざまな功績がある。中でも戦前において日本初のノーベル賞受賞者にもっとも近かった「エックス線回折のラウエ斑点」の研究論文があることはあまり知られていないように思う。
あまり深入りすると大河ドラマでも間に合わないくらいのシーンが次々に浮かんで来そうだからやめるが、とりあえず、りんという後妻の姿にくわえて、二人の前妻の面影をおいてみた時、この物語はよりいっそう奥行きが増して見えるような気がした。
マキノノゾミ自身による演出は、さすがに笑いの壺を心得ていて軽妙で味わい深かかった。山野史人のフユヒコは、少し固いように感じられた。津田真澄のしんの存在感が今一つだったのはおそらく本のせいだろう。マキノノゾミの迷いが若干本に出ている。早月の椿真由美も本のせいで損をした。もちろんアンサンブルもよくできていて高い水準でのことではあるが。




