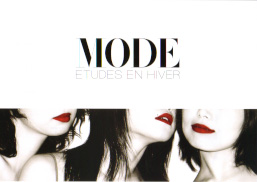
|
題名: |
冬のエチュードShakespeare2005 |
|
観劇日: |
05/12/25 |
|
劇場: |
シアター・ブラッツ |
|
主催: |
MODE |
|
期間: |
2005年12月22日〜25日 |
|
作: |
構成:松本修 |
|
演出: |
松本修 |
|
美術: |
伊藤雅子 |
|
照明: |
大野道乃 |
|
衣装: |
竹内陽子 |
|
音楽・音響: |
徳久礼子 |
|
出演者: |
石村実伽 西田薫 金子智実 山田美佳 南真理子 中田春介 榎本純朗 坪内志郎 齊藤圭祐 緒田果南 西田夏奈子 秋定史枝 加納健詞 足立聡 佐藤亮介 久我真希人 |
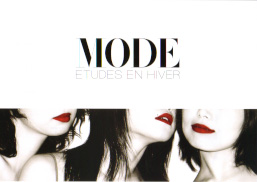
「冬のエチュードShakespeare2005」
「今回、役者たちにある簡単なテーマというかキイワードを与えて(裏切り、嫉妬、憎悪など)、それぞれが演じてみたい場面をシェイクスピア戯曲から選んで、持ち寄ってもらった。最初に僕のほうからは戯曲を指定しなかった。およそ100場面ほど集まり、連日繰り返されたワークショップで劇として立ち上がりそうなものを選択した。最終的には僕が『現在、観るに値すると思える場面』を採用し、構成した。ただし『現在観るに値する表現』となっているかは、いささか心もとない。」松本修はパンフレットにこう書いている。
したがって、タイトルの「エチュード」は文字通りと受け止めてよさそうだ。つまり、何かを模索している途中なのである。何かとは、むろん、シェイクスピアのことだ。
秋に観た唐十郎の『唐版・風の又三郎』は、松本が近畿大学の教師として、教材に選んだもので、本気かどうかは分からなかった。これも含めて、同じ時期に唐十郎を立て続けに三本見たのだが、たぶん時代の空気が唐十郎の「詩情」を求めていてそれとシンクロしたのだろうと勝手に理解していた。ちょうど、シャンソンの当たり年だと僕が騒いでいたのとおなじベクトルを向いていると思っていた。それはそれでいいのだが、次の関心がシェイクスピアに向かっていたとは意外だった。
2005年の初頭にカフカの『城』を観て、ある劇的感興の方法論を獲得してカフカを超えた、つまり、カフカでなくても構わないという方法的領域に到達したという感想(劇評参照)をもって、次はなにをやるのか興味津々だった。
何故シェイクスピアかと言えば、この劇を観た限りでは分からなかった。と言うより、松本自身が、「ずいぶん回り道をしてきたが、今回、何故だか、ようやくシェイクスピアにたどり着いた。」(パンフレット)というようにその関心は十分対象化されたものではない。したがって、この劇ではさまざまな工夫、実験を試みている。取り上げたタイトルは『ハムレット』、『オセロー』、『マクベス』、『ジュリアス・シーザー』、『トロイラスとクレシダ』、『リチャード三世』、『アテネのタイモン』などで場面はそれぞれの断片がランダムに登場するという構成である。
関西弁あり、パンク姉ちゃんあり、ジャズにロック、半裸の親父に女の下着姿等々。これらは俳優の工夫もあっただろうが、とりあえず「観るに値する表現」にはなっていたといってよい。一つ一つは面白い見せ物にはなっていたが、しかしこの程度のことなら日本でやっていなくても世界のどこかで観られそうだ。想定内と言うことで、あまり感激はない。いったいシェイクスピアをどうしようとしているかはまだ見えなかった。
劇中、何人かの俳優が「す」に戻ってベンチに座り、シェイクスピアについて語る場面がある。このときの俳優の発言に、今日シェイクスピアをやろうとするときに押さえておかねばならないと考えられる課題が語られる。こういう議論をせりふでやろうとするのは、無理がある。だから台本はあるのだろうが、あたかも稽古場で俳優たちが会話しているような言葉使いで話された。
箇条書き的に言えば、
シェイクスピアの自筆の原稿は、いっさい残っていない。
したがって、その実在には疑問がある。(フランシス・ベーコン説やらシェイクスピアの親族説など多数あることは事実)また、部分的に書き加えられたものもあると考えられる。他人が書いたものをありがたがるのは如何なものか?
次に、当時の公演形態として舞台装置などなかったために、シチュエーションの説明に膨大な言葉を必要とした。『言葉、言葉、言葉』とはシェイクスピア演劇の本質部分である。
チェーホフとの対比では、心理描写がきめ細かく表現される近代演劇に対して、物語性が重視される古典的な形式の演劇である。
なにはともあれ四百年前の芝居を今日やる意味はあるのだろうか?
英語圏で、引用される書物はダントツに『聖書』だが、次はシェイクスピアである。(これがあったかどうかは不確か。)
書かれた言葉は400年前のエリザベス朝のもので、現代英国語ではない。しかも「ヴァース」といって「強弱五歩格の韻文」の一定のリズムを持っている。こう言うものは翻訳したら失われてしまう。(しかも平民の台詞が散文で書かれていて、貴族のそれはこの韻文というわけである。)
ざっとこのような議論だったと思う。
最後の翻訳の問題について、昨年秋、ある講演会で面白い話を聞いた。第一部は小田島雄志の講演で、シェイクスピアの『愛』にまつわる言葉をいくつか取り上げて解説すると言うものであった。彼は英文学者というよりは、単に演劇好きの翻訳家であることがよく分かった。それはたわいのない閑談であったからどうでもいいのだが、面白かったのは第二部の座談会で、いろいろ感心したことが多かった。それは今年一月から『女子大生が演じたシェイクスピア劇』と言う展示会をするのでその露払いとも言うべき催しだった。日本女子大英文科では戦前から、ほぼ毎年、長い稽古期間を設けて原語でシェイクスピア劇を上演するという演習を続けてきた。ここで演劇にはまってしまった関係者は多いらしい。出席者は、同大名誉教授、塚野千晶、新劇俳優で詩人の村松英子、同学非常勤講師、翻訳家、演出家、酒井洋子、劇団昴、松本永実子である。それぞれ思い出話をするのだが、ここでの酒井洋子の発言がすごかった。
「私はシェイクスピアの翻訳劇を見るのは大嫌いである。どうしても観たくなったら、ロンドンに行く。」思わず辺りを見回して、小田島雄志先生がいないかどうか確かめた。この人の断固たる物言いに、会場はやや唖然の呈であったが、僕はこの当たりに日本でシェイクスピアをやることのある種の困難さがあるのではないかという思いを強くした。
つまり、かつて福田恆存が「翻訳したら面白さは90%なくなってしまう。」といったように、僕らが日本語で見るシェイクスピアはたった10%の残りをどうにかようやく楽しんでいることになる。僕はシェイクスピアを見るときはいつも隔靴掻痒を感じているが、それは失われた90%の幻影をどこかで感じているせいに違いない。では何故、10%にもかかわらずシェイクスピアは楽しめるのかといえば、物語が面白いからにほかならない。その面白さはたとえば黒沢明の「蜘蛛巣城」(「マクベス」)『乱』(『リア王』)あるいはミュージカルの「ウエストサイド物語」(「ロミオとジュリエット」)などといった翻案された映画を見れば逆にその本質が見えてくる、と僕は思っている。11月に見た青年座研究生が演じた『冬物語』もまた因果は巡ってハッピーエンドに終わる壮大な物語であり、テーマ性などよりも物語そのものが面白いのである。
世界中でシェイクスピアが好まれる理由は、演劇としての構成の確かさと話の展開の面白さ、これにつきると僕は考えている。さらにいくつかのせりふは教訓となり、アフォリズムとなってもいいが、それはあくまでも結果であって、物語から切り離して成立するものではない。
ここで、僕らは失われた90%の面白さの手がかりを見つけることが出来る。「『聖書』に次いで多い引用」という側面であるが、つまり、教養としてのシェイクスピアである。英語圏、とりわけ英国ではシェイクスピアは何といっても国民文学であり、日本で言えば百人一首や忠臣蔵、歌舞伎狂言のようなもの(近ごろではそうでもなくなったかも知れないが)で誰でも大概の内容は知っている。だから、引用もたとえ話も言い換えや言葉遊びもできるということになっている。僕らにはこの言わばシェイクスピア学といった分厚い知識文化の層を持ち得ない。ついでに言えば、英国の知識層の共通文化としてはギリシャ神話がある。僕は高校生の頃英文学や思想書にギリシャの神々の名前がたびたび登場するのに閉口して、『イーリアス』『オデッセイ』を読もうとしたが一向に頭に入らない。何故彼らが自在に神々の名を操れるのか不思議に思って、自分は頭が悪いのではないかと悩んだものだ。あとで分かったことだが、オクスフォードやケンブリッジに入学する頃には誰でもギリシャ神話をシェイクスピアと同じくらいそらんじているということだった。こういうものはかなわないとしたものだ。
それからもっとも大きな問題は、劇を上演する場合のせりふの調子、「ヴァース」という「強弱五歩格の韻文」のリズムは、どう翻訳しても失われることである。せりふ回しは、劇を観ることから来る快感のほとんどといってもよい。たとえば「知らざあ言って聞かせやしょう。浜の真砂と五右衛門が、歌に残した盗人の、種はつきねえ七里ヶ浜、その白波の夜働き、以前をいやあ江ノ島で・・・」と言う弁天小僧菊之助のせりふを聞いて受ける心地よさは、その五七調が日本人の言葉の体感と呼応しているからにほかならない。『ヴァース』と言うのも英国の古語でつづられているとは言え、現代の英国人にも心地よく響く語感であろう。こういうものを別の母国語を持つものに伝えあうことは、どこかであきらめなければならない。
勿論観客の中には酒井洋子のような原語で演じたことのあるものやこれらの事情に通じているものもいるには違いないが、大多数は翻訳された=90%面白さを失った残りのシェイクスピアを見るのである。教訓や警句を受け取るものがあってもいいが、多くはその物語に感じ入るのだ。
それを解体し、テキストとして取り出して再構成すると言う試みがあってもいいのだが、『残りの10%』を切り刻んで何が生まれるのか?そう思えば、何だかむなしい気がしてくる。
おそらく「嫉妬」と言う主題のもとに、劇中「オセロー」の断片が、いくつか取り上げられた。イアーゴにたき付けられるオセロー、デズデモーナを責めてついには扼殺してしまうオセローが、他の劇の「嫉妬」の場面とともにランダムに提示された。その後、「嫉妬」とは直接関係のない「オセロー」最後の場面が演じられる。
このとき何故か僕はほっとした。「嫉妬」と言う出来事を見せられても、それは物語の断片に過ぎず、結末まで見てはじめて「嫉妬」がその劇特有の特別の意味を持たされるのである。つまり、「嫉妬」といってもそれはその物語において構造的なのだ。
そういうある種の居心地の悪さを感じて、「オセロー」を完結させたのではないかと思うが、それならむしろ「オセロー」をいかに見せるかに腐心したほうがいい。
話は変わるが、学生時代にシェイクスピアをやりたいと提案するものがいた。どうもシェイクスピアの信奉者らしい熱心さで説くのだが、「そんな時代ではない。」と皆にべも無くことわった。たしかに当時はやりたいものがたくさんあってそれどころではなかった。ただ、どんな時代でもシェイクスピア大好き人間はいるものである。シェイクスピア専門の劇団があるくらいだからそれは理解出来る。しかし、芸術家は時代を呼吸している。その時代がどんな音楽を奏でようとしているかをいち早く察して、指揮棒を振るうように作品を世に問うのだ。
松本は、いまがそれだと感じているのだろう。
しかし、シェイクスピアは不利である。
カフカは戦後実存主義の系譜に入るが、現代=「ポストモダン」の時代と斬り結ぶ要素を十分持っていた。不確定性とはなにも量子論や相対性理論の世界に限ったことではない。そういう意味で捉えれば、カフカの精神性は現代物理学の神髄と呼応しているとも言える。
シェイクスピアの何をもって、このカフカによって獲得し得た新しい領野をひろげていけるのか?
どんなことをやってもシェイクスピアはシェイクスピアだ。物語の強固な骨格を解体するのは相当な力技になるに違いない。
