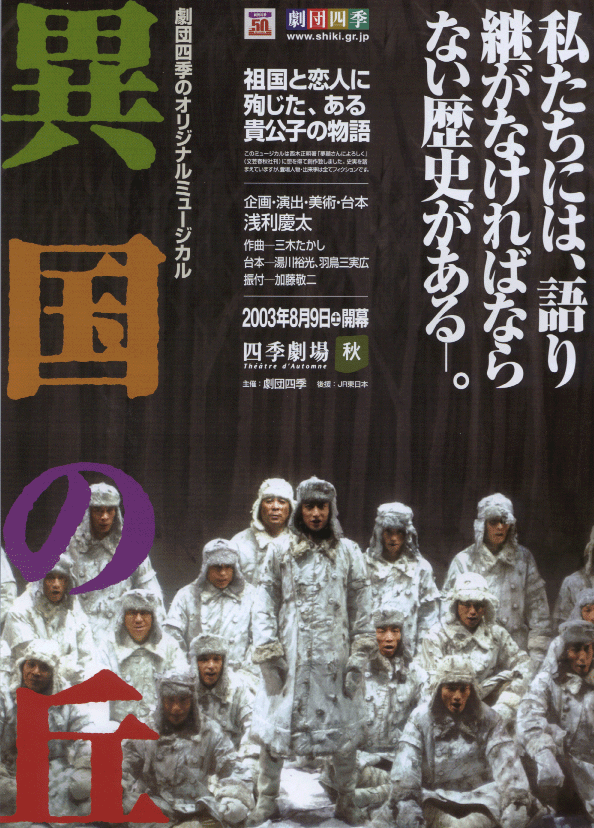
|
題名: |
異国の丘 |
|
観劇日: |
03/9/17 |
|
劇場: |
四季劇場 |
|
主催: |
劇団四季 |
|
期間: |
2003年8月9日〜 |
|
作: |
浅利慶太 |
|
演出: |
浅利慶太 |
|
美術: |
浅利慶太 |
|
照明: |
紫藤正樹 |
|
衣装: |
大栗未来 |
|
音楽・音響: |
三木たかし他 |
|
出演者: |
石丸幹二 佐渡寧子 中島徹 深水彰彦 深見正博 江上健二香川大輔 岡本隆生 八重沢真美 秋本みな子 青山裕士 日下武史 武藤寛 松宮五郎 久野綾希子 他 |
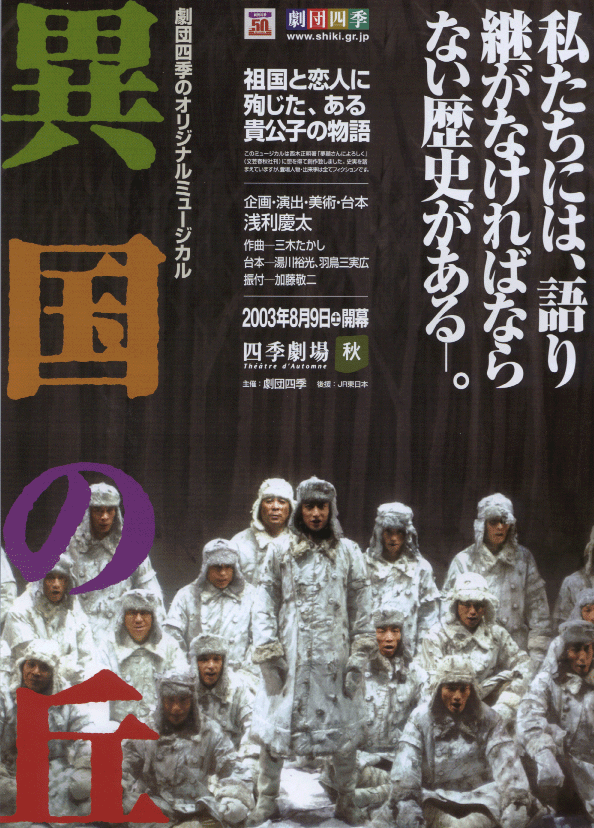
「異国の丘」
「ミュージカルは嫌いだ」とタモリが常々いっている。突然歌いだすのが気味が悪いというのだが、あれは対応のしようがないことに内心照れているのである。日本人の習慣にしゃべりながら自然にメロディがついて言葉が音楽になると言うことはない。英語なら抑揚を極端にすれば音楽になる、というのは中学生でもわかる。タモリは、無理して外国人のまねをやっているようなものだから「不自然だ。だから気持ちが悪い。」といっているのである。言葉の違いから来るものともいえるが、オペラという伝統芸術の約束事に慣れたものには案外平気なのだろう。では我が民は歌わないのか。万葉のはるか以前から歌垣などと言われる習慣が広く行われていたことは周知である。若者が恋の相手に思いを訴えるなどというのがこれである。王朝文学はすべて歌で成り立っているといって言い過ぎではないが、本人の前で節を付けて歌ったという話は聞いたことがない。歌舞伎に七五調はあっても役者が歌うことはない。我が国ではどうも舞台の上でも歌わないのである。
しかし、能は謡曲にのせて演じられるし人形浄瑠璃もまた太棹の音調に合わせて動く。洋の東西を問わず、言うまでもないことだが芝居に音楽は欠かせない。だから、日本の現代演劇では、音楽の必要性に応じて役者が歌う事もある。これはあきらかに明治以降のオペラやオペレッタ、ミュージカルの影響にほかならない
タモリは、エノケンやアキレタボーイズを知っているはずだが、浅草を知らない世代(田舎者でもある)だから、これを楽しむ術を知らない。あるいはこのルールについて容認したくないといっているのだろう。しかし、何度か見ているうちに慣れてきて、やがて楽しくなって病みつきになるかもしれない。かつて彼が批難していたゴルフに、いまは「はまって」いるように。
しかし、このミュージカルを見て、タモリの言い分は間違っていることに気がついた。あれは突然歌いだすのではない。通常のせりふに既に音符が割り振られ、音楽として発声されているのだ。少なくとも役者はそのような気分で抑揚またはメロディのあるせりふをウタうのである。
そもそも、それがミュージカルではないかといえば、それまでの話だが、日常会話にまで節回しを付けて演じるこの形式は、我々の感覚から言えば特殊である。だから、井上ひさしが、「唐来参和」のものがたりは一人称で語る小説の形を求めていると感じたように、(後に小沢昭一が独り舞台に乗せたの驚いていたが)その話が音楽で表現する形式を求めている、言い換えればミュージカルにふさわしいものがたりというものがあるのではないかと考えてしまう。そこは欧米人の感覚と少し違うかもしれない。「キャッツ」はエリオットの詞に音楽をつけたものであり、「ロメオ&ジュリエット」の翻案にバーンステインが才気あふれるスコアを書いたものが「ウエストサイド物語」だ。ビクトル・ユーゴーの大河小説さえミュージカルになる。その延長で言えば「曽根崎心中」でもミュージカルになるのだが、それは理屈で、お初と徳兵衛が不倫の唄でも歌いだしたら僕らには大いに違和感がある。
この「異国の丘」は、吉田正(中嶋徹が語り部として演じる)がシベリア抑留中に作曲した有名な歌謡曲の首題をベースに、近衛文麿の息子文隆(石丸幹二)と蒋介石政府要人の娘、アイリン(佐渡寧子、木村花代とWcast)の恋愛と彼らがからむ日中の和平交渉、そして文隆のソ連による抑留という波乱の物語をミュージカル仕立てにしたものである。
前半は舞台がニューヨークの上、戦争中の政府高官の子弟同士の恋愛という、ちょっと「ウエストサイド・・・」を思わせるドラマチックな仕立てでミュージカルらしい。ところが舞台が上海に移って、南京政府との和平の条件を探る極めて危険で政治的にデリケートな場面になると、さすがに唄で表現するのは難しくなる。相手は「白髪三千丈」「腹芸」の本家である。こちらも「阿吽の呼吸」とかいって間合いを計って動くのを信条とする。それでも、アイリンの父宋子明(岡本隆生、日下武史とWcast)にバリトンで心情を歌わせ、文隆に政治的メッセージをテノールで伝えさせることを、浅利慶太は強引にやればよかった。しかし、浅利はこの曰く言い難い心のうちを歌詞に託して表に出すのをためらった。後半は、音楽的感興に盛り上がることなくストレートプレイのように進行したと言ってよい。
文隆のシベリア抑留は、ソ連政府が彼を自国のスパイに仕立て上げ、帰国して政治家になることを強要するためだった。文隆は、偽装転向を勧められたがこれを拒否してついにシベリアの土となる。名もなき兵士達の望郷の想いはいたいほど解るが、この文隆の心のうちは理解しがたい。もののふの覚悟と言ってもこの公家の末裔には不似合いである。これは唄にはしにくいだろう。
このように「異国の丘」は必ずしもミュージカルという形式で表現されるべき物語ではない。むしろ史実としてしっかりと認識すべきというなら特に後半はストレートプレイの方がすっきりと頭に入ってくる。そんなことをいえば、「これがミュージカルだから客が入るのだ。」と浅利慶太は言いそうだ。「演劇好きの実業家」の言うことだから反論はしないが、和製ミュージカルなどと言われるものなら単なる西洋かぶれである。タモリに気色悪いといわれても仕方がない。だから、東洋的な考え方を西洋合理主義の言葉に翻訳して音楽を付け、全編歌うようにせりふを吐くというものに意地でも磨き上げて見せなくてはならない。この点浅利はこういう中途半端さで、甘いところを露呈してしまった。もっともそれをやるとなれば作曲家三木たかしには重荷だろう。我が国の過去にはいずみたくと言う才能があって、美しいメロディラインを創作したが、徹頭徹尾ミュージカルであることは難しかった。三木には恋の告白のアリアに見るべきものがあっただけで、音楽劇の大きな骨格を作り出す構想力はもとより、会話の音符化などは望むべくもない。
僕は浅利慶太が「李香蘭」を書き下ろしたと聞いたときから、二つのことが気になっていた。一つは、上に述べたようにミュージカルという表現形式に照らして、どのようなポジションを確保できているか?と言うことである。いまひとつは、長い間オリジナルをやっていなかった浅利慶太が何を発言しているかという点である。この「異国の丘」のチラシには「私たちには語り継がなければならない歴史がある。」という文言が見える。シベリア抑留と中国との和平工作のことだろうが、長年ソ連と共産中国に遠慮して我が国の進歩的知識人と言われる人々が触れなかったことである。浅利には遠慮する理由がないから若いときからこの種の発言を繰り返して、保守反動などと攻撃されていた。それに嫌気が差したから劇団四季の経営に専念していたはずで、こういう時代が来て、さぞかし溜飲を下げていることだろう。
確かに、日本の近代史なり昭和史は見直される必要がある。これからの我々の進路を決めるために、我が国をいったんそのような時間的なパースペクティブにおいて考えるべきだと思う。おそらく浅利慶太もそう考えたに違いない。しかし、その歴史とは「語り継ぐべき」ものだという。シベリア抑留という過酷な運命にみまわれた人々の記憶を語り継ぐことが大事なのだと浅利は考えている。例えば同じように原爆の体験もまた語り継ぐべき(民族の、と言う枕詞を入れてもいい)歴史である。こういう認識には危ういところがあって、「語る」言語を共有する集団の歴史という概念を前提にしているから、異民族には伝達しにくい。そして「体験」は時間の経過とともに必ず風化する。また吉田正は、シべりア抑留から帰還して以来、その体験を家族にさえ決して語らなかったという。更に原爆について言えば、被爆は差別を生んだ。そんなものを誰が語るものか!体験は言語にならないのである。ただそれは、記録されるだけである。それを語り継ぐことは、本質的にあらかじめ挫折している。
浅利のように歴史をある種浪漫チックに考えるのは勝手だが、そこから我が国の未来など決して見えはしない。
そのような観点から「祖国と恋人に殉じた、ある貴公子の物語」と言うサブタイトルが出てきたのだろうが、近衛文隆を貴公子という大時代な言い方でたたえるところが浅利慶太の真骨頂で、歴史はロマンででき上がっているとでも考えているのだろう。ようするに、浅利が語り継ぐべきと言っている物語は、戦後長い間進歩的知識人が意図的に無視してきた歴史の封印を解くと言う意味はあっても、我が国の未来を開く新しい視点を提供するものでないと言う意味で、戦後の論壇と同根あるいは背中合わせの議論だと思う。
僕はこう考えている。シベリア抑留はスターリン独裁の政府が決めたことである。彼らには勝手な理屈があって、それが正義だと思い込んでいた。俘虜も人間だ、家族もいるだろう、望郷の念もあるだろうとは考えなかったのか?考えもしなかったから何年も家畜同様ただでこき使ったのである。それはロシアの文化だっただけでなく、一皮剥けば我々自身の姿でもある。権力者が人権蹂躙するなど今でも日常茶飯である。それが社会であり、そういうことをやってしまうのが人間の愚かさで、世の中は自分も含めてこのどうしようもない馬鹿でできている。だから、せいぜい自分で気をつけていようと思うばかりである。
そんなことにならないように、賢く振る舞うにはどうしたらいいかと考えるために、僕にとっての歴史はある。
抑留経験のある知り合いの大人が、あるとき吐き捨てるように「ロ助け」と一言だけ言ったので驚いたことがある。想像を超える憎しみがこもっていた。何があったかは聞けなかった。吉田正もまたその事を口にしなかったという。
「異国の丘」は、吉田正が収容所の中で作曲した。帰りたいという素朴な心情をはげますように歌ったもので、曲想は穏やかである。復員してからは、都会的で洗練された旋律を2000曲あまりも作り続け、ミュージカル「異国の丘」を見ずに亡くなった。この浅利慶太の壮大なセンチメンタリズムを目にしなかったことは、幸いだったと思う。(2003.10.3)
