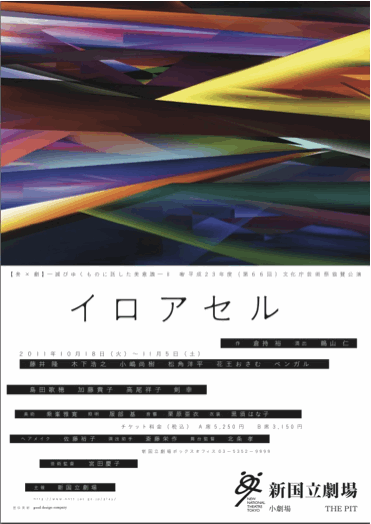
「イロアセル」
世の中には、音を聞いたり、文字を見たりすると色を感じる者がいるらしい。
たとえばドの音は赤、レは薄茶、ミはピンク,また別の人は、ハ長調が黄緑、イ短調がブルー、変ホ長調がグレーなどと、音を聞くたびにそれに対応した色が頭の中に見えるというのだ。
文字を見ると色が思い浮かぶ人もいる。
漢字の「田」は薄い黄、「科」の偏は緑で旁は赤とか、「かな」にもそれぞれ色が見えるらしい。
こういう人の脳を調べると、聴覚や視覚で反応する局所部分の他に、脳全体に分布する感覚系の活性が見られるという。 これは「共感覚」といって、200人に一人ぐらいの割合であらわれる能力と言うから、それほどめずらしくもない。
音楽を聴きながら色を感じているとか、色がついた文字を見ているとか、ホントかいなと思うところもあるが、実際ランボーや宮沢賢治、ムンクやカンディンスキーなど詩人、音楽家や芸術家に多くみられると言うことで、近年ではかなり研究が進んでいる分野なのである。
これは脳の中の出来事だから、はたから見て他人にわかるわけではない。
ところが、ある島の住人は、言葉を話したり、書いたりするとその人特有の色が現れ、他人がそれを見ることができるというのである。
この芝居は、その島での出来事を描いたものである。
台本には、冒頭からこんな風にト書きが書かれているという。
ネグロ:さあ着いた。
バイツ:着きました。
二人が声を発したとたん、ネグロの周囲には「黒く濃い色の何か」が、バイツの周囲に
は「白く淡い色の何か」が立ち上る。
他にも、
二人が言葉を発すると、やはり色のついた何かが立ち上がる、グウの色は茶色、ポル
ポリの色はムラサキ。・・・・・・などなど。
一体どんな風に色が出るのか?
舞台の天上に、楕円形の張りぼてをスクリーンに見立てて、そこにもやもやした色つきの煙のようなものを投影し、声と同期させて表現した。吐く息に色がついているようなものと想像したらいい。照明の服部基が苦労の末にたどり着いた方法であった。
最初に「共感覚」のことを言ったのは、それを作者の倉持裕が知っていたかどうかはわからないが、なんとなくヒントを得たのではないかと思ったからである。
とはいえ、「声に色がついていたら・・・」という何とも 舞台上で表現しにくい思いつきは、一体何のための設定だったのかといえば、発言が誰のものか特定できるということにあった。
この色なら誰、あの色なら誰とわかっていて、おまけに、「ファムスタ」というポータブルなモニターで互いに監視しあえる仕掛けになっている。つまり、 嘘は言えないし、無責任な発言も許されない。この島は、一人ひとりの言葉が「重い」社会なのである。
言葉に色がついている以外に変わったところはなく、町長もいれば町議会議員もいる。「ファムスタ」を製造している会社もあれば、その下請け企業もあり、「カンチェラ」というよく分からない個人競技のスポーツ選手もいるという具合で、普通の社会と変わらない。
開幕、町長のネグロ(剣幸)と町議会議員のバイツ(木下浩之)が「ファムスタ」の業務用版とも言うべき高性能機械を高台に設置して、住民の言葉をモニターしようと登場するところをみると、なるほどこれは町民の意見をあまねく収集するという意味では究極の民主主義ではないかと思わせるものがある。
しかし、一方住民全員の発言が捉えられるということは、それをいち早く把握できる権力者にとっては有利であり、反対に住民にとっては、真綿で締め付けられるような息苦しい管理社会ということになる。そのことに気づいている住民が見あたらないというのも変な話ではないか?
あるとき、この島に本土から囚人が収容されることが明らかになる。
丘の上に鳥かごのような牢屋がつくられて、そこへ囚人(藤井隆)が看守(小島尚樹)につれられてやってくるが、しかし、何の罪で何年の刑なのかは説明がない。囚人は、人が良さそうに穏やかな態度で島の住人にも興味を示している。それに対して看守は、こんな島に望んできたのではないと著しく不機嫌で、官僚的な応対に終始する。
物珍しさから、島の住人が次々にこの俄作りの監獄を見学しにやってくると、横柄に応対する看守と島の人々に関心を寄せる囚人が発する言葉に色がないことを発見する。しかも、その場所に来ると、自分たちの声、言葉にも色がつかないのである。
ここは、自分が自分であることを隠せるところであり、本音で自由な発言が可能になる唯一の空間であった。
ところで、そのころ、島の実力者である「ファムスタ」のメーカー、株式会社ブルブランの社長、ポルポリ(ベンガル)は、その重要な部品の供給元でシステムエンジニアの株式会社グウ電子社長、グウ(花王おさむ)と会って、良好な関係を継続したいと申し出る。グウ電子を買収して傘下に収めるという野心がないことを確認しようというのである。
グウは、そんなことは考えたこともないといって、今後も部品の改良をはかって協力する旨約束をする。
グウには、「カンチェラ」の選手で元世界チャンピオンであるアズル(加藤貴子)という娘がある。この「カンチェラ」とは、倉持裕が考え出した架空のスポーツであるが、どうやら手で持てるくらいの大きさの道具を使って演技をし、採点で競う個人技のスポーツ、新体操に似たようなものらしい。
「カンチェラ」は、看守も知っているくらいだから、本土でも盛んでTV中継まであるポピュラーなスポーツである。しかも、この看守、アズルのファンなのであった。
アズルには、ライ(高尾祥子)というライバルがいて、かつてはアズルがトップを保っていたが、最近ライが伸してきて、最大のスポンサーであるブルブラン社の支援をアズルから奪ってしまっている。
他に彼らとは交わらない、村八分のように避けられている前科のある女、ナラ(島田歌穂)が登場する。「前科」の詳細は不明だが、すべて発言が明らかになる島民にとって、何を考えているかわからない不気味な存在として敬遠されている。
ただし、登場する場面がきわめて少なく、何故、わざわざ島田歌穂を配したのか理解に苦しむという存在感のなさであった。
エルデ(末角洋平)は、「カンチュラ」の審査員としてほんの一場面で登場するだけで、これもあえて登場させる意味があったかどうか疑問のところであった。
まあ、ここまでは普通の社会で、普通にありうる出来事と言っていい。
ところが、島の住民が三々五々、丘の上の牢屋を訪ねて、誰からモニターされることもなくさりげなく本音を語るので、次第にその心の内が囚人にだけは明らかになり集積されていく。
島の実力者ポルポリは、町長ネグロに賄賂を送って癒着しているとか、忠誠を誓っている下請けのグウが実は、ポルポリを疑っている。そのポルポリは、本音では下請け企業であるグウの会社を買収しようと思っているとか、ほんとうかどうかは本人同士が話し合ったわけではないからわかっていない。
また、アズルのスポンサーだったブルブラン社がライに乗り換えたのには、ライの裏工作があったとかポルポリのグウに対する思惑が働いたとかいうものもある。これもまた本音のところはだれにもわからない。
人々のうわさ話を聞くうちに、囚人の中では状況を把握するのが困難になってくる。情報は個々別々にもたらされ、真実は果たしてどうなのかが見えにくいのだ。
そこで、囚人は「手紙」と称してビラをつくり、それを大量にバラマキはじめる。新聞のようなものが島に生まれたのである。
このビラにはたとえばこんなことが書かれている。
「株式会社プルプランの成功」という見出しのもとに、ファムスタの技術を三十以上の国々において国際特許を取得したポルポリ社長の「読み」は正しかったと書いている。この技術の応用がなければ、国の補助金に頼るしかないこの島は、いまごろ無人島と化していたに違いない。また、近年「カンチュラ」の発展にも力を入れていると彼を持ち上げている。
また、「カンチュラの不正判定」という記事では、プルプランの「ファムスタ」独占に疑問の声を上げ、同社がスポンサーである「カンチュラ」のライ選手が連勝を重ねているのは、良質の道具を提供しているからであると、ライバルのアズル選手の復活を願っている。
「バイツ議員放埒な女性関係」という記事もある。
彼には交際中の複数の女性があり、中には「カンチュラ」のライ選手の姿もある。年齢差のあることを理由にバイツ議員は「彼女にとっては疑似恋愛なんでしょう。」と否定するが、ひそかに南の島で会う約束をしていた、記事は伝えている。
そして、発言がすべてモニターされているこの島で、それから逃れるために、ヘリコプターを飛ばして、はるか上空で町長と、ポルポリ社長、あるいは本土の役人と町長がひそかに会議を行っていることが暴露される。
(これらのことは、実際に台詞の中に折り込まれているが、天上からまかれた複数のビラの内の一枚を劇場から出るときに失敬してきたもので確認した。ぱらぱらただの紙がふってきたと思ったら、何とガリ版刷りのわら半紙にまじめにぎっしり書き込んであったのには驚いた。さすが新国立劇場!)
囚人の檻の中が、最初はベッドと腰掛けぐらいの簡素なものだったが、いつの間にかテーブルやら椅子やら薄型テレビまで設置されていて、誰の差し金かはわからないが監獄とは思えない豪奢な様子に変わっている。囚人のご機嫌取りがはじまっていたのである。
ビラが飛び交って、大混乱のさ中、丘の上の監獄に町の方から鈍い大きな爆発音が聞こえてくる。なんと、「ファムスタ」のメーカー、株式会社ブルブランの工場が爆発したのだ。同時に、「ファムスタ」のモニターシステムが壊れ、島の住人の声から色が消えてしまったのである。
エピローグ。
囚人のいなくなった檻に、いったんは本土に引き上げた看守が、島の様子を見に一人でやってくる。変わってしまった様子に満足し、島の住民を追い返すと檻の中に入ってテレビのスイッチを入れる。
「カンチュラ」の世界選手権で、復活したアズルの演技が実況中継され、優勝が決まるる中、溶暗。
この芝居は、新国立劇場2011/2012シーズンのテーマである「【美×劇】─滅びゆくものに託した美意識」というシリーズの一つとして、倉持裕が劇場の注文に応じて書き下ろしたものである。
シリーズのテーマについては後ほど論評するとして、この芝居における「滅びゆくもの」とそれに託した「美意識」とはなにかということをはっきりさせておこう。
滅んでしまったものとは、あきらかに島の住民の声と言葉からその人間固有の色彩を発するという現象である。それは、人々の発言を相互に監視し合い、嘘も無責任も許さない「ほんとう」だけが行き交う社会であった。
たとえば、アズルは実力においてライに負けていると自覚していて、それが唯一の真実と思っている。スポーツとはそういうものだからだ。ところが、「カンチュラ」とは個人技の採点競技であり、情実が入り込む余地がないとはいえない。スポンサーを奪われた事情も、純粋に実力だけとは言い切れないのだが、アズルは、自分たちの社会は「ほんとう」だけが規範になっていると信じているために、疑うことを知らない。「ほんとう」が支配する社会は善意に満ちているという前提がアズルのなかにある。
また、この社会では、「ファムスタ」についても、メーカーと下請けの間にビジネスパートナーとしての対等の立場が成立していて、支配と被支配の対立は存在しないことになっている。
町長もまた、住民の声を絶えずモニターしていることによって、住民の希望を捉え、善政を施しているつもりである。
つまり、声や言葉、書くものにまで色がつくことによって、嘘も無責任も許さない社会とは、善良な人々の「善意」に基づいている社会なのであった。
ところが、「ほんとう」とされていることには誰にもいえないもう一つの真実、あるいは「ほんとう」に対する言い難い「疑念」が存在していた。それを匿名であるという条件で話すことにより、不確実で誰が発信したか明確でない情報が飛び交うことになる。これは、様々な色彩で彩られている美しい世界の秩序を否定する悪意となってそれまでの社会を覆い尽くすことになった。
この芝居は、発信源がはっきりしていて、確実な情報によるコミュニケーションが成立している社会を一種の理想郷と描いて、圧倒的な情報の力を持つマスメディア、あるいは匿名性の陰に隠れて発信される無責任で不確実な情報がはびこる今日のネット社会のようなものを対置させた寓話と受け止めることができる。
しかし、「ほんとう」と「善意」でできた社会という「おめでたい」発想を素直に受け止めるほどナイーブではない僕のようなものにとっては、いくら「寓意」を込めたと言ってもそれはただの現実、それこそが正しい現実認識ではないかと、せっかくの仕掛けにもさっぱり感動しないのである。
ありもしない理想を思い描いて、それが現実に負けて滅んでいくからといって、誰が惜しいと思うだろうか。あいにくそこに美学を感じるという感性の持ち合わせはなかったので、芝居の骨格だけはわかったが、どうにも無理矢理注文のテーマをこなしただけと言う印象は免れなかった。(もうちょっと考え抜いてくれよ!)
だからといって、何かをやりそこねた失敗作ともいえないのは、メーカーと下請けの構造の問題やスポーツにおける採点競技のあやうさとか町長と追随するだけの議員とか、現に存在するエピソードにそれぞれ現実感があり、それだけでも社会批評になっているからだ。つまり、嘘も無責任も許されないという前提などなくても,人間が生きて行く以上それらの問題は存在する。 色つきの言葉があろうがなかろうが、人間社会は厳然として「本音」と「建前」でできあがっているのである。そこのところの捉え方がかろうじて文学になっており、面白かったといえるのだ。
もしも、もう少しこの芝居で描きたかったことに言及するとすれば、僕が説明するよりも、パンフレットにある作家の倉持裕と演出の鵜山仁が開幕までの期間に交わした往復書簡の中から抜粋する方が早い。
こういう演出家の種明かしはきわめてめずらしいともいえるが、観客が万一芝居を取り損なった場合を考えてのことだったのではないか?というのはいじわるな言い方かな。
鵜山はこう書いている。
色を発する、また発しない言葉のグラデーション、登場人物相互の愛憎がより際立てば、この「島」を巻き込んだ色仕掛けのドラマ、何とか沸点にたどり着けるのではないかと期待しています。
「持てるもの」の独自性を武器に「島」の平準化に抵抗する選手(エリート)。一方、「持たざるもの」たちの反乱が、ついに平等な社会を生み出すことはないだろうという皮肉。そこに絡む男の計算、女の情念、そんな葛藤の渦の中でスポーツが、「犯罪者」が、マスコミが、大衆が、そしてアートが果たす役割、孕む危険。
この島に吹き荒れるのは二律背反の嵐です。では、その嵐が過ぎ去り、一つの価値観が崩壊したあとに、一体何が残るのか・・・・・・最終章の解釈は様々ですが、いずれにせよ、一人ひとりの登場人物の顔が走馬燈のように舞台を回る、そんなエンディングを目指したいな・・・・・・と。
鵜山の言うとおりなら、随分様々なものを詰め込んだ芝居と言う印象になる。確かにディテールにこだわって説明すれば、主要な筋立てから派生するエピソードまでこのような要素で構成されているとはいえる。
ところが、この書き方に端的に表れているように鵜山の演出は、一つ一つの要素を次から次に繰り出していく「段取り仕事」で、それらが有機的に編成されて一つにまとまっていくと言うベクトルをもたない。それは、鵜山の悪いときに出る一種のくせで、大概は戯曲の「でき」に問題があるときに限られる。この本の場合は、無理な設定に問題の原因があったであろう。材料は提供するが、あとは知ったことかという態度なのである。
たとえば、栗山民也ならこういう場合、特定のエピソードに対して、「足を止めて打ち合う」くらいのこだわりを見せつつ、そこを突破口にして全体を繋いでいくという力業を見せようとするのだが、鵜山仁は、存外あっさりと投げ出してしまう。
また、最重要キャストである囚人役に、訳のわからないお笑いタレント(観客によってすでに色がついている)を起用することに栗山なら断固反対しただろう。こうしたことでも、鵜山は案外恬淡としている。
おかげで、観客が囚人役にそれ以上のものを期待するという余計な先入主を与えて損をしてしまった。実際、藤井隆は自分が何をやっているのかサッパリわからない体をさらして仕舞いまで行ったので、どこかで笑わせてくれると期待して肩すかしを食った観客が随分いたのではないか。
(藤井は、大しておかしくも達者でもない役者なのに起用された。TVのせいで集客力を見込めると判断した役人プロデューサーの発想だろう。近頃、そういうキャスティングが多くて、天下り役人の弊害がこんなところにも出ていると腹が立つ。自分のところで養成した役者という財産を使わずに、デパートの中にある劇場と同じことをやっている。)
話が横道にそれてしまったが、要するに鵜山が言おうとしたことは、「本音」と「建前」の二律背反が、結局「本音」の勝ちになり(つまり、それが当たり前の現実)「建前」に慣らされてきた精神はどうなってしまうかと言っているのである。はっきり言っておこう。何の心配もない。彼らはそれが現実だと思って「本音」の社会に慣らされていくだけである。
「建前」の社会が美しいのは気持ちとしてよく分かる。
様々な色彩が飛び交うまるで繪のような世界をあてがって、それが【美×劇】というテーマにぴったりだったろうと倉持裕は言いたいのだ。せいぜいその程度の発想としか考えようがない。
そもそもどんなきれいな色がつこうと、おべんちゃらを言う奴は必ずいるものだし、自分が何を考えているかさえ自覚していないものもいれば、「平気で嘘をつく人々」はどこにでもいるのだから、そんな「色」ははじめから「アセテイル」と言ってもいいようなものだ。
倉持が幻惑されたのは、むしろ「滅びゆくものに託した美意識」の方かもしれない。「滅びゆくもの」とは文字通りなくなるものだが、なくなっていくのに何を託せるのか。これは形容矛盾ではないか? (とまあ、大人げないことを言っても仕方がないか。)
滅んでいくことが時空を超えた「美」として永遠に定着する、くらいの意味合いなのだろうが、なんとまあ、センチメンタルで非現実的なことか。
このシリーズ第一弾の「朱雀家の滅亡」(劇評参照)における「滅びゆくもの」とは「お上=天皇」の統治になる日本国であり、滅ぶことによって「永遠の美」を獲得する(と考えられる)「美しい国、日本」のイメージ=美意識=美学であった。もはや呼び戻すことが出来ない世界に対する甘美でせつない憧憬、そんな気分が思わず「美意識」と言わせた心理の本質にある。せいぜいそれくらいの話にすぎない。永遠と思われる想念も一瞬おとずれる性的オーガズムのようなむなしい快感である。
ただし、三島由紀夫の思い描いた「滅びゆくもの」にはこの戯曲を「理解」して上演したいと思う宮田慶子などの人間がいるほどの現実感と説得力があった。そのセンチメンタリズムには人の共感を誘い、いっとき酔わせるだけの魔力があったのだ。
ところが、どう頭をひねってもそれほど共感を呼び、葬り去ってもなお信じるに足る「美意識」などあるはずもない。そこで、倉持としては、「美意識」を「正直」という倫理・道徳と読み替えて、安易な物語をつくりあげようとしたのである。その結果、滅びることの先に「再生」を見るというとんでもないウルトラCを編み出した。
鵜山仁は、往復書簡でいう。
滅びが美しいのは、つまるところ再生への期待をはらんでいるからでしょう。何かが壊れてしまったとき、そこには、かつてそれを創り上げたエネルギーの全貌が立ち現れる。壊れたあとが更地になれば、またその場所に、新しいものをつくり出すことが出来る。
滅びによって思い知らされた人間の力の有限性は、逆にわれわれに、束の間、有限をはるかに包み込む無限を感じさせてくれる。その脱力感と、新たな可能性の胎動こそが、きっと次の命の始まりなのだろうと、昨夜、友人とギロンしました。
とすればむしろ滅びは生命の、想像力の、創造の源なのかも知れない。
冗談じゃない。不死鳥伝説と間違えているのではないか?
フェニックスは美しい鳥だが600年ごとにヒーリオポリスの神殿で自らに火を放ち、その灰の中から再生する。
しかし、日本的な「滅び」とは文字通り、あとかたもなく消えてなくなることである。イエス・キリストは復活したが、「平家物語」の平氏は永久にこの世から消えた。「諸行無常」である。お初徳兵衛の道行きも「七つの鐘が六なりて、残る一つが今生の鐘の響きの聞き納め・・・寂滅為楽と響くなり」と、この世の生を捨ててあの世での再会を誓い合うのである。「滅びが美しい」とするセンチメントには諸行は無常であるという仏教的世界観にある人生についての一種の諦念とそれからくる寂寥感といったものが潜在している。
倉持が、その意味を取り違えたのは(鵜山の解釈だっただけかも知れない)おそらく若さ故のことだったろう。しかし、鵜山が一見して戯曲と関係なさそうなこの屁理屈を何故思いついたのかは明らかである。
東日本大震災のことを念頭に置いて、この劇の上演を幾ばくか支援の足しにしようとしたのだ。
しかし、津波でさらわれた街を「滅び」と呼ぶのは早計である。「滅び」とは跡形もなく、なくなることだと言ったが、東北の街々は「滅んだ」訳ではない。あの(ファッキンな)仮設住宅にまだ何十万もの人々がいて、日々生活を営んでいる。元に戻すまでの道のりはつらく苦しいものになるだろう。「更地」になったから新しくはじめられるというのは、実に無責任な、よそ者の言に過ぎないし、「再生」という口当たりのいい言葉だけで、なにかがはじまると思ったら大間違いなのだ。そのことは、この間無能をさらけ出した我が国の政治家と官僚の低レベルをあげつらうまでもなく、すでにしてこの地方は再生の気力も萎えるほど「とうの昔に滅んで」いたともいえる。何が均衡ある国土の発展だ。
少なくともここでいえることは、腹の足しにもならない「美意識」を称揚することでも口先で「再生」を歌うことでもない。決定的に不足しているのは、どのように世界を構想するかというラディカルな議論である。倉持もつまらぬ「寓話」など書いていないで、この議論に参加するのがいやしくも芸術家の務めと心得なければならない。
「【美×劇】─滅びゆくものに託した美意識」などという言葉が、もしも70年代までの我が国で目にとまったら、「保守反動、ナンセンス!」の怒号が飛び交ったに違いない。それは現実とまともに向き合わない芸術至上主義の態度であると批難されたのだ。芸術至上主義では、鵜山が言うような「次の命の始まり」が「新たな可能性の胎動」とはならず、「滅んだもの」への憧憬に文字通り「耽溺」する他ないからである。
あれから40年もたって、この屁の突っ張りにもならない言葉に出会って、何とも絶望的な気分になった。新国立劇場が、こんな問題意識なのかと思えば、僕自身がさっさと滅んでしまいたいと思ってしまうものである。
最後に、この芝居は暗に、匿名性のメディアとしてのネット社会批判とも受け止められると書いたことについて。
「アラブの春」を導いたのは、このネットシステムの恩恵に他ならない。匿名の無責任な発言でも共感を獲得すれば力になることが明らかになった。また、米国での経済格差に対する抗議の街頭デモが自然発生的に起きたのはネットによる呼び掛けがきっかけだった。
このメディアは、無責任で、勝手な発言が横行し、ほんとうかどうか疑わしい情報も多く含まれる。
だからといって、新聞やテレビに間違いがないかと言えば、世間をミスリードしたことは枚挙にいとまがない。さらに、権力のチェック機能と言いながら、裏で結託して原発推進を操作するなどの事例に見られるように、油断も隙もならないのである。
ネットについて一つだけいえることは、この便利なメディアの普及によって、アラブにしても米国にしても、人々の自由を棄損する状況にだけは「ノン」の声を上げることに、誰も躊躇しなくなったということである。それは為政者にとって、ますます脅威であり続けるに違いないし、その中から形ある合意が形成される可能性もあるということだ。
既存メディアの多くは、いずれインターネットに吸収されていくのだろうが、どうあれ、僕ら自身のメディアリテラシーを鍛えておかねばならないのは確実である。したがって、この芝居で仮想した色つき言葉の島社会も本土の無色透明社会も同じように住民である僕らの情報への感度が常に鋭敏であることが重要なのである。
さて、最後に役者のことを少し語っておこう。
藤井隆についてはすでに書いた。いっこうに面白くならないまま終わってしまったのは,役柄のせいなのか?
島田歌穂は、実にもったいないキャスティングであった。あの役なら、いなくても劇は成立した。
秀逸だったのは、ベンガルで、登場場面が多いわけではないが、飛び抜けて現実感があった。彼が出てくると舞台が活き活きと起伏に富んだ世界に変わるのである。これは、寓話だろうが何だろうが、いかがわしい戯曲など関係ないと居直ったせいなのか、あるいは彼の地なのか?
あとの役者は、鵜山仁の段取り仕事につきあっただけという無気力きわまりない出来であった。
鵜山が言う「束の間、有限をはるかに包み込む無限を感じさせてくれる。その脱力感」とは正反対のただの脱力感と疲労感に襲われて、ようやくたどった家路であった。
