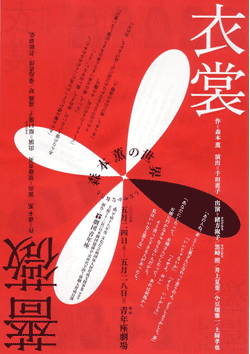 }
}|
題名: |
「衣裳」/「薔薇」 |
|
観劇日: |
06/5/27 |
|
劇場: |
青年座劇場 |
|
主催: |
(社)日本劇団協議会 |
|
期間: |
2006年5月24日〜5月28日 |
|
作: |
森本薫 |
|
演出: |
千田恵子「衣裳」須藤黄英「薔薇」 |
|
美術: |
伊藤雅子 |
|
照明: |
宮野和夫 |
|
衣装: |
|
|
音楽・音響: |
堀江潤・清水麻理子 |
|
出演者: |
『衣裳』緒方淑子 黒崎照 井上夏葉 小豆畑雅一 土師孝也 『薔薇』原口優子 遠藤好 桑島貴洋 若松泰弘 |
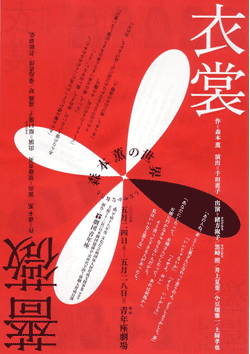 }
}
「衣裳」・「薔薇」主催は青年座とばかり思っていたら、(社)日本劇団協議会・次世代を担う演劇人育成公演というのが正式の勧進元らしい。文化庁芸術団体人材育成支援事業のお金が出ているということだ。次代の芸術のために税金をつぎ込むのに、誰も文句は言わないだろう。心配なのは社団法人に天下りがいないかということだけだ。こんなところにも役人がぶら下がっていたら何をかいわんやだ。
「衣装」・「薔薇」ともに森本薫二十四歳の作品である。およそ五十分の芝居を休憩を挟んで二つ見せる趣向。
これが、若い作家のものかと驚くほど老成していて完成度が高い。なにしろ構成がいい。開幕から適度な緊張感でつなぎ、惹きつけて盛り上げてどんでん返しで、すとんと落とす。絵に描いたように切れ味のいい芝居である。五十分が短いなどとは思わせない濃厚なやりとりで、間然するところがない。
まず、「衣裳」。
洋館の応接間、正面にアーチ型の出窓があり縦型のピアノが置いてある。下手に隣の部屋に通じる薄暗い出入り口、その前にソファと長イス、上手にはティテーブルと椅子が置かれ、応接間は上手手前にある短い廊下で袖とつながっている。舞台奥は、一段高くなった廊下が横切っていて、上手に窓が一個シンボリックに下がっている。下手に出入りの戸口が切ってあり、その先は玄関という想定である。
この伊藤雅子の装置はなかなか工夫してあって、引っ越したばかりのがらんとした洋館の様子を上手く表現していた。しかも、基本的な構造はそのままにして、次の「薔薇」の舞台では避暑地のプール脇や林の中などになったりして違和感がないのだから、これは考え抜いた伊藤の手柄だといってよい。
明かりが入ると、舞子(黒崎照・育成対象者)と嶺(小豆畑雅一)それに舞子の母親、勢喜(井上夏葉)が板付きですでにいる。舞子と嶺は世間話をしているようだが、舞子は煙草をふかし、ひねくれた言い方をする女で、どこかに屈託がある様子である。大人びた物言いをするが、まだ独身で、いい相手がいさえしたらいつでも嫁ぐなどとやや皮肉っぽい調子でいうのに、嶺のほうも容赦なく不遜な態度をとがめ立てする。
実は、この二人の会話を聞いていてもいったいどういう関係なのかはわからない。嶺が丁寧に「お母さん」と勢喜に話しかけて、ようやくそれが義理の仲で、舞子の母親が勢喜だろうと分かるようになっている。
それにしても、嶺が、舞子の妹の千紗(緒方淑子・育成対象者)と結婚しようと思っていて、今夜訪ねてきたがあいにく千紗は勤め先からまだ帰っていなかったということはだいぶ進まないと分からない。三人の会話の中にさりげなく伏線を張りながら次第に関係を明らかにしていく手法は、観客の興味を先へ先へと送って老練な推理作家を思わせる。きわめつけは、嶺がさりげなく下手の隣の部屋の薄暗がりをみて、そこに赤子が寝ていることをほのめかすところである。果たしてその子はなにか?母親はだれか?嶺はどこまで分かっているのか?
と、そこへ玄関に人がきた様子。千紗が帰ってきたと思ったら舞台奥下手の廊下に現れたのは初老の紳士である。別人というところがうまいなあ。応接間に招じ入れられたのは日疋(土師孝也)で、これも初めは何者か分からない。この洋館を探し出して住むように世話したということだけは分かるが、夜更けに訪ねてきたのは何故なのか?どうやら千紗の帰りを待っているようだ。嶺は応対に窮して、無理やり世間話をしかけるが日疋はまともにはとりあわない。
そのうち玄関の辺りが騒々しくなって車の走り去る音などが聞こえると、上の出入り口に千紗が現れる。酔っている。勤め先で仕事が終わってから誘われたというのである。まるで娘っ子が着るようなワンピース姿で髪もおかっぱ、とても女事務員には見えない。勤め先といってもそこは義理で引き受けているような様子が分かる。わがままな性格のようで、居合わせたものの言うことを聞くでもなく勝手なことをいって歩き回るが、足下がおぼつかなくなって、ついに気持ち悪いと言い出す始末。もう部屋で休みなさいと母親がいうと、嶺がかいがいしく抱きかかえて手前の廊下に消える。
日疋が私はついでに寄っただけだからもう帰ると立ち上がったとき、血相を変えた嶺が応接間に飛び込んでくる。そして、日疋につかみかからんばかりに「畜生、ぶん殴ってやりたい。」と激しい剣幕で迫るのだが。その後嶺の口からもれたのは意外な言葉であった。「あの娘は、別れたくないというんだ。」と日疋をにらみつけるところで、観客はああそうだったのかとわかる仕掛けになっている。
演出したのは千田恵子。戯曲もものにする若手の作家兼演出家である。「巨匠森本薫に挑戦」といっているが、解釈がいろいろあって難しかったという意味である。二十四歳の巨匠もないものだが、たしかに演出上の迷いがいくつか見られた。
その一つは姉舞子の存在である。戯曲の言葉通りならば、舞台に現れた人物で申し分ないが、妹千紗との関係が今一つはっきりしない。開幕直後の嶺との屈折した会話の中に千紗との関係を予感させるところが出ていなければならない。千紗は酔っていて天真爛漫でいればそれで許されるといってもいいが、何と言ってもこの劇の磁場の中心にいる。千紗が現れて、舞子はこの千紗の放つ磁力の影響を受けて微妙に変化するはずだ。
それというのも、母親は十三年前に夫を失って寡婦である。舞子には職がない。そして千紗と三人、この一家は千紗を通じて一人の男によって養われている。舞子の屈折はそこに原因がある。そういう意味では母親、勢喜役の井上夏葉の解釈は正鵠を得ていたのではないかと思う。本来この母親の造形を基礎に据えて、その上に他の登場人物を重ねたら座りがいいと考えたがどうか?
育成対象者の二人、黒崎照、緒方淑子の二人は細かな表現にまだ難がある。ディテールにこそ真実は宿る。多分に演出の責任ではあるが。
小豆畑雅一、土師孝也は動と静、ベテランらしく納得のいく演技であった。ただし、小豆畑は結構腕がじゃまになるらしい。
「薔薇」の演出は須藤黄英、これが初演出。千田恵子より二歳下の若手である。こちらの演出は非常に堅実で正攻法、よく考え抜かれていた。役者が皆達者だったせいも大きい。
物語は「衣裳」と比べたらはるかに分かりやすいが、それほど奥行きは感じない。
幕開きは神村(桑島貴洋)の家の応接間、妻の杉江(遠藤好)が訪ねてきた菅(若松泰弘)の応対をしている。神村はあいにく入浴中で、菅と杉江がとりとめなく近況やら昔話をしている。そのうちにこの二人はその昔、恋人同士だったことが明らかになって、舞台はその時代へ一気にさかのぼる。
避暑地の夏、プール脇に菅と杉江がいる。やがてプールから上がった神村が夏子(原口優子・育成対象者)をつれてそこへ現れる。
四人は屈託なく世も山話をして時を過ごしているが、神村はなかなか活発な男でじっとしているのが嫌いらしい。ふとしたきっかけで菅と夏子が二人っきりになる。夏子は明るくて奔放、若さが輝いている。夏子が菅を散歩に誘うと、多少戸惑いながら菅は応じる。
神村が探しに来ても二人は隠れたりしてからかうそぶりだが、こういうことが始まると、いやでも夏子と菅のあいだには共犯意識が生まれる。残された神村と杉江のあいだにどんなことがあったかは描かれていないが、いつの間にか恋人が入れ替わっているところを見れば、もともとの関係はそれほど強い恋愛感情で結ばれてはいなかったかも知れない。
菅は夏子の中に、落ち着いた大人の杉江とは正反対の魅力を感じたに違いないし、夏子の中に菅を誘って虜にしてやろうという野心が燃えた可能性もある。その心模様はそれほどはっきりと描かれたわけではないが、いずれにしても、二人は結婚した。そして神村と杉江も。ここの恋愛心理やいきさつを細かく説明しなかったところが終幕部分に生きている。
それからだいぶ経って、久し振りに菅が神村、杉江夫妻の家へ現れたのが最初の場面である。
舞台は現在へ戻る。神村はまだ風呂から上がってこない。何気なく杉江が夏子の近況を聞いたところから物語は一気に驚きの展開を見せる。
菅が語り始める。
長いあいだに夏子の心は「ある疑い」によって蝕まれていたのだ。菅がいまだに杉江への思いを抱き続けているのではないか?自分は杉江から無理やり菅を奪ったのではなかったか?という疑念が次第に夏子の中で膨らんでいったらしい。
むろん、そういう心の動きは夏子一人では起きようがなく、菅の何かと共鳴して二人のあいだに醸成されていったことに違いない。夏子が自身を追いつめると同時に菅の心も揺れ動いた。菅は自分の身を持て余して杉江のもとを訪ねたのだった。
何も言わず聞いていた杉江が神村を呼びに席を立った。一人取り残された菅・・・
舞台溶暗の後くぐもったピストルの音がする。
戯曲を丁寧に読み込んで、非常に誠実に正確に作り込んだ芝居であった。この最後の場面だけででも、演出家須藤黄英は称賛に値する。
菅をやった若松泰弘がよかった。もともと文学座の役者だから青年座に招聘された理由は定かではないが、女に翻弄されそうな雰囲気があってこれほどの適役はなかなかいない。上体が揺れてなにかに追われているような不安定な心理状態をうまく表した。
杉江の遠藤好は達者というより言葉がない。この人がどっしりと要のところにいたから芝居はリアリティを保った。
夏子の原口優子はこの芝居ただ一人の育成対象者である。ただ、この役者はすでにでき上がっている。コケティッシュで活発、他は幸いあまり複雑な表現はなくてよかったが、そうでなくてもさまざまな役を十分やっていけそうである。あとはいい演出家に出会うことだ。
桑島貴洋は出番が少なかった。
森本薫、恐るべしである。とても二十四歳の作品とは思えない。
「衣裳」には劇の持つ謎解きの面白さと世間の不可思議さを伝える独自の味わいがあってむしろ老練な作家の手腕を思わせる。
また、「薔薇」の方は、もともとラジオドラマとして書かれたものだが、それはともかく恋愛を物語る原典のひとつになったのではないかと思う。この後同様の話を数多くの作家が書いたのではなかったか、ここにそのオリジナルがあったと感じるほどだ。
戦後まもなく結核に倒れて35才でなくなるが、代表作「女の一生」は杉村春子が一千回を越えて演じ続け、今なお文学座によって上演されている。
最後にどうしても分からなかったことについて。
それは、この劇のタイトルである。何故あれが「衣裳」で「薔薇」なのか?
先日「やわらかい服を着て」(永井愛・新国立劇場)のシアタートークでタイトルについて面白い話を聞いた。
作者は本ができ上がってからタイトルを考えようといくつかの候補をメモしていたようだ。しかし、いざとなると、自分では決めかねてプロデューサーに相談した。プロデューサーはスタッフみんなの意見を聞いて、札入れなどはしなかったようだが、実に民主的に決めたのだそうだ。ぴったりだとか意味が分かるとかではない。何となく許せるか、という気になりさえすれば、それでいいというのである。
その伝で行けば、「衣裳」も「薔薇」もあまり深く考えないほうがいい、ということか?
