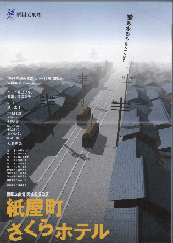
|
題名: |
紙屋町さくらホテル |
|
観劇日: |
97/11/7 |
|
劇場: |
新国立劇場 |
|
主催: |
新国立劇場 |
|
期間: |
1997年10月22日〜11月12日 |
|
作: |
井上ひさし |
|
演出: |
渡辺浩子 |
|
美術: |
堀尾幸男 |
|
照明: |
服部基 |
|
衣装: |
緒方規矩子 |
|
音楽・音響: |
宇野誠一郎 |
|
出演者: |
森光子
梅沢昌代 深沢舞 井川比佐志 辻萬長 三田和代 松本きょうじ 小野武彦 大滝秀治 |
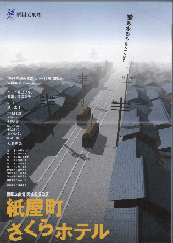
「 紙屋町さくらホテル」 (’97)
この芝居は、新国立劇場のこけら落としである。これをみた97年秋に僕は母親宛に手紙を書いている。そのなかに短い感想を述べたところがあったので、それをここに掲載することにする。
いま思い出しながらあらためて稿を起こすより、当時の心情が伝わると思うので。 また、2001年の再演も見ているので、ここで触れていないことなどをそっちの感想に書こうと思っている。
「拝啓、おふくろ様 その後お変わりありませんか?先日お送りした「石原莞爾」を巡るお話は楽しんでいただけたでしょうか。 あのあと、ふとしたきっかけで、国柱会がまだ存在することが分かりました。田中智学が僧籍を得た一之江〈江戸川区〉の寺が本拠になっていることまではわかったのですが、いまいったいどのような活動をやっているものか興味の湧くところです。まさか、この時代に国粋主義でもないでしょうが。
さて、先日新国立劇場のこけら落としに行ってきました。近所に出来たのでたいへん便利です。最近建った東京国際フォーラム〈旧都庁跡地〉などもそうですが、これまでの建築に比べて内部の空間がかなり広くとられるようになったと感じました。照明にも新しい工夫がみられ、設計全体がなかなか気分のいい空間に仕上がっています。 もっとも、オペラ、新劇、小劇場と大きさの異なる三つの劇場がどこに配置されているのかすぐには判然としないため、ひどく歩かされ、中劇場にたどり着くのに息切れしてしまいました。
客席は、天井が高く、すり鉢状にしたにいくほど狭くなる古代ギリシャ、ローマの野外劇場風で、椅子はそれぞれゆったりとつくられています。詰めたら2000人は入りそうですが、これで最大1200人ですから、興行的にはともかく、観客にとっては有り難いことです。
だしものは井上ひさしの書き下ろし「紙屋町さくらホテル」。広島で被爆した丸山定夫率いる移動劇団の話を虚実取り混ぜて喜劇に仕立てた井上得意の世界で、彼が珍しく開幕に間に合わせることが出来た芝居です。もっとも、開幕12日前に、かろうじて脚本が上がったのだとあとで分かりましたが〈注文したのは3年前〉。
三十年前、日生劇場のこけら落としはジャン・ポール・サルトル作「悪魔と神」〈尾上松緑、日下武史〉でした。作品の主題といい、スケールといい浅利慶太が最先端の新劇を見せようと意気込んで見事に成功した芝居でした。面白いものをやろうとしたら、あの当時はやはり海外に作品を求めなければならない時代でした。 そしていま新国立劇場のこけら落としが、井上ひさしであることに感慨を覚えています。 井上ひさしは、軍や国家を批判します。一貫して庶民の立場から権力に抵抗します。国立劇場が、国家や権力に抵抗する芝居を許容するようになったことは、新劇の歴史を思うと隔世の感があります。
さて、舞台には緞帳がなく、がらんとした空間に、高い天井からいく筋かの照明りが斜めにさしています。舞台奥は、相当に深くしたがって真っ暗で何も見えません。客席と同じくらいの奥行きがあると思わせる大きな舞台です。 溶暗。真っ暗やみの中で、音楽。 オーケストラがそこで演奏しているような臨場感のある音響効果に驚きます。
照明りが入ると、舞台手前に、いつの間にか机と椅子が置かれ、大滝修司、小野武彦が板についています。巣鴨プリズンに出頭してきた海軍大将〈大滝〉と元陸軍大佐、いまはGHQのスタッフ(小野)のやり取りがあり、回想シーンになろうとしたとき、遠くから「スミレの花咲くころ」のコーラスが聞こえてきます。 何と、舞台の中央部分が下にすこし動いたかと思ったら、真っ暗な奥の方からその空隙いっぱいに張られた巨大な板の上にのせられた、大きな舞台装置が周りながらこちらに進んでくるのです。歌声はそこから聞こえてくるのでした。
森光子を主役に持ってきたところは、いかにも商業主義でいやらしいと思いましたが、さすがに渡辺浩子プロデューサー〈兼演出〉、全体として最良のキャスティングが出来たようです。梅沢昌代は文学座のじつに達者な役者です。三田和代のただならぬ才能はますます磨きがかかってきたし、井川比佐志の存在感、枯れた大滝修司もいい。辻萬長はいの上芝居の常連、小野武彦、松本きょうじも守備範囲の広い役者です。井上の脚本に付き物の歌を伴奏する新しい奏者兼役者がまだ学生のかわいい深沢舞、と申し分のない配置でした。
今後国立劇場がどうなっていくか、興味のあるところですが、渡辺浩子芸術監督のことですから、あまり間違った方向には行かないだろうと期待しています。国立劇場が権威になるのはいいとしても、その権威が俳優の鑑札を出すようになっては、この国の芝居はダメになるだろうと思います。
もともと、イギリスをはじめヨーロッパの演劇や音楽は大衆向けのものがなかったわけではありませんが、その多くは貴族がスポンサーになって、練り上げてきた俳優養成と興行のシステムです。 日本の演劇は、貴族化した武士をパトロンとして室町に始まり、やがて江戸でもっとも盛んになります。その芝居小屋にお金を落としたのは、支配階級ではなくて庶民でした。歌舞伎以外にも数多くの大衆娯楽が庶民の手で生み出され育てられてきたことは周知のとおりです。
今も、おそらくこれからもそのエネルギーは変わらないと思います。 国立劇場がこういうエネルギーに対抗するするような権威になってはおしまいで、むしろそれをかき立てていく存在にならないといけないと思います。 この国では、小劇場が時にはテントを張って客を集め、あるいは街角をゲリラ的に「開放して」舞台にするようなアンチエスタブリッシュメントも。今もどこかの温泉で年寄りの涙を誘う出し物を披露している旅芸人の泥臭い芝居も、観客を集めて見せるに値するなら大道芸だって認めなければならない。 国が国体などといういかめしい概念で国民の上に重くのしかかっていた時代、侵略から堅く身を守っていなければならなかった時代はすでに遠い。
経済の主導権が、消費する市民の手に渡ったときに、国家の役割はかなり小さくなったと思うのです。 そんなことを考えながら、新国立劇場の行く末を見守っていこうと思っています。 敬具」
