

|
題 名: |
木の皿 |
|
観劇日: |
06/6/23 |
|
劇場: |
本多劇場 |
|
主催: |
加藤健一事務所 |
|
期間: |
2006年6月23日〜7月2日 |
|
作: |
エドマンド・モリス |
|
翻訳: |
小田島恒志 |
|
演出: |
久世龍之介 |
|
美術: |
石井強司 |
|
照明: |
五十嵐正夫 |
|
衣装: |
|
|
音楽: |
|
|
出演者: |
加藤健一 大西多摩恵 加藤忍 鈴木一功 平田敦子 44北川 伊藤順 はざまみゆき 大島宇三郎 有福正志 |
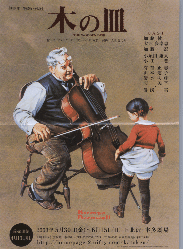
「木の皿」1952年、米国テキサス州の田舎町での出来事。78歳になったロン・デニソン(加藤健一)は、次男のグレン・デニソン(鈴木一功)一家と一緒に暮らしている。年を取って体力も視力も衰え、物を壊したり、煙草の火でぼや騒ぎなど、少しばかりボケもやってきていた。普段面倒を見ているグレンの妻のクララ(大西多摩恵)は、もはや限界とばかりに、ロンを老人ホームに預けることを提案、聞き入れてくれなければ家を出ると宣言する。ロンが素直に応じるわけがないと思っているグレンは、シカゴに住んでいる兄で長男のフロイド(大島宇三郎)に連絡、説得と費用分担を願い出ることにする。なんと16年ぶりに父親を訪ねてきた兄は、なるべくならかかわりたくないという態度、しぶしぶ費用負担は承知して早々にかえろうとする。しかし、老人ホームがどんなところか知っているグレンは、ぎりぎりまで決心がつかない・・・
米国の50年代といえば、長かった大戦に疲弊してミゼラブルな状態の欧州、同じく敗戦国として貧乏のどん底にあえいでいた日本を尻目に、一人勝ちの好景気を謳歌していた。ブロンディおばさんが、ギンガムチェックのテーブルクロスの上にオーブンからとり出したご馳走を広げ、「アイラブルーシー」は底抜けに明るいアメリカンウェイオブライフを見せつけてくれた。大型冷蔵庫はじめ夥しい電化製品、自家用自動車・・・我々が目指す豊かさとはまさにこれだと世界の誰もが確信した。
この一家も、グレンの同僚の若者エド・メイスン(44北川)を間借り人に置くほどの大きな家に住んで「アイラブルーシー」とまではいかないが、極く普通の生活をしているように見える。しかし、実は週給50ドルの給料では老人ホームの費用を捻出するほどの余裕はなかった。
これが一応平均的な米国人の暮らしだとすれば(テキサス州が格別プアーホワイトのエリアとは聞いたことがないから)我々があこがれた消費生活の裏には経済の問題も家族の問題も現実のこととしてしっかりと存在していたのである。
この芝居を見ながら、まず考えさせられたのはそのイメージの落差であった。豊かさを享受するための収入は誰にも約束されたものではなかった。皆、ぎりぎりのところで暮らしていたのである。
そういえば「セールスマンの死」のウイリー・ローマンのせりふに「ローンを払い終わった頃に必ず壊れる電器製品・・・」というのがあった。壊れた頃には購入すべき新製品が用意されている。消費は美徳との掛け声のもと、我々は二十日鼠のように永久に止まらない輪の中にのせられて回転しているようなものだ。消費至上主義の本質はそこにあった。
しかし、その頃我々には、輝けるフィフティーズしか見えていなかった。オープンカーでデートする若者、居間でテレビを見るハッピーな家族、蛇口からお湯が出てくる生活、アメリカ人はなんて幸福なのだろう。
初演は54年で、ヒットしたようだが、その頃すでに身につまされる思いで多くの観客が劇場に足を運んだことだろう。
そして、いま半世紀を経た日本では、最大マジョリティである団塊の世代にとって、まずは息子グレン・デニソンの立場として、現実の問題となっているのである。やがてまもなく老人ロンの立場になるのはいうまでもない。日本の観客にとって、この芝居はひとごととは思えない深刻なテーマを差し出しているのである。
僕の同期生たちの中には、早期退職をして親の面倒を見ているものが少なからずいる。週末のたびに故郷の親の元を訪れているものもいる。あるいは90歳を過ぎた故郷の父親の元に単身で住み込んでしまった女性の同級生もいた。何れにせよ80歳前後になった親の世話をすることはたいへんには違いないが、誰かがやらなければいけない。我々ならどう考えるか?
この芝居は、老人問題を巡って「家族」というものの考え方を提示したといえるが、物語としてもそれぞれの人物像も極めてよく出来ている。米国で何度も再演された所以であるが、仔細に眺めると、我々日本人と米国人との考え方の差は歴然としてある。そう思った。それは指摘しておいてもいいのではないかと考えたのだが、しかし、それに異を唱えるものもいたので驚いている。何が正しいか、答えはそれぞれが考えることなのではあるが・・・
ロンを老人ホームに預けることを言い出したのはクララである。クララはこのボケの始まった舅が失態を繰り返すのが許せない。目を離した隙に何をしでかすか分からないと思えば、気の休まる暇も無いのである。
娘のスーザン(加藤忍)は19才になって独り立ち出来そうだ。クララにとっては子育ても終わり、来し方を振り返ってみる余裕も生まれる頃だ。結婚して子供が産まれ夢中でここまでやってきたが、気がつくと卯建の上がらない亭主と頑固でボケのきている舅がいるだけだ。自分はまだ若い。スタイルだって衰えてはいない、いまなら人生をやり直せると思ったのは無理もないことである。
そのきっかけとなったのは間借り人の若いエド・メイスンの存在であった。この男の熱い視線にクララの中の女が目覚めた。しかし、エドが自分に惚れてここから連れ出してくれると考えるほど初心ではなかった。とは言え、舅があくまでも居座るのならここの生活を捨ててもいいと覚悟するほど煮詰まっていたのである。
僕はクララの考え方に強烈な「個人主義」を感じた。亭主とは惚れて結婚したが、いまとなっては収入も少なく優柔不断で一緒にいても面白くない。つまりはたいした男ではなかった。舅は威張りくさった典型的なテキサス男でもはや面倒見切れない。自分は自分、一人でもやっていける。何故、私が我慢してこんな家にとどまっている必要があるだろうか?そこにはまともな「個人」が家族を構成していなければならないという前提がある。クララにとって家族とは完全な「個人」の集まりでなければならないのだ。
一方、ロンは身体が利かなくなったこともボケが始まったことも分からないわけではないが、それを認めたくない。自分はまともで一人前だと思っている。いまだってディビー・クロケットのつもりになってアラモの砦に駆けつけようという勢いだ。皿を落としてこわすというので、木製の皿でオートミールを与えられ、それが屈辱だと怒っている。実はいつかはこの家を出て、チェッカー仲間のサム・イェーガー(有福正志)と農場を買って二人で暮らすことを密かに夢見ている。自分で自分の面倒を見るのが一人前の男のすることだ。ここにも「個人」がいる。ただしこちらは年老いて肉体的には欠陥だらけの精神的なだけの「個人」である。
長男のフロイドは、16年間父親の元を訪れていなかった。したがって彼の家族について、ロンは何も知らされていなかった。写真は忘れてきたのか見せる気も無かったのか持っていない。その晩、子供の頃の思いで話になって、フロイドは父親に抱きついておいおい泣いた。16年、自分の生活があったのだと言い訳をする息子の肩をたたいて、ロンはそれを慰める。お前にはお前の暮らしがある、そのことは理解している。俺にも俺の暮らしがある、だから心配するな。というわけである。ロンにはあと二人の子供がいるが、こちらはグレンの呼びかけに返事すらよこさなかった。それにしても、義絶の仲でもなく16年も平気で会わない親子というものがはたして我が国にいるだろうか?親と子には違いないが、ここにも「個人」と「個人」がいる。
結局、クララとの仲を取り戻すために、グレンは父親を老人ホームに入れると決心する。その日、反対していた孫娘のスーザンが、サム・イェーガーが暮らすホテルの一室を借りてロンと一緒に暮らそうと契約をしてきた。鍵を差し出すスーザンにロンは、いまの自分には老人ホームという地獄と戦うことが当面の目標だといってそれを断る。「個人」の尊厳とはそういうものだと云おうとしたのかも知れない。
力なく老人ホームに向かうロンをクララはじっと見ていた。ついに勝利したと思ったのか、それともちょっとは後ろめたかったのか、それはわからない。
初演で加藤健一は、父親を老人ホームに追いやるかどうかで悩む次男グレン役を演ったが、今度は得意の老け役ロンに挑んだ。いよいよ覚悟を決めて家を出る段になったら急に元気になったのはご愛嬌か?クララ役の大西多摩恵も適役といえる。チェッカー仲間のサム、有福正志が飄々として味わい深い老人ぶりだった。全体に久世竜之介の演出は納得のいくもので、俳優のアンサンブルも極めてよかった。本のできがいいとすべてがうまくいく、ということだろう。
この物語は、人情話的な要素の陰に、非常に合理的で冷たい思想が潜んでいると思う。夫も妻も、親も子もまずは「個人」として存在し、その上でどのような関係を結ぶか、極論すると理にかなった方法で契約するのが結果として家族であるとなりそうである。しかも、そうした「個人」を基本単位にした個人主義が米国の民主主義の基礎となっている。そういうことをいやおうなく考えさせられた芝居だった。
我が国では、おそらくクララは「鬼嫁」と呼ばれる。ロンは、老いを認められない欠陥老人として、再教育の対象にしなければならない。つまり老成する必要がある。16年間親と会わない子供はおそらく我が国にいない。こんなことが普通に見える国なんてどこかおかしいに決まっている。
どうしてこんなにも違うのか考えてみた。
この芝居の舞台になった50年代の日本は、まだ戦前である。戦後民法が改正されて、家長制はなくなったが、実際に進駐軍が考えた民主的な民法が機能し始めるのは高度成長に沿ってのことである。新しい民法の概念では「個人」が基本的な単位だが、旧民法のそれは「家」であった。「家」は、思想的には儒教の考え方と一致しているから根拠はそこにあるといってもいいかもしれない。しかし、乱暴にいえば、丸山真男ではないが、おそらく我が国において農耕社会が成立するプロセス、いわばその古層においてでき上がった社会システムであろう。封建時代を通じて武家社会を維持する基本概念だったが、明治維新においてもそれを変える必要はなかった(近代化とは考えなかった)ためにそのまま明治憲法下で法制化された。「家」には家長がいて、「家族」がいた。家長は50歳にもなれば、隠居して家督を長男に譲る。次男以下は「家」からでることになるが、父親と母親の面倒は家長を継いだ長男が見ることになる。かくて三代にわたる家族が同居するスタイルが長い間我が国の家庭の姿であった。
戦後の新しい民法は個人が基本単位だから男も女も同等の権利が与えられた。これは現実にみあった当然の変化である。また、戸籍に「家」という概念はなくなった。「家」に縛りつけられることはなくなったのである。同じ頃、地方から都会へでて働くことが多くなった。核家族の増加である。
スタイルが変って、新しい民法の精神は着々と浸透しつつあるが、実際に「家」とういう考えがすたれたわけではない。結婚式は○○家と○○家として行われる。盆暮れの鉄道や道路の混雑は「故郷」という家への繋がりを示している。つまり、いまだに人間関係はウエットなのである。年取った親が一人で暮らしていれば、時々様子を見に故郷を訪れる。動けなくなれば、早期退職を願い出て面倒を見る。少なくても我々の世代まではそういう感覚でいる。
法的には「個人」であっても、我々には徹頭徹尾、他と切り離された孤独な「個」という「個人」でいることは出来ない。それが出来るのは「神」という存在が孤独を救ってくれる、「個」を保証してくれると考える場合だけである。我々の「個」は関係性の中の個であり、それは互いが保証するものである。
これから我が国がどう変化していくかは分からないが、この根本のところはあまり変らないような気がしている。
実は、僕は長男だが、両親は年の離れた三男にまかせてしまったからあまり偉そうなことをいえない。しかし、この芝居の長男フロイドの生き方を肯定するわけには行かない。
クララにしても、ロンは78歳、あと何年生きられるか知れたものではない。もう少し寛容の精神で、ロンの幸福な最後を見届けてやることは出来なかったものかと思う。
日本人ならきっとそう思うに違いないと言ったら、Yが猛烈に異を唱えた。
あんな頑固爺は、さっさと老人ホームでもどこでも送り込むべきだというのである。自分が老いて身体が言うことをきかなくなったことも自覚出来ない。家のものに迷惑をかけていながら、口を開けば偉そうなことを言う。こういう爺さんがもっとも始末に負えないのだと語気荒く言う。
僕は、最後の場面を見てみんなが「ロンはかわいそうだな」と感じるに違いないと思ったのだが、クララの言い分は当然だという見方があるのに驚いた。
同時に、日本人のウエットな感覚はこれから大いに変るのかも知れないといやな予感がした。いやな予感は暗雲のように広がって何やら落ち着かない気分にさせられる。
やがて気がついた。それは、なんのことはない、僕に対する警告ではなかったのか?