

|
題名: |
奇跡の人 |
|
観劇日: |
03/3/28 |
|
劇場: |
シアターコクーン |
|
主催: |
ホリプロ |
|
期間: |
2003年3月2日〜4月5日 |
|
作: |
ウイリアム・ギブソン |
|
翻訳: |
額田やえ子 |
|
演出: |
鈴木裕美 |
|
美術: |
堀尾幸男 |
|
照明: |
小川幾雄 |
|
衣装: |
八重田喜美子 |
|
音楽: |
井上正弘 |
|
出演者: |
大竹しのぶ
鈴木杏 キムラ緑子 吉田綱太郎 長塚圭史 歌川雅子 松金よね子 辻萬長 田鍋謙一郎 小椋あずき 小村裕次郎 岡本易代
日向葵子 小林洋子 鈴木美紗 石丸椎菜 黒沢朋世 |
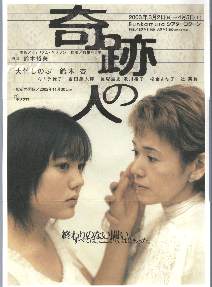
「奇跡の人」
確か中学英語の教材だったと思うが、手押しポンプからほとばしる水を手に浴びて、この冷たくてさらさらと流れる気持ちの良いもの、これはWATERと言うものなのだとヘレン・ケラーがはじめて理解する有名な場面をいまでも覚えている。英語とは言えその行間からあふれかえってくる幼いヘレンの瑞々しい歓喜が伝わってきて、「人間てすごいなあ」と感動したものだ。 ところが、三重苦という困難をどのように克服したのか、そこに至るまで、どんなことがあったのかまったく記憶がないのは、おそらく自伝からそこだけ抜粋したものを学んだからに違いない。
僕にとってこの芝居は、まさにその長い欠落を補う物語であった。
僕らは、普段ほとんど意識していないが、言葉でものを考えている。伝達手段としての言葉の前に、既に言葉によって光景を描写したり、とりわけ抽象的な事柄について思いをいたすときは言葉によって以外に何も構成できない。いったい僕らはこの言葉というものをどのようにして手に入れるのだろうか。人間の子供は生まれて数ヶ月の間に五十万語もの言葉を浴びせかけられ、それらが脳の成長に応じて段階的に蓄積されていくという。これは僕らのまわりの子供をみていれば普通にわかる過程である。
しかし、耳が聞こえず目も見えない子供にとっては、この言葉を獲得する自然の回路が遮断されている。脳は成長に応じて発達するが、そこに受容されるのは唯一触覚だけと言う世界は僕らには想像しにくい。もちろん、自分と他者の区別、ものの存在あるいは気配と言うところまでは感得することが出来るだろう。とは言えこの子供が社会で生きて行くためには、決定的に他者との意志の疎通が必要である。そのコミュニケーション手段は言葉なのだが、この抽象的なものをどのようにして理解させることが出来るのか?僕は、それは絶望的に困難な課題ではないかと思っていた。そして、ヘレン・ケラーがその宿命と格闘していた時期が、日本に置き換えると、ようやく鹿鳴館時代にさしかかるころであり、この時代の医学を思えば、ますます途方に暮れたのではないかと想像した。
ところが、それは僕の思い込みにすぎなかった。 僕はこの芝居を観るまで知らなかったが、物理学者グラハム・ベルは、どんな事情からか聾唖教育に携わっていたようだ。電話とはその研究の成果として誕生した発明だったというから、意外にも、この時代の聾唖教育はいまと遜色のないほどの水準にあったのではないかと認識を新たにした。いや、そういえば誰でもヘレン・ケラーになれるという誤解を生むが、「手がかりはある、しかしその先は本人次第」というレベルでの方法論は確立していたという意味である。 そのベルとの縁で、パーキンス盲学校にいたアニー・サリバンとヘレン・ケラーが出会うことになる。サリバン先生(大竹しのぶ)がはじめてケラー家にやってきた日、暴れるヘレン(鈴木杏)の手を取って、指で作ったアルファベットを押し付けるのを見て、僕は「ああそうか」と合点がいった。この子にとって、脳が受け取れる、ただひとつ外界に開いた感覚器官は触覚である。この触れるという行為を通じて、言葉を脳に送り込み、それが意味するものを理解させ文法を教え、その先に文章を構成させると言う過程こそその方法だったのだ。ただし、指で作った形が何か意味のあるものだと気づくまで何年かかるか、なんの保証もないのである。ヘレンの母親ケート(キムラ緑子)がわたしも手伝うというと、サリバンは自分の百万回が半分に減ると思えば助かるというが、それほど困難で根気のいる仕事なのである。
そのか細い可能性について、父親のアーサー(辻萬長)をはじめとするケラー家の人々はあまり理解を示していなかった。サリバンの若さも信頼を得るには障害だった。その方法についても、たとえは適切ではないかもしれないが、自分がモールス信号を受け取っても解読できないと思えば、無駄なことだ。そう感じるのは当たり前である。感官と受容器と言う脳を巡るフィジカルな構図=考え方自体がまだ一般的でなかったと言う事情もあっただろう。
しかし、サリバンは自身が盲人であった時期を持つ身であり、盲学校で得た学識にしたがって、その方法以外に道はないと確信していた。ヘレンの知能の高さを見通したサリバンは、言葉の存在を認知するという一点が開けば怒濤のようにそれが流れ込み、彼女に全く新しい世界が始まることを信じていた。 この若いサリバンの方法に一時は解雇まで考慮するほど疑いを持ちながら、次第に協力的になっていくケラー家の人々がこの芝居にそれぞれの陰影を投げ掛ける。
南北戦争の退役軍人である南部保守の典型をみるような父親アーサー・ケラー。サリバンの理解者であるが、それにも増してヘレンへ偏愛を注ぐ母親ケート。アーサーの先妻の息子で、父親に対して屈折した感情を表すジェイムズ。ヘレンの伯母エヴ。召使いヴァイニーの一家。 この戯曲の主旋律がヘレンとサリバンだとすれば、これらのわき役達は伴奏として、それぞれがどのような音を奏でればよいのか難しいところである。 演出の鈴木裕美がこの点をかなり考え抜いた形跡は感じられる。 父親アーサーの厳格であろうとして腰折れになる喜劇性を、極く押さえた形で造形したのは辻萬長の力もあっただろうが、伴奏音のバランスの良さという点で成功していた。
母親ケートのサリバンへの信頼とヘレンへの偏愛は(その間で揺れ動く心情も含めて)もっとめりはりをつけて表現しなければならなかった。期限を切ってヘレンを預け、その二週間がすぎたら取り戻そうとする、そんなサリバンへの信頼とはどういうものだったのか。その愚かしい母親の一面を、キムラ緑子が曖昧に演じたことに責任があるとしたものではないだろう。
問題は、ジェイムズ(長塚圭史)の存在である。ヘレン・ケラーにとってこの義理の兄の存在が実際どういうものだったのか僕は知らない。この芝居で見るかぎり、父親とのいさかい、継母への反感はわかるが、一方でヘレンとサリバンにとって、彼はなにものだったのか?いいかえれば彼はこの物語にどのような伴奏を奏でるべきだったのか。その課題に鈴木裕美は明確な答えを出したとは言い難い。
伯母エヴについては、わずかな登場場面にすぎないが、松金よね子の力技に任せた感があった。
鈴木裕美は、確かに才能のある演出家に違いない。
かなり昔の話になるが、会社のマーケティング担当者だったころ、ある日女子大生がアポ無しで、演劇の公演パンフに広告が欲しいという用件で訪ねてきた。割にキュートなお嬢さんで、「どんな芝居か、内容次第では」と応えると、「出してくれる可能性があるんですか」と驚いた様子だった。説明できるものをつれてくるというので、「では後日改めて」というと、慌てて待ってくれという。そのものが近所にいるのですぐにつれてくるというのだ。これは試されたなと僕は気分を害した。五分もしないうちに、年の割に老け顔で目だけがくりくりしている女の子をつれて戻ってきた。態度がでかくて親分肌、いかにもチャーミングな斥候を放って相手を探るといった戦略を考えそうな猪口才な印象だった。どすのきいた声で理屈っぽいことを話していたが僕にはチンプンカンプンだったと記憶している。
それが、自転車キンクリートを作ったばかりの鈴木裕美だった。 こういうタイプの人は演出家に向いているといえるだろう。事実その後の活躍は折に触れ目に付いていた。最近は「OUT」の演出を見ている。 この芝居もそうだが、ディティールの作りにはかなりの気配りが感じられるが、構想力というか、全体の骨格を組み上げることにツメの甘さを感じることがある。例えば、この芝居は三幕の構成であるが、それぞれの締めくくりをもっと印象深くして、観客が物語の進行を確かめるという方法もあっただろうと思う。「OUT」の時もこの、舞台の上に句読点を打つような作業に欠けているという印象を受けた。 既にいくつか演劇賞をとっている実績は分かるが、上るべき階段はまだ目の前にあるといっておきたい。さて、大竹しのぶである。 大竹しのぶはアニー・サリバンを八十六年から演じている。当たり役で、はまり役といっていいのかもしれない。だから台詞はしっかり入っているはずである。しかし、この入っていることがわざわいして、せっかちに歯切れが悪くなり聞き取れないことが何度かあった。入魂の、と言ってしまえばそれまでだが、俳優の仕事は「言葉」を観客に渡すことだ。この基本を忘れては舞台は成立しない。大竹には「我流」の台詞術があるだけだと知っているはずの鈴木裕美がこれを放置したのは情けない。
ヘレン・ケラーの鈴木杏については力演だったが、他を見ていないので未知数としか言い様がない。ただ、感がよさそうな印象は受けた。俳優として大事な要素だ。安孫子里香、荻野目慶子、中島朋子、寺島しのぶ、菅野美穂、そして六代目の鈴木杏がこれらの系譜にふさわしいかどうか、これからであろう。 俳優に関して最後に少し気になったことがある。赤ん坊のヘレンを診察した医者(吉田鋼太郎が盲学校の校長アナグノスと二役)は、扮装はかなりの老人なのに、声が極めて若々しかった。あれは、冗談だったのか?堀尾幸男の装置は、回り舞台が忙しかったが、シンプルで好感が持てた。いつも思うが、ドアの建て付けは見ているほうが心配になる。何かしっかり固定できる方法はないものだろうか?
つい最近、ある講演で、東大教授でヘレン・ケラーと同じ障害を持つ方がいること聞いた。日本語の手話いや触話というのであろうか、それは、両手の十本の指と関節を使って五十音表に基づいて行われるのだそうである。ボランティアの助けを借りて、当然だが難しい学術論文も書くという。 こういう話を聞くと、冒頭にも書いたが、あらためて「人間てすごいなあ」と思う。「奇跡の人」が繰り返し上演されるのは、どんなことがあっても生きていく、その勇気を観客に与えてくれるからであろう。そして、ヘレン・ケラーが言葉というものを獲得して「人間」になる瞬間のあふれかえる歓喜は、誰にでも理解でき、感動を呼ぶものだ。それがほとばしる水によってもたらされたこと、その清涼感が、ヘレンのその後の生き方と相まって、この物語をいっそう高貴で香り高いものにしている。(2003/4/4)