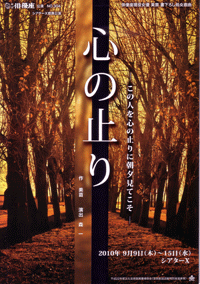
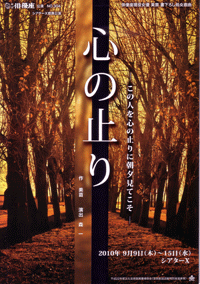
「心の止り」―この人を心の止まりに朝夕見てこそ―あまり深く考えないたちなので、未だにタイトルの意味がわからない。「心の止まり」という言葉ははじめて目にした。「止まり木」なら何となくわかる。「心の止まり」という慣用句があるのかと思って検索したら真っ先に「心臓が止まる。急性心不全」などが出てきたので、たぶん「心の止まり」は造語なのだろう。そう勝手に思ってしまった。
誰かを「心の止まりに朝夕見てこそ」のあとに続く言葉も想像ができない。想像はできないが、何となくこれは女の脳が考えついた言葉ではないかと思った。
「朝夕見る」とは毎日あるいは四六時中見ていることだから、それは男には無理だ。男の脳は日常性を感じるには散漫で、気まぐれかつ集中力がないから、何かに心を止めてしつこく執着することができない。論理的に発展させないと気が済まないから気がついた時にはとんでもなく離れたところにきている。一所にとどまっていられないのである。
こんなことを言うのも、劇の中に脳の話が出てくるからだが、それは神経細胞を電気が走るというようなことで、男と女の脳の違いについてではない。最近、男女の脳の差異について俄勉強したばかりなのでついでに、知ったかぶりを言ってしまった。
結局、劇を見終わってからも「心の止まり」はわからなかった。自分は「この人を心の止まりに朝夕見てこそ」などという心境もひょっとして「詩心」も理解できない朴念仁だと思って、考えるのを結局あきらめてしまった。明かりが入ると、引っ越しの最中である。
ごく普通の民家のダイニングテーブルを置いた居間で、手前に縁側の廊下、上手の壁にカウンターを切った台所がある。縁側の上がり口には踏み石、庭の所々にこぶし大の石を数個づつまとめたものが意味ありげにおかれている。
山室修一(村上博)、響子(片山万由美)夫妻の家である。
下手にはドアを隔ててもう一つの部屋があり、引っ越しはそこへ新たな住人が入るものであった。山室夫妻が長男の家族と同居するために増築した二世帯住宅だったが、長男が米国に住むことになったために人に貸すことにしたのである。
部屋を借りることになったのは、夫をガンでなくしたばかりの瀬尾鮎子(美苗)、都心から郊外のこの地に移ってピアノを教えながら傷心を癒すつもりである。
山室修一は、大学を定年退職した考古学の元教授。妻が勝手に決めた貸家のことでは明らかに不快の様子である。
縁の下から家の外壁に、暗い緑色の分厚い書籍を模した固まりを煉瓦に見たてて途方もない数を積み上げてある。最前列で見たからか、目障りであった。これが後ろからどんな風に見えるのか分からなかったが、こういうアブストラクトとありふれた民家のたたずまいとは全く調和しない。学者の家だからその雰囲気をだそうとしたものか。それが田中敏恵の狙いだったとしても、引退したこの学者は今や、からきし知的でも威厳があるでもない。ただの不器用なだめ亭主という内容からいうと何かの勘違いではなかったかと思われる。引っ越し屋の屈強な若者二人、勝俣真司(小田伸泰)と小出賢(蔵本康文)が梱包したグランドピアノを運び込んで一段落したところへ、 鮎子の引っ越し先を聞いてきたという、見知らぬ女が訪ねてくる。
女優と名乗る叶美咲(荒木真有美)は、鮎子の亡くなった夫の愛人であったという。六年ほど前から関係があった。しかも、いまお腹の中には夫の子が宿っているといわれてショックを受ける。鮎子は全く気づいていなかった。にわかには信じがたいといって拒絶するが、叶は妊娠中の子供の認知をしてくれたらそれ以上のことは言わないと言って帰る。作曲家であった夫との思い出の中に、そのような兆候は感じられなかった。ピアノの生徒も集まりだして教室が順調に行き始めたある日、鮎子が庭の所々におかれた小石に興味を持って見ているところを山室修一が見かける。修一は、突然やってきた同居人のことを内心迷惑と思って遠ざけていたが、鮎子が小石に関心を示しているのを見て思わず声をかける。小石は、発掘調査に出かけた沙漠から持ち帰ったもので、それ自身に格別の価値はなかったが、修一にとっては大事なもののようであった。
鮎子は触っていけないものだったのかと恐縮するが、修一は意外にも差し上げてもかまわないという。それが、始まりだった。いや、始まりだと作者が言いたげなのはよく分かった。
小石を鮎子の手のひらにのせて、修一が言うには「沙漠の夜はすばらしい」と言う意外な言葉であった。手を伸ばせば届きそうな満天の星、それがどんなに感動的なものかを思い詰めたような形相で説明し始める。鮎子も思わず、星の話をうけて宇宙の神秘について語る。
ビッグバンの後、宇宙が冷えていくと同時に水素のような単純な原子が生まれ、やがていくつかの陽子や中性子や電子が集まりさまざまの原子ができあがったがそれだけではどんなに重い原子でもせいぜい鉄までしか生まれなかった。現在地球上にある多様な原子は、星の最後である超新星爆発によって宇宙にばらまかれたもので・・・と鮎子の口から宇宙起源説が語られるのは意外であった。
修一も本棚から大きな図版をとりだして、それに応える。
なるほどと宇宙の神秘に関しては随分勉強になったが、この場面で肝心の考古学については、期待していたのに何一つ言及されなかったので、拍子抜けであった。考古学で、沙漠の発掘といってもどこなのか?
取りあえず、沙漠の夜の満天の星と宇宙起源説によって二人は胸襟を開いたというわけで、おめでたい限りなのだが・・・・・・。
修一の妻の響子は、夫の学問に興味を示さなかったし、外国の発掘現場に誘っても一度も同行したことはない。共通の趣味があるわけでも、一緒に何かをしたこともないのを、修一は今になって気になりだしている。響子に言わせれば、それどころではなかった。夫が留守勝ちの家を切り盛りし、ひとりで子供を育て上げたようなものだと言うことになる。
要するに修一は、退職して夫婦が毎日顔をつきあわせるようになって、共通の話題も、趣味もなく不満を鬱屈させていたところに、他人というストレスの種が増えたと思って不機嫌な毎日だったが、この同居人である年下の未亡人は、教養もあって話が分かると認識したとたん、天の助けと思ったのだ。
鮎子の気持ちの表現は、控えめでよく分からなかったが、夫に先立たれ、しかもその夫に裏切られたという思いがわだかまって、どこかで孤独感を癒したいという気持ちがあっただろう。
そうなると修一は、一緒に食事をしたり、買い物に行ったりすることが楽しくなる。鮎子の『認知問題』が裁判沙汰になっていることを知って、知人の弁護士を紹介し、相談に乗ってやる。果ては、鮎子の部屋でピアノを習い出すという入れ込みようであった。
それを見ている響子は、たとえ二人が男女の仲ではないとはいえ面白くない。それが響子の精神的軋轢になったのかもしれないが、ある日突然、ピアノの音が気になって寝られないから教室をやめてくれないかと言い出した。断固たるもの言いに、唖然としているうちに、響子の様子がおかしくなる。卒中の様相である。
すぐに入院となって、修一は付き添いで病院に寝泊まりすることになるのだが、下着やら何やらを家に取りに戻っても、鮎子の手助けがなければ何もできない。このあたりの細々と書き込まれたやりとりは、いかにもという描き方でリアリティがある。
響子の病状は快方に向かっていたが、半身に麻痺が残っていた。病院でリハビリを続けているうちは、修一の食事は鮎子が作った。つくったからには一緒に食べる。
そのうちに、響子のリハビリが一定の成功を見て、在宅で介護を受けながら麻痺した手足を回復させようと言うことになり、響子のベッドは居間に運び込まれる。戻った響子は、しかし、呂律がまわらないし、手足も思うように動かない。トイレに行くのも介助がなければとうてい無理という有様で、おむつの世話になるしかない。
あるとき、響子がしきりに修一を呼ぶのだがどうやら下の世話を頼んでいるらしい。気配を察して鮎子がやってくる。響子は、修一にたのむわけにも行かず、他人の鮎子にも遠慮せざるをえないのだが、鮎子はいやな顔も見せずに手際よく済ませてしまう。夫の世話で慣れていたのかも知れないが、それにしても舞台の上で、見せられる光景は恐ろしく現実味があった。
修一がたのんだ介護ヘルパーの関口久惠(佐藤あかり)は、大音響で話す明るい性格が、病人のいる家には有り難かった。とはいえ、保険で事細かに決められた介護以外にサービスはできない事になっているとちゃっかりしたところもあって、やることの限界は実にはっきりしている。このあたりは、現行の介護保険のあり方が、杓子定規にできていることに対する批判になっている。(ようだ。詳しくは僕も知らない。)
リハビリの甲斐あって、響子の言葉は回復の兆しが見え、手足は次第に動くようになっていた。その間も、修一と鮎子は買い物に行き三人分の食事をつくった。響子の誕生日を祝う日が来た。居間はベッドがあるので鮎子の部屋に飾り付けをした。関口久惠もやってきて、響子が昔着ていた洋服をあれこれとりだして着替えを手伝う。料理は朝から鮎子がつくった。久しぶりに晴れやかな顔をした響子が現れ、席についてワインで乾杯したあと、修一からプレゼントと言って、紙包みが渡される。洋服であった。うれしそうにしていたが、修一が、鮎子が選んだものだと言ったとたんに、響子の顔がゆがんだ。「私、化繊は着ないのよね」と吐き捨てるように言うと、その場において去ってしまった。
追いかけて右往左往しているうちに修一と鮎子が鉢合わせをすると、そこで抱き合ってしまう。慌てて離れるが互いに惹かれ合っていたことがわかり、一瞬複雑な空気が流れる。響子が「離婚届」の書類を用意していたが、修一にそういうつもりはなかった。鮎子とも響子が想像しているような関係ではない。若者の恋愛沙汰であれば、そのまま行き着くところまでいってしまっただろうが、そこは分別盛りの二人である。
修一は、退職して妻と顔をつきあわせて暮らすようになると、互いに理解の及ばないところがあることに気づいて困惑していた。鮎子はそのストレスを解消してくれる対象であった。しかし、妻が倒れるとかえってそれを支える役割がまわってきて、妻との新しい関係が生まれる。
一方、鮎子は、夫に先立たれ寄る辺ない身になった。その上、夫に裏切られたという心の傷をどこかで癒す必要があった。
こういう二人の関係を恋愛と言っていいものかどうか?二人が抱えていた、心の渇き。それを潤す優しい時間。それが、つまりは「心の止まり」ということなのか。こういうある程度年齢を重ねた男と女の出会い、あからさまな恋愛感情というのではなく、いつの間にか自分の心にできた疵やほころびを繕うのに必要な異性関係というものがあるのではないか、というのが作家の問いかけらしい。エピローグ、発端の引っ越し場面にもどる。鮎子はすでにいない。最後に運び出されようとしている梱包されたピアノを前に、修一が鮎子から届いた手紙を読み上げ、それを引き取るように、再び舞台に現れた鮎子が手紙に書かれた心境を独白しながら幕が下りる。「心の止まり」とは、その中に書かれた言葉で、むしろ人の心の日常的な「揺らぎ」というものの存在をくっきりと描き出しているように思われた。
最初に書いたように「心の止まり」がどんなことなのかよく分からなかったが、このように感じたのはおそらく僕だけではなかったと思う。いずれにしても、作家が今までに描かれなかった男と女の関係があるのではないかと懸命に訴えているように見えた。
これは、この芝居の瀬尾鮎子役で出演している女優美苗の処女戯曲である。夫の中谷一郎がなくなる前に、戯曲を書きたいと思っていた妻の背中を押した。本の書き方を教えてくれる講座を受けるように勧めたというのである。ガンで夫を亡くしてからも受講し続けて、ついに自身が所属する劇団で、処女戯曲を上演するところまでこぎ着けたのである。
美苗が描きたかった主題は、はっきりしている。中谷一郎が闘病生活の末になくなったことも劇に投影しているだろう。しかし、美苗は個人的な体験や自分一人の境地を超えて、多くの人が共感を寄せてくれるに違いない普遍的なテーマがそこにあると確信している。それが、鮎子と修一夫妻の人間関係によって描かれていることはむろん理解できる。
ところが、そういう「境地」が作家の中で十全に対象化されているかと言えば、少しあやしいところがあった。本来それを補完するべきエピソードがまるでそっぽを向いていて、説明的であろうとすればするほど主題との関係性が希薄になり、散漫の印象を与えてしまった。
たとえば最初に紹介した沙漠の星と宇宙論は、修一の考古学がどんな専門分野で、研究対象は何か、なぜそれを選択したかなど、修一の人格にまつわる説明もなしに唐突に始まるのはいかにも据わりが悪い。しかも、修一にとっての考古学が何であったか、観客は最後まで分からなかった。ビッグバン宇宙論についてもしかりである。
また、引っ越しの場に始まって引っ越し風景で終わるというのは工夫であったが、この作業員の若者が、わざわざ鮎子にピアノを習いたいとやってくるのは、なぜピアノなのかはともかく、なぜ鮎子でなければならないのか、動機も必然性もあまり明らかではなかった・。
本来はそのような挿話よりも、修一と響子の過去の生活がどういうものであったか、どのようにしてすれ違っていったのか。とりわけ、息子が、いったんは二世帯同居をきめながらなぜ米国で暮らすことを選んだのか、という家族の関係がもう少しきめ細かに解き明かされるべきだった。母親が卒中で倒れたというのに息子夫妻が何も言ってこないのはどうしたことか?息子の嫁が米国人で、どうにも動きがとれないというなら話は分かる。赤の他人である鮎子が、下の世話までするような献身的な看病をしなければならないというのも、こういう説明があればもう少し説得力があったに違いない。
鮎子の境遇にしても、夫との日常が書き込まれていないために、愛人がいたというインパクトが弱い。作曲家である夫が女優と関係した動機も事情も必ずしも明瞭というわけではない。作曲の仕事が流行歌などであれば印税収入は相当なものだが、それ以外ならたいしたことはない。女優が権利を主張しているという著作権料も音楽が使用されなければ一銭にもならないのである。一体この夫の仕事は何で、女優が主張している権利とはいくらなのか?
その点でも、修一が弁護士を紹介するだけで、それ以上踏み込まなかったのも惜しい気がした。修一が、認知裁判にもう少しコミットしていたら、修一と鮎子の関係はもちろん、登場人物たちの人間関係がもっと活き活きと動き出したに違いない。主題をより鮮明に見せるエピソードの配置というところでは、こうした不満が残ったが、総体としてみたら戯曲としての一定の完成度はあったというべきだろう。俳優座が本公演に選んだ芝居についてこう言うのも妙な話かも知れないが、演出の森一が上演について賛否両論があった事や、第一稿からかなり稿を重ねたらしいことを正直に吐露しているところを見ると、上のような議論があったことを覗わせる。
それにつけても、シナリオ学校というのか戯曲制作講座というのか、書き方を教える技術は、よくできている。この芝居を見ながら、そこで何が講じられ、何が教えられたのか、美苗が学んだその場へ遡行する事ができるような気がした。必要なことを過不足なく書いて、テンポよく並べるという点では、作家は優秀な生徒であった。もちろん、そのように見せたのは森一の功績である。寄り道の多い、起伏の激しい本をひとつの主題に収斂させようとした努力は十分実っているといえる。この戯曲が必ずしも堅固な骨格をもって構築されているとは言えないが、見る場所ごとにその形を変えて、一体この構築物は全体としてどんな形状なのか想像することを楽しむことができるという言い方もできるかも知れない。
作家で演出家の青井陽治が、パンフレットに寄せた文でその形のなさに戸惑いながら、作家としての美苗の将来にエールを送っている。
「リアリズムなのかと思えば、紋切り型。紋切り型かと思えば、血の迸るような生さ。生なのかと思えば、高度に構築された、寓話。寓話かと思えば、今の世の実像。実像かと思えば、抑制のない人間ばかりがうろうろする風俗劇。風俗劇かと思えば、哲学。哲学かと思えば、詩。詩かと思えば観念。観念かと思えば、俳優の肉体が割り込んできてこそ、真価が奥から光り始める家の設計図・・・・・・まるで、新派の名作のように。」(青井陽治「矛盾した人の描く、矛盾した人々」より)響子の片山万由美が達者なところを見せた。家庭の主婦にはじまり卒中で身体が不自由になった患者、中高年の女のわがままや嫉妬の表現。変化に富んだ役どころを体当たりで演じきった。押し出しはそれほどないと見えるが、時折見せる怒りには緊張感が走り、生な女の部分を表す時には迫力があった。
反面、鮎子の美苗は抑制が効きすぎて、存在感が希薄になった。鮎子を、知的で合理的な女として演じようとしたのが、裏目に出たような気がする。それにしても、「風俗劇」とか「新派の名作」とか言われて、俳優座も変われば変わったものである。美苗は、2005年5月に見た斉藤憐の「春、忍び難きを」に出ていた。この芝居は、戦中から戦後にかけての地主である旧家を舞台にした国家権力への批判をテーマにしたものであった。元来俳優座は反権力の立場を堅持してきた劇団だから、そういうテーマを持たない劇には批判的であったはずだ。それは美苗としても百も承知だろう。しかし、斉藤憐が描くような「国家権力」は実際にはすでに見えなくなってしまった。むしろ、それはもっと複雑な様相で現れるようになっている。昨今の出来事で言えば、特捜検事が事件をでっち上げて、えん罪を生み出す構造が明らかになった。
たとえば、この背景にあったのは(あまり、コメントする者はいないが)世論の厚生省批判である。直接的には消えた年金問題であるが、それ以前にも薬害問題があった。役人の天下りや無駄遣いも問題になっていたが、なかでも厚生省の役人は、あらゆる役所の中でもっともたちが悪いという評判であった。しかし、役人はなにがあっても責任を追及されることはないことから世間の不満が鬱屈していた。
検察は、おそらくこの世論とやらの動向を汲んで、厚生省の役人を懲らしめる機会を覗っていたに違いない。この構造は、ホリエモンや村上ファンドの事件にも通底するものがある。
こういう問題は明らかに国家権力の行使が問題なのだが、斉藤憐のように、国家は常に人民の敵で、いつかは消滅すべきものだというイデオロギーにとらわれていると、もはや取り扱うことが難しい。世論とか世間の正義感、つまりは人民の側の意思が国家機関を動かすという構図は、あり得ないことだからである。権力批判ならこういう方向へ行ってもらいたいが、今のところ俳優座に限らず取り扱うものは少ない。それはおそらく国家というものの認識が変わらないとはじまらないことである。俳優座が取り上げる内容としては、どうなのかということを言いたかったのだが、余談になってしまった。このような男と女の心の微妙な揺らぎと言ったものも劇のテーマとして掘り下げる価値があることを俳優座が認めたことは喜ばしいことである。美苗の次回作にも期待したい。
シアターχは両国にある。めずらしく客席に大銀杏を結った頭が見えたのが印象に残った。
