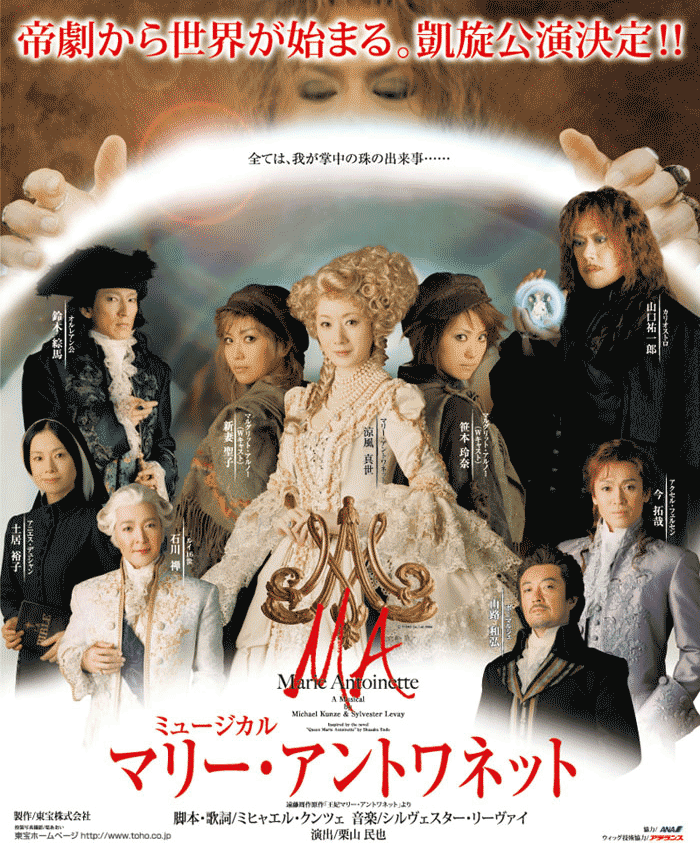
「マリー・アントワネット」
遠藤周作の原作をミュージカルにしようと、「エリザベート」「モーツアルト」で成功を収めたミヒャエル・クンツェ(作詞・脚色)とシルヴェスター・リーヴァイ(作曲)に制作を依頼したのは、東宝のプロデューサー増田憲義であった。マリー・アントワネットは、フランス革命で処刑された悲劇の王妃として、池田理代子のマンガをはじめ宝塚の「ベルばら」などで日本での知名度は十分であり、判官贔屓(藤本みゆきがそういっている)も手伝って好意度も高い。いいところに目をつけたものだ。王妃の生涯は、アントニア・フレーザーによる伝記が名高いが、遠藤周作の小説は、適当にフィクションが雑えられていて物語として複雑な構造を持っているところが取り上げやすかったのだろう。
最近、コッポラの娘、フランシスが撮った「マリー・アントワネット」を偶然TVで見たが、これはフレーザーの原作を使っていたようだ。衣裳がすごい映画だけどこれはなんだと思って見ていたら、丁度彼女が民衆の非難の的になった首飾り事件の場面だった。あのあと恋人との愁嘆場があったり逃走劇があったりするものの、凋落の一途をたどって、あっさりと処刑されて終った。それ以上彼女に何があるといわんばかりであった。
最後に衆人環視の中でギロチン、二万人あまりが歓声を上げるというのは、身もふたもない話で、こんなものがミュージカルになるのか見に行く前から極めて疑問に思っていた。主人公が高潔な人柄で尊敬され、その死を人々が惜しむというなら立派な悲劇として成り立つだろう。ところが、マリー・アントワネットの生涯のどこを探しても大衆に尊敬されるどころか愛されたなどという形跡はない。
「マリー・アントワネットが話題に上る時、必ず漏らされる嘆息がある。それは『あの偉大な女帝マリア・テレジアの娘なのに、どうしてあれほど軽薄であったのか』というものである。一口に軽薄というが、自らの命を縮め、ブルボン王家を滅亡に追い込んだほどの軽薄さであるから、並みのものではない。とんでもなく軽薄であったのである。いまのはやりの言葉を使うなら超軽薄とでもいうべきところだろうか。」(藤本ひとみ「マリー・アントワネットの生涯」中央公論社)研究者にこう軽薄を乱発されたら王妃としても立つ瀬がないというものだ。欧州では歯牙にもかけられない存在にも関わらず、日本でこれほどの人気なのは、王妃というイメージだけで飾られてあまり実態が知られていないからだというのである。この後、東宝はドイツに持っていき、日本発のミュージカルとして欧州制覇をもくろんでいるらしいが、不評の主人公で果たして大丈夫なのか?
その点では、遠藤周作の原作をとりあげたことで、幾分緩和されているといってよい。それというのも、マリー・アントワネット(涼風真世)に対してマルグリット・アルノー(新妻聖子・笹本玲奈Wキャスト)というイニシャルMAが共通する貧民の娘を対置して、王妃のそば近くにいる観察者の視点を確保してシンパシーを表していることである。このマルグリットの存在が、王妃の「軽薄さ」を幼さゆえの純粋さに昇華させているという効果をあげていて、西欧の彼女の見方に影響する可能性もある。さらにカリオストロ(山口祐一郎)という実在した希代の詐欺師、錬金術師を実際よりも大きく描いて、王妃の運命を左右した悪魔的存在、狂言回しとして登場させているところである。他に劇作家ボーマルシェ(山路和弘)がドラマの進行を説明する役回りを担ってあの時代がどういうものだったかを俯瞰して見せる。そのように脇を固め、非運にみまわれた王妃の姿に光を当てながら、僅か数年の間に、二百万人を超える死者を出したともいわれるフランス革命の狂乱と歴史の残酷さ、人間の愚かしさを描き出して見せている。かくも大きな犠牲を払わなければ、近代の重い扉を開け放つことは出来なかったのだと、物語は告げているのだ。
シルヴェスター・リーヴァイの曲は、前奏を聞いているとあれれ、演歌が始まるのかなと思えるような情感豊かなものがあって、まさか日本を意識したわけでもないだろうが、非常に耳に心地よい曲想の歌ばかりだった。訳詩の竜 真知子が付けた詩も素直な感情が込められた美しい言葉の連なりで、旋律がそれほど難しくないことから思わず口ずさみたくなるものであった。例えば、開幕してまもなくのマルグリットの独白は、宮廷の華やかな舞踏会を背景にうたわれる「百万のキャンドル」である。
百万のキャンドル 煌めく世界で
この世の深い闇を
見ようとしない人たち
パリは泣いているわ 見捨てられたまま
苦しむ街を 見ないふりして
平気で踊るの?
なぜなの それでいいの?
気づいてよ 早く
変えるのは あなた
あなた達でしょう
衣ずれのワルツ 優雅にさざめき
母親の叫びも 知らずに笑う人たち
一歩外にでれば この世の地獄よ
嘆きと涙 溢れる街を
見つめて 今こそ
その目をそらすなら
神の天罰を
変えるのは あなた
あなた達でしょう
百万のキャンドル 眩しすぎるから
あなたたち みんな 目が眩んだの?
どうか どうか 闇に目を向けて
民衆が「今日食べるパンもない」と訴えると、それを聞いたマリー・アントワネットが「パンがなければお菓子を食べるといいわ。」といったことは有名だが、孤児として生まれたマルグリットは、それが許せない。ある日劇作家のボーマルシェにだまされ、彼を追いかけて宮廷の仮面舞踏会に紛れ込んだマルグリットは、王妃に民衆の苦しみを訴えて嘲笑をかう。この頃王妃は、スウェーデンの貴公子フェルセン伯爵(今拓哉)に熱を上げ、毎夜のごとく舞踏会に興じ、衣裳や身を飾る宝飾品に贅沢三昧を繰り返していた。王室の財政は火の車、飢饉が続いて民衆の暮らしは極限までひっ迫し、貴族や僧侶などの特権階級に対する不満が渦巻いていることに王妃は全く気づいていなかった。
このもっとも華やかな場面の涼風真代は、さすが元宝塚、ラメの入ったアイシャドーをきらきらさせて、薄いブルーのドレスの裾を翻らせて踊る姿が印象的だった。もう少しタッパが欲しかったが、あの夢見るような真ん丸目におちょぼ口、他の誰がこの役をやることが出来たであろう。
さて、フランスの歴史を大きく揺り動かす準備をはじめたカリオストロは、マルグリットを売春宿のラパン夫人(北村武子)に出会わせ、そこで働くように仕向ける。ところがまもなく、王妃の命により逮捕されたラパン夫人は、シテ島のノートルダム寺院の前でむち打ちの刑に処せられ、マルグリットはこれを助けることも出来ず、王妃に対する復讐の気持ちを燃えたぎらせる。一方、王位を狙うオルレアン公(鈴木綜馬)は、民衆の王室への不信感が高まっているとして、カリオストロとボーマルシェに民衆を扇動して王妃を失脚させるよう依頼するのだが、それを受けたカリオストロの仕組んだ計画にマルグリットも一枚加わることになる。世に言う首飾り事件である。
これは、宝石商ベメール(広田勇二)が、もともとルイ十五世の愛人デュ・バリー夫人のために作った大小のダイヤモンド600個をはめ込んだ時価にして数十億円もする首飾りが、買手のルイ十五世が亡くなったために宙に浮いてしまったことに端を発する。困ったベメール(史実ではシャルル・ベーマーとそのパートナーであるポール・バッサンジュの二人)はマリー・アントワネットに売りつけるべくラ・モット伯爵夫人(Belle)に相談を持ちかける。ラ・モット伯爵夫人はかねてからマリー・アントワネットと親しいと吹聴していたのだ。彼女は、王妃に取り入って宰相の地位が欲しいルイ・ド・ロアン大司教(林アキラ)から何かと金品を巻き上げていたが、チャンスとばかりにロアン大司教に王妃の要望だからこれを代理購入して欲しいと頼み込む。王妃に会わせてくれるなら喜んで、と引き受けたロアン大司教は、マリー・アントワネットになりすましたマルグリットを本物と思い、代理購入した首飾りをラ・モット伯爵夫人に渡すと、そのまま行方不明になってしまう。いつまでたっても代金が支払われないことに業を煮やしたベメールが王妃の側近に問い合せたことから事件が発覚した。
怒ったマリー・アントワネットは、身の潔白を証明しようとパリの高等法院に関係者を告発する。しかし、政治的に宮廷と対決していた高等法院は、ラ・モット伯爵夫人一人を有罪とし、ロアン大司教をはじめマルグリットもすべて無罪としてしまう。これによってこの事件は王妃の陰謀に違いないという噂が広がり、マリー・アントワネットを批難する世論が形成された。カリオストロの書いたシナリオ通りになったわけである。
ところで、この事件で、庭先の暗がりで王妃を装ってロアン大司教と会った女は、逮捕された後で実際にはニコル・ド・オリヴァ男爵夫人と名乗っているが、これは、もともと素性の怪しい女が貴族を騙ったもので、本名はマリー・ニコル・ルゲイ・デシニーという娼婦であったことがわかっている。遠藤周作は、この女の存在をヒントに、革命のために立ち上がったマルグリット・アルノーの人物像を創造したと思われる。マルグリットの造形には根拠がありしたがって説得力もあるといってよい。後に、ナポレオン・ボナパルトがこの事件をフランス革命の原因の一つに数えたというから、王制の継続に甚大な影響を与えた陰謀だったのだ。
獄から解放されたマルグリットは、弾劾されるべきは王妃であると民衆に訴える。孤児院でマルグリットを育てた修道女のアニエス(土居裕子)が、人を傷つけることで問題はなにも解決しないと説得するが、彼女は耳を貸そうともしない。そうして1789年、市民は国民議会をつくり、バスティーユが破られ、ついにフラン革命が勃発する。マルグリットは貧しい婦人たちを率いてベルサイユに行進する。国王一家は、オレルアン公によってパリのチュイルリー宮殿に幽閉され、その処遇は議会の決定にゆだねられる。そして、その国王の動きを監視するために過激派ジャコバン党の決定によって、マルグリットが王妃の召使いとして送り込まれることになり、彼女は初めて王妃の人となりをそば近くで目にすることになるのだ。
米国独立戦争から帰還したフェルセンの手引きで、国王一家は国外逃亡を企てる。マリー・アントワネットの故郷オーストリア国境の手前で見つかり、パリに連れ戻されるとまもなく、王制は廃止される。
その頃、王妃からフェルセン宛のラブレターを預かったマルグリットは、内容を疑ったが密かに届けようとフェルセンに会う。ところが、それは国王一家を救い出すようにという命令を書いたものだった。フェルセンにはもはやどうすることも出来ない。マルグリットはこのことには口をつぐんでいようと決める。
まもなく、革命の混乱の中、国王ルイ十六世は共和国政府によって裁判にかけられ、反革命の証拠が多数挙げられたことによって、僅差の投票で死刑宣告される。このルイ十六世は、もともと国王としての能力に疑わしいところがあって、実は王妃のいいなりになったための結果ではないかと考えるむきもある。
国王処刑のあとは、マリー・アントワネットにも告発有罪の影は忍び寄っていた。覚悟を決めた王妃は、最後にフェルセンを呼び、別れを告げようとする。これを警戒したマルグリットではあったが、王妃の最後の願いと思って、逢瀬を見て見ぬふりをする。
そして、1793年十月、証言台にたったマルグリットは、手紙の一件をなかったと証言し、王妃を庇おうとしたが、すでに時の勢いを止めることは出来なかった。かくて、マリー・アントワネットは、市中を引き回された後革命広場の断頭台に向かう。
舞台の真ん中に巨大なギロチンの血塗られた刃がおりてくる。荷車をおりたマリー・アントワネットがその下に静かに身を横たえる。
群衆は、「自由のために流れる 血がある 憎しみこそが敵を倒す 武器だ 慈悲などいらない つかめ自由を!」と歌い、
カリオストロは、
「私が描き出した 人間こそ不思議だ 何故かどこかで見たような 歴史を繰り返すそれぞれの手がつかんだのは 傷一つない 自由か」と歌う。
それにマルグリットが応えるように歌う。
「ひとりひとり 血が通った 人間なのに 何故なの 人は自由を求めて 憎しみを武器にする 愛を忘れた暗闇には 自由の光はない」
自由を求める熱狂、その抗し難い力と、憎しみに燃え、血と暴力であがなわねばならない革命というもののむなしさにマルグリットの思いは沈んでいく。「愛を忘れた暗闇には 自由の光はない」はずなのに、カリオストロの「何故かどこかで見たような 歴史を繰り返す」というフレーズが僕らの胸に重く響いてくる。この最後を締めくくる合唱「自由」には人間がより賢く生きていくためにこのような物語に学ぶようにとの願いが込められているような気がする。
非常に充実した内容で、音楽も詩も心地よいミュージカルであった。
しかし、難を言えば二幕の半ばからは話が暗く沈んで、どうも気分が盛り上がらない。一体栗山民也は革命をどういう視点で捉えていたのかと考えてしまった。というのも、幕間でロビーをうろうろしていたら、出演者がそれぞれこの作品に思うところを書いた色紙が張り出してあって、そこにひときわはっきりした書体で「主権在民」と書いたものを発見したからであった。ロビスピエール役の福井貴一のものだったが、この時僕は少しショックを受けた。なるほど革命派側から見た場合は、マリー・アントワネットは民主主義の敵、打倒されるべき対象に過ぎないのだ、と思った。確かにそうではあるが、その視点から見ると、このあまりにも無邪気で能天気な王妃のどこに反革命の憎しみを燃やすことが出来るだろうか?とも思う。一方で、餓えと貧困に苦しむ民衆の立場から言えば暴力革命こそ社会を変える唯一の手段ということも否定されるべきだとは思わない。
栗山民也の演出は、二幕以降マリー・アントワネットを見捨てたようであった。もはや時代は国民の共和制に移り変わった。前世紀の遺物である王妃には素早く歴史の表舞台から消えてもらうしかない。あたかもそのような救いのない扱いであった。「主権在民」は栗山民也の演出プランからでたものではあるまいか、などと勘ぐりたくなるような気さえした。
なぜそう思わせたかといえば、マルグリットの扱いが二幕になっても目立って大きくならなかったことにもよる。もともとマルグリットは遠藤周作の工夫で、マリー・アントワネットに対抗するだけの役回りであった。一幕目は王妃が主役、二幕目はマルグリットが、革命の熱狂を冷めた目で見ることが出来、そのむなしさに目覚めるという主題を一身に担う筈だった。しかし、衣裳、照明ともそこにアクセントがなくタダ単に地味な女の子がそこにいるという具合であった。笹本玲奈も新妻聖子もそれなりの実績もあり存在感もある。しかし、ここにはもっと涼風真代に対抗出来るだけのキャラクターを配するべきではなかったかという気がする。さすれば、最後のマリー・アントワネットの処刑も観客の心のなかにもう少し同情すべき余裕が出来たのではないかと思った。
ざっと考えても、ロシア革命、2000万人〜3000万人、文化大革命、2000万人〜3000万人が命を失ったと言われている。それを思えば、マルグリットの歌の意味が胸に迫ってくる。もう一度繰り返そう。
「ひとりひとり 血が通った 人間なのに 何故なの 人は自由を求めて 憎しみを武器にする 愛を忘れた暗闇には 自由の光はない」
題名: |
マリー・アントワネット |
観劇日: |
07/5/22 |
劇場: |
帝国劇場 |
主催: |
東宝 |
期間: |
2007年4月3日〜5月30日 |
作詞: |
ミヒャエル・クンツェ |
作曲: |
シルヴェスター・リーヴァイ |
翻訳: |
浦山 剛/竜 真知子 |
原作: |
遠藤周作 |
演出: |
栗山 民也 |
美術: |
島 次郎 |
照明: |
勝柴 次朗 |
衣装: |
有村 淳 |
音楽・音響: |
甲斐 正人 |
出演者: |
涼風真世 笹本玲奈 |
