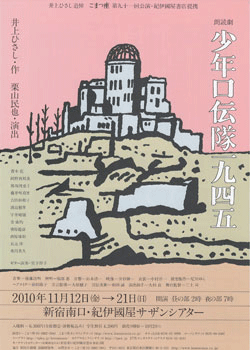
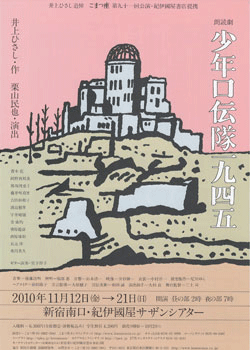
「水の手紙」 「少年口伝隊一九四五」二つの劇の二本立て公演である。なぜこの二つが一緒なのか少し疑問に思って劇場に出かけた。
こまつ座の井上麻矢が説明するところによると、一年以上前に劇場の予約をいれていたが、井上ひさしの病状が進んで、予定していた新作を書くことができなくなったためだという。
本来なら、夏に上演するはずの『木の上の軍隊』とともに、二本の新作を書くはずだったが、途中で沖縄戦をテーマにした『木の上の軍隊』だけに集中することにした。病気の治療を進めるうち、それもままならなくなり、予約していたサザンシアターを返そうと思ったが、それももったいない。何か別のものをできないかと座付き作家井上ひさしに相談したところ『絶対に何かやれるはず、しかもまだ皆さんがあまりご覧になっていない、小さくても上質のものはないか。』といわれて思案の結果、この二本の朗読劇のダブル上演が実現できたのだという。四月に井上ひさしは力尽きて、七月の上演を予告していた「木の上の軍隊」は、未完に終わった。
未完というよりも、一行も書かれていないらしい、と朝日新聞の石田祐樹記者が伝えている。(6月26日の記事)65回目の「沖縄慰霊の日」(6月23日)が過ぎて、本土はどれだけ沖縄のことを考えてきたかということに寄せて、井上ひさしと沖縄の関係に言及した記事であった。「木の上の軍隊」は、内容についてはほとんど分かっていない。だが、この芝居の構想には、実際にあった出来事が背景として存在している。
沖縄の離島、伊江島で終戦から一年半もたった昭和22年3月に、日本の降伏を知らず大きなガジュマルの木の上で隠れて生き延びた二人の日本兵が名乗り出た。
伊江島は、沖縄本島の中央に大きく突き出た本部半島の北西約9kmに浮かぶ島である。東西8.4km、南北3km、周囲約22km、中央やや東寄りに標高172メートルの城山が突起のようにひょっこりそびえているのが特徴で、北部海岸線は断崖によってすっぱりと海に切れ落ちているが、全体としては比較的平坦な地形である。現在は約4,800人が暮らすサトウキビと観光の町になっている。昭和18年3月、伊江島には満州からの部隊が移動してきて、住民を「徴用」しながら飛行場の建設を始めた。
一方、陸軍は19年3月、敗色濃厚となった戦局を沖縄で食い止めようと第三十二軍(司令官、牛島満中将=自決後大将)沖縄守備隊を創設する。
伊江島は、飛行場があったために米軍の攻撃は必至と見られ、学童を本土に疎開させ、昭和19年3月までに島民の一部を本部町・今帰仁村・久志村に移した。同年10月10日、米軍がこの日大挙して伊江島上空に現れ飛行場などを空爆、このとき島内の主立った建物はほぼ壊滅状態となった。
明けて20年3月25日、伊江島南方沖に海を覆い尽くすばかりの米艦隊が停泊し、本島方面に激しい艦砲射撃を繰り返した。4月1日、沖縄本島読谷村および北谷付近に米軍が上陸作戦を開始、一段落した4月16、17七日にかけていよいよ伊江島上陸となる。
このときの抵抗戦に際しては、軍が民間人を動員し槍を持った婦人までもが戦闘に参加させられた。米陸軍の記録によると、多数の民間戦闘員の中には乳飲み子を抱えた女性もいて、これが勇敢にも軍に切り込んできたとある。この激戦のさ中、当時の東京毎日新聞投書欄で、ある主婦が「当局に伺いたい」と迫った。戦いに母親が倒れたら子供たちをどうしてくれるのか。それがはっきりしない、ちゃんと保護すると約束しろという趣旨の内容であった。特に激戦となった「学校台地」における戦闘は、米軍の中でも「血塗られた丘」と表現され、上のようなものも含めて双方に多数の戦死者が出た。
民間の戦闘員には自決用の手榴弾が配られたために、逃げ込んだ壕内での軍による強要された集団死があったり、「集団自決」の他に米軍のスパイ嫌疑をかけられ「処刑」されるものまで出るなど、戦争と言うよりはもはや惨劇としか言いようのないありさまだったことを伝え聞くと、胸の震える思いがする。
6日後の4月21日になって米軍が城山に星条旗を掲げて終戦宣言が出され、伊江島としてはここで戦争は終結する。が、本島ではまだ6月23日まで戦争は続いている。総力戦と称して住民を戦闘に巻き込んで戦った沖縄戦で起きたこと、その縮図がここ伊江島の戦闘にすべてあると言われるほど、想像を絶する悲劇がくりひろげられた。
この闘いで、民間人千五百人余、日本軍二千人、米軍二百数十人が犠牲となった。生き延びて捕虜となった島民は約二千二百人、全員いったんはナーラ収容所に集められたが、ここを日本本土爆撃の基地として飛行場を建設するため、5月になって、すべての島民が渡嘉敷村及び座間味村へ強制的に移送された。島には米軍の建設部隊と本土攻撃部隊の米国人だけが居残った。
隠れた兵隊二人は、夜になって木から下り、食料や水など生活に必要な物資を調達し、互いに助け合っていきていたという。
それから二年あまり、ようやく島を離れていた人々が帰ってくる。島の半分もあるような大きな長い滑走路が三本できあがっていた。米軍の極東アジア戦略基地として居座るつもりのことに、島民は愕然としたという。
二人は、隠しておいた食料が奪われることがあったので、これらのものは友軍がくる日のために蓄えているというメモを残した。すると、返信の手紙で「兵隊はすでに皆故郷へ帰っている」とはじめて終戦を知らされる。半信半疑のまま、どうせ死ぬ身だ、一度は人を信用してみようと二人で話し合い木から下りたのであった。この話を井上ひさしは1985年頃に知ったという。
平成二年(1990年)四月に、これをもとに書かれた「木の上の軍隊」が紀伊國屋ホールで上演される予定だった。当時は「 戦争が終わっているのに伊江島で長い間、木の上に隠れていた兵隊の話。占領軍がジャズなんか流しているのを謀略だと思っていたという筋立て」というように語っていた。二人の兵士には、すまけいそして市川勇、演出はどうしたことか当時八十五才で矍鑠としていた千田是也である。客席の真ん中に二人が暮らした大きな木をおくという演出プランもできあがっていた。
ところが、この戯曲は結局書かれなかった。当然公演もすべてキャンセルである。
僕はこの年、会社を辞めて独立したばかりで芝居どころではなかったから、この騒ぎを知らない。それから二十年たった。
今度こそ書こうと思って、「組曲虐殺」公演(2009年10月)の時に予告した。二人の兵士には、藤原竜也と北村有起哉を予定していた。
なぜ書かなかったか、あるいは書けなかったかはナゾである。書斎の机の上には「琉球語便覧」(伊波普猷監修)がおかれていたという。
さて、本公演の演目の一つ「水の手紙」は、井上ひさしが平成十五年に開催された「第十八回国民文化祭やまがた2003」の総合フェスティバルのプロデューサーをつとめた際に基調講演の代わりにといって上演された群読劇である。
このときに上梓された「やまがた水宣言」は次のように始まる。劇の構想が分かると思うので、あえて引用する。
「蔵王、鳥海、飯豊、朝日の山山に降り注ぐ雨は、そしてまた山山に降り積もる雪は、森や林を潜り抜けると清らかな水となって、やがて最上川に集まって行く。これが山形の水の流れです。
最上川の水は日本海へ注ぎ込み、ゆっくりと七つの海へ拡がって、小さいけれども美しい、この水惑星、地球を作り上げています。そしてそのうちに、海海は雲に姿をかえて、またもや蔵王、鳥海、飯豊、朝日の山山に雨や雪となって降り注ぎ、降り積もる。これが地球の水のめぐりです。
こうして水は地球をめぐりながら、ヒトや草や木や生きものたちに生命をめぐんでくれている。これがたったひとつの地球の決まりごとです。・・・」今度の公演では、「世界はひとつ、水でつながっている」という同じ主題で、スケールを地球規模にひろげて描いた。
暗い空間の真ん中に直径1.5メートルあまりの地球が浮かんでいる。 その下の黒い床には土色の大きなまあるい円が描かれていて地球の形の投射のようだ。 ごく細い柱と梁が何もない空間の真ん中あたりで全体を引き締めるように直線で舞台を囲っているのが、知的で詩情あふれる群読劇には効果的である。おそらく伊藤雅子が栗山民也の求めに応じたものだろう。
ヴィオラの徳高真奈美の演奏が始まると、新国立劇場演劇研修所を卒業した二十名の 若い俳優たちが三々五々円の中に進み出て、「水の惑星、地球」から静かに語り始める。
宇宙飛行士が眺めた地球は、水に覆われた星。まるで、いまにも水がしたたり落ちるように水で満たされている。宇宙に何千億の星があっても、地球のような奇跡の星がいくつあるだろうか。この水の中から生命は誕生した。生命は、水によって生かされている。私たちの体の三分の二は水である。胎児は水に抱かれている。生きているものすべてにとって水はかけがえのない財産である。
しかしこの頃、この水の様子がおかしい。
世界各地から届く「水の手紙」に耳を傾けてみよう。
以下は主立ったエピソードを僕なりに意約したもの。確認のために本を探したが、現在までに手に入らなかった。(見つかったら書き直します。)大体の内容をご理解いただけると思う。アラル海沿岸の町に暮らす子供からは、父親が遠くに出稼ぎに行って帰らない寂しさを訴える手紙。
湖の縮小によって岸辺がはるか沖に後退し塩分濃度も上がって魚がとれなくなった。 漁師だった父親はいま、生まれた土地を離れて不慣れな仕事をしている。この湖に流れ込む川の水は、綿花を作るために畑に引かれ、再び帰ってこない。乾いた湖は砂漠化し、砂の上に竜骨がむき出しになった船の残骸がいくつも横たわっている風景を記憶している人は多いだろう。かつてはシルクロードのオアシスとして豊かな自然の恵みを与えてきた湖が、わずか数十年の間に三分の一に収縮してしまったのは、人が自然に手を加えたために起きたことだ。
南太平洋の環礁群島ツバルの少年からの手紙。
地球温暖化のために北極南極の氷が溶け出し、海面が上昇すると言われている。ツバルの国土は、平均海抜二メートル。わずかな水位の上昇が国そのものを消滅させる危険があり、自分たちは今その危機に直面している。どうか先進国の皆さんには、温室効果ガス抑制の運動を加速させていただきたい。
メキシコ、カリフォルニア半島に住む少年からの手紙。
北米大陸西部のロッキー山脈に降り積もった雪解け水を源にコロラド、ユタ、アリゾナ、ネヴァダとカリフォルニアの州界を流れてメキシコのカリフォルニア湾に注ぐ全長2,330kmの大河、コロラド川。その河口には、もう水が流れてこない。途中には大きなダムがいくつも造られ、貯水湖の水は灌漑と都市の水道のために使われる。広大なコロラド高原を浸食して、あのグランドキャニオンを形成してきた奔流は、海に到達する前に消滅してしまう。半島の付け根にある河口には、かつて豊かに蛇行して海へ注いだ広大な流れのあとだけがむなしく残されている。
中国、黄河河口に住む少年からの手紙。
支流を合わせると地球を半周する長さと言われる長大な黄河。大量の黄土を運んで、広大な三角州をつくり何度も河口を変えた暴れ川。それがこのところ河口まで流れが到達しない日々が増えてきた。巨大ダムのおかげで大河を制御することはできたが、農業用・工業用水の需要が飛躍的に伸びて中流域で大量に取水されるためだ。しかも、劣悪な灌漑設備のために効率が著しく悪い。逆に砂漠化も進行している。断流の河口を見るたびに何かが変化しているという漠然とした不安を覚える。
メキシコシティに暮らす子供からの手紙。
アステカ時代、テスココ湖の上に築かれた街であるにもかかわらず、二千万人が暮らしのために汲み上げた地下水はすでに涸れかかっている。300km先の水源から海抜2,240mのこの髙地まで揚水され運営されている水道網は老朽化が進行し、その40%が地中に漏れ出している。近頃は栓をひねっても水が出ないことが増えた。このままでは、あと二十年もしたら危機的な状況を向かえるといわれている。
トルコ、イラク国境付近に暮らす少女からの手紙
チグリス川は、トルコの高原を源流として国境を越え、イラクを南北に縦断してペルシャ湾に注ぐ全長約1,900kmの大河である。河口付近で、ほぼ並行に流れてきたユーフラテス川と合流する。世界で最も早いメソポタミヤ文明をはぐくんだ流域である。近年、水の需要が高まるとともに上流にあるトルコと下流域にあるイラクが対立している。特にイラクにとって流量を制限されることは、産業全体の死活問題にかかわる。古来、川の水は争いのもとであったが、人間の知恵で解決してきた。しかし、国境付近の川をはさんで軍が対峙し、緊張が高まっていた。一触即発という状況を見ていたトルコ側、イラク側それぞれの国の少年と少女が百人あまり、誰言うともなしに手を携えて川に入り、軍と軍の間に割ってはいった。無言で・・・・・・。
客席が静まりかえった瞬間であった。
「いまや水は、ヒトに酷使されて、疲れ果てている。水が病みはじめたのだ。ヒトはいま、水の有限性の壁にぶつかっている。」
井上ひさしの特徴ある手書きの文字をパンフレットからひろって、劇の紹介を終えよう。
しかし、私たちは、
「地球の他に帰る場所はない。」
「水は命の源
人は水と闘い
水に感謝し
水を愛で
水と深く関わりながら
それぞれの文化や
知恵を育んできた」
「水からヒトは生き方を学ぶ
水がヒトをヒトに結びつける
世界は水で結ばれている
世界は一つ、水で結ばれている」世界から送られた「水の手紙」を読み終えると二十人の読み手が静かに舞台を去って幕となる。
照明(あかり)がそのままの舞台に、すまけいが登場する。「水の手紙」に引き続き、「井上ひさしへの16通のラブレター」というコーナーである。これは、井上ひさし追悼公演でもあり、彼と縁の人たちが毎日日替わりでこのコーナーに登場し、思い出を語り手紙を読むことになっている。
僕らの場合は初日だった。ちなみに登場予定を書き記しておくと、麻実れい、白石加代子、熊谷真美、井上芳雄、石原さとみ、小曽根真、神野三鈴、高畑淳子、佐藤B作、辻萬長、剣幸、木場勝己、土井裕子、藤原竜也、大竹しのぶ、の諸氏である。関係の濃淡はあるだろうが、こまつ座の芝居を比較的数多く見ている立場から見て、ほぼ順当な人選だと思った。休憩をはさんで、朗読劇「少年口伝隊一九四五」である。
舞台最前列いっぱいに十二個の学校で生徒が使う椅子が並べられる。台本を手にした十二人の俳優(「水の手紙」に登場した俳優の一部)が、そこに腰掛けて割り振られた台詞を読み上げるという趣向である。 舞台上でギター演奏をするのは宮下祥子。
この本は、新国立劇場俳優研修所の俳優たちが教材として使っているものであり、かつまた初演した朗読劇でもある。したがって、台詞は台本を手にしなくとも十分に入っていたに違いない。(ただし、もともと本が書かれたのには、あるきっかけがあった。その事情は少し込み入っているので、あとで説明する。)
物語は、広島で被爆した三人の子供が、輪転機を失った新聞社のニュースを口頭で街に伝え歩く「口伝隊」になって活躍する話である。
はじめは、椅子に座って台詞を吐いていた俳優たちに次第に動作がついてきて、劇が三分の二くらいまで進行した以降はほとんど本を持ちながら立ち稽古の様相であった。それがごく自然に見えるところが栗山民也の神業的演出で、ほんとうにうまいなあと感心してしまった。こう言うのを見せられると俄然気分が乗ってくるものだ。
ついでに言っておくと(前にもいったような気がするが)ミュージカルの地の台詞から歌へ移行する時のタイミングといい、気分の演出といい東西随一といっていいのではないか?東西と言ったって西のことなんか知らないくせにと言われそうだが、西でも評価の高い蜷川幸雄には逆立ちしたってできないのだから、西でも一番。この理屈どこか変かな?帝劇でも日生でも経験豊富なのになぜか栗山がKURIYAMAにならない。日本のマスコミもいい加減である。少し左がかっていると思われているのかなあ。ぷんぷん。(格調高く書こうと思ったけど、どうも地が出てしまった。)もとい。昭和20年8月6日午前8時15分頃、広島のはるか上空をB−29が単独で飛んでいるのを目撃した市民は多い。きらきら光るものを三個放出した。落下傘のようだ。(この落下傘に原爆がくっついていたように劇では描かれているが、実際は、原爆の威力を上空からデータとして記録するラジオゾンデであった。)
続いて何か黒い固まりが落ちた。この日まで、広島に空襲はない。市民は訝しく思っていたが、米軍はすでにこのまちに原爆投下を予定していて、その破壊力を正確に検証するために、あえて「手を付けなかった」のだ。7月16日には、ニューメキシコ州において完成したばかりの核兵器を実際に爆発させる実験(「トリニティ実験」とよばれる)を成功させていて、これを実戦で使用した場合、どのような戦果(「戦禍」)があるのか把握する必要があった。続いて数都市を攻撃する予定だったからだ。
広島駅から十五分ほど南に行ったところに小高い丘がある。比治山と言って山全体が樹木の茂った公園である。この朝、東の麓の家で英彦が妹と遊んでいる。また、南の麓の下駄屋では正夫が祖母の肩をたたいていた。そして、北の麓の小川のそばで勝利が母親の手伝いをしている。何れも国民学校の六年生で、この日はたまたま疎開先から帰ってきて家族と一緒にいた。
黒い固まりは、広島市のほぼ中央にある相生橋に向けて投下されるとふらふらと空中を泳いでいたが、やがて後尾に取り付けられた安定板が空気をつかみ、放物線を描いて落下していった。目標地点からやや東南にそれた島外科病院上空、580メートルに達したところでこれが炸裂した。午前八時十九分であった。
「炸裂したのはリトルボーイ。
アメリカ俗語で『おちんちん』
長さ4.3メートル、
直径1.2メートル、
重さ4.5トンの原子爆弾だった。」炸裂の瞬間、中心の温度は一万二千度、その熱線は地上付近では五千度に達していた。生きているものは一瞬にして蒸発、または黒こげになり、あるいは皮膚がはがれた。さらに爆風が町を襲う。「畳一畳あたり十トンの圧力をかけて、地上のものを吹き飛ば」す。熱線は、放射線でもあった。
「内臓や血管や骨髄などの人間の体のやわらかなところに、殺人光線がこっそり潜り込んでいた。」
その日のうちに十二万人が亡くなり、二十万人が負傷し、被爆していた。
熱せられた空気と爆風で巻き上げられた塵芥がキノコ雲を形成して上昇気流に乗り、上空で冷やされると、これがお昼頃になって落ちてきた。雷を伴い、粘りけのある大粒の黒い雨が一時間以上降り続いた。この雨は放射能を多量に含んでいたため、広範囲に被爆被害を広げることになった。山じたいが楯になった比治山の東側。骨組みだけ残った国民学校が迷子の収容所になっている。その校庭にどこから飛んできたのか、端がぎざぎざになった土管がごろごろ転がっていた。英彦、正夫、勝利があれから三日、この土管をねぐらにしている。三人は、同じ学校の生徒ではなかったが、近所の小川で遊んでいた顔見知りである。それぞれがあの朝、家族を失っていた。
勝利が乾パンをもらって帰る途中で、手榴弾を差し出す兵隊に会った。もはや死にかけて力のない兵隊は、それを自分に投げつけてくれというのだ。しかし勝利が躊躇しているうちに動かなくなった。
勝利はその手榴弾を持ち帰り、翌朝三人で校庭の井戸のそばに埋めようとした。そのとき、英彦に見覚えのある若い女のひとがやってきて、メガホンを校舎に向けると「わたしは中国新聞の口伝隊です。」と演説のようなものをし始める。英彦の母親がやっていた裁縫教室にきていた「花江さんじゃ。」とすぐにわかった。
花江さんもすぐに英彦をみとめ、三人を新聞社のそばに造ったバラック小屋に住むようつれていく。花江さんは、あの日取材のために尾道に行っていて無事だったのだ。
新聞社の建物は残ったが、中はすっかり焼け焦げている。その中を片付ける仕事を三人に委嘱し、社の炊き出しを支給するということにしてくれた。勝利が、 口伝隊として三人で活動することを申し出ると、それもみとめてくれた。手榴弾は、勝利が小屋の隅に埋めた。
翌八月十日朝から、比治山東側の、まだ家がまばらに建っているあたりをまわって、新聞社がつくった原稿を読んで回る。みんな身近な情報を求めていたので、少年口伝隊はどこでも歓迎された。ただ一軒を除いては。
蟹屋町の壊れかけた家の前に、品のいい老人がいつも待ち受けていて、読み上げる原稿に文句を言うので少年たちは困っていた。しかし、老人の言うことにはもっともなところがある。むしろ当局の言っていることに、理屈の通らないことがあることも、なんとなく感じているのだが・・・。
八月十三日の朝、老人は家の前にいた。しかし、十四日はでていない、重大発表があると言っていた十五日になっても姿を見せないので心配になって家の中をのぞくと、やせ衰えたおばあさんが横になっていて、老人は、本の表紙を団扇代わりに扇いでいた。 見たこともないほどたくさんの本が散らばっているので、本屋でもしていたのかと問うと「文理科大学で哲学いうもんを教えとった。」という答えであった。
おばあさんの足首に紫色の斑点があるのを見ると、一同は頭を下げて老人の家をあとにした。
三人はすでに知っている。まず熱が出て、体がだるくなる。それからものを食べなくなり、顔に表情がなくなる。髪の毛がごっそりぬけて体中が痒くなり、おしまいに足首に紫の斑点が出る。さもなければ唇や歯茎から血が流れ出る。そうなれば人は死ぬということを。
「ラジオからの甲高いお声をさかいに、広島ががらりと変わ」り、戦は終わった。焼け野原にバラックが建ちはじめ、岡山医大から調査団がやってくる。老人の家のおばあさんが亡くなり、それから教え子たちがやってきて家につっかえ棒を交って、台所と風呂を使えるようにしてくれた。口伝隊の三人は相変わらず小屋に住み、ニュースを伝える仕事を続けている。
時々、花江さんが他の町で印刷された新聞を持ってくる。
トルーマン大統領が、たった二発の爆弾で平和をつくり出したという談話を発表しただの、チャーチル首相が、本土上陸作戦があったら米兵100万、英兵20万の戦死者を出したはず、原爆はそれを防いだだのといっている。スターリン議長は、日本はアジアを侵略しようとしたのである。天に向かってつばを吐いたようなもの、といったなどという記事が出ている。三人は、どいつもこいつも許せない。生かしておかれん、と言い合った。
中には訳の分からんことも書いてあった。政府は、九月初旬に予定されている占領軍の進駐に当たって、彼らの性的慰安施設の設置を決めたというもの。この「性的慰安施設」とは何か?と花江さんに聞くと、「うちにはよう答えられない」というので、三人は蟹屋町にやってきた。
老人がいうには、日本人はこうなった以上、アメリカ軍をもてなして慰めなあかんという意味のことらしい。三人は、この間までやっつけなきゃならないと言っていたアメリカを今度は慰めるのかと腹を立てている。
老人は、「声のおおきか方へ、ふとか号令の方へ、よう考えもせずになびいてしまうくせが人間にはあっとってじゃ。」と、この現実をつくってしまったのは、その「くせ」のせいかも知れないという。
雨が、強く降り出していた。今夜は泊まっていけと言われ、風呂に入ることになった。正夫が石けんの泡で頭をこするたびに、ざくざくと髪の毛が抜けるのを英彦は見た。そのとき英彦の頭の中には、勝利が隠した手榴弾のことが浮かんでいた。
その夜から正夫は老人の家で寝ている。交代で看病に訪れるが、すでに顔から表情が消えていた。
九月にはいって、周囲の町からアメリカ軍が続々と広島に入ってきた。
九月十七日の朝、花江がやってきていい知らせだという。「アメリカの原爆効果調査団」の先生たちが、何人かの広島の子供に学資を提供する「精神養子」というのを思いついて、花江に相談があったので、英彦と勝利を推薦しておいたというのである。明日正午、面接にやってくると聞くと、二人は「うん」とうなずいた。そして、互いに顔を見合わせ、にっこり笑った。英彦は、やはり勝利もあの手榴弾を使うつもりだとわかったのだ。
このあと、英彦は「昼には帰る」と勝利にいうと、刺すような強い雨の中を蟹屋町で伏せっている正夫のもとに向かった。まるでぬるい風呂に入っているような土砂降りであった。この日、枕崎台風が広島を襲った。
「リトルボーイ数個分の力を秘めた
水と風の大きな塊が、
いま薩摩半島南端の枕崎を通って、広島へ直進している。
瞬間風速七二メートル、
平均風速五〇メートルの巨大台風が
ひたすら北へ駆け上がってくる。」正夫が、屋根をたたく雨の音におびえ、あおむけだと火だの水だのに襲われそうでかなわんというので、うつぶせにしてあげた。そのとき英彦が見た正夫の両足首には紫色の斑点が鮮やかに浮かんでいた。
英彦は、激しくなった風雨のために小屋へ戻れなくなった。夜になってドーンドーンという地響きがする。山津波だ。原子爆弾で焼かれてもろくなっていた山肌に雨がしみこんで、山が広島の町に向かって崩れたのだ。そこへ激しい風雨がたたきつける。そして高潮が川へ逆流をはじめて、各地で堤防が決壊、街は水につかった。「2,012名の命が水底に沈んだ。その中には手榴弾を握りしめた勝利もいる。」
正夫を抱いていた英彦が叫んだ。「もうたくさんじゃ。わしらは何でこげんおっとろしい目にあわにゃいけんがいのう。」頭がおかしくなりそうだと英彦が言う。老人は、「狂ってはいけん」といいながら、正夫と英彦を細い腕で抱きしめる。
「命のあるあいだは正気でいな、いけん。」お前たちに、ことあるごとに狂った号令を出すやつらと正面から向き合うという務めが残っているのだから。「わしらの体に潜り込んだ原爆病は、外見にはこともなげに見せかけてやれやれ助かったと安心した頃を見計らって、いきなりだましがけにおそうて来る代物じゃ。海も山も川も、いきなりだましがけにあばれてきよるけえ、いっつも正気で向かいあっとらにゃいけん。」
しかし、正夫にはそれができなくなってしまったというと、老人は、正夫の代わりに正夫のしたかったことをしなさい、これから先はなくなった子供たちの代わりに生きるのだと英彦を諭す。
「・・・・・・そんじゃけえ、狂ってはいけん。おまいにゃー、やらにゃいけんこつが、げえに山ほどあるよってな」一同がはじめの位置に戻り、舞台にはひとり宮下祥子が奏でるギターだけが響く。暖かく、そして明るく澄み切った旋律が長く続いたあとに、短いエピローグが読み上げられる。
「比治山の北の麓の妙蓮寺という寺に、
じいたんが建てたお墓がのこっています。
墓石にはこんな文字が彫られています。昭和二十年九月十七日 勝利 行方不明
昭和二十年九月十九日 正夫 原爆症
昭和三十五年一月七日 英彦 原爆症」ギターの弦音が、犠牲になった人々の御霊を鎮めるように流れて、観客が劇の余韻を味わう中を、やがて次第に明かりが落ちていく。
原爆の日、八月六日から枕崎台風が襲った九月十七日までの広島の様子を、三人の小学生の物語を通して描いている。 原爆症の症状が出ている正夫が「あおむけだと火だの水だのに襲われそうでかなわん」というとおり、 わずか四十日あまりの短い間に、火と水の二つの災厄にみまわれたのである。 ようやく復興の兆しが見えたと思った矢先に、その希望を砕くように再び不幸が襲ったのだ。
この二つを一緒に語ることにやや抵抗を覚えるむきもあるかも知れない。一つは自然災害で、誰にも文句を言えないが、原爆はどうだ、と言う意味である。このわずかに覚える違和感は、劇が成立した背景をおいてみれば、なるほどと了解できるかも知れない。
この劇は、2008年に日本ペンクラブが計画した『世界P.E.N.フォーラム「災害と文化」—叫ぶ、生きる、生きなおす—』の趣旨に賛同した井上ひさしが、その参加作品として書き下ろしたものである。ペンクラブは作家をはじめ文筆業に関係する人たちの世界的な集まりであるが、テーマである「災害と文化」とは一体どういうことなのか。
企画した吉岡忍が語ったところによれば、次のようないきさつがあった。2005年のスロベニア大会の時に初参加した吉岡は、規約のことや中国・ベトナムの言論状況などが議論され、肝心の文学の話が出てこない。まるで国連総会に出ている気分で、すっかり失望してしまった。
そこで吉岡たちは、日本での開催を前にして、文学者の国際交流はどうあるべきか検討する。「文学的なテーマを設けて、向き合うべきだ」と言うことはいえるが、具体的なテーマとなるとなかなか思いつかない。各国にはそれぞれ抱えた問題がある。政治的な立場の違いや宗教的な対立を避けて通るというのはなかなか難しいのであった。
しかし、あらためて世界を眺めると「スマトラ沖の大地震と津波、米国南部を襲った巨大ハリケーン、パキスタン北部の地震、ヨーロッパ中北部の猛暑、フィリピンの地すべりなど、社会的にも大きな影響をもたらしている。人間はいたるところで自然災害に翻弄されている。」
そのような自然災害に文学はどう向き合ってきたか調べると、どこでも関心が高いことは分かったが、防災やその対策と言ったものばかりで文学的、文化的なアプローチはない。
古典を見ると、戦争の悲惨と並んで、災害のすさまじさ、それによる人心の荒廃が描かれ、作り手や書き手の心情も書き込まれている。
現代においても、現実の災害現場に踏み込んでいき、人間を描いたドキュメンタリーもあれば、家族や友人を失った悲しみ、そこから立ち直っていく人間像を描いたフィクションもある。そこから自然を再発見する作品もあれば、災害によって生じた亀裂から、社会を見つめたものもある。それは小説や映像ばかりではなく、音楽にもある。
しかし、それらを集めた世界的なフォーラムやシンポジウムは全然なかった。「日本は地震と噴火、水害や雪害、津波などの被害が多い、災害の宝庫だから、これをテーマに国際的なフォーラムとして、取り組んでみよう」と決めた。
文学の書き手や作り手が経験や思考を語り合う。フォーラムに参加した市民がその議論に加わる。そうすることで、文学的表現と災害とが出会うことが出来る。ここから、世界各地の災害の現場を直視した作品を一堂に集める、という日本ペンクラブ主催の世界フォーラムとなったというわけである。
基調講演を大江健三郎がおこない、日本からの参加作品は、本作の他に立松和平が自作長編「浅間」のドラマ化作品の朗読、高田宏が書き下ろしエッセイを朗読するなど、上演に当たっては舞台にかけるのにふさわしい、細心の工夫をほどこした。なお、このときの本作のタイトルは、災害と文化というテーマを意識して「リトル・ボーイ、ビッグ・タイフーン」であったが、後に改題した。
また初演以来、新国立劇場の演劇研修生がこの劇を担当している理由について、大笹吉雄がその興味深いいきさつをパンフレットで紹介している。
「政治学者の丸山真男を尊敬する人たちが、毎夏、偲ぶ会を催している。2007年のその会のために、丸山の軍人だった若き日、救援のために被爆直後の広島に行き、それがもとで放射能に二次感染した体験を語る録音テープが残っているが、それを素材にした朗読をこまつ座でやってくれないかという申し入れが井上ひさしにあった。が、井上ひさしは忙しくて時間がなく、これを新国立劇場の演劇研修所に持ちかけた。」
「話を受けた研修所はラフスケッチの朗読劇を偲ぶ会で披露し、思いのほか好評を博した。これを聞いた井上ひさしが」ペンクラブのために用意しつつあったこの劇を研修所の所長で井上の信任あつい栗山民也演出、研修生出演で上演することにしたというのである。この初演が成功し、以後劇は研修所の手にゆだねることになった。
それにしても、丸山真男が「広島に救援に入った」とははじめて知った。(そこかい、といわれそうだが。)この時期丸山は三十才を過ぎて、東京帝大助教授である。それが八月六日、爆心地から5キロメートルの兵営に陸軍二等兵として駐屯していたのである。帝大助教授が、のちに上官の顔色をうかがうすべを学んだというようなことをいっていたらしい。赤紙を出した役人は、何を考えていたのだろう。偲ぶ会というのも、丸山真男が亡くなって随分とたっているのに、大がかりなことを企図するほど力があることに感心する。上のような劇が書かれた事情を考えれば、ヒロシマが二つの災害に襲われたとすることに得心がいくのではないか。庶民の立場からみれば、どちらにしても怒りの持って行きようがないというのも一面、真実である。
また、朗読劇の形式としたこともペンクラブの主旨に合わせてあるが、会話の部分の方言と地の文の混じり具合が至芸と言ってもいいくらい絶妙であり、短編小説と言うよりは長文の散文詩とも言うべき美しい日本語で書かれていることに感動する。三人の少年も哲学じいたんも花江さんもこの詩の中に埋もれているが、その姿は「読むこと」によって見るものの心の中に鮮やかに浮かび上がってくる。
被爆から巨大台風までのヒロシマの様子をスケッチした佳品という趣でもあるが、三年後を舞台にした「父と暮らせば」、被爆直前までの「紙屋町さくらホテル」とあわせてヒロシマ三部作と呼ぶという大笹吉雄の見解に賛成である。さて、前に戻って「水の手紙」のことである。
先月(10月)僕は「ボトルウォーターの輸出が疲弊経済を救う—地方再生のマーケティングー」という本を書いて、デジタル出版社から出した。新書版でと思って何社か持ち込んだが、無名のものに許された席はなかった。
それは、文字通り地方経済を救うために自分たちの足下に眠る資源である水を輸出しようという提案である。水が今世紀には石油に変わる戦略資源になるということを理解してもらうには、世界の水事情を説明しなければならない。
その中に、この劇で紹介されたエピソードがいくつか入っている。たとえば、大河の水を分け合うという話では、いまナイル川も流域の国家間でトラブルを抱えてる。水の汚染が深刻なところも数多く存在する。最も重要なのは、この劇では言及されなかったが、大陸の地下に眠っている帯水層の水が大量に汲み上げられてあと五十年もすれば枯渇するとという深刻な事態を迎えていると言うことだ。
「水の手紙」が描く世界は、次の言葉で表現されているように、ヒトが善意に基づいて水を分けあって生きていくことを期待している。
「水からヒトは生き方を学ぶ
水がヒトをヒトに結びつける
世界は水で結ばれている
世界は一つ、水で結ばれている」しかし、すでに水は「商品」であるという合意が少なくとも先進諸国の間では形成されている。
そのような見地から見れば「水の手紙」は確かに問題提起に違いないが、現実的な解決の道筋を示すものではない。そこで、劇評としてふさわしいかどうかはおいて、できるだけ手短に僕の考え方を述べてこの文を締めくくろうと思う。
この劇の始めの方で、日本は平均降雨量が年間2,000mmという途方もない雨が降る国だといわれる。面積は約37万平方キロだから7兆4,000億トンという真水が天から降ってくるのだ。北米大陸最大のオガララ帯水層に眠っている地下水は、長年にわたって米国の穀倉地帯の灌漑を維持してきたが、この地下水量が4兆トンと推定されているからその倍近くの量になる。むろん降った雨すべてが滞留するわけではない。
たとえば、富士の湧水で有名な柿田川は、毎日100万トンのそのまま飲用できるミネラルウォーターを海に流し続けている。年間3億6千万トンである。この川が二本あれば世界のミネラルウォーター市場の需要を十分満たすことができる量だ。
僕の本に目を通してくれた米国の友人Dr.Watermanによると、最近News Week で The New Oil という水の特集を読んだが、カナダ、アイスランドなどが主要な輸出国で、日本は入っていなかったという。おそらく氷河に着目してのことだろうが、上の数値を見れば日本が水資源大国であることは間違いないところである。(あまり自覚のないところは問題である。)
水はこれからますます「商品」として、資本主義の経済システムの中に組み込まれていくだろう。ただ、人類にとって生死にかかわる「商品」といいよう、それによって強欲なまでに利潤をむさぼるわけにはいかない。それは、自らが資本主義的なシステムを壊すことにつながるからだ。(最近の例では「リーマンショック」がある。)資本主義が自ら生き延びていくためには、「環境問題」のように、基本的にそれ自身の中にある矛盾を克服する方向を目指さざるをえないのである。
水に関して言えば、そのためには資本主義のシステムの中で、取引のルールを決めて公正に運営することが重要になる。そこで、我が国は資源大国の一角としてイニシャティブをとれる可能性が高いと、僕は思っている。
その根底にあるべき思想は、この劇にある「世界はひとつ、水でつながっている」というものであることはいうまでもない。このあたりの考え方を本には書いたが、興味のある方には是非読んでいただきたい。
井上ひさしは、なくなった。
世代も違えば考え方もすべてが一致するわけでもなかったが、あの文体が、そして時に露悪趣味で奇想天外な発想とユーモアの質が好きだった。もう、いないと思えばなにか脱力感のようなものを感じてしまう。この公演は、井上麻矢がいうように、確かに「小さくても上質なもの」ふたつをそろえてくれた。
