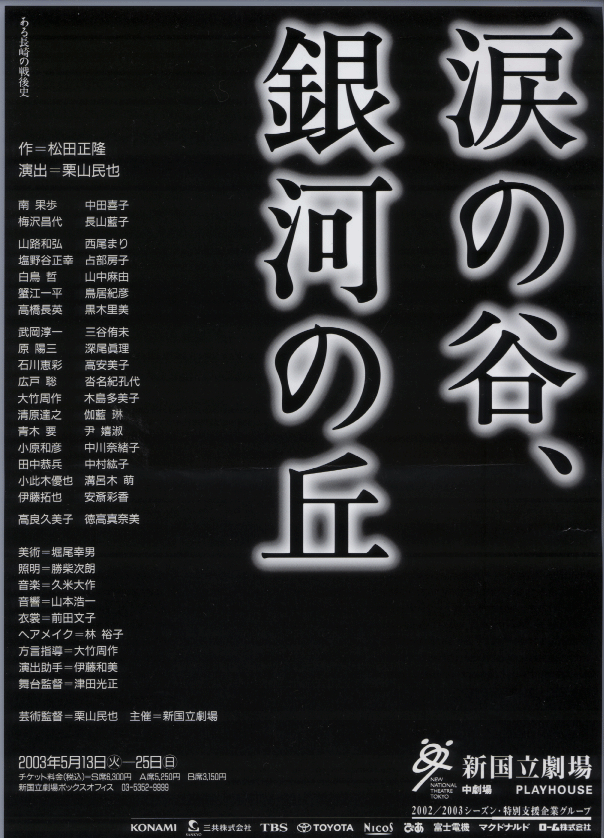
|
題名: |
涙の谷、銀河の丘 |
|
観劇日: |
03/5/16 |
|
劇場: |
新国立劇場 |
|
主催: |
新国立劇場 |
|
期間: |
2003年5月13日〜25日 |
|
作: |
松田正隆 |
|
演出: |
栗山民也 |
|
美術: |
堀尾幸男 |
|
照明: |
勝柴次朗 |
|
衣装: |
前田文子 |
|
音楽・音響: |
久米大作 |
|
出演者: |
長山藍子 中田喜子 梅沢昌代 南果歩 白鳥哲 山路和弘 塩野谷正幸 占部房子 西尾まり 蟹江一平 高橋長英 黒木里美 他 |
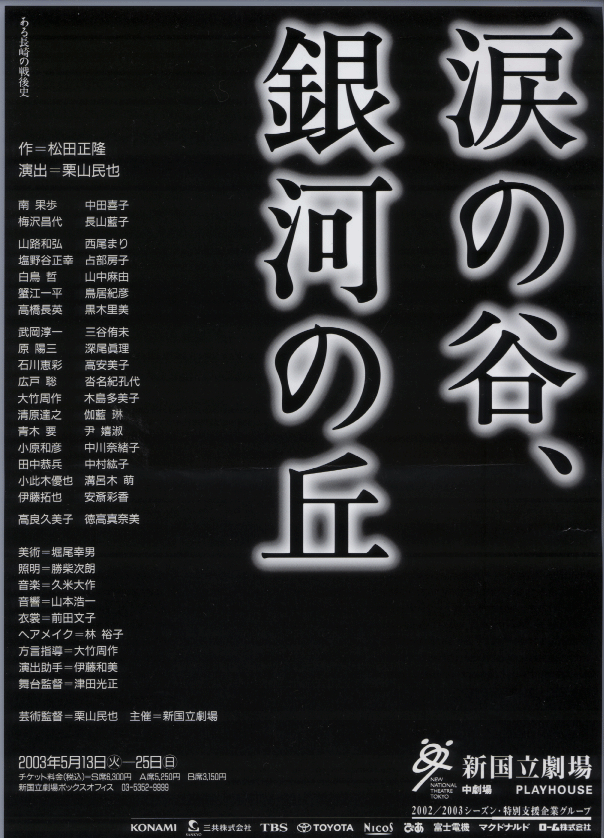
舞台中央が姉妹の住む家。回りをコロスが囲む。
「涙の谷、銀河の丘」*増補
長崎の街は何度かいったことがある。駅から電車道があって、多分北の方角に向かうと、やがて片側から土手が迫って、道は谷間をいくようになる。そのあたりが浦上ということだが、港周辺の密集地帯から3キロほども離れた丘の上に立つと、なぜそこが爆心地なのかいぶかしい気がしたものだ。米軍の事情を僕は知らない。長崎に住む人には、そこが浦上であることに格別の思いがあるようだ。遠く隠れキリシタンの昔から続く受難の地というイメージは、長崎の原爆の意味に深い陰影を作っていることがしのばれるのである。
松田正隆もまた、そのことを問い掛けている。時折舞台にはギリシャ劇のコロスのように、おびただしい死者達が現れ、その鎮まらぬ魂の声が、時に嘆き、怒り、うめき声をあげて舞台を満たし、長崎という悲劇の本質を糾すのである。
物語は、戦後まもなく京城から引き上げて、廃虚と化した長崎に住むようになった四姉妹と末の弟の話である。
一家は、父親の友人である岡田(山路和弘)の世話で落ち着き先を得る。ヤミをやっている復員兵の増本(塩野谷正幸)の助けもあって、ようやく食べていけるようになったころ、岡田がふたりの子供を残して原爆症でなくなってしまう。一方、増本は、長崎が戦争の被害者であることを認めながら、兵隊として自分が中国で犯した罪によって戦争の加害者でもあることを意識している。その矛盾が激しい憎悪となって進駐軍に向けられ、ある日暴力ざたの中で命を落としてしまう。水商売に入っていた三女ふく江(梅沢昌代)は増本の子を宿していたが、それを機に長崎をでる。増本に犯されそうになったことがきっかけになって、四女しの子(南果歩)は何かに憑かれたようになり、占いが近所の評判を呼んで、客を集める。その謝礼は馬鹿にならなかったが、二女、久美(中田喜子)は気に入らない。
必死で生きてきた姉弟の上にも高度成長時代がおとずれ、長女、道子(長山藍子)は造船所の下請けで事務員となり、書道教室を開いているしの子、高校生の吉夫(白鳥哲)と暮らしている。二女、久美は嫁いで既に二人の子供がいる。
そんなある日、ふく江の娘と名のるマリ子(西尾まり)が現れ、しばらく滞在することになる。ヒッピーやロックの時代である。マリ子の奔放な振る舞いに静かな生活がかき乱され、それぞれが自分の来し方を振り返る機会になるが、そのマリ子も精霊流しの夜、どこかへいってしまう。そして、高校を卒業する吉夫は、東京にでて就職することを決心し、姉たちに送られて長崎を後にする。
戦争から五十年、平成七年のある日、しの子が書道教室の生徒、立花(高橋長英)と結婚することを道子に告白する。明日は結婚式という日、今はカリフォルニアに住んでいるふく江ももどって、しばらくぶりに姉妹が顔を合わせる。そこへ久美の息子、充(蟹江一平)がやってきて吉夫が佐賀で交通事故に遭い死んだと告げる。吉夫は東京で借金の保証人になったことで全てを失い、長崎の近くまでやって来てホームレス同然の暮らしをしていたらしい。コンビニの弁当を万引きして捕まったこともあったようだ。
呆然としながらも、姉妹は懸命に生きてきた戦後の五十年を考えざるを得ない。豊かさを描いた絵の具が乾き、ひび割れを始めたような不安が姉妹の胸をよぎるのである。
長山藍子の長女はそれらしい雰囲気を十分漂わせて美しく、時に表す苦悩の表情が年長者の役らしい陰影を作った。中田喜子は、気丈な次女役で、いかにもさっさと結婚してしまいそうなはっきりした性格を好演した。梅沢昌代も難役をこなして元気、四女の南果歩は老け役にやや問題ありだが、この四姉妹は極めて調和がとれていて、好印象であった。
塩野谷正幸の増本は、この人の特徴である、いかつい身体に乏しい表情、ある種不気味さを漂わせているのはいいのだが、もう少し、いやほんの少しでいいのだが、顔の筋肉を使っていただかないと、何を考えているか伝わらない。 (流山児なら、いいと言うのかもしれないが)
西尾まりの存在感は、この芝居にとって強いアクセントになった。戦後まもなく増本と三女ふく江の間に生まれた子供だから団塊の世代である。松田正隆の思い入れが、日常性を蹂躙するようにして去った、不可思議な存在として、必要以上に大きく神秘的に描かれたかもしれない。それを西尾まりは正々堂々と演じきった。
吉夫の白鳥哲はませた高校生だッた。
一体に、栗山民也の演出は、コロスの使い方によくわからないところがあったが、それはこっちのせいとして、全体に極めて丁寧で、中劇場にふさわしいスケール感もよく出していた。さて、松田正隆は、長崎に生まれ、長崎を舞台にした芝居を長崎の言葉で書き続けている希有な作家である。「母たちの国へ」(2001年1月、新国立劇場)を見たが、骨格のしっかりした芝居で、日常的で静かな言葉遣いの中に、被爆という実存に関わる主題が立ち現れるのが見事であった。
「涙の谷・・・」は、京城から引き上げてくるところから始まり、戦後の五十年をまるまる描いている。
松田は1962年生まれというから、この芝居で言えばちょうど二幕目、ヒッピー風のマリ子が一家の前に現れるころ、産声を上げたことになる。
とすれば、この物語の大半は、彼が経験した時代のことではない。調べたわけではないが、彼は確か鴻上尚史(第三舞台)や成井豊(キャラメルボックス)と同じ世代に属するはずだ。ところが松田正隆だけは、敗戦から今日までと言う長いスパンで日本の社会を見ている。その点、同世代の中で、僕には特異に映る。
なぜ松田はそのような視点を持つようになったのか?もちろん、長崎生まれという環境も作家志向という資質もあっただろうが、最も大きいと思われるのは、劇作の原点に別役実と唐十郎がいたことだろう。
彼は九十年に劇団「時空」を創成するが、そのあたりのことを「母たちの国へ」(2001年1月、新国立劇場)の公演パンフレットで語っている。
「・・・自分で戯曲を書くにはどうしたらいいのかなと思い始めて、京都書院の戯曲コーナーへ行き、別役実さんの本にであったのです。登場人物に名前も台詞もト書きも、簡潔なところにひかれた。そして人間存在の本質的なことを描いてあることにも。」
「・・・留年が限りなく続くとわかった。で、劇研に入ったんです。地味ながらアングラっぽいことをやっている劇研で、みんなが唐十郎はすごいとか言っている。読んでみたら、身体でわかる面白さがあったんですね。別役作品も唐作品も、何も理解できていなかったとは思うのですが。卒業して旗揚げした劇団では、最後に舞台がワーツと壊れたりする唐さん風と、公園に集まってきた人たちがしゃべりあっているうちに共同体が出来ていくというような別役さん風とを交互にやっていたというわけです。」
「やっていくうちに、どちらも自分じゃない。表面的なことだけなぞって借り物で作ってるってことが見えてきた。エピゴーネンですよね。それに唐さんの、あふれる詩情と滑稽さと悲しみとが三つどもえになったような台詞は自分には書けないとわかった。一年ほど休んで考えて、とにかく自分の身近なことを書いてみようと思い、母親をモデルにした『紙屋悦子の青春』を書いたんです。・・・」(演出家、西川信廣との対談)
別役実、唐十郎との幸福な(と僕は思いたい)出会いの後、自分の文体と方法を見つけ出したというのであるが、おそらく彼らの世界観から影響を受けたことも間違いない。別役も唐も突き詰めていけば、敗戦と言う現実にぶつかる。左翼も反体制も高度成長もそこから始まるのである。松田が、経験の中に無い、廃虚となった長崎とそこにうごめく人々を描けるのは、戦後史を見る揺るぎない視点を確保しているからに違いない。
僕は70年に別役実や唐十郎の芝居に関わった。それから二十年後に当時と同じような年齢の若い人たちが「すごい」とか言っていることに感慨を覚える。僕らは若い人たちに何一つ受け継いでもらうべきものを渡してこなかったと悔やむことが多いからである。
松田は、この芝居の中で極めて今日的なテーマをいくつか挿入していて、必ずしも結論を示してはいないが、若い世代の関心のありようを表していることが興味深かった。
まず、復員兵の増本が、あるとき「日本も原子爆弾を持たなければ、アメリカの奴隷になり下がる!」と叫ぶところである。当時の言葉としては不自然で、これは明らかに現代政治論である。冷戦後の東アジアの安全保障をどのような枠組みで考えるかについて、多くの議論が存在する。極端だが、日本の核武装と徴兵制を言うものまでいる。松田はどう思っているかわからないが、とりあえず問題意識として提示されたことは間違いない。
また、同じ増本が、戦争において加害者であり、被害者のいわば象徴のような長崎にいることのアンビバレンツを言うところである。大東亜戦争がどういうものだったのか、その全体をとらえようとする視点を確保しようとしているのだろう。
そして、宗教の問題である。浦上天主堂の真上で炸裂した爆弾は同じ神を信仰するキリスト教国が落としたものであるという矛盾は、広い意味で宗教とは何かを問い掛けるものだ。
終幕近く、吉夫が零落してホームレスになり万引きで捕まるなどの境遇になって、仕舞いには交通事故で命を落とすという設定は、そのまま松田の「戦後五十年」の総括となっているのではないか?
僕は若い世代が、戦争体験者や復古主義や左翼の論調から離れて、日本の戦後史を丹念に検討しながら、自分たちの未来を描く議論をして欲しいと思う。
松田はこの芝居でどんな態度表明もしていないが、おそらくその議論をリード出来るものの一人であることに間違いない。
(2003.5.26)
*増補
この稿を書いたすぐ後で、長崎に原爆が落とされた事情が分かった。米軍によると、8月9日は北九州小倉に原爆投下を行う予定だった。南太平洋の基地から朝早く飛び立ったB29は午前8時頃小倉上空に達したが、あいにく雲が厚く投下地点を視認することが出来なかった。
やむなく、次の候補地(熊本だったか)に向かうがここも曇り空で投下不能。燃料が乏しくなる中長崎上空まで来ると(候補地のひとつではあった)雲の合間から僅かに市街地が見えた。帰還が迫っていたので最後のチャンスと見て、 計器で計測しながら投下地点と思われる場所に移動。ただ、その瞬間確実に市街地を視認できる状態ではなかった。結果として、人口が密集しているところから約3キロメートルずれて、偶然浦上の上空500メートルで原爆が炸裂したというのが真相のようである。この稿で「米軍の事情を僕は知らない。」と書いているが、上のように分かったとしても、長崎の人々にとって、この爆心地が暗示するものの意味はあまり変わらないように思う。 原爆で傷ついたものは想像以上に広く深い。
