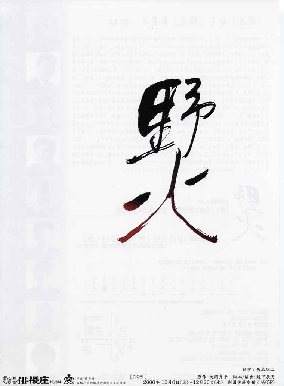
「野火」
昨年5月に見た「死の棘」(原作:島尾俊雄、作、演出:鐘下辰男)の執拗さ、過剰さに辟易して、当分鐘下辰男はいいやと思っていたが、大岡昇平と聞いて心が動いた。偶然数カ月前に読み直したのと、この世代が戦争をどのように描くのか、あるいは描けるのかという興味もあった。(鐘下は昭和39年生まれ)一方で、いかにも鐘下好みの小説をとりあげたものだという心配もあった。
「死の棘」は愛人の存在に気付いた妻が嫉妬のあまり、気が触れていくのに誠心誠意付き合おうとする主人公の話で、島尾俊雄が16年の歳月をかけて書き上げた自伝的小説である。島尾は海軍特攻で、クリスチャン、戦争の体験が底にある。妻の嫉妬はくりかえし行き場のないところまで夫を追い込み、夫は贖罪の意識からそれにじっと耐え続ける。
客席にプールを作りその上に木の床を載せた舞台で、全員水浸しの熱演は十分劇的であったが、その自虐趣味に同化出来るような説得力はなかった。信仰があるからそれを受容できる、としか考えられない異様な状態が延々と描かれて、何故そこまで狂った妻につきあえるのか、理解の限界を超えた。木戸銭を払ったのに、こっちの精神が異常を来しそうになって大いに閉口したのであった。
「野火」は、吉田健一が「日本の現代文学に初めて小説と呼ぶに足るものが現れた」と評する如く、日本の悪しき私小説の伝統とは完全に縁を切っているが、極限状況を描いたという点で、鐘下がこのところこだわっているテーマだといえる。
俳優座の五階にある稽古場は小劇場ほどの広さがあって、たまに公演に使われることがあった。その空間の対角線上に巾一間、高さ三尺ほどの木の廊下を渡して舞台にした。中央には風呂桶のような水槽がおいてある。他にタイル張りの細い柱が一本、むき出しの水道の蛇口が一つ、という島次郎の装置はいたってシンプルである。
開幕早々、一人の洋装の女(伊勢佳世)が舞台に登場する。そして、この女はほとんど無言のまま終いまで舞台に居続けることになるのだが、私=田村(田中壮太郎)の最初のせりふが「妻に連れられ、ここにきた時・・・」と始められるので、妻かと思ったのは極く自然の成り行きだった。それなら、この妻は夫を精神病院に入れてまもなく離婚、そこの医者と懇ろになったことになっている。ただし、この小説で妻に言及したのはその終焉直前の数行で、ひととなりなど他に語るべきものは少しもない。ところが、その女はやがて妻と特定したものではないと分かった。劇中、少しばかり移動したが、じっと成り行きを見ているだけで、劇に参加する気配はない。
ならばこれは何者か?
むろん、あの月明かりの夜、海岸にほど近い無人の村の教会で偶然遭遇した現地の女を撃ってしまう場面には多少しぐさによってかかわりを持つくらいのことはあった。また終幕にいたっては「私」が最初に発したせりふを反復してみせた。
しかし、なにしろ小説全体は戦地フィリピンにおける日本兵の凄絶な生きようを描いて、女の登場する場面などない。にもかかわらず、鐘下辰男は、この小説を舞台に上げるに当たって、戦場という男の極限状況をじっと見ている異性の視線が必要だと考えたのであろう。それが何故なのかという疑問が通奏低音のように聞こえて来る劇であり、そこに鐘下辰男が「野火」に向き合った動因が潜んでいると考えられた。
ところで、大岡昇平について先年から気になっていることがあって、それがこの劇と関係があるかどうかについてはあまり自信がないが、どうしてもここで吐き出しておきたいという衝動を抑えきれなくなった。
ある時僕は、何故そんな気になったか忘れてしまったが、大岡昇平がすでに妻子が在りながら召集された不運とその別れの心境に思いをはせ、個人の日常に襲いかかる戦争というものの理不尽さを考えさせられた。その時僕は少し感傷的になっていたかもしれない。むろん何十年も経って戦争など縁もないいまの時点では、多少の感傷は許されていいと思った。ただし、その時点の大岡昇平は、出征に当たっていっさいの感傷を排して冷徹に状況を分析し、ふりかかった運命を引き受けている。にもかかわらず、もれてくる心情に僕は心を動かされざるを得なかった。
昭和十九年六月十日、東京麹町の東部第二連隊で、三ヶ月間の教育召集を終えた大岡昇平は除隊の日を迎えていた。しかしその日、彼は南方行きを命ぜられた。中隊百人中半数はそのまま除隊した。不運であった。
僕の大正五年生まれの父もこれより一年ほど前だったと思うが教育召集に応じて、運良く三ヶ月で帰ってきた。朝鮮半島まで行ったことと中隊長が若くてできる人だったということ以外いっさい口にしなかった。そのときすでに長姉が生まれていて、隠居した親の面倒も見なければならない立場だった。そのまま戦場にもっていかれたら・・・という思いはあっただろう。僕は父からついにその時の心境を聞く気にはならなかった。
大岡昇平は父より年長で、すでに三十五歳だった。しかし、その年代の補充兵さえ必要とするほど戦況が悪くなっていた。タイミングが悪かったというしか言いようがない。
神戸にいる妻子を呼ぼうかどうか迷ったが、不慣れな東京に出てくるのを案じて、すでに別れはすましてあると遺言を友人に託すだけにした。この友人が気を利かせて結局妻子が面会に来ることになった。出発まで日がない。面会に当てられた小学校の教室で待つが、その日はやって来なかった。
翌日、品川駅に集合して列車に乗ることになっていた。連隊は、近衛第一連隊と同じところ、現在の北の丸公園一帯にある。それぞれ約五十kgの背嚢を背負って(後にも先にもこんなに重いものを背負ったことはなかったという)、隊列は田安門(現在の武道館の側)を出た。九段下の軍人会館(現在の九段会館)の前を通り、内堀沿いに竹橋を目指した。他の営門から出たものとここで合流。竹橋からは一直線である。日比谷公園裏で小休止、愛宕下を通って芝公園に向かう。途中兵隊たちは商店に入って電話を借りたり、知らせを受けてやってきた家族と同道しながら歩いた。赤羽橋からまっすぐに行くと札ノ辻から田町に出るが、その手前から右に入り、高輪の高台を行く道をとる。二本榎(高輪二丁目)を通り過ぎて、午後二時、ついに品川駅を見おろす坂の上に出た。(おそらく現在の新高輪ホテルの辺りか)ここで中休止の号令が出て背嚢を下ろし、銃を組んだ。
「歩道に腰を下ろして夢中で汗を拭いていると、『大岡、面会だぞ』と道の向こう側から呼ぶ声がした。見るとそこには夢のように妻が立って、じっとこっちを見つめていた。
妻は白い単衣に下の子を紐で背負い、上の子の手を引いて歩道に立っていた。髪と衣服の汚れと乱れは、十間以上離れてもよく見て取れた。私はこの妻の姿に私が死んだ後の彼女の姿をみたと思った。同時に妻のほうでは変わり果てた私の姿に、『死』を見たといっている。・・・・・・我々が会えたのは全く偶然であった。しかしもっと別に話すことがあるはずである。(この前に、どうしてここに来ることが出来たのかという話をしている)・・・この最後の別れのときに、私が小説の言葉を言わないからといって、彼女を愛していないわけではない、といってやりたかった。あるいは嘘でもいいから、彼女の納得のいく小説の言葉を一言いってやりたかった。しかし、この瞬間にも、どうしても私の口から出てこないのである。
先に涙を流したのは私である。涙は汗と一緒に流れたので、私はそれを手ぬぐいで顔ごとふき取ることが出来た。妻もやがて顔を左右に反けながら黙って泣き続けた。そして我々はやはり何も言わなかった。」
「集まれ、の号令に我々は不意を衝かれ、もぎ離されるように別れねばならなかった。・・・・・・妻が『あそこまで』と決めていたのは道が駅前の電車道と交わるところであった。彼女たちはそこを越え、停車場の安全地帯へ上がってそこで止まった。そこから先は車や人が混雑している。私はこの時、『どこまできても同じだよ』といったそうである。妻はそのまま動かなかった。私は彼女を見つめ、首肯いて前を向いた。駅の低い木の庇の下へ入る時、私は振り返ろうかと思ったが、何故か自分を抑えてしまった。」(『出征』昭和25年より)
こうした情景は洋の東西を問わず、いつの時代にも繰り返されてきた悲しい出来事である。にもかかわらず、今でも世界のどこかでこういう別れが起きていることを思えば、人間とは何と愚かで救いようもないバカなものだとつくづくそう思うのである。
さて、とんだ寄り道をしてしまった。劇に戻ろう。
田村上等兵は、結核と分かって野戦病院行きを命ぜられた。病院では肺浸潤と診断されたがこの程度で入院させるわけにいかないと三日で帰された。原隊へ戻ると、お前の居場所はここにはない、病院に頼み込んで居させてもらえと追い返される。その押し問答が何度かあり、とうとう田村は行き場を失った。フィリピンの山の中を彷徨することになるが、途中、野戦病院で一緒だった安田(塩山誠司)と永松(田中茂弘)が一緒にいるところに出くわす。彼らも追い出された口だった。
安田は熱帯性潰瘍で足が腫れ上がって歩けない。どこかに一定量のたばこを隠し持っているらしく、永松にそれを渡しては食料や必要な品に交換してもらっている。永松は安田の子分格に収まっているが、互いに信用しているわけではない。とりあえず持ちつ持たれつの関係である。
この関係を端的に表すように安田が、永松の押すギーギーいう錆だらけの車椅子で現れるのは、アイディアであった。フィリピンの山中に車椅子はないだろうという野暮は言いっこなしでよい。安田のメイクアップに凄みがあって、はぐれた兵隊の風情十分であった。
田村は一人山中をさまよった。畠を発見して芋にありついたこともあった。
そして、あの月夜の晩、田村が海岸に近い無人の村で偶然出くわした女を射殺する。連れの男が逃げたのを見て、田村は大急ぎでそこを離れるが、その時二合ばかり入った一袋の塩を手に入れた。これが後々田村の命をつなぐことになる。
まもなく米軍の攻撃によって日本の守備隊はバラバラになってしまった。雨期がきて食料が無くなり、日本兵の屍体がそこいら中に転がっていた。「餓え」がこの山中を覆っていた。
ある時、気が触れた瀕死の兵隊(矢野宣)と出会った。夕日の丘の上で、死ぬ前に「俺が死んだらここを食べていいよ」と右腕を差し出された。田村はその誘惑をようやくのことで抑えたが、このとき右腕を左腕が押さえるくせがついた。
降伏もままならず、餓えて雨期の山中をさまよっているうち、体力がなくなって田村は河原で気を失った。倒れていたところを助け起こしたのは偶然、あの永松であった。永松は、一片のせんべい状のものを口に押し込んだ。なつかしい脂肪の味がする。「猿の肉だ」と永松がいう。安田と一緒だったが、立場が逆転していた。永松が猿を獲ってきて安田を養っているらしい。安田は、永松を操って生き永らえてきたが、今や永松はずる賢い安田を警戒している。安田が田村の持っていた手りゅう弾を巻き上げてしまうと、ついに永松が態度を変えた。やられるまえにやってしまえと安田を撃ったのである。永松が安田の手首と足首を蛮刀で切り落としたのを見て、田村は夢中で銃の置いてあるところへ駈けた。永松が追いかけてくる。一瞬早く銃を手にした田村に永松が笑顔を見せながら近づいてくる。田村はそのとき永松を撃ったかどうか覚えていない。その後、銃の遊底蓋に雨粒が落ちてくるのを見ていたところで記憶が途絶える。ゲリラによって後頭部を殴られたのであった。
あれから六年、いまは、東京郊外の精神病院にいる。一年前から食膳の前で、叩頭し食べ物を拒否するようになり、右手を左手で押さえるしぐさをするようになったためである。医者は「罪悪感を補填するために現れるコンプレックス−メシヤ・コンプレックス」あるいは「離人症」といっている。
田村は永松が「猿」といっていたものを知っていた。しかも自身がそれに対して強い誘惑に駆られたことを知っている。自分は、殺しはしたが食べなかった。しかし、食べなかったのは単なる偶然に過ぎなかったのではないか。田村はこの「単なる偶然」について苦しんでいたのである。
原作は次のように締めくくられている。
「もし私が私の傲慢によってその罪に落ちようとしたちょうどその時、あの不明の襲撃者によって、私の後頭部が打たれたのであるならば・・・
もし神が私を愛したため、あらかじめその打撃を用意したもうならば・・・−
もし打ったのが、あの夕日の丘で、餓えた私に自分の肉を薦めた巨人であるならば・・・
もしも彼がキリストの変身であるならば・・・
もしも彼が真に私一人のために、この比島の山野まで遣わされたのであるならば・・・
神に栄えあれ。」
鐘下辰男は、原作のテキストをほぼ忠実にせりふにしている。劇にするに当たって、小説の脚本化には二通りあって、一つは、小説の世界を咀嚼し、いわゆる換骨奪胎して、舞台上に再構成する方法と、島尾俊雄の『死の棘』でやったようにストーリーやテーマよりも作家が『書いた』という『行為』に注目して、小説家の『行為』そのものを舞台上に表現しようとする方法である、といっている。
「・・・田村一等兵がフィリピンの戦地でどういう経験をしたかというストーリーよりも、田村がこれを書き続けようとした彼の『行為』そのものにこの作品の中核が存在するわけです。もちろんそれは原作者大岡昇平の『行為』でもあるわけです。その『行為』をどう私たちは『演劇』という『行為』へと転化出来るか、それは無謀と同時に無茶な冒険心がなければできないものなのだということを、今回私はあらためて稽古を通し痛感した次第なのです。」(「パンフレット」から)
作家の『行為』を舞台上に表現するというのは確かに冒険である。通常そういうことは大学の文学部の作家研究ゼミででもやることであるが、その結果がそんなに面白いことになるとは思えない。
僕はたまたま原作を読んでいたから、小説のどのプロットを取り上げたか分かったが、一般的に中編小説の僅かな部分を抜き書きされただけでは、作家の『行為』に到達する前に劇に向かう気持ちが萎えてしまうのではないかと心配である。それよりも、小説の脚本化に当たって、換骨奪胎とは猪口才な物言いであり、小説家の「書く行為」に同化しようという小生意気な態度も感心したものではない。どんなに偉そうなことを言っても、せいぜい出来ることは、小説を読んで、自分がどう感じたか人さまに伝える「行為」くらいであろう。
僕は、見終わってすぐに、原作にこういう耶蘇臭い匂いはないはずだと強く思った。
最後に、小説の終わりの部分(先ほど引用した)が田村のせりふとしてあり、続いて女が開幕の田村のせりふを反復し、こういって劇は終わるのである。
女「・・・復員後、私が取り繕わねばならなかった「生活」それらがどうして私の欲しないことばかりさせたがるのか、ほんとうは不思議でした。新聞報道は私のもっとも欲しないこと、つまり戦争をさせようとしている。現代の戦争を操る少数の紳士諸君はそれが利益でしょうからそれは別として、再び彼らにだまされたいらしいあなた方が私には理解出来ない、おそらくあなた方は、私がフィリピンの山中で遭遇したような目に遭う他ないでしょう。その時あなた方は思い知る−戦争を知らない人間は、半分は子供である。」
(水の流れる音)
女「われ深き淵より汝を呼べり、われ山にむかいて目をあぐ、わが助けはいずこより来るや・・・」
この聖書の引用は、原作にはない。鐘下は、これより前、田村の口からこの同じ言葉を言わせている。田村はインテリだから教養としての聖書を知っているだろう。しかし、「野火」全編を通じて田村が神の名を呼んだことはない。
大岡昇平は、十二歳の時、青山学院中学でキリスト教に感化された。この熱病は約一年で収まり、その後宗教から離れている。(漱石を読んだことが因だと言われている)このことがあったから、ひょっとして鐘下は誤解したのかもしれない。いや、我田引水したのか。つまり、鐘下は田村が神に救いを求めたのだと言う信念に基づいて、この劇を作ったのだ。田村一等兵という弱きもの、戦場、熱帯の気候、餓えという悲惨、そこで右往左往する獣のように振る舞う人間たち、鐘下辰男にとってそれらは救いようのない存在ではなくて、「救われねばならない」存在だったのだ。だから田村は聖書を引用し許しを請うたのだった。
したがって、あの女は、女性性であり、母性でありそして何よりもそれらの救いようのない有り様を眺めている超越的な視線だったのである。田村にとって一個の女性だった妻は、今や母性の象徴となり、母性を越えた存在になった。
小説家大岡昇平の「書く」という「行為」に同化しようとした鐘下辰男にとって「野火」とはそういう小説だったのである。
しかし、それは誤解である。誤解でなければ大岡昇平に対する侮辱である。
小説の最後に、いくつもの「もしも」=ifが並んでいる。あれは、自分がしてはならないことを「しなかった」のは、何か運命を操る超越的な力が自分だけに及んだのではないかと反芻しているのである。「もし」そうだとすれば、それが「神」というものだろう。しかし、『神に栄えあれ』は反語である。田村がそれを信じているわけではない。むしろ、それを信じられないところに田村の絶望と苦悩があるのだ。
野火が見えれば、必ずそこに人がいる。餓えや孤独を癒す何ものかがある。そこに行こうと言う誘惑と闘い、最後に安田の肉を切り刻んだ永松を撃ち、そこから先の記憶がない・・・という物語に仕上げた大岡昇平の「書くという行為」は、「偶然」と言う冷徹な「事実」を、自らが引き受ける以外にないということを表現しているのである。一種のニヒリズムのように見える。しかし、最初と最後に繰り返されるせりふの中に、
「現代の戦争を操る少数の紳士諸君はそれが利益でしょうからそれは別として、再び彼らにだまされたいらしいあなた方が私には理解出来ない、おそらくあなた方は、私がフィリピンの山中で遭遇したような目に遭う他ないでしょう。その時あなた方は思い知る−戦争を知らない人間は半分は子供である。」
とあるのは、自分の体験が確実に「伝わらない」であろうという確信とそれが繰り返されるという予言である。人間は救いようのない愚かなものであると断言しているのだ。「その時あなた方は思い知る−戦争を知らない人間は半分は子供である。」というのは、警告である。あなた方は、子供のように無邪気に戦争を賛美し、結果として多くの子供を犠牲にするに違いないと突き放しているのである。
鐘下が、そこに大岡の反戦の意志を読み取るのは勝手である。しかし、そうであっても今日、残念ながらそのメッセージがすでに無効であることは明白である。
「私は、この負け戦が貧しい日本の資本家の自暴自棄と、旧弊な軍人の虚栄心から始められたと思っていた。そのために私が犠牲になるのは馬鹿げていたが、非力な私が彼らを止めるために何もすることが出来なかった以上やむを得ない。当時私の自棄っぱちの気持ちでは、敗れた祖国はどうせ生き長らえるに値しないのであった。しかし、いまこうしてその無意味な死が目前に迫った時、私は初めて自分が殺されるということを実感した。そして同じ死ぬならば果たして私は自分の生命を、自分を殺すもの、つまり資本家と軍人に反抗することに賭けることは出来なかったかと反省した。」(「出征」より)
もとより、この時期の権力は「反抗するもの」を抹殺するほど強大であった。そんなことをしたら戦場に駆り出される前に殺されただろう。
戦後、大岡昇平は、政治左翼とは無縁であったが、徹頭徹尾反権力の態度を貫いた。反戦というならば、レイテ島の修羅を生き抜いてその体験が何であったかを追求してきた孤高の生き方そのものこそ大岡昇平の反戦の思想というべきであろう。(いま思い出したが、僕は「レイテ戦記」を読もうと思い立って、その前哨戦で「野火」を読んだのだった。)
さて、劇は予想した通り、鐘下好みの「極限状況」を描いた。「野火」のテクストをそのまませりふにしたのはいいが、原作が冷静な状況描写、分析的で乾いた怜悧な心理描写なのに、終始俳優が叫んでいたのには少々閉口した。餓えと病で苦しんでいるのにあの大声はどこから出てくるものか、演出家はもう少し考えてもらいたい。
それにしても、聖書の引用で終わるのはがっかりだった。人によっては、大岡昇平を戦後の実存主義作家の系列にいれることがある。いわば、人間は救われないものだという地点から反転するのが実存主義ということが出来るが、人間は救われなければならないというのでは真逆ではないか。大いに迷惑である。
僕としては、鐘下辰男の結論に到底同意出来ない。
題名: |
野火 |
観劇日: |
06/12/15 |
劇場: |
俳優座劇場稽古場 |
主催: |
俳優座 |
期間: |
2006年12月6日〜12月20日 |
作: |
鐘下辰男 原作:大岡昇平 |
演出: |
鐘下辰男 |
美術: |
島 次郎 |
照明: |
中川隆一 |
衣装: |
伊藤早苗 |
音楽・音響: |
井上正弘 |
出演者: |
矢野 宣 塩山誠司 田中茂弘 田中壮太郎 田中美央 蔵本康文 脇田康弘 林 宏和 伊勢佳世 |
