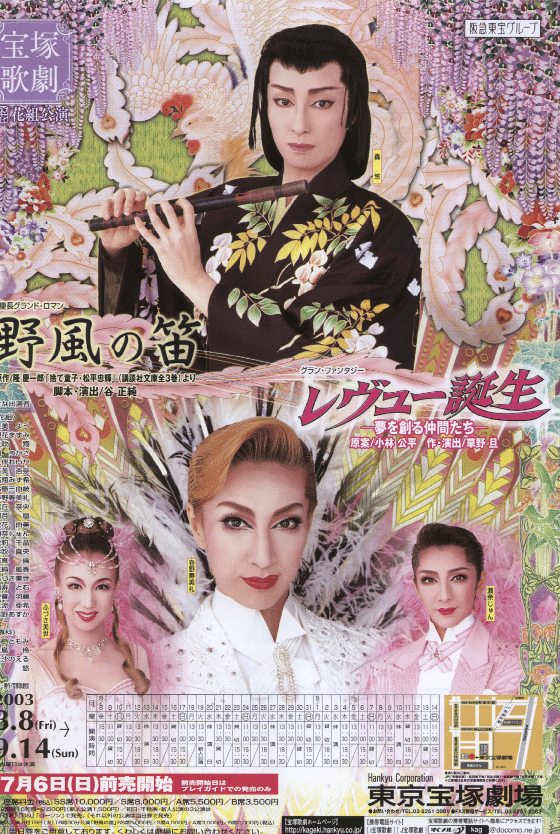
|
題名: |
野風の笛 |
|
観劇日: |
03/9/2 |
|
劇場: |
東京宝塚劇場 |
|
主催: |
宝塚歌劇団 |
|
期間: |
2003年8月8日〜9月14日 |
|
作: |
谷正純・隆慶一郎 |
|
演出: |
谷正純 |
|
美術: |
|
|
照明: |
|
|
衣装: |
|
|
音楽・音響: |
|
|
出演者: |
轟悠 春野寿美礼 瀬奈じゅん ふづき美世 他花組 |
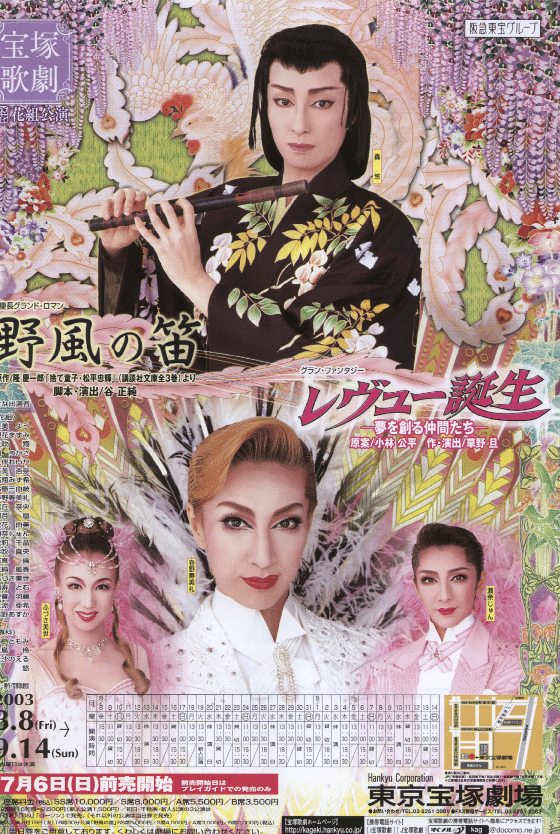
「野風の笛」「レヴュー誕生」
ついに宝塚を見た。俳優の顔が見えるところに席を取るのは至難の業と聞いていたが、案の定、二階席の左端で双眼鏡を忘れたことに後悔するはめになった。どんなに目を凝らしたところで役者が天井でも向かないかぎりあの度派手なメーキャップ姿を見る事は出来ない。少し残念だった気もするが、それは贅沢な望み?らしい。
衣装の絢爛さと舞台の色彩の饗宴、それが短い「場」を次々につないで現れる。蕩尽と言う言葉さえ浮かぶほど、それは豪毅で晴れやかに輝いている。なるほどこれが宝塚かと感心するばかりであった。見ているうちに、この形式はどうも歌舞伎がモデルではないかと感じた。それぞれの「場」が「型」によって決まりが付けられ、次の「場」に移ってゆく、そのテンポが歌舞伎に似ている。少女歌劇が温泉場の客のために始まったことは聞いているが、その当時の観客の嗜好に合わせたとすれば、浅草(軽演劇など)の影響はあったとしても、その根のところに歌舞伎があってもおかしくはない。
話は、徳川家康(汝鳥伶)の六男、忠輝(轟悠)の半生である。この子は生まれてすぐ家康に悪相だと疎んじられ、家臣花井三九郎(未沙のえる)に預けられ、その子主水正(春野寿美礼)とともに成長する。天下を手中にした家康が、忠輝の成長ぶりを見て、自分の目に狂いがあったと内心恥じるが既に秀忠(夏美よう)に家督を譲った後である。これに気づいた秀忠は、弟の才能を恐れこれを亡き者にしようと画策する。伊達政宗(立ともみ)の娘五郎八姫(ふづき美世)を正室に迎えていた忠輝は、誤解を恐れてこれを遠ざけ、自由に振る舞っている。正宗の腹の底には忠輝をけしかけ、秀忠の後を襲って将軍の岳父にならんと言う野望があると見抜いたからだ。こうした中大坂冬の陣の際密かに大阪城を訪れた忠輝が、秀頼、淀君親子に別れを告げていたことが秀忠の知れるところとなり、家康に厳罰をくだすべきと主張する。家康は、これを退け、織田信長より伝わる「野風の笛」を授けて、以後十年間の謹慎を申し付ける。
秀忠が禁止令を出したキリシタンの行く末に忠輝がからむなど、話は大河ドラマのように発展しかかるのだが、主水正の命を賭けた諌言が功を奏しまもなく秀忠と和解、世に出ぬまま天寿を全うしたというのである。
なかなか波乱万丈の半生であったとわかる。しかし、どこかつまらないと感じるのは、後の半生を隠居して過ごしたことにある。この時代の謀反話につきものだが、権力が盤石のものになって、人心も世の乱れを望んでいないのだから、謀反の正当性がほとんど存在しないのである。由井正雪や天一坊も事件としての面白さはあるが、それで世間がひっくり返るような迫力はない。所詮忠輝もまた同じようなものだ。徳川体制初期には、脆弱な部分があったに違いないが、すでに官僚的組織で運営されつつあったのだから秀忠と言えども思うがままというわけにいかなかったに違いない。忠輝に詰め腹を切らせるなどしたら秀忠も悪党として一流であった。忠輝も悲劇の人として語り継がれたかもしれない。
まあ、こういう若殿様もいたんだな、ということがわかって、劇画を見終わったような気分になった。
それが宝塚ではないかと言われれば、確かにそうだが今回は原作の選び方を間違えたのではないか?と思う。徳川家康、伊達政宗、花井三九郎など年寄り役がさっそうと例の化粧で出てくるのも変だが、中年太りで白髪頭という宝ジェンヌもかなり違和感があったことは否めない。
さて、この日は豪華二本立てで、後半は「レヴュー誕生」と題して、パリのレヴューを再現するというもの。
ラインダンスというものをはじめて目にした。あれは難しいものに違いないが、いとも簡単にやっている。それもそうだが、昔のニュース映画で見たころに比べると格段にスタイルが良くなっていると思った。もちろん、背の高さや足の長さをそれなりに揃えようと思ったら宝塚だけでは間に合わないだろう。あれは日本人の平均よりちょっと上の方かと思う。ただし、ああいう集団で肉体を強調する趣向が果たして日本人の感覚に合っているのかどうか僕には疑問だ。
レヴューと言えば、大きな羽飾りと派手な被り物だが、これが次々に登場してシャンソンを歌う。僕はシャンソンは好きだから、十分に堪能した。
日本でパリがもっとももてはやされたのは、戦前の一時代である。ムーランヌージュのパリ、古きよき時代のパリを再現して、この劇団にとってももっともふさわしい舞台になったと思う。
劇場の外にでたら、お揃いの服を着た一団が整然と並んで、楽屋から退出するお目当ての女優を待っていた。こういう女の人たちが、宝塚90年の歴史を支えてきたのに違いない。僕が女だったら、この列に並んでいただろうか?
(9/26/2003)
