

|
題名: |
奴婢訓 |
|
観劇日: |
03/12/26 |
|
劇場: |
新国立劇場 |
|
主催: |
メジャーリーグ |
|
期間: |
2003年12月25日〜28日 |
|
作: |
寺山修司 |
|
翻訳: |
原作 ジョナサン・スイフト |
|
演出: |
J A・シーザー |
|
美術: |
小竹信節 |
|
照明: |
丸山邦彦 |
|
衣装: |
多田真由子 |
|
音楽: |
尾崎弘之 |
|
出演者: |
旺なつき
サルバドール・タリ 根本豊 井内俊一 小林桂太 小林拓 村田弘美 木下瑞恵 吉野俊則 大島睦子 高田惠篤 亜湖 中村亮 浅野泉 渡辺湖
マーク セバスチャン・ジョーンズ 山本由美子 金川和彦 飛永聖 内形奈尾子 森陽子 高橋優太 |
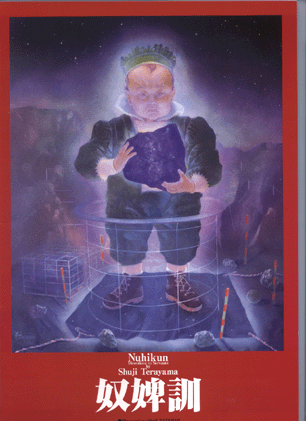
「奴婢訓」昔、唐十郎が麻布の「天井桟敷」に殴り込みを掛けたことがあった。何が原因だったか忘れてしまったが、いずれにしろ互いに相いれる間ではなかった。反=新劇という気運の中で「状況劇場」も小劇場運動の前衛にいた。しかし明らかに両者には肌合いの違いがあった。
唐十郎は東京の下町に育った。芝居を志して明治大学文学部に提出した卒論のテーマはジャン・ポール・サルトルで、もともと論理的、理知的な指向がある。一方、寺山修司は津軽に生まれた。高校時代、短歌雑誌に投稿して注目され、その詩人としての才能は若くして既に有名であった。歯切れのいい東京言葉と、津軽訛りのとつ弁は好対称で、からかいの的にはなったが、二人の話がかみ合うことは想像できなかった。だから、いつかはやるだろうと僕らは面白がってみていた。見ていただけで、寺山修司がもっとも景気よくやっていた時代の「ハプニング」や観客参加型演劇に付き合う気はなかった。木戸銭を払って、脱日常性の経験やら役者の挑発を受けて芝居に「参加」するほど暇ではなかった。
寺山は、芝居だけでなく映画も作り、同時にたくさんの本を出した。それらの膨大な(といっていいと思うが)情報を眺めながら、何となく寺山修司のイメージを作っていたが、気がついてみれば、その舞台を見た記憶はすっかり失せている。この「奴婢訓」は見ていなかったが、いわゆるデジャヴという気がしたのは、どこか記憶の底に寺山修司が残っていたからかもしれない。
彼は言葉の輝きということを心得ていて、単なるアフォリズムではなく、それに鮮やかなイメージを付け加えた。例えば他の劇中にも使われたフレーズだが「テーブルの上の一枚の地図・・・地図に消えているタスマニア、ヨハネスブルグ・・・ペキン、ザンビア、モザンビーク」と並べただけで、時代が抱えている不安というようなものに加えて見知らぬ場所の光景を指し示すことが出来た。そのきらびやかな言葉は、寺山修司の情念ともいうべきものから放たれている。それは不思議なことに普遍的な表象となって輝き、僕らはこの詩人の感性に驚き共感を覚えたものだった。
寺山の情念と書いて、これほど彼にふさわしい言葉はないと思った。研究者でもない僕にそれを言う資格はないかも知れないが、彼の感性の底にはやはり津軽という風土があると僕は確信している。風雪に閉ざされた長い冬が終わる5月になると、突然二千本のソメイヨシノが満開の花をつけて近郷近在百五十万の人々を呼び寄せる。夜店が開き、サーカスのジンタが響く。オートバイの曲乗り、見せ物小屋の看板の地獄絵、「親の因果が子に報い・・・」というだみ声。そしてなによりも呼び子が時折見せる幕の向こうの底知れぬ闇。人さらいや犯罪のうわさ。子どもにとってこのような経験はいつまでも心に残る情景である。
奴婢訓を見ていて、二人の女が一枚の板を背中に乗せ、その四本の足をテーブルの支柱に見立てるやり方や金属製の狭い空間に潜って四つんばいになった男が自分の裸の尻を叩く道具、また、テーブルを挟んで一方が倒立した椅子に腰掛け(実際には逆さまの椅子に身体をくくり付けている)、それが回転して交互に入れ替わる装置(考案:小竹信節)などに、人間の肉体を「もの」と見立てて扱う感覚は、いかにも西欧的で、それが寺山のどこから出てくるのか不思議だった。
僕はこれらを観ながら、衣装や白塗りに近いメークのせいもあったが、ボッシュやブリューゲルの大衆を描いた絵の肉感的な人間やヨーロッパの小説本の挿画として細密な線で描かれた人間を思いだしていた。
この芝居の冒頭には宮沢賢治の創作したセロ弾きのゴーシュや、ジョバンニ、カンパネルラなどが登場し、エスペラントに象徴される無国籍な寓話性をモチーフにするのかと思ったが、途中から上のような「金属と肉体の対極」から発散する背徳の気配によって賢治のイメージを圧倒する。後でわかったことだが、寺山修司は前にこの戯曲の元になった「物語・奴婢訓」を書いていて、その高級ポルノ的作品はジャン・ジュネの「女中ごっこ」から想を得ていた。ジャン・ジュネは、獄につながれながら自らの倒錯した性を語り、マルキ・ド・サドばりの悪徳の物語を紡ぎだした。最も実存(主義)的な小説家・詩人と讚えて、サルトルは大冊の評論を捧げている。僕は「女中ごっこ」をしらないが、この「ごっこ」という構造とスイフトの「奴婢訓」を結びつけた寺山の感性はさすがだと思う。つまり、スイフトの訓戒に「主人不在」という仮説をあてはめ、代わる代わる主人を選んで、これを遊び「ごっこ」にしてしまうものである。芝居では「シンデレラ」のように、靴にぴったり合う足の持ち主が主人ということになっているが、この靴が運び込まれるたびに大きくなって、仕舞いには人がすっぽり入ってしまうほどになってしまう。結局主人は誰でもあり、誰でもないということなのだが、無論こんなアナーキーなことをスイフトが考えるはずはない。18世紀のスイフトは、他にも馬人の国で飼われる家畜人ヤフーなどという痛烈な風刺小説を書いて(「ガリバー旅行記」)、人間と社会を辛辣に批判した。奴婢と主人が存在する社会構造を憎んでいたからだろう。彼は、その欲求不満の心の中に、いつかはやってくる民衆こそが社会の主人になる「時代」を思い描いていたかもしれない。しかしながら、20世紀の寺山修司がこの芝居で見せたのは、やってきた「時代」を皮肉たっぷりに揶揄することであった。
「奴婢訓」の文庫本を渡されて「とりあえず、この中から興味のあるところを即興で創ってみろ。」と根本豊はいわれたそうだ。芝居は、ワークショップの中で次第にでき上がったものである。78年、晴海の見本市会場で、はじめて公開ワークショップが行われた。その後ヨーロッパで絶賛され、海外公演を重ねている。上演のたびに修正が加えられたようだが、今回初めて見て、さすがに完成度が高く感覚も古くなっていないのに感心した。つまりは、時間をかけて知恵を出し合って磨きをかけるというやり方が、結局いいものを作り出せるということなのだろう。昨年見た松本修の「AMERIKA」も一年を掛けたワークショップの結果であった。そんなふうに金と時間をかけるのはたいへんだが、いったん作り上げたものは、この芝居がいい例だが、30年はもつのである。
ところで海外での評判が上々だったことは、日本の演劇という物珍しさもあっただろうが、喜劇の要素と分かりやすさという点で納得できる。原作がアイルランド、いやイギリス人(スイフトは英国籍のはずだが、アイルランドに住んで、アイルランド人の気質を濃厚にもっていた)であったこともハードルを低くした理由かもしれない。そして、美術・衣装・機械を担当した小竹信節の創造したイメージが、異国趣味を感じさせながら、そのコンセプトが西欧に根を持つということを理解させ得たからでもあろう。この美術については、小竹が何枚も寺山にスケッチを見せ、寺山はそれに触発されていくつかのシーンを考え出すという具合に、いつも嬉しそうに打ち合わせをしていたそうだ。僕がボッシュやブリューゲルを思ったのはおそらく小竹のセンスに対してだったかもしれないが、小竹はむしろ寺山の感性にあっていたのである。
このように寺山修司の嗜好は西欧で受ける要素を多分にもっている。さきに、人間の肉体をものとして扱うことに西欧的なものを感じると書いたが、それは聖書を根拠にした僕の感覚である。詳しくいうほどのことはないが、「処女懐胎」という異様な教義は人間が自然の生き物、つまりは肉体をもっているという事実を忌避しようという指向を含んでいる。マルキ・ド・サドもジャン・ジュネもそれは嘘だといった。そう言って迫害されたのである。金属と裸体のイメージは人間の肉体の部分を際立たせ、実存的に言うならば即自的側面を強調する。そういう意味で、反=聖書的な気分が横溢していた西欧の芸術的前衛と寺山修司は響きあったのである。彼もまた、それを知っていて、むしろそうすることの快感に身をゆだねたのであった。
唐十郎もまた海外公演を行った。しかし、「天井桟敷」ほど成功したといううわさは耳にしない。上のようなコンテクストで言うならば、唐十郎の生まれ育った東京の下町には、例えば「下谷萬年町」と言った途端に江戸の町並みが湧いてくる時の集積というものがある。そこに根拠を置く最も彼らしい部分である「粋」とか都会性とか、その感覚を伝えるのは至難のことであっただろう。
では寺山の情念の中に反=聖書的といえる契機があっただろうか?
津軽には、明治期からミッション系の女学校が二つもあった。カソリックの教会は旧制高等学校の時代から貧しい学生を寮に収容した。狭い地域に文明開化の象徴がいくつも早くから存在したのである。津軽という風景には、キリスト教的教養が薄墨のように塗られていて、時によって、描かれたものに淡い陰影をつくることがある。
この公演によって僕は寺山修司の天才を確認した。では、何度も見たいと思うかといえば、もう一つのりきれないものがある。その西欧的感覚のゆえに。
旺なつきが意外によかった。と付け加えておく。
(2004/1/18)