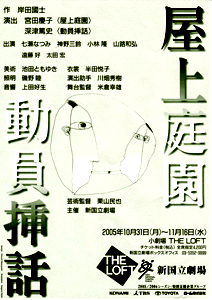
|
題名: |
屋上庭園/動員挿話 |
|
観劇日: |
05/11/4 |
|
劇場: |
新国立劇場 |
|
主催: |
新国立劇場 |
|
期間: |
2005年10月30日〜11月16日 |
|
作: |
岸田國士 |
|
演出: |
宮田慶子〈屋上庭園〉 |
|
美術: |
池田ともゆき |
|
照明: |
磯野 睦 |
|
衣装: |
半田悦子 |
|
音楽・音響: |
上田好生 |
|
出演者: |
七瀬なつみ 神野三鈴 小林 隆 山路和弘 遠藤 好 太田 宏 |
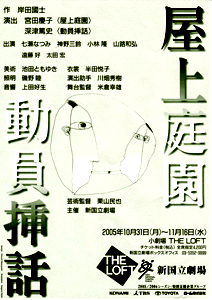
「屋上庭園」「動員挿話」
岸田国士の短い作品を二つ選んで、一つの公演にしたものだ。なぜこの二つなのかはわからない。岸田国士がどんな作家だったか理解できると思ったのか?とすれば、この「習作(エチュード)」のようなものと「挿話(エピソード)」ではいささか不満ではある。
「屋上庭園」はちょうど演劇学校の稽古用の台本として適当ではないか。せいぜい四十分という長さ、それに、登場人物が4人で状況はシンプル、俳優が内面を素直に表現することが出来れば観客にはストレートに通じる。分かりやすい。が、人間模様のスケッチみたいなもので、作家の思想や心情が十分に書き込まれた物語ではない。
これを宮田慶子が演劇学校の先生に見せるように丁寧に心配りしながら磨きあげた。書かれたせりふの内容をどのように解釈し、声と身体でどのように表現するか、まるで教科書でも見ているような正確さであった。それは、それで十分評価に値する。ただ、ぜいたくなことを言えば、轆轤で引いた茶碗を、あれは何というのか、両手でわざとゆがませて味をつけるような、ほんのわずかな「破綻」、たとえば人間の底に潜む小さな悪意などのことだが、宮田にはそのような演出家としての老練なしかけを見せてもらいたかった。
発表は大正十五年、初演は意外なことに新国劇、昭和二年である。貧乏な文士志望の男、並木(山路和弘)を当時は総帥沢正がやった。劇評に「沢田の失敗者(並木のこと)は、恐ろしくテンポの速いせりふと、目まぐるしい動きが、何だか陽気な人間に見せてしまって・・・」とあるから、何事も大仰なあの新国劇の調子でやったのだろう。
それがあるからか、山路和弘の並木は、十分な間とためをつくって、成功者にたいする僻み、ねたみやら俗物への優越感やら激しく揺れる心のうちを表現して真に迫った。
新国劇でやるくらいだから、あまり難しい理屈はない。あえて言えば、当時「屋上庭園」(銀座松屋)という百貨店の集客戦略は高層(といっても今では問題にならないが)の建物の上に土をいれるという点で新奇性があった。それだけで金は取れない。都会のオアシスとか言ってぜいたくな気分にさせるものだが、なに、シャワー効果を狙ってのことだ。一端客を屋上に導いて、おりながら買い物をさせる魂胆である。時代をリードする百貨店のイメージを背景にそれに取り残されていく一向に売れない文士(芸術家)の悲哀を対称的に描いたといってもよい。
並木が妻君(神野三鈴)をともなってこの屋上にくると友人の三輪(小林隆)と何年かぶりでばったり出会う。三輪も妻(七瀬なつみ)を伴っている。並木は「半襟でも買ってやろうかと思って」寄って見たと言うが、そんな余裕があるように見えない。着ている服はよれよれで帽子は破れ靴も磨いた形跡がない。妻君の身につけている着物もあか染みていて着古しのようだ。卑屈で暗い表情をしている。三輪はリュウとした身なりに蝶ネクタイ、つば広の帽子、足下はぴかぴかの革靴である。妻君は手書きの友禅見たいな着物をまとい、金持ちの妻女に身についた屈託のなさと明るさを振りまいている。
互いに一目で相手のいまの境遇を見てとった。屋上庭園とは面白いものを作ったとかこの屋上から飛び降り自殺したものがいた、などと世間話をしている。そのうち妻君同士は女のものを買うのに男が付き合うのは退屈だろうからといって、二人で階下の売り場へ行ってしまう。残された並木と三輪は、近況について話し始めるがどことなくぎこちない。
三輪はもともと事業家の子息で、いまは親の資本で会社を興し立派にやっているらしい。並木は小説家になりたくて、職も持たずにもっぱら書いている。しかし、売れない。あまり売れないからそろそろ何か働かなくてはと内心思い始めているが、決心がつかない。自分の才能に自信はあったが、近ごろではそれも揺らいでいるように見える。
とりとめない話をしているうちに、三輪が同情していくらか都合をつけてやってもいいということを相手が傷つかないような言葉を選んで慎重に切り出す。並木は即座に断る。久しぶりに会った友人に金を無心するなど自分には出来ない。その話はやめにしようと、また、世間話に戻るが、内心ではその金があったら・・・とさまざまな想念が浮かんでは消えていったであろう。どこか上の空である。突然、並木は三輪に「君、その、都合が良かったら二十円ばかり・・・」と思い切ったように言い出した。三輪はいやな顔一つ見せないで札入れをとり出し、数え始めた。
この当時の二十円は、盛りそば10銭、公務員の初任給75円という指標(パンフレットの資料による)に照らすとおよそ7、8万円ということになる。三輪は「それくらいなら有るとも・・・」といって札束から二十枚を数えて渡す。すると途端に並木は落ち着きがなくなり、後悔し始めたようだ。三輪はなにもそう気に病まなくてもいいと押し問答をしているうちに妻君たちが帰ってくる気配である。並木は「構わん」といっている三輪の手を押しのけて、丸め込んだ札束を三輪のポケットに投げ入れてしまう。
妻たちが戻ったので、それ以上のやり取りが出来ず、結局は気まずく挨拶を交わして三輪と妻君は売り場へ立ち去ることになる。
並木の妻は、三輪の妻君が高いものばかり選ぶので困惑したという話をするが、それにいらだって並木が不機嫌に当たり散らすので、自分たちが買い物している間に何かあったのだと悟った。三輪とケンカでもしたのかと心配になった妻君がただすと何もありはしないといって話題を変える並木。
最後に、妻君が「あなたがどんどん友達を失っていくのが心配で・・・」といって並木にすがり、すすり泣くところで、溶暗、幕。
神野三鈴を最初に見たのはユ01年の「おばかさんの夕食会」(世田谷パブシックシアター)であった。いかにも女優らしい女優だというのが第一印象だった。あれから5年、この最後の場面の演技を見て、よくもこの高みに到達したものと感心した。こまつ座をはじめ、あちこちに客演しているのを見ていたが、何よりも伎倆、表現力が格段に進歩した。どこか演劇の学校あるいは俳優養成所で指導を受けたとは聞いていないから独学だろう。そしてこの間に良い演出家に鍛えられたのだ。残された課題は「ニュートラル」をどう演技しないか、という技である。まだ成長するだろう。楽しみだ。
さて、次の「動員挿話」だが、これもまた一時間ちょっとの小品である。昭和二年、帝劇の初演である。
演出の深津篤史はこれを反戦劇に仕立てようとした。昭和二年にこの芝居を反戦劇と解釈して上演したらどうなっていただろう。大正デモクラシーの余韻は残っていただろうが、満州事変まであと4,5年のきな臭い時代である。知れたものではない。
舞台奥に大きな黒板のような壁を上手から下手にかけてつるしおいた装置である。下手に馬がいる。明かりが入ると一人の男が壁に向かっている。チョークで旗を書いているのだ。日の丸を丁寧に書いては次の旗にとりかかる。これは従卒の太田(太田宏)でこの家の主、宇治少佐(山路和弘)の部下である。壁のほぼ全体に日の丸を書いて太田は立ち去る。この日の丸は、やがて少佐夫人鈴子(神野三鈴)によって一つ一つ消されていく。こういう場面が初演当時あったはずがない、と僕は思う。深津の工夫に違いない。
宇治少佐が、戦地に赴任するに当たって、愛馬と、その世話をしている馬丁の友吉(小林隆)も当然同行するものと決まっている。いや決まっていた。
友吉の妻数代(七瀬なつみ)が夫の戦地行きに断固反対なのだ。数代の言い分はおおよそこうである。
自分は二回目の結婚で友吉といういい伴侶を得ることができた。友吉とは絶対に別れないと心に決めている。戦地に行って自分と離れたら死ぬかも知れない。将校の立場で戦場に行くならいいが、馬丁は戦の方法も知らず戦地で死ぬ確率は高い。召集ではなく自分の意思で行くか行かぬか決められるのなら友吉には行って欲しくない。どうか他のものをやってください。友吉と私は一心同体を誓ったものだから、ここで旦那様のお帰りをお待ちします。それがかなわないなら、私と友吉にはお暇を取らせていただきたい。
この頑張りと理屈は、数代が女学校をでているインテリだからだと誰もが思っている。
友吉は確かに数代と約束を交わしたが、その日がこんなに早く来るとは思っていなかった。数代は友吉を説得し、友吉も一旦はその気になって主人に申し出る。しかし、世の常識に照らして、女房が言うから戦地には行けないという道理が通用するものではない。少佐をはじめ夫人鈴子も数代の説得にかかる。数代は鈴子にしても夫を戦地に行かせたくはないはずだ、何故女だけが夫と別れてその帰りを待つという境遇に甘んじなければならないのかと逆に鈴子を説得にかかる。鈴子がものも言わずに日の丸を消し始めるなど、おとなしく聞いているところをみると案外同意したところがあったかも知れない。という演出に見えた。
しかし、友吉は馬丁仲間の手前もあって迷いに迷う。外にあっては世の慣い、内にあっては女房の理屈、数代はあなたが行けば私は死ぬしかないと最後通告をするので友吉はほとほと困窮する。
出発の日、ついに友吉は行くことを決心して荷物をまとめ身支度を整えているが、数代はまだ説得を試みている。多いにもめるが、友吉の決心の方が勝ったと思った途端、数代はどこかへいなくなってしまう。腹にさらしを巻いて股引を履こうとしたところへ女中のよし(遠藤好)が慌てた様子でやって来る。たった今、数代が井戸に飛び込んだ!というのである。
この数代の言い分は、愛情で結ばれたものを無理やり引き離して戦場に、つまり死ぬかも知れないところへ送り込むことがどれだけ理不尽なものかということであり、その限りでは理屈に合っている。いまなら理解できるという人は多いかも知れない。
ところが当時の見方は「この、ばか女!」である。
新国立劇場が編集したパンフレットの中に昭和二年十月の「演藝画報」に載った劇評が収録されてある(仲木貞一)。その一部を紹介すると、
「・・・嘉久子(村田嘉久子=数代役)の異變(アブノーマル)な一女性を示した芝居・・・少しばかり学校に行って、新しい思想にかぶれかけて、そして私欲一点張りの、強情きわまりなき性格破綻者としての馬丁の女房・・・いわば性格悲劇の芝居だ。・・・間違った随分自分勝手な考えをぐんぐん押し通していく強さ・・・この馬車馬見たような女が井戸に入って死んだと聞いても、見物は少しも同情を持たぬように出来ているところが可いのだろう。(少佐夫人の)社会も国家も道徳も考えない馬丁の女房の、自由な情意生活をうらやむ当たりが殊に可い。この点を強調すれば尚良かった。・・・この馬丁の妻君の性格を斯くなら占めた原因を社会悪に持っていって、その点を強調したなら、この女性は、観客の同情を十分に引いて、もっと効果を上げただろうと、いらぬことまで考えさせられた。」
今から八十年前の批評は、数代のわがままは性格破綻、つまり精神病みたいなものだ、だから井戸に飛び込んで死んだとしても誰も同情しないというものだった。確かにあの執拗さは少し異様に思えるが、自分が正しいと確信している時は、傍から何を言われても納得しないということはよくある。その確信が堅固な論理によってでき上がっていたらなおさらである。彼女はだれも自分を説得出来ないのに望んだ結果が得られなかったから抗議のために死んだのだ、と言えなくもない。友吉を会社の論理と妻の言い分の狭間に立って、往生している現代の夫の姿に重ねれば、思い当たるふしはあるだろう。
ところが、この時代の批評家は、「馬丁の妻君の性格を斯くなら占めた原因を社会悪に持っていっ」たら「もっと効果を上げた」と考えている。社会悪とは「少しばかり学校に行って、新しい思想にかぶれ」たことをいっているのである。つまり女子の高等教育は革新思想という社会悪を育てる可能性があり、馬丁の女房はその犠牲者だという論理になるのだろう。これが当時のジャーナリズムの見方だった。作者がこの女房のほうが正しいと考えているなど思いも及ばないのは当然である。「女のくせに」と憎々しげに切り捨てている。岸田国士があれだけ堅固な論理を数代に言わせられたのは、少なくともそういうことを考えていたからだ。しかし、幸いなことに世間はそうは受け取らなかった。岸田国士は国家についても、社会や教育についても具体的には何も言及していない。世間が女は精神病だから仕方がないと片づけたのは、これが「挿話」エピソードにすぎないからである。
批評家の評価が正しいとすれば、岸田国士は「私欲一点張りの、強情きわまりなき性格破綻者」を描くことで、その原因となった「女の教育は考えものだ」という思想の持ち主ということになる。
いまの時点に立てば、作家の想念にはもっと複雑なものがあったと理解出来るが、当時はそう思われても仕方がない何かが岸田国士の中にあったのだろう。
岸田国士は軍人の家に生まれ自身も士官学校の出である。一度は任官したが、文学を志、帝大からパリへ留学して演劇を学んだ。一風変わった経歴である。戦争が激しくなって大政翼賛会の演劇部長を務めた。プロレタリア演劇とは一線を画した人生である。
岸田がどんな思いを演劇に託したのか、この二つの芝居では判断の仕様がない。というのが最初に書いた「不満」の中身である。
七瀬なつみの数代は、一途な頑なさに説得力があった。ただ、深津篤史の演出は極力動きを抑え、それを強調するものだったが、表情がよく見えなかったのは残念だった。
最後に一言いわざるを得ない。友吉の立場に対して、万感の同情を寄せるものである。
(2005年11月27日)
