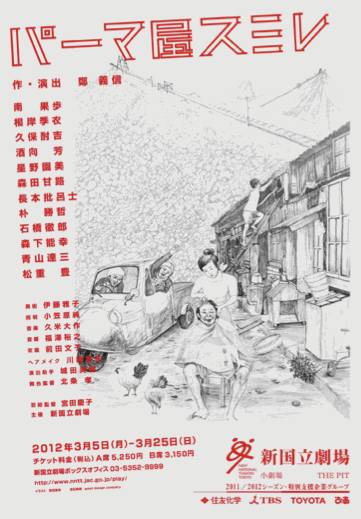
「パーマ屋スミレ」
前作「焼き肉ドラゴン」(08年4月初演、11年2月再演)は、万博(1970年)にわく大阪の空港近くのコリアンタウンが舞台であった。
この芝居のための取材のとき、鄭義信は、筑豊の炭鉱から移住してきた在日がその集落に少なからずいることに気づいたという。彼らが空港の拡張工事をあてにしてやってきたのは、1960年前後にはじまる日本のエネルギー革命がかかわっていた。
第二次大戦後、中東やアフリカ北部で次々に大油田が開発され、エネルギーの主役は世界中で石炭から石油へ大きくしかも急激に転換された。我が国の炭鉱も次々に閉鎖され、そこで働いていたものたちが離職する。中でも戦前から既に数万人はいたと推定される在日であったが、その内の何人かが新たな仕事を求めてあの同胞の住む町を目指したのであった。
「焼き肉ドラゴン」の二女の結婚相手の男を炭鉱出身としたのは、そういう事情に通じていたからであろう。
鄭義信は、このとき、九州の炭鉱町のいくつかには「アリラン峠」と呼ばれる、決まって集落の高台を占める場所があって、そこは在日コリアンが暮らす町であった、ということを聞いた。
伊丹は軍用空港として、その拡張整備に朝鮮半島からの出稼ぎ労働者を集めたところだが、むしろ山口、筑豊の炭鉱は事業規模の大きさに加えて距離的に近いこともあって、その数は圧倒的に多い。
労働環境の苛烈さや徴用、「強制連行」などの問題、事業閉鎖にともなう労働運動の激しさからいって、在日の問題を浮き彫りにしようとするならこの題材をこそ取り上げるべきだとこのとき思ったのだろう。
この芝居は、大阪万博の年を遡ること五年、東京オリンピックの翌年であるの1965年、閉鎖が間近いある炭鉱町の有明海を見下ろす「アリラン峠」に暮らす在日一家の話である。
開幕十五分ほど前に席に着いたが、すでに木下(李)茂一(朴勝哲)と若松沢清(長本批呂士)が楽器を手に、当時の流行歌を賑やかに歌いながら演奏しているのは「焼き肉ドラゴン」の客入れと同じ趣向である。
遠くから祭り囃子が聞こえている。
舞台正面にバラックのような店舗兼住宅。下手側に開いた出入り口の軒下に赤白青の螺旋に回転する例の床屋のサイン灯が見える。下手手前には手押しの井戸ポンプに金盥、下手奥に通じる通路には物置やら便所やら木造の建て屋が雑然と連なっている。 正面奥に、古ぼけたタオルの蒸し器、粗末な道具入れの棚、狭い待合の長いすなどがならび、広いとも言えないたたきの店にぽつねんと床屋の椅子が一つ置かれている。上手は畳を敷いた小あがりになっていて、その横のベンチではラジオの大音響にもかかわらず禿頭の老人がうたた寝をしている。
この設えは、待てよ、とすぐに気づいた。
床屋の店構えといい、水道や通路の様子といい「焼き肉ドラゴン」の装置とほとんど同じ配置なのだ。焼き肉屋の小あがりは、畳敷きの座敷になっていて、長椅子でうたた寝している禿頭の老人の禿具合も「焼き肉・・・」のオボジとそっくりである。
島次郎も手抜きをしたものだとこのときは思ったが、あとで美術は伊藤雅子だと気づいた。つまり、これは演出家の指示で意図的に似せてつくったものだったのだ。
やれやれ、これは一体どういうつもりだ。大阪も筑豊もコリアンタウンは一般にこういうモノだと示したいのか、それとも他に深遠なる含意でもあるのかとにわかに興味がわいた。
スーツにレインコート姿の中年男(酒匂芳)が現れて、老人に近づくと耳元のラジオのボリュームを下げる仕草で劇が始まる。
この男は、高山大吉といって、寝ている老人、高山洪吉(青山達三)の孫である。とはいえ、この孫は1965年の劇中の時点ではまだ高校生である。つまり、劇は、中年になった現在の高山大吉の回想と言うことになる。大吉は、自分の青春時代のことを語って聞かそうとしているのだ。
65年に高校生なら大吉は団塊の世代で、中年というよりもすでに老年のはずだが、少々若作りなのは気になった。
この中年男=大吉が劇中にとどまって、次々に舞台に登場する人々を紹介し、時代背景などを説明しながら進行する。
舞台下手奥からがたがた音がすると、なんと懐かしい三輪軽トラックが現れて、中から派手なシャツにつなぎの七分ズボンという奇妙な出で立ちの年若い男がでてくる。その小太りの少年がその時分高校生だった本人だと中年の大吉が紹介する。
余談だが、軽三輪などよく探し当てたものだと感心した。これはようやく貧しさから抜け出そうとしていた日本社会を象徴的に表現する大道具として作家兼演出家が新国立劇場にわがままを言ったものだろう。排気量360cc=牛乳瓶二本分の軽自動車は坂道でよくエンコしたものである。大衆が3C、すなわちカー、クーラー、カラーTVを手にする時代はすでに足下までやって来ていた。
軽三輪を運転していた男は、張本英勲(石橋徹郎)。炭坑の落盤事故で片足の関節が伸びたままになった。
少年が女っぽい仕草をするのは、当時ファッションデザイナーを目指していたというからなのだという。都会にあこがれて家出し、博多でこの張本英勲に見つかり連れ戻されたこともあった。
祭りに出かけようとしていた大吉は浴衣に着替えようと須美おばさんの店を訪ねたのである。須美(南果步)おばさんとは、高山洪吉の二女で、洪吉が引退したあと床屋の店を継いでいる。須美はいつかこの街を離れて、どこかでパーマ屋をやりたいと考えていた。店の名前は「パーマ屋スミレ」と決めている。
店先へ、須美の妹、三女の春美(星野園美)とその夫で炭鉱夫の大杉昌平(森下能幸)が現れる。春美は太った巨体を浴衣で包んでいる。昌平が細く小柄で対称的なとりあわせなのは、こういうコミカルな組み合わせを多用する鄭義信の好みだ。これから仕事にむかおうとする昌平と春美は一時も別れがたい様子である。大仰な愁嘆場が続くうち、自転車に二人乗りした男女が到着。
乗せていたのは、張本成勲(松重 豊)。
須美の夫で、大吉を軽三輪に乗せてきた英勲の兄である。長年炭鉱で働いてきたが、この日は非番である。
荷台に腰掛けてきたのは、 洪吉の長女、初美(根岸季衣)で大吉の母親。
連れ合いと喧嘩して、実家に駆け込むできたのだ。連れ合いというのは、炭鉱の組合で専従を勤める支部長、大村茂之(久保酎吉)だが、大吉の父親ではない。実父は炭鉱の事故でなくなっているらしい。大村は、初美がやっているスナックの客の一人であった。
須美と夫の成勲の仲はぎくしゃくしていた。成勲が「先山」(切りはのリーダー格)から外されてからまともに働かなくなったからだ。それに、職場を失わないために日本国籍を取ったことで家族から孤立していた。オボジは成勲に対して「国を失ったものは犬にも劣る」とにべもない。
戦後二十年の間にそれぞれの事情で国籍は選択を迫られた。大吉と母親は韓国籍を選び、三女春美は昌平と結婚して日本籍になり、オボジ、須美それに成勲の弟の英勲は朝鮮籍のままと家族の中に三十八度線があると言う複雑な構成になっていたのだ。
そこへ、家出をした初美を追いかけて、楽器を演奏する木下と若松をしたがえて、大村が「聞け、万国の労働者・・・」と歌いながらやってくる。エネルギー革命と対峙する炭鉱の労働運動はイデオロギーと絡んで激しさを増していることを思わせる。資本側が第二組合を作って切り崩しにかかっているところを大村たちがかろうじて踏ん張っているという図式であった。
初美の不満は、大村が運動にのめり込んで毎晩遅いと言うことにあるようだが、何とも他愛ない夫婦げんかである。
その騒ぎの中、遠くからサイレンが聞こえ、大吉が走って戻ってくる。麓の坑口のあたりから黒煙がでている、というのだ。
駆け出そうとする英勲を須美が制止し、昌平を心配する春美にかわって「わしが行く」といって成勲が自転車にのり、大村たちが後を追う。
サイレンが不気味に鳴り響く中、中年の大吉が状況を説明する。
有明海の底深く張り巡らされた坑道のどこかで炭塵爆発が起こったのだ。
切りは(採掘の先端)では絶えず石炭の粉塵がたちのぼる。散水してそれをおさえ、引火しないように火の気にも細心の注意を払うことになっているが、増産の要請に加えて労使対立と組合の分裂などによって安全性に対する注意が散漫になっていたのだろう。トロッコの車体やなにか金属どうしがぶつかった火花で埃のように舞っていた微粒子が爆発的に炎上、火は瞬く間に坑道を駆けめぐった。直接爆発で亡くなったものは数人だったが、坑道に充満した一酸化炭素中毒によって大勢の死傷者を出した。
実際、劇中の事故の二年前、1963年11月に三井三池炭鉱で同種の事故があり、死者458名、負傷者839名という途方もない規模の犠牲者を出している。このときの中毒患者は今なお後遺症に苦しんでいるという。
春美の夫、昌平は爆発のあと、救援のために坑道に入って惨状に驚いた。うめき声を上げる同僚を運びだそうと必死に動き回る。しかし、一酸化炭素による中毒がどれくらい恐ろしいか、この当時はまだよく知られていない。
昌平の後遺症は強く出た。頭が締め付けられるような痛さに手足のしびれ、時折おとずれる意識障害、苦しさから逃れるための暴力などによって、春美は片時も昌平の側から離れられなくなってしまう。CO患者としての手当は出たが、第一組合は差別された。
葬式が済んで、大村たち組合は補償問題に取り組んでいた。炭鉱の未来はないと思った弟の英勲は、北朝鮮に行ってやり直そうと考えている。しかし、それを聞いた一同はそこがすでに「楽園」などではないことを知っていた。兄の英勲は、北に行っても足の悪いお前の居場所はないと、弟の弱気を辛辣に批判する。かく言う成勲の身体にも異変が起きていた。
頭痛と倦怠感に、手足のしびれ、舌がもつれて呂律が回らない。
あの日、昌平に遅れて構内に飛び込んのだが、すぐに兆候は出なかった。しかし、次第に症状は重くなり、やがて身体の自由が奪われた。
成勲は、あの日非番であったためにガス患者のふりをしていると陰口をきかれていた。秋になって、CO患者の労災認定が打ち切られる。
二年後(1967年)の夏、大村支部長たち第一組合の労災認定闘争は続いている。昌平の症状はますます悪くなっていて、一人で放っておく訳にいかない。わずかな補償金では病院通いがやっとで、働きに出られない春美が窮地に陥っている。援助を惜しまない須美。
成勲の須美に対する乱暴な態度に、英勲は義憤を感じている。いや、実は惚れていたのだ。愛情のない夫婦生活よりも、自分と北に行って幸せになろうと、しきりに誘う。
そうしたなか、CO法が成立し、軽症患者の治療補償は困難になった。
その年の秋、英勲は、いよいよ北行きを決心して出発しようとしている。成勲は、弟が須美を誘っていたことを知っていた。自分がこんな身体になった以上、ついて行きたければ行くがいいというが、須美に、もとよりそんな気はない。兄の須美に対する態度を責める英勲との間で口論がはじまり、やがてとっくみあいの喧嘩になる。
制止されて、床屋の椅子に腰掛ける成勲の手にカミソリが握られている。須美がそっと近づき、それを奪うと、英勲が身体を翻して北に去る。
一年後(1968年)の大晦日、アリラン峠にはいつものにぎやかな餅つき風景があった。CO法の補償からはずれたものが集団訴訟を起こしていて、大村も須美もその応援と世話で忙しくしている。その後幸い成勲は、不自由な身体で鉄道の踏切番の仕事についている。
つきたての餅を口にしているところへ放心したように足を引きづりながら春美が現れ、これから警察に行くという。「そうするより他に仕方がなかった」と泣き崩れる。狂ったように懇願する昌平の首を絞めたのだ。
明くる年(1969年)の春、閉山が決まったアリラン峠から木下と若松が去り、今大村と初美、大吉、それに洪吉の一家がこの住み慣れた土地を去ろうとしている。大村が大阪の空港拡張工事に新たな仕事を得たのであった。初美はそこのコリアンタウンで店をやろうとしていた。
春美の裁判も終わり、懲役十年の刑が決まった。須美と成勲は、この地に残る。
リヤカーに荷物を積み終わると、桜がちらほら舞う中を名残惜しそうにあたりに目をやりながら一家が去っていく。
中年の大吉が現れて、その後の家族の物語を語る。
大阪に移ったその年に、大村があっけなく亡くなってしまった。翌年、ハルベも逝き、すっかり気落ちした母、初美のために大吉はファッションデザイナーの道をあきらめて、韓国系の銀行に勤めることにした。(サラリーマン風のスーツ姿の理由がここで判明する)その母も就職したとたん、安心したのか急に弱って足早に逝ってしまった。しかし、自分は日々の忙しさに追われ、昔を思い出す暇もなかった。時代は高度成長からバブル経済へ、そしてあの狂乱が終わって長い低迷期に入ったいま、深い喪失感とともにあの町のことを思い出す。北に帰った英勲からは便りもなく、刑務所を出た春美は行方不明。成勲はあれから様々な合併症と戦いながら十年ほど生きたが、いまはただ一人須美おばさんだけが存命である。あのアリラン峠で時折、近所の老人相手にはさみを持つこともあると聞く。
大吉一家が去ったあと、舞台に残された二人。成勲を床屋の椅子に移して、須美が髭をあたってあげようとしているところへはらはらと桜が舞っている。
目を閉じている成勲、おとがいに手を当てている須美の上に、いよいよたくさんの桜の花びらが降りしきり、降りしきり、やがて溶暗。「焼き肉・・・」のラストシーンよりは短かったとはいえ、十分すぎるほどの花びらを散らして幕となる。
なんともはや、こう言うのをどう言えばいいのだろう。剽窃というはあたっていない。なぜなら自分の作品の盗作というのは形容矛盾だからだ。しかし、作者の名を伏せてあったらどうか。この作品と前作「焼き肉・・・」を比較したら、思わず「剽窃?」と、その類似点の多いことに驚いてしまうに違いない。
「焼き肉・・・」で物語の中心になっているのは、やはり三人の姉妹であった。長女は故あって片足の関節が動かない。これは弟英勲と同じ。二女の婚約者は、ひねくれたインテリの元炭鉱労働者で、乱暴者のところは成勲によく似た存在である。三女の結婚相手は、人のいい日本人で、これは春美と昌平に投影されている。
結局、一組は北朝鮮、一組は韓国、そして一組は日本に残るということであったが、この芝居では英勲が北へ、初美は他所へ、須美は残ると多少の違いはあっても似たような結末であった。
宮本研の「美しきものの伝説」と「ブルーストッキングの女たち」は、登場人物が重なっていて、一見同じ作者であることに驚くが。この場合は方や群像劇、一方はその中の一人の人物にフォーカスすると言うテーマの違いがあった。もっとも、「ブルー・・・」を書いた動機ははっきりしていて、これは、三田佳子主演という条件付きの急な注文に応じたものという事情があった。(知人会公演、劇評を参照)
むろん二つの劇の間に、この芝居のような物語上の共通点はいささかもない。
一体、どんな事情があって、これほど似通ったものを書くことになったのか、聞いてみたい気もするが、理由はどうあれ、何とも気の抜けた態度ではないかと思った。
「気の抜けた」というのは、こう書くのもいささか品がなくて躊躇するところだが、いってしまえば設定の大部分を「焼き肉・・・」から借りてきて、時と場所を変えただけという省エネをやってのけたという印象があるからだ。
もちろん、社会的テーマ性からいえば、エネルギー問題や炭鉱・労災問題などが背景にあるこの芝居の方が、国有地立ち退き問題よりは影響力がはるかに大きく深いと言える。
作者としては在日が深く関わった社会問題としてそこのところを強調したかったのだろう。
それでは、一家の運命を翻弄したエネルギー革命や労働問題に格別の批評的観点があったかと言えば、そうでもない。確かに会社と対立した支部長大村は、イデオロギー闘争を思わせる労働歌を歌い、後遺症に苦しむ第一組合所属の昌平は待遇において差別された。成勲も十分とは言えない補償の中、不自由な身体で生きざるを得なかった。劇の大半は、このあたりの労働争議について63年にはじまる三井三池炭鉱の事故と閉山を巡る数年のいきさつを参照したとみえて、 かなり詳細な描写をしている。実際の事故と二年のずれがあるのは何か理由があったかも知れない。
一昔前ならば、ここで、理不尽な差別に怒り、資本家の横暴を告発するというパターンになって大いにシンパシーをかき立てるところだが、さすがに今時それは「受けない」ことを作者も知っている。しかし「受けない」と言っても当時の闘争の様相は、(個別には待遇改善や賃金問題だったとしても)政党や労働団体の応援もあって印象としては資本家と労働者の階級対立と捉えられていたのは事実であった。社会全体がいわゆる「大きな物語」を共有していた時代である。実際、作業用のヘルメット、首にタオルを巻いた坑夫の煤けた顔の集団が暗い坑道にひしめいている写真を見て、「革命前夜」を想像したのは僕だけではなかったと思う。
ところが、大村が拳をあげても、昌平の後遺症とその悲劇的結末にもかかわらず、いっこうに感情移入することが出来ない。補償を巡る裁判闘争と言ってももはや結末を誰もが知っているからである。だらだらと長いだけの裁判に腸がむしられるような裁決、声高に叫んだ「労働者が主体の社会」は来なかったし、そんな四十数年も前のことはすでに忘却の彼方である。なのに当時のシュプレヒコールと同じように劇がいきり立ってみえるのではしらけるばかりだ。
そういうことは、作家としては百も承知だから、なんだか淡々と事故が起こり、動機にリアリティのない「類型的な」労働争議はお祭り騒ぎと見まごうばかりの賑やかさで進行していくのである。
「強制連行」にはじまる朝鮮人炭鉱労働者をとりあげて、ここは一つ「差別」の問題で多いに盛り上がろうとした形跡はないわけでもなかったが、いかんせん作者自身にそのように描く動機が見あたらないのである。
「焼き肉・・・」の劇評にも書いたような気がするが、鄭義信はこの1965年にはようやく八歳を迎える世代である。77年に成人だから高度成長のまっただ中を思春期が通過している。過去に同胞が受けた恥辱と恨みといっても、それを彼は実際に経験したことはない。伝聞で憤怒をかき立てるという精神状態は人間そう長く持続できるものでもない。
したがって、その底に体験のない「差別」には現実感が希薄なのだ。あの「月はどっちに出ている」(映画、脚本担当、1993年)の、差別用語が本音で飛び交うもはや笑うしかない激烈な脚本は年長の原作者(梁石日=昭和11年生)の経験であった。
唯一リアリティを感じるのは、豚を飼っている話である。
アリラン峠には決まって豚小屋があったという大吉の説明には、おそらくその光景とともにあの強烈な臭いが作家の記憶にあるからであろう。家畜は、残飯を集める手間を惜しまなければえさ代はただですむ。特に夏場の腐臭がひどかったからおおかたはいやがったのだが、コストパフォーマンスがよかった。それを在日はやっていたという記憶が、鄭義信の原体験にあるのだろう。
在日差別のテーマは、「焼き肉・・・」に比べれば、かなり希薄になっている。日本国籍を選んだ成勲とオボジの対立に故郷喪失という民族意識の問題がわずかにみられるが、日本人との間で生じる差別の問題は、まったく扱われない。
時と場所を変えたのはいいが、背景となった「出来事」に今どう向き合えばいいかとまどうばかりで、余計に、「焼き肉・・・」との類似が目立ってしまっているのである。
それもこれも、この芝居が回想劇であることによって決定づけられている。
初老になった大吉は舞台上にほぼ出ずっぱりで、彼らの行動を見守っている。芝居は、彼の記憶の中の出来事を披瀝しているという構造である。フォーカスされているのは、その実は炭鉱でも労働運動でもない。「家族」である。「焼き肉・・・」は回想ではないが、やはり主題は「家族」である。この家族構成がともに「在日二世の三姉妹」でほぼ同じとあれば、いよいよこれは何のために書いたのか訝しくなるのである。
大急ぎで結論めいたことを言えば、鄭義信は、ひょっとして、在日であることをこのような形つまり、「追憶」されるべきなつかしい過去としてそっと封じこめてしまおうとしたのかもしれない。
「焼き肉・・・」では、一家の中心である在日一世の夫婦が、自分たちを襲った不幸は運命だった、宿命だったかも知れないとつぶやいて幕が下りる。それには僕は少なからず驚きを禁じ得なかった。むろん不幸というものが、誰のせいだと恨んでみても所詮はむなしいことではあるが、あの時代、「差別」を運命として受容することなど同胞が許すはずのないことだった。
この芝居とほぼ同時代の1968年2月、静岡県寸又峡の旅館にライフルとダイナマイトで武装した殺人犯が逃げ込んで、客や経営者を人質に立てこもった事件があった。いわゆる金嬉老事件である。彼は在日二世であった。人質解放の条件として殺人の動機(借金の取り立てにきた暴力団員を射殺)とはまったく関係のない「差別」についての謝罪を要求、マスコミを呼びつけて長広舌をふるった。三日ほど説得に応じず、その雄弁ぶりには誰もが驚いたものであった。むろん当時韓国では「差別と戦う民族の英雄」扱いである。
つまり、極端かも知れないがこの事件は、65年の段階でさえ受け入れがたい「差別」の実態がまだあちこちに残っていた形跡を示しているのである。
しかし、勝手な推量だが、あれから半世紀近く経って、鄭義信はもうここいらで在日であることの荷物を下ろしたかった、いやすくなくとも重いトランクを手荷物程度の軽さにしたかった。そのために、このような「嘘」を創りあげたのである。
「焼き肉・・・」の終幕は、運命を受け入れる長い長い嘆息にも似た花吹雪できわめて感傷的に締めくくられた。この芝居の成功のあと、あれではまだ、在日の運命が、悲劇に見えると危惧したのかも知れない。つまり、いらぬ同情をかい、あるいは日本人の罪悪感を刺激するのは本意ではないと考えたのだろう。
そこで、あれは記憶の底にある遠い過去の出来事として、時々懐かしく思い出す物語なのだと言うことを念を押すようにして描こうと思ったのである。
エピローグの大吉の台詞は、大阪に移ったあと程なく大村も母親も死んで、刑務所から出た春美は行方不明、自分は高度成長のさ中を忙しく過ごして今日に至っていると、足早に「その後」を語って素っ気ない。怒りも恨みもこめられていない。さらりとした感触の終幕を見せることによって、自らの荷物を傍らに置こうとしたのだ。
「焼き肉・・・」は、鄭義信にとっての「三丁目の夕日」だったと劇評に書いた。
あの時代が懐かしいのは、「家族」がいたからであり、その「家族」を根拠づけている思想はまだ「戦前」のものであった。進駐軍の民主化政策によって、民法はその根本において「家」から」「個人」へと180度転換されたが、いわゆる下部構造が変わったわけではなかった。 日本人の70%は依然として農村に縛られていた。つまり、昭和三十年代までは、まだ「戦前」だったのである。したがって「差別」もまた「戦前」とともに残っていたのだ。
「個人」は、産業構造が変わるとともに麻薬が効いていくように我が国社会に時をかけて浸透していった。「家」は戦前における「公共」であったが、それを代替するものを欠いた社会が戦後であった。
三十年代までは、貧しかったがそのバランス感覚があった。「差別」もまた「公共」であってみれば、それも含めて「生きている」という実感があったはずだと鄭義信は「追想」しているのである。
「逝きし世の面影」(渡辺京二)は、江戸期までの日本文明が、欧米の産業技術(戦争技術)と出会って滅んだといっている。我が国敗戦によって、こんどは「家」という紐帯から解き放たれたのはいいが、西欧が長い時間をかけて獲得した「個人」という概念と出会って、これと格闘しなければならなくなった。「個人」とはまことに過酷で冷たく孤独な運命を引き受けたもので、この生き方において我が国の人々の心の中にまだ実感があるとはほど遠い、しかも翻弄され続けているというのが僕の認識である。
これは、産業技術のような模倣やその発展系でしのぐことですませられることではない。幸い震災などのこともあって、ようやく戦後の不毛な議論が途絶え、とりわけ若い人たちの中に我が国風土と時代を根拠にしたオリジナルの思想が生まれつつあるのは幸いなことである。
鄭義信にも、「三丁目・・・」はもういいから、この劇の背景となったエネルギー革命、石炭から石油への転換という歴史を踏まえて、脱原発や再生可能エネルギーについて言及するという態度こそ芸術家に求められていることではないかといいたい。いや、大吉の台詞の中になにか一言あれば、この劇の「現在」に対するスタンスが浮かび上がって、回想の意味が深まったのではないかと思うのである。
鄭義信が、「在日」の問題をこのような形で描かざるを得なかったのは、いうまでもなく今日の韓国との関係が存在する。「冬ソナ」は2003年の放映(NHK-BS)であった。これをきっかけに、韓国ドラマの輸入が盛んになって、いまでは韓流スターやアイドルが、CMに登場するまでの活躍をみせ、新大久保の韓国レストランには若い女性がおしかける活況になった。一方、サムソンやLG、自動車の「現代」が世界シェアを拡大し、産業界でも一目置かれる存在となっている。
こうした時代を迎えて、大日本帝国の併合と「差別」の過去を声高に批難し続けることに、どれほど劇の見物人に訴えるものがあるのか疑問なのは当然のことであろう。我が国と韓国は、冷静に過去を振り返れる状況を迎えたのである。
とはいえ、時折、この状況に水を差すようなことが起こるのは仕方がないとしても、在日がこれに何の発言もしないのはいささかおかしいと思っているので、この際だから取りあえず二つのことをいっておこうと思う。
まず、「従軍」慰安婦のことである。
ついこの間もソウルの日本大使館前の歩道に慰安婦の少女像と言うものが据え付けられることがあった。日本国の国家賠償を迫ったものだが、戦後五十年も経ってからはじめて提訴されたことであり、しかも、賠償は条約で解決済みであった。腹の虫が治まらないというのだろうが、賠償請求に名を借りたプロパガンダであることは明白で呆れるほかない。
次ぎに、「強制連行」はこの劇の台詞に時折登場することばだ。僕がこれを耳にしたのはいつ頃だったか忘れてしまったが、はじめて聞いた時は妙な言葉だと思った。「強制」というのは、本人の意に反してと言う意味である。「連行」は文字通り連れて行くということだが、本人の意志に反しているわけだから、単に連行するするのではなく、逃げられないように拘禁することが必要である。すると、「強制連行」が実態として示しているのは「逮捕」および「拘禁」なのである。
いやしくも法治国家である以上「逮捕」には法的な根拠が必要である。その要員も拘禁しておく施設もいる。
「逮捕」の法的根拠は、いい加減だったかもしれないが、戦前の九州の炭鉱にこれらの要員や施設があったという話は聞いたことがない。
「徴用」というのがあったことは知っている。軍需物資調達のために提供される労働力のことだが、これは、日本人なら誰でも参加「させられた」。だからといって、たこ部屋に入れられて監視されるようなことがなかったのは周知の事実である。みな工場には家から通ったのであった。
これだけでもないが、事実があやしいと思われる戦時中の出来事について、賠償や謝罪を要求されるたびに、政治家が頭を下げて目の前の嵐がとおりすぎるのを待っているのは仕方がないかも知れない。ヨン様ファンの中年のおばさまたちはどうか知らないが、しかし、何という言いがかりだと、心を痛めている日本人が少なくないことに思いをはせるのも在日の知識人の役割ではないかとひそかに考えている。
さて、これは剽窃ではないかと始めた劇評であったが、結局だめ押し、あるいは同じ思想の強調というのがその正体であったというのが結論であった。
これは、鄭義信が自身の心境とともに在日の現在を正確に読み取っていたからできたことである。
最近見たあるドキュメンタリーに登場した在日の親子の会話を紹介してこの稿を締めくくろうと思う。
韓国籍を選択しようかどうか迷っている18才の息子に、一足早く日本籍になった父親がこう言ったのである。
「住んだこともない、言葉もわからない国に帰属するとはどういうことだろうか?結局われわれは韓国系日本人として生きていかなけりゃ、しゃあないんとちゃうか?」
こうしたものを受けたのだろう、
この芝居の最後の台詞である。
はらはらと桜が舞い落ちてくる舞台の真ん中で、家族が散り散りになったあと、身体の不自由な成勲を椅子にかけさせ、髭をあたっている須美がいる。
賠償裁判があるから、「うちはここを離れるわけに行かない」という須美。それに対して成勲が呆れたように大声をあげる。
「お前は朝鮮人ちゅうより、ほんなこつ九州女ばい。意地っ張りばい。」
これを聞いて僕は多少なりと驚いた。
ここには、鄭義信が作った嘘がある。
思っていても口に出すのは生理がそうさせなかったはずの言葉である。
しかし、鄭義信にとってはこれでいいのだのいう確信があった。
荷を下ろすとはそううことだったのだ。
これをあの金嬉老(2010年3月、出所後移住した韓国で没)が聞いたらなんと言うだろう。
とんでもないと怒り出すだろうか?いや、あの能弁で回転が速そうな殺人者は、存外、にやりと笑って脇を向き、フンと鼻をひとつ鳴らすかも知れない。
