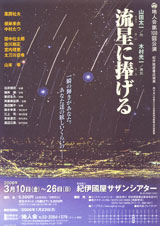
|
題名: |
流星に捧げる |
|
観劇日: |
06/3/24 |
|
劇場: |
紀伊国屋サザンシアター |
|
主催: |
地人会 |
|
期間: |
2006年3月10日〜26日 |
|
作: |
山田太一 |
|
演出: |
木村光一 |
|
美術: |
石井強司 |
|
照明: |
室伏生大 |
|
衣装: |
渡辺園子 |
|
音楽・音響: |
斉藤美佐男 |
|
出演者: |
風間杜夫 根岸季衣 山本學 中村たつ 宮内理恵 太刀川亞希 田中壮太郎 佐川和正 |
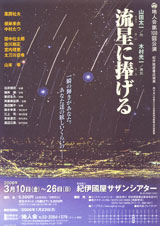
「流星に捧げる」
地人会百回目の本公演である。他に八十ほどの特別公演や朗読劇などがあって、1982年以来精力的に劇制作を続けてきたことには驚嘆する。その割にはあまり騒いでいない。山田太一というどう見ても大向こう受けするとは思えない作家の作品を、記念すべき公演に持ってきたのは、百回がどうしたという気概でも示そうとしたのか。
そう思ったが、パンフレットに寄せた大笹吉雄の文によると、地人会上演作品のうち9回は水上勉で第三位、10回が井上ひさし、山田太一作品はダントツの17回だそうだ。それから考えるとやや地味な作品ながら、筋は通っているといえるかも知れない。もともとテレビのシナリオライターだった山田を劇の世界に引っ張り出したのが木村光一で、浅からぬ因縁があったのだ。
二年前に見た「夜からの声」は、「話し相手」というボランティアの男(風間杜夫)が主人公で、痴呆症(いまは認知症)と鬱病が背後にある物語であった。(劇評参照)
この芝居もまた認知症が中心にあって、発端がブログという如何にも山田太一らしい設定になっている。「話し相手」は電話だったが、こんどはインターネットを持ち出したことでテレビ的話題性というか、新しく出現し日常に浸透しつつある「人間のネットワーク」が強調されている。認知症は現在進行形の重要な社会問題だと山田太一は考えているようだ。
舞台は古い大きな洋館の居間。上手奥の屋根の上に風見鶏がシルエットになって見えている。
明かりが入ると毛利家の家政婦落合時子(中村立つ)の独白が始まる。二十八年間勤めてきたが、この日は珍しく訪問客が多い。自分の連れ合いが末期ガンで、今日は自宅治療のために退院させる日だというのにやって来る客の応対に追われ、困惑している。主人の毛利信行(山本学)は、名門、善明女子学舎の創業者一族であり、元教授で理事、十年来車椅子の生活で他に家族はいない。
毛利信行は、覚えたばかりのパソコンで自分のブログに書き込んだらしい。「世田谷の一軒家、動かない風見鶏、車いすの老人、ひとり・・・」むろん匿名である。これに反応した連中が、この家に違いないと見当をつけて次々にやってきたというわけだ。追い返そうとする落合時子を制止して、毛利は一人一人話を聞こうとする。
一ヶ月後、何人かはこの洋館の二階に住み着き、何人かは通って来て世話を焼いたり、話し相手になり、投資話で老人を利用しようとしている。
フリーターの川田忠弘(田中壮太郎)と工務店の営業マン鈴木さんご(佐川和正)、それにOLだが出社拒否症の女、古矢久美(太刀川亜希)は車いすの生活に二階はいらないだろうといって、アパート代わりに引っ越してきた。
落合時子が出て行けというと、聞きつけた毛利が「君こそ二度と現れるな、顔を見たくない」というので、二十八年も奉公して情けないと思うが、一方毛利が耄碌し始めている、いやボケが始まっているのではないかという疑いを持つ。
ユニフォーム会社を経営している井原尚彦(風間杜夫)は、中国に工場を作る資金が足りないので投資を願い出ている。ビジネスとは縁のない暮らしをしてきた毛利は意外にも検討してみるという。その結論を得るために井原はときどき顔を出している。投資話を持ち出すと、始めははぐらかしているのかと思うが、ほんとうに失念しているらしい。ところが次の時はちゃんと読んで内容も理解したようである。ボケが進行しているようで不安がつのっていくのだが、なかなか実行されないないまま時が過ぎていった。
保険会社に二十五年勤めて最近辞めた藤井彩(根岸季衣)は、洋館の居間をオフィスにして占いビジネスでもやろうと思っている。毛利はこれにも快く使うことを認めていた。藤井と井原は同世代ということもあり、気心が通じている。
毛利が車いすの身体になったのは交通事故が原因だった。十年ほど前息子をのせてドライブの途中事故に遭い、自分は助かったが息子を死なせてしまった。その後愛人がいたせいもあって妻が家を出ていって、家政婦の他に家には誰もいなくなってしまったのだ。
毛利のボケは著しく進行している。そんななか毛利が手首を切って自殺しようとする騒ぎがあった。浅い傷であったが、いよいよ自意識がなくなると見て毛利が試みた最後の抵抗であった。一同は深く同情を覚える。そして自分が自分であることを認識している時間はほとんど無くなった。しかし、洋館に集まった人々は相変わらず、毛利の面倒を見、世話を焼き誰一人出て行こうとしない。
藤井彩が、井原の投資話に毛利がのったことを知っていた。井原に問いただすと、七百万円の預金通帳と銀行カードに暗証番号、証券の類い、およそ毛利の全財産とおぼしきものを預かったというのである。ただし、時期が遅くなって、井原の会社は倒産、事業は実現出来ず、妻とも離婚してしまったのだ。そのさなか、二百万円ほど手を付けてしまったが、残りはまだ手元にある。それをもって逃げても良かったが、井原は毛利のいく末が気になってそうはしなかった。人のいい井原に藤井は、結局ボケていくことを知っていた毛利はあなたに自分のことを託したのだといって、この先の責任を押し付けようとする。井原は、自分のこともあって決心しかねている。
ある夜一同が集まったパーティの席へ毛利が現れ、井原を亡くなった自分の息子と思って話しかけ興奮する。藤井を愛人としてあるいは家政婦の落合を別れた妻として、昔の思い出の世界に浸っているらしい毛利を、一同が優しく見守り肯定する。おそらく久し振りに会った思いでの人々を前に毛利は我を忘れる。突然力を振り絞って車いすから立ち上がり腕を上げて喜びに浸るのを皆で支え、こんなにまでなっても、まだ人間らしい感情が、それを全身で表すエネルギーが残っていたことに驚く。やがて、疲れて車いすに眠る毛利を一同はいとおしい存在として認める。
藤井が長く勤めた保険会社をやめたのは愛人の妻に関係がばれたのがきっかけだった。井原が離婚したことを知った藤井が、井原に関係を迫る場面があったりして、山田太一らしい仕掛けが、ボケた毛利の人間性(ヒューマニズム)をもり立てる小道具にもなっていた。
老人の孤独が、ネットというこれまでになかったヒューマンネットワークで結ばれることによって癒される可能性を謳うと同時にボケが必ずしも否定的に捉えられるものではないという作家の主張は、その限りでは正しいと思う。ぼけた老人はむしろネット社会で出会う赤の他人の方が付き合いやすいというのも説得力がある。そして、認知症の老人をだまそうという悪意はどこにも見られず、後味の良い劇だった。
ただ、ボケにつけ込んで数千万円をだまし取る事件があったばかりで、現実はこうした善意の人ばかりではないところがむしろ社会的な問題である。そうした事件を前にして、僕らはどう考えたらいいか?山田太一は、認知症という現実が、僕らの日常であることを示してくれたが、それは人文科学的側面だけを見せたに過ぎず、それだけではきれい事に終わってしまうと思う。事実、夜空に美しい光跡を残して消えていく流れ星を人生にたとえて、その最後の輝きを讚えるという詩情は、文学的すぎるのである。とはいえ社会科学、自然科学的視点から見たボケとはどういうものか、というテーマはもはや演劇の世界の範疇を越えているかもしれない。
しかし、僕らにとっては自分のボケや身内のボケという現実が襲ってきた場合の対処方法が気にかかる。
僕は、子供の頃近所に精薄はいたが、ボケ老人を見たことはなかった。最近では駅まで行く間に徘徊とおぼしき老婦人を見ることがある。いったい統計的にこれが増えているものなのか?あるいは原因はなにか?医学的に見てどういう症状なのか?ということがもう少し明らかにされてもいいのではないかと思っている。
とりわけ、自己を認識出来なくなった人とはどういう存在なのかということを考える手がかりがほしい。
いずれ山田太一がこうした視点で、再びボケをテーマに書いてくれることを期待したい。
