

|
題名: |
桜の園 |
|
観劇日: |
03/1/10 |
|
劇場: |
シアターコクーン |
|
主催: |
シアターコクーン |
|
期間: |
2003年1月8日〜26日 |
|
作: |
アントン・チェーホフ |
|
翻訳: |
小田島雄志 |
|
演出: |
蜷川幸雄 |
|
美術: |
中越司 |
|
照明: |
原田保 |
|
衣装: |
小峰リリー |
|
音楽: |
井上正弘 |
|
出演者: |
麻実れい 京野ことみ
牧瀬里穂 菅野菜保之 香川照之 高橋洋 飯田邦博 毬谷友子 佐藤誓 西尾まり 森塚敏 中山幸 名取幸政 塚本幸男 伊東千啓 他 |
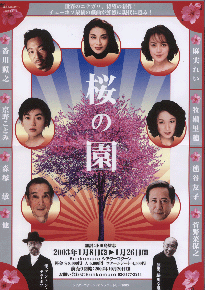
>朝日新聞1/22夕刊記事について<
「生き生きと京野ことみ」という見出しのこの記事は、彼女が「桜の園」のアーニャ役で出ているという事実を伝えただけで、いいも悪いもない、結局、シアターコクーンのパブリシティにすぎなかった。92年に映画デビューし、年一回くらいの舞台出演があるという経歴はわかったが、女優としてどうなのか全くコメントがない。こういう意味不明のばかばかしい記事を書く記者も「生き生きと・・・」など苦し紛れの見出しを編み出した編集者も舞台芸術にかかわる資格がない。健全な批評家精神こそ俳優も作り手も育てるという気概を持って書けといいたい。京野も女優としてやっていこうというなら、年一回などといわずに根性入れてやれということだ。若さだけではいつまでも持たないことくらいわかっているだろうに。(1/26)
「桜の園」」
シアターコクーンの舞台裏は、正面に大きな搬入口があって、ここが開いていると客席から直接、駐車場の出入り口の向こうに渋谷の街のネオンや飲み屋の看板が見えるようになっている。
大きな書き割りかと思っていると、時々トラックが現れたり、タクシーが通ったりするので、外だと気づいてびっくりするものだが、この日は開幕前にそこが開いていた。
後ろの席の男達がしきりにこれを気にして、その意味を議論していたので、「いや、これは単に趣味の問題で、たいした意味はないんです。芝居と日常性の関係なんて難しいことはなにもないんですよ。」といってやりたかったが、無論我慢した。
その手前には、第一幕一場の屋敷の居室〈子供部屋といっているが)が用意されている。白く塗った板材と垂木で組み上げたデッキチェアのようなテーブルと椅子が舞台いっぱいに置かれている。テーブルの一つ一つには花瓶にいけられた満開の桜、白一色の世界である。
ロシアの大地主の屋敷にしては、シンプルで安っぽい家具を並べたものだ、これは何か新しい解釈でもするのかと期待もわくが、白い直線でできた立体をいくらきっちり置いてみても、たくさん並ぶと客席からはじつに雑然とみえていらいらするものだ。この中に人間を放り込んだらまるで焦点のあわないことになるなあと心配にもなっていた。
白いシンプルな椅子は、抽象性の高い記号になる。 しかし、たくさん集まると、がらくたになる。中越司ともあろうものが、こんな装置を作ってはいけない。 ひょっとして、桜の園そのものをシンボリックに表現したかったのか? そういえば、一幕一場で事務屋のエピホードフ(佐藤誓)がこの椅子にけつまずいて見事に倒れ込んだ以外には、たいした役に立たず、家具の量は場を追うごとに整理されていって、同じ居室なのに二度と同じシーンは見られなかった。あれが桜の園のつもりだったとしたら、もっと他に表現はあっただろうに・・・。
さて、お屋敷の台所にも入らせてもらえなかった小作人のせがれが、成長して事業家になり、主家筋の経済状態を心配するとしたら、どんな心境からであろう。
このロバーヒン〈香川照之〉という男は、女主人であるラネーフスカヤ(麻実れい)が五年ぶりにパリから帰ってくるのを待っている。二つの理由で。
ひとつは桜の園を別荘地にして分譲し、その金で女主人の窮状を救い、自分はその事業を取り仕切る、という提案を受け入れてもらうために。 いまひとつは、この女主人に会うために。 彼はこの美しく天真らんまんで多少身持ちが悪くても魅力的な女性を遠くから、憧れとも敬愛とも畏れともつかない、いやその全部かもしれない複雑な眼差しで眺めてきた。自分には金輪際手に入らない女だが、まるで磁石に引きつけられるように、何かをして差し上げなければという気持ちが湧くのだ。
ラネーフスカヤは、おそらくそれに値する女であろう。金に無頓着で、男にほだされやすく、財産を浪費して零落しようとも気にしない。まるで浮世離れしたような生き方は、男にとってはじつに魅力的に映るのである。(チェーホフが描く女のひとつの傾向である。〉
ロパーヒンが、ラネーフスカヤの兄ガーエフ〈菅野菜保之〉に「小作人のせがれで、いまは事業欲につかれた俗物」と軽べつされていることを知っているにもかかわらず、この家の経済状態を何とかしければと奔走するのは、心の奥底にあるラネーフスカヤに対する複合感情で、それが唯一の強い動因なのだ。
この関係を香川ロパーヒンは、表現しきれていなかった。 彼の表現力では、始めから無理があったのだが、蜷川自身がこの関係を見誤った形跡が見えた。 それは、ロパーヒンが競売で桜の園を競り落としたあと、コニャックの匂いをさせてラネーフスカヤの前に現れ、小作人のせがれが、主人の土地を手に入れたと、一分三十秒ほど驚喜乱舞する場面である。香川照之はおそらく蜷川幸雄の振り付けによって、この長い場面をようやく?演じることができたのだが、これによって、小作人が地主の屋敷を買い取るという快挙と時代の流れを強調したいという蜷川の意図がわかる。
しかし、ここはロパーヒンが競売場に入ってから競り値をつり上げる情景の説明に注意深く耳を傾けなければならない。
彼は、心ならずも競売に参加し、だんだんと人手に渡してなるものかと興奮のあげく、法外に高い値で競り落とすことになるのだ。 ロパーヒンはとんでもないことをしでかしたことに気づく。桜の園を手に入れた途端に、実はラネーフスカヤを永久に失ったのである。 彼はがく然として、その気を紛らすために酒を飲んだ。そして状況を納得し、落ち着いて屋敷に帰ってきた。
案の定、みな驚き怒り、ラネーフスカヤは嘆いた。ロパーヒンの心の奥にあった憧憬は、深い悲しみにかわっていた。その喪失感と悲しさを打ち消すようにして、「しかし、おれは桜の園を手に入れたのだ。」と自分を納得させ、励ますために喜んで見せるのである。
こう考えれば、ばかに長い時間をかけて、香川ロパーヒンに振り付けまでして喜びを表現し、強調することはおかしい。かなり間違っている。
ロパーヒンが桜の園を手に入れたければ、いくつもの手段があったはずである。しかももっと安く。彼はそれをしなかった。他に事業があるのにこの話に奔走した。どこからどう見ても自分の所有物にする動機は不明であり、したがって桜の園を手に入れたのは、彼にとって思いもかけなかったことなのだ。
蜷川は、ロパーヒンを単なる俗物の商人ととらえた。それは正しいのかもしれない。しかし、ラネーフスカヤとの関係を見抜けなかったために演出的には何も構築しなかった。だから、観客の目にはロパーヒンがなぜこんな連中のために、やっきになるのか不思議にうつった。欲しかったのだったら自分でお金を出して買えばよかったのだ。
ロパーヒン=俗物の商人説は、じつに衣装にまで徹底していて、小峰リリーが用意したズボンはこの時代にはなかったと思われる細身のもので、確かにその効果は出ていた。ついでにいえば、ワ−リャ〈牧瀬里穂〉の修道尼の様な黒服は役柄のイメージをあまりに固定的にするので感心しなかった。彼女は古風ではあるが堅い女ではない。まずは、演出意図を忠実に表現できる力量を評価したい。
ラネーフスカヤの麻実れいは、適役と言えるが、この舞台では役柄を作りそこねたという気がする。多分に演出の責任であるが、親の反対を押し切って弁護士と結婚して子供をもうけ、夫のなきあと愛人とパリで暮らす、という長い人生を背負っていることを、あまり感じさせない。いくら能天気でも、年齢にふさわしい世間擦れは隠せないものだ。物語の中心にある存在なのだから登場人物との距離をそれぞれ明確に表現すべきなのだが、この設計図ができていないらしく、何かといえば宝塚的な大きな笑い声でその場をごまかすのが異様に聞こえた。舞台から客席の最後部まで大声で笑いながら上がって退場させるのだから無理がでる。
この生活感をそぎ落としたような印象が、たとえばパリの愛人、おぼれてなくなった小さな息子を思うとき、つまり舞台上にいない存在を語るときのリアリティを著しくそこねてしまった。
香川照之は、どういう出自か知らないが、もう一度発声練習からやり直したほうがいい。それから表情の研究も。仏頂面が顔に張り付いていて変化に乏しい。表情というのは、心の中で何かを思えば自然におもてに現れるものではない。心の中で思ったことを表情に表す技術が必要なのだ。2000人の観客を前にして心にあることを理解させる技術(Art)は学び、研究しなければ手に入らない。それができてはじめて俳優といえる。
若いころの蜷川は灰皿を飛ばして鍛えたものだときいているが、そのエネルギーはなくなったのだろうか? 香川という素材は誰かがやらねばならない時期にきているし、彼なら、きっとそれに応えてくれると思う。
さて、蜷川の読み込み不足は、まだいくつもあった。 ロパーヒンとワーニャの関係である。
ワーニャはラネーフスカヤの養女だが、出自は身分的にロパーヒンとたいしてかわらない。この互いに魅かれあって、ついには結ばれなかった二人の心理は、もっと情感豊に表現できたはずだが、じつにあっさりと済ませてしまった。 もっとも香川と牧瀬里穂ではその切ない複雑な愛情を表すのに何年もかかりそうだ。
ラネーフスカヤの娘アーニャ〈京野ことみ〉の家庭教師にして手品使いシャルロッタ(毬谷友子)の扱いについてはほとんどギブアップしたようだった。 まさか、マイケル・フレインの英訳本をつかったせいで「家庭教師」という習慣がわからなかったなんてことはあるまい。 元来このボヘミアン女のポジションは分かりづらいのだが、今度のは、存在させないほうが、まだましだった。毬谷友子はもったいないことをした。もうこんな扱いを受けるなら余計なお世話かもしれないが、蜷川の芝居はことわったほうがいい。
娘のアーニャは、お嬢様には違いないが母親と違って、しっかりしたところがある。トロフィーモフ〈高橋洋〉の衒学的な言辞に適当に応えながら、新しい生き方を模索している。桜の園が売られると母親から離れて暮らすことを決意するくらいのしっかりした娘である。この戯曲のただひとつの救い、それは若々しい未来、すなわちアーニャである。それなのに京野ことみは、役柄をただの夢見る乙女にしてしまった。女子高演劇部のヒロイン役のように。 しかしまあ、こういう人に灰皿を投げつけてはいけないでしょうね。かわいいからではなくて、あまり効果はないだろうから。
ドゥニーシャ〈西尾まり〉とヤーシャ(中山幸)の関係についても言及したいが、もうめんどうになった。一言だけ言うと、ヤーシャという面白いキャラクターをいかしきれていなかったのが残念。
蜷川幸雄は公演パンフレットで書いている。 「・・・あまりに不条理で不確かな、そしてそれゆえにこそ現代的であるこの戯曲に取り組むのは、スフィンクスの謎に挑むオイディプスのような気分だ。未知の領域に対する好奇心と恐怖とが僕をこの作品に引き込む。 今回はシンプルな舞台空間の中で俳優の演技によって内的なスペクタクルをを描き出したいと考えている。でも、実のところぼくはいつも、初日の舞台を見てはじめて、そうか、こういう作品だったのか、と分かるのだ。今度もきっとそうだろう。ぼくはそういうタイプの演出家なのです。」 この中の「シンプルな舞台空間の中で・・・内的なスペクタクルを描き出す」というくだりを誰か分かるものがいたら解説して欲しい。(・・・もうなんというか、始めからよれよれなのだよ。)
商業主義は大いに結構。貧乏はなんの自慢にもならない。 しかし、これほど赤裸々に「分かっていない作品」〈上の文章はそういう意味だろう〉と告白するものを劇場にかけていいのだろうか?
「初日の舞台を見てはじめて、そうか、こういう作品だったのか、と分かるタイプ」の人は演出家とはいわない。俳優だって困るだろう。このパンフレットの文章は翻訳して外国の連中に見せてはいけない。「世界の蜷川」のブランド価値にかかわるから。
僕は、蜷川幸雄が、かはいそうだと思う。
本来、蜷川は、反体制、反権力あるいは対峙する力のぶつかり合いといったエネルギー渦巻く世界をすみかとしてきた。まさに「内的スペクタクル」を舞台に吐き出すように、絢爛と興奮の美学をついにはブランドにまで高めることができた人だ。 その独自性を世界が評価したのだろう。
「チェーホフ?!そんなしゃらくせえものをおれがやれるかい。」といってしまえばよかったのだ。
興行主は、有名な戯曲を、名の知れたタレントでやるならリスクが少なくていいと思うのは当然だ。今回はその上に「NINAGAWA」というブランドを乗っけてさらにリスクを減じた。多分興行的には成功するだろう。それが商業主義というものだ。 そして、結果は・・・「こんな芝居だった。」 大方は、テレビでよく見る顔に出会えて満足して帰ったであろう。
しかし、違うやり方もあるはずだ。「おれはこんなものを、こんな俳優とスタッフでぜひやりたい!だからお金を集めてくれ。」というのも商業主義である。 なぜ興行主が用意した席にやすやすとのって、投げやりの芝居を作るのか? その方が楽には違いない。もう貧乏はしたくない。それもわかる。
しかし、観客というものは、興行主よりも貪慾で残酷であることを忘れないほうがいい。