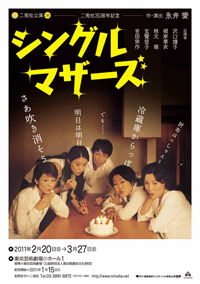
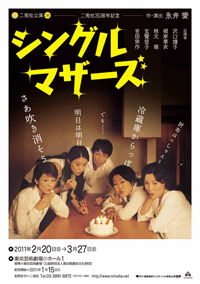


「シングルマザーズ」二兎社三十周年だそうである。永井愛と大石静、昭和二十六年兎年生まれの二人が作った劇団だから二兎社。互いの作品を上演しながら十年たったところで、大石がTVドラマの作家として転出した。後は永井愛が自身の作品を舞台に上げる劇団として孤軍奮闘。それにしても三十年は随分続いた。おまけに今年二人の干支は一回転する。(今時還暦なんぞ流行らないけれど。女の還暦も祝うのかな?)
興行を意識するなら、三十周年記念公演とか何とか銘打って、オールスター超大作!とでも考えそうなものだが、ポスターにはただ「二兎社三十周年」とすこぶる愛想がない。 つましく「シングルマザーズ」では、なんだか景気が悪いから「記念公演」と威張ってみせるわけにもいかなかった、かもしれない。
何を見るのか例によって、全く情報がないまま劇場にいったのだが、開幕早々永井愛にしては随分「生」なテーマをとりあげたものだと不安がよぎった。東京芸術劇場小劇場は、いつ行っても使いにくそうな小屋だと感じていた。こんども、なんだかしまりのない空間だと思ったのは、なにも太田創の装置のせいではない。
昔の日本家屋の柱組で、天井と屋根の部分はたるき一本で省略してある。全体に煤けた様子があるのはよほど古い建物なのだ。アパートの二階という設定である。この省略の仕方は、太田創の特徴がよくでている。上手にドアがあり、その外に階下に通じる階段がある。入り口近くに箱やら書類やら雑然と置かれていて、そこから少し進んで中央柱の上手寄りに粗末なソファセット、その奥に流しとトイレがあるらしい。下手には事務机が二つ並んでパソコンが載っていたり書類が積んである。下手壁は、ガラスがはまった窓になっていて、どんよりと外光が入ってくる。わきの壁に「シングルマザーの子供に未来を!児童扶養手当の削減をやめて!」と書かれた手書きのポスターが見える。
要するに、古い木造アパートの日本間を事務所代わりに使っているという風情がありありと分かる装置なのだ。これ自身はよく雰囲気を醸しているのだが、全体が高い台の上に乗っかっているだけで、袖幕もなにも工夫がないからどうしても作り物っぽい感じがするのである。
豊島区の「あうるすぽっと」も似たところがあって、設計したものは、四角い空間に台だけ用意すれば劇ができると思っているらしい。それはそのとおりなのだが、同じ役人が作ったものでも新国立劇場小劇場と比べたら雲泥の差である。こっちは客席も舞台も自在に変えられる。どうせ税金を使うなら、このくらいの気遣いがあってもよさそうなものではないか。「二〇〇二年一月」の文字が壁に投影される。ここは、「ひとりママ・ネット」事務局である。それは、全国の子供を持つ寡婦で構成する相互扶助の団体で、シングルマザーが抱える様々な問題の相談に乗ると同時にポスターにあるとおり政府への働きかけも行う市民がつくったネットワークである。
代表の高坂燈子(根岸季衣)は、目下のところ児童扶養手当を削減しようとしている政府の動きに野党議員を巻き込んで反対しようとしている。最近、衆議院の厚生労働委員会で参考人として発言を求められ、自らシングルマザーである体験から説得力のある見解を開陳して評判になった。
とはいえ、与党議員はもとより野党議員からも「もっと困っている者がいる」などと言うつぶやきが聞こえる始末で、必ずしも削減に反対という空気にはなっていない。燈子としては、削減を阻止する署名運動を行う一方「ひとりママ・ネット」の会員を増やして、数の力でシングルマザーの窮状を訴える必要があると感じている。児童扶養手当とは、子供を抱えている片親世帯に対して国(支給事務は地方自治体)が補助をする制度である。収入によって、一世帯あたり月額約1万円から4万円くらいまで細かく規定されているが、この芝居に登場する難波水枝(玄覺悠子)に事務局長の上村直(沢口靖子)が語る台詞に「二万円ぐらいにはなるわよ」といっているところをみると、子供をひとり抱えて就労している世帯でそのくらいの手当になるものらしい。ただし、こどもがひとりふえても三千円くらい増額されるだけである。
ついでに言えば、やはり廃止で問題になった「母子加算」というのは、生活保護を受けている寡婦世帯(最近は男親世帯も対象)にたいして支給される手当で、同じく月額二万円くらいになる。難波水枝は、まもなく小学校に上がる子供を抱えて、キャバクラに勤めているシングルマザーである。子供が小学生になる前に、夜の仕事を辞めてどこか事務の正社員になるべく事務局長の直に簿記を習っている。知り合いから「ひとりママ・ネット」を紹介され訪ねたところ、直が簿記二級受験のための勉強を見てくれることになったのだ。ところが、相談の電話がかかってくるわ、子供が熱を出したと連絡が入るわでなかなかはかどらない。
事務局長の上村直には六年生になる息子がいる。学校が家庭に求めてくる細々とした雑用に応えるのは、仕事を抱えたシングルマザーにはつらいものがあるなどと水枝と話している。このあたりのディテールの描き方は十分な取材を背景にしていると思われ、たしかに、子供の世話と仕事を両立させるのはたいへんなことがわかる。そのうちに、要領を得ない電話がかかってきた後、事務所のドアが開いてひとりの男がおずおずと顔を覗かせる。小田行男(吉田栄作)というサラリーマン風の男は、手土産の菓子をさしのべて、自分の妻から電話がなかったかと訊ねる。ついこの間、家へ帰ってみると、テーブルに書き置きがあって、妻が二人の子供とともに忽然と姿を消していたというのである。ここに連絡があったはずだが、何か隠しているのではないかと疑っている。心配で心配でたまらず夜も寝られないと訴える長話を聞いているうち、男は「・・・・・・パパは待っているぞぅ。イイコにして待っているぞぅ。」と呼びかけるように言うのに直が激しく反応する。この男どこか変だ。
二〇〇四年四月になっている。
燈子たちの努力にもかかわらず、児童扶養手当はなくならないまでも支給条件が厳しくなった。
難波水枝の簿記二級は、どうやら時間がとれなかったと見えて、今度はパソコン検定に挑戦中である。直が仕事の合間をぬって教えている。正社員の道はなかなか遠いのだ。そこで今や「ひとりママ・ネット」のスタッフ同然の立場にいる。
相談にやってきた大平初音(枝元萌)は、子供を三人抱えて離婚したばかりのシングルマザーである。元夫から養育費が入らなくなったので追求しようと訪ねたら、浮気相手の女の腹が八ヶ月くらいに見えたというのである。元夫は景気が悪いだのリストラに遭いそうだのといってまともに払ってくれそうもない。
やっと見つけた保育所は、三人とも別々で送り迎えがたいへんである。それも養育費が止まって、仕事がなければ追い出されることになる。燈子は、初音に生活保護の申請をすすめるが初音は、 自分は働けるのだからそればかりはしたくないという。
とはいえ、幼児三人を抱えて働ける状態にないのだから、生活基盤を安定させ精神的ゆとりも持てる現実的な解決方法ではないかと燈子は説得しようとする。
すると初音は、「シングルマザーで貧乏で、生活保護で心療内科・・・この世の果てだ」という。どうやら、自分はそこそこ大手の会社で仕事もできて、給料もそれなりにもらっていた。当時流行の理想の条件「三高」を満たす相手との結婚、三人の子供を育ててきた専業主婦としての誇りが許さないと言うことらしい。妻の座を若い女に奪われた悔しさもにじませる。
水枝の場合は?と聞かれ、養育費などはなからあてにしていなかったと、ここで初めて水枝の事情が明らかにされる。子供の父親には他に家族がいたのである。相手は水枝が子供を産んだことも知らないらしい。「そうなんスよ。」とか「じゃないんスか?」とか言う男っぽい言葉遣いやこだわりのないサッパリした性格は、初音とは正反対である。
燈子が、アンケート調査で「シングルマザーの七割は生活が苦しいと訴え、しかし、七割は一人で子供を育てていることに誇りを感じている」という結果がでていることを紹介するが、初音は「自分は、残りの三割だ。」といってきかない。
どうもシングルマザーもいろいろである。
役所に出かけていた直が帰って、初音の相談に加わる。直もまた、養育費は相手に払わせるべきだという主張である。そういう自分は、一度も養育費を手にしていなかったのだが、それはいえなかった。養育費を受けているケースは二割にも満たないという。
何とかなだめて初音を帰した後、二年前に訪ねてきた小田行男が現れ、自分は妻と別れたという。妻は、自分をDV男に仕立て上げて子供を奪おうとしているが、あのときここを訪ねてきたのは真剣に妻子の行方を捜していたからで、そのことを弁護士に証言してほしいということらしい。
そのうえ二年前、直がおびえたような態度を見せたのを覚えていて、自分はDV男と誤解されたようだが、実は暴力をふるわれていたのは自分の方だったという。
この二人の長い会話の中で、小田行男は妻子に対して激しいDVを繰り返したにもかかわらず、その所行の結果の重大さにたじろいで、心理的に立場を逆転させることによって合理化していたことがわかる。
また、直が夫と別れた理由も家庭内暴力だったことが判明する。二〇〇六年のクリスマスの時期。
養育費を払わせる約束を取り付けた初音が、「ひとりママ・ネット」事務局を手伝っている。児童扶養手当削減反対の署名を集めるための書類を会員に送る準備をしていると、その仕事のボランティアに応募した小田行男がやってくる。驚いた直を尻目に、行男は妻と離婚して、いまはDV加害者のための教育プログラムに参加しているという。二年前、直にいろいろ言われたことに反省し、感謝しているとも言う。
書類を封筒に入れる仕事をしながら、四方山話をするなかで、子供に別れた夫のことを説明するのに苦慮する話や母子福祉政策が就労支援に重心を移行させようとしていることや母子家庭の六割が貧困で、この五年の間に年収十七万円も減少しているという実に様々な「ひとり・ママ」世帯の日常から統計的実態までが語られる。
こうした話をしながら、直と行男が何となく親しくなるのではないかという予感を抱かせるのだが・・・二〇〇七年十一月十六日。
児童扶養手当削減案が国会で決まるかどうか大詰めに来ていた時期である。再び、小田行男が訪ねてきて、今度は別れた妻が再婚するという。なぜか片足を怪我しているらしくびっこを引いている。行男は、妻は帰ってくるべきだと思っていた。 妻が再婚することを心の奥では許していない。その怒りが爆発し、家の皿を割った上に踏みつけて足の裏を切ったのだった。もう行男に歯止めはきかなかった。「お前ら勝手に離婚しておいて、国の世話になんかなるな。俺の税金をこんなものに使いやがって・・・」と叫ぶ。
直には、DVが容易に直るものではないとわかっている。
おりもおり、直の別れた夫から電話がかかってくる。夫の暴力がトラウマとなって応対してこなかった直は、思い切って受話器を受け取る。とたんに怒鳴り声が電話から漏れてくるのをきいて、客席も緊張する。意外にも関西弁になった直が、ということは事務局長からプライベートな立場に豹変して、息子が夫に会いたがらない理由を毅然として言い伝え、電話を切る。直の沢口靖子が大阪出身と大概は知っていることを前提にしたうまい工夫であった。
ホッとしたところへ再び行男が顔を出して、たった今、与党のプロジェクトチームが児童扶養手当削減を凍結することにしたというネットのニュースを伝える。
「ひとりママ・ネット」の活動目標は一応これで達成されることになり、引き続き推移を監視していくと言うことで、めでたく劇の方も終わりを告げる。二〇〇一年四月、自民党をぶっ壊してやるといって小泉純一郎が首相になった。掲げた政策は財政再建と郵政改革である。郵政改革は、小泉純一郎の宿願であった。財政投融資の原資に群がって甘い汁を吸ってきた自民党主流派が力を失うという意味では自民党の半分がぶっ壊れたことになる。郵政三事業の民営化も促進された。
一方、バブルのつけを先送りし続けて無策のまま「失われた十年」をつくった自民党政治の立て直しのために財政再建は必然のテーマであった。かくて、小泉竹中路線「骨太の方針」によって国家予算縮減の具体案が示されたのであった。
厚生労働省所管の福祉予算は、毎年二〇〇〇億円ずつ減らされることになった。「改革には痛みを伴う。」とあのライオン頭が吠えるのに、年寄りの女性をはじめみんなが「純ちゃーん」とエールをおくった。ところがまもなく、後期高齢者などと言う隔離政策を匂わすことばに何が始まろうとしているかさすがに気がついた。早い話が、痛みとは何かを考えていなかったのだ。この芝居は、小泉政権が福祉予算削減をはじめる2002年から福田内閣で児童扶養手当削減を凍結するまでの約六年間を描いたものである。
永井愛は、これを書くきっかけになったエピソードを披瀝しているが、それによると、これ以上もない単純な理由であった。
あるとき、新聞の投書欄を見ると二兎社の制作スタッフのひとり安藤さんが投稿しているのを発見した。生活保護家庭の母子加算を復活せよという主旨で、なかなかいい文章だったという。安藤さん自身は対象者ではなかったが、同じシングルマザーという立場で発言していたのである。
またそれからしばらくあって、TVのニュースを見て驚いた。突然安藤さんの笑顔がアップになって映ったというのである。院内集会で児童扶養手当削減を撤回せよという話をしているところであった。
永井は「安藤、なかなかやるじゃないか」と思ったらしい。ところが、感心ばかりもしていられない。何しろそういう安月給に甘んじさせているのは、他ならぬ自分だからである。また、いつかワーキングプアーの話をしている時に、シングルマザーこそずーっとワーキングプアーだったことに気づいた。
それやこれやの出来事が、この話を「私に書け」とささやいた、というのである。
安藤さんが所属しているNPO法人「しんぐるまざーず・ふぉーらむ」(代表:赤石千衣子)は、孤立しがちなシングルマザーの出会いを促進、精神的な助け合いの場を作り、政策提言も行うという集まりである。そこをおとずれるなど、様々なシングルマザーズを取材して書かれたのがこの芝居であった。僕自身がシングルファザーだった経験に照らしても、実にリアリティのあるエピソードが満載で、なんというか「身につまされる」思いであった。さらにその後、互いに仕事を持ちながら子育てをすることになったが、幸いなことに近所に六ヶ月の乳児から預かる無認可の保育所があって、小学校に入るまでの期間は公立私立を問わずすべて保育所が日中の面倒を見てくれた。ある意味では、子供がもっとも手のかかる期間は他人まかせであったといってもよい。
仕事を持ちながら子育てをすると言うことは、シングルマザーでなくてもたいへんなことはいうまでもない。たとえば、この芝居にもあるように、熱が出たといって連絡が入ると戻らないわけにいかない。仕事にとっては、ハンデキャップである。普通の仕事の場合、このような中断を前提にしていることはない。
したがって、よほど寛容な雇用主でなければ、それが初めから分かっているシングルマザーを雇うことはしないということである。さらに悪いことには、労働者派遣の規制を緩和したことで、正規社員の道はきわめて狭くなり、そのしわ寄せがシングルマザーにきていることもある。まともな仕事に就けないという実態があるのだ。この芝居は、そうしたシングルマザーのおかれた厳しい現実を相当程度詳細に伝えている。物語の動因になっているのは、直接的には児童扶養手当削減に反対する政治政策運動であるが、その背景にある働く女性の賃金差別や子育ての役割分担を社会に問う問題提起となっているという点で、永井愛が「書かねばならない」と自覚したことを網羅しているといえる。
もちろん、そうした苦しい状況にありながら、劇に登場するシングルマザーとその陰に見え隠れする子供たちは、屈託なくたくましく育っていっているのは好ましいことで、見るものの救いになっている。
そのこどもたちが、成長の過程で貧困のために平等な教育を受けることができないと言うことになれば格差は固定して、やがて社会の崩壊につながることは大きな問題である。ただし、この芝居の射程は必ずしもそこまで届いているといえるかどうか疑問に思った。
初めに、永井愛にしては随分「生」なテーマをとりあげたものだ、と書いたのはそのことである。
児童扶養手当は、確かにその月額二万円ほどの手当が、シングルマザーにとって文房具や学校の様々な納付金や修学旅行の費用になるのは有り難いかも知れない。その切実さはよく分かる。しかし、この手当は「児童扶養」といいながら世帯に対して支給されるもので、児童ひとりひとりを基準にするものではない。つまり、児童が二人、三人世帯の場合は、ひとりにつき五千円〜三千円が加算されるだけということになっている。これでは、劇に登場する水枝(子供ひとり)の場合と三人の子持ちである初音では、子育て支援に不公平が生じる。
手当の根拠は、子供を持つ寡婦の所得が相対的に低いという統計結果によって、国が所得を補填するという考え方であろうが、それでは児童扶養手当という名称が適当かどうか疑問である。おおざっぱなことをいうようだが、生活保護の思想的根拠と大差ないと言っていいかもしれない。
つまり、児童扶養手当がそのようなものだとしたら、苦しい生活を保護する役割を果たすかもしれないが、その根本的な原因である女性の賃金差別や子育てのハンデキャップを取り去ることはできない。
東京都新宿区は、生活保護世帯の自立を促すために積極的に就労支援をすることによって成功を収めていることで知られているが、この芝居でも、直が役所に意見を求められたという場面で、児童扶養手当もシングルマザーの就労支援に方針を転換しつつあることをほのめかしていた。ただしそれにしても、一方で保育所が足りないという状況は就労そのものを阻害しているのである。児童扶養手当削減を阻止しようと立ち上がったシングルマザーの戦いは、要するに月額二万円の支給額が一万円に減らされる、または支給期間が短縮されるのはかなわないというものであり、それに対して国の方は、総額二千五百億円(約百万世帯の対象者がいるからそのぐらいである)の予算を半分にしようという構図であった。
福祉予算を二千億円ずつ減らすという国の方針があったから、何となくこれに手をつけようとしたのだろうが、女性たちの評判があまりに悪かったから、国はいったん決めた上で施行を凍結してしまった。劇にとっては、めでたし、めでたしなのだが、一体これで何が解決されたのか?問題を矮小化したとまでは言わないが、すべては宙ぶらりんで中途半端なままである。まるで「生煮え」の料理を出されたような感覚だった。ただし、この劇にとってそういう批評が少し酷なのは、物語が二〇〇七年末の凍結決定までで終わっていることを言い添えておかなければならない。
それというのも、このすぐ後二〇〇九年八月に民主党政権が誕生すると「子供は社会が育てるもの」という考えの基「子供手当」支給が決まったからだ。「子供手当」は児童扶養手当などと言う無思想でケチなものを吹き飛ばしてしまうインパクトがあった。水枝も直も月額二万六千円、初音に至っては、月額七万八千円支給される。(はずだった。)
何とも唐突にいいだしたもので、最初聞いた時は、一時流行った共産主義の集団でやったような子供だけ集めて暮らすのかなどとイメージしたのだが、何のことはない、ただ単に親に現金を渡すだけと言うことだった。
「子供は社会が育てるもの」といいよう、あまり深く考えたわけではなかったことは、すぐにばれた。「コンクリートから人へ」というスローガンが意味したことは、公共投資でばらまかれたカネが自民党の票田を養っていたという構造を変えようとしたにすぎない。つまり、物事を深く考えたわけではなくて、ただ単に政敵に不利になるように政府支出金のばらまき対象を変えるだけという貧しい発想だった。
この後の民主党のていたらくは、周知の通りである。
しかし、「子供は社会が育てるもの」というテーゼは、何か新鮮な響きをもっていて変化の兆しを感じさせる。
男が外で稼ぎ、女は専業主婦になって子供と年老いた両親の面倒を見ながら家庭を守るという日本人の生き方がスタンダードだった時代は、もうとっくに過ぎた昔のことである。戦後の民法の「世帯よりも個人」という思想は、役所はもちろん至る所で徹底し定着しつつある。日本はいつの間にか個人主義の社会になっていたのである。 個人主義の社会は基本的に子供を必要としない。放っておけば出生率は下がる一方であろう。まして、子育てに時間と金がかかるということなら無理をするまでもない。 年寄りは年金を受給して別所帯を営み、夫婦は共稼ぎでなければまともな収入を得ることができなくなり、それぞれが勝手な生き方をしはじめているのである。いい悪いではない。これが日本人の選択した生き方だったのである。女性の大学進学率は40%を超えて、男よりも多い。これだけの教育コストをかけて、良妻賢母というシャドーワークに押し込めておくことは社会資本の無駄遣いというものである。女性の勤労意欲も高い。
問題はすでに明らかである。
シングルマザーであろうとなかろうと、夫だろうが妻だろうが子育ての時間をアウトソーシングする以外に仕事と収入を確保する手立てはなくなっているのだ。そのサービスのコストは社会全体で負担するべきだろう。具体的にはただひとつ、公的な保育所のシステムを充実させることが必要なのである。僕の経験から言えば、子供に手がかかるのは小学校低学年までのおよそ十年の間である。二、三人育てるにしても合計十五年ぐらいで、こんなものは今時の長い人生にとってはあっという間である。
子供は社会が育てるというのは誤解を生みやすいかもしれない。子供はあくまでも家庭に属しているものだが、子育ての時間を親に代わって社会が負担してあげる仕組みといえば、保守派にとってもそれほど大きな抵抗を感じないのではないか。だから、社会的コンセンサスを得るには、もっときめ細かな「仕組み」が提案されるべきだったのである。シングルマザー奮闘記も「子供手当」の登場によってなんだか後退しかすんでしまった感があるのは残念であった。
さて、この劇はもう一つの筋立てを持っている。
ドメスティック・バイオレンスの男が登場して「ひとりママ・ネット」と関わりを持とうとするのであるが、この設定はどうも唐突である。シングルマザーというテーマの隣にDV男をおいてみると、いかにも据わりが悪く、必然性が希薄だと感じるのだ。どんな理屈をこねてみても、これは一目見てこなれていない筋立てだと思う。これは、永井愛にしては「生」なテーマだといったもう一つの理由である。ところが、 それぞれ数年をおいた四場で構成されているこの芝居は、DV男小田行男が「ひとりママ・ネット」を訪ねてくる場面が四場とも必ず挿入されている。不思議なのは、だからといって、他の登場人物とからみながら劇全体の狂言回しになるというわけでもなかったことだ。
DVは離婚の原因の三割ほどを占めていて、意外に多い。何故男は妻や子に暴力をふるうのか?そもそも、DVは精神疾患の一種なのか。あるいは、遺伝的な傾向なのか。それとも幼児体験の心的外傷が原因なのか。小田の言い分を聞いても、あまり合理的な説明がない。それどころか小田には自覚症状すら見あたらないのである。後で反省して教育プログラムに参加するといっても、それで暴力への衝動は抑えられるのか?教育プログラムとはどんなものなのか?この男をめぐる法的な問題は?
「片付けられない女」は一種の脳機能障害だという指摘をしたことがあるのに、こういうことについて永井愛の見解は、全く書き込まれていない。これでは小田の存在の意味が理解不能になってしまう。何故いなくても劇は成立するはずなのに、この男をあえて登場させたのか?
「読み解く」という流行の言葉はいやだが、そこを考えざるをえなかった。児童扶養手当削減に反対する運動を描くのは、一種の政治的プロパガンダである。シングルマザーの困窮した生活ぶりと、さりながら母たちは強くたくましく働きながら子育てを続けているといった様子を見せるというのでは、シングルマザーを施しまがいの児童扶養手当を配ることによって、社会的弱者に追いやり固定しているものの「構造」は見えてこない。
問題なのは「女性差別」意識である。
児童扶養手当削減法案は、シングルマザーに対する絶えざる圧迫であった。一体何ものが、月額二万円の手当を取り上げようとしていたのか?小田行男は、シングルマザーに理解を示しながら、最後には「お前ら勝手に離婚しておいて、国の世話になんかなるな。俺の税金をこんなものに使いやがって・・・」と叫んでいなくなる。
これがおそらく世間の本音であろう。この台詞一つで、この芝居と小田行男の存在が一瞬交錯する。必然性が希薄と知りながらDV男を登場させたのは、この一瞬を描きたかったためにちがいない。小田行男は圧力を加え続ける世間というものの象徴だったのだ。シングルマザーはひとりで子供を育てていることに誇りを持っているという。自分の生き方を自分で決めたという自信がみなぎっている。この女の自立と自由の姿に、小田行男たる旧時代の倫理がたじろいでいるのある。
女性は、長い間家庭の中に押し込められていた。近代化、つまりは経済のパイが拡大することによって、労働者として、消費者としてあるいは他の何ものかとしていわば社会参加(アンガージュマン)の空間ができた。資本主義の発展は、すべての事象を平準化、中性化の方向へ牽引する。それによって、いまや女性は一切の束縛、女性性からすら解放され自由を獲得したのである。この自由を、もはや誰も取り上げることはできない。
旧時代の倫理はこれに驚愕し、嫉妬し切歯扼腕して邪魔立てしようとする。もはやそれに対抗するには暴力しかない。
しかし、暴力で他人の自由を奪うことは不可能である。自由とは心の問題だからである。このようにして、一見物語との関連が希薄に見えるDV男の存在が、シングルマザーが要求する税の社会的分配の正当性を際立たせてくれているのである。 短兵急に書いてしまって、分かりづらかったかも知れないが、勝手に「読み解いた」結論である。
よく稽古されていて、アンサンブルという点で気持ちのよい舞台であった。 枝元 萌と
玄覺悠子は初めて見たが、永井愛が注目するだけの役者で、あて書きにしてもよく雰囲気がでていた。玄覺悠子のサッパリした性格と屈託のない造形には妙な存在感が漂っていて、特に印象に残った。
沢口靖子は、舞台では見たことがなかった。もっともTVドラマは敬遠してるからまともに見たのは初めてかもしれない。お人形さんのような幼い顔立ちと細い体つきは、舞台では損だが、何しろまじめにしっかりと伝えようとする誠実さがあふれた演技で好感が持てる。最後のところで大阪弁になるのは永井愛のうまさであったが、不意にお人形さんに生活感が加わって、ああ、この人でなければならなかったのだという感動と納得で一瞬腑に落ちた。スウェーデンのミステリー「ミレニアム」の書評でも触れたが、DVはあの福祉の進んだ国ですら四割強のカップルの間で行われている。人間の業と言うべき問題かも知れないが、それが事件になるのを聞くたびに、悲しみで途方に暮れてしまう。

題名: シングルマザーズ