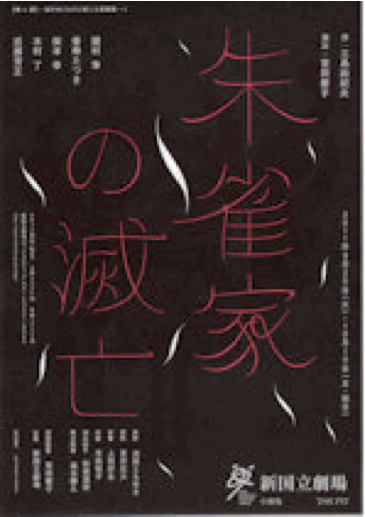
「朱雀家の滅亡」
いやしくも舞台に上げる以上は、 演出家もプロデューサーも、 戯曲を「理解」していると考えるべきだろう。「理解するとは、そちら側に行くことだ。」といったのはジャン・ポール=サルトルだが、その伝で行くと、制作者は三島由紀夫がこの本で示そうとしたことに少なくともシンパシーを感じ、同じ側にいるということになる。
いまどきこの戯曲を選ぶというのはタイミングがよすぎると思ったら、二年も前に上演することが決まっていたらしい。それはそうだ。「日本国の滅亡」とも言うべき有様のときに「滅びの美学」などといってみても、あの瓦礫の山と爆発した原発建屋をみると「美学」とはほど遠い現実に、なにを気取っているのだと思うものが少なくないに違いない。この「間」の悪さときたら、せっかくの「美学」に酔いたい制作者たちには気の毒なことであった。
舞台正面、数段高くなった真ん中にコの字に組まれた朱塗りの柱がある。本のト書きには弁天社にいたる鳥居とあるが、鳥居そのものでは今時ものものしい印象が漂うとの配慮が働いたものと思われた。つまり、立場としては「そちら側」に行くが、鳥居のデフォルメによって過剰なナショナリズムをおさえるくらいの自由は、戯曲の「解釈」として許されるだろうというわけである。三島が生きていたらなんと言っただろう。
上手は広く開いていて庭から海が見えることになっている。下手は、本来温室で、そこで劇は展開するはずだがなにもない。代わりに一段低くなった舞台が客席に張り出し、真ん中に大きなテーブルがでんと置かれていて、四幕すべてがそこで展開するというのは、起承転結の骨格をきわだたせたい戯曲の気分に反しているが、むしろ戦時色の匂いを消して時の流れを抽象化したい作家の意図には効果的な工夫であった。これも神話の時間的スケールを思わせるという「解釈」の結果であろう。左右にも客席が振り分けられているのは、能の舞台を模したものと思われ、三島由来の形式美を見せようとした演出家の並々ならぬ意気込みを感じさせる。
副題に、「エウリピデスの『ヘラクレス』に依る」とあって、ギリシャ悲劇を典拠にした物語である。
ゼウスと人間の女の間に生まれたゆえにゼウスの妻ヘラに疎んじられ、十二の試練を与えられたヘラクレスが、その最後のものを果たしに死者の国ハデスに出かけたまま帰ってこない。
三島が戯曲のあとにつけた「後記」によると、
「遠征中のヘラクレスの留守を守る、その父と妻と子の三人が、テーバイの僣王リュコスにいじめられて、生命さえ危うくなっている。・・・ここへヘラクレスが帰って、たちまち僣王を征伐し、家族を救うが、一家が喜びによみがえるのもつかのま、女神ヘラの呪いによってヘラクレスは狂気に陥り、うつつなく我子と妻を殺してしまう。狂気からさめたヘラクレスは絶望の淵に沈むが、親友テセウスの友情によって、運命に耐える決心をするのである。」というドラマティックな悲劇である。
登場人物といい、話の展開といい人間の情念のすさまじさや運命の過酷さなど、柄の大きなつくりと普遍的な主題を持つあの悲劇と対比すると、この芝居の筋書きと実に難解で理解しがたいテーマでは、わざわざことわることもない、こじつけと思われるほど現実感の薄い物語と感じる。
ところが、特に第三幕「夏」を見て合点がいった。この部分だけは、 きわめて西欧的な価値観が充溢していて、弁天様が基調のところにどうにも収まりが悪いのだが、これはギリシャ悲劇なのだと思わせれば、違和感が幾分緩和されるのである。つまり、ギリシャ悲劇ならしようがないかと思えるほど、日本的と西欧的という異質のものが混在するなかで、独自の世界観が浮かび上がるように、三島が計算づくで仕掛けた「フィクション」なのである。
三十七代続いた朱雀家の屋敷。
明かりが入ると、女中のおれい(香寿たつき)が和紙に包まれた着物を手に弁天社の鳥居から出てくる。それを待っているのは学習院のセーラー服姿の松永璃津子(柴本幸)、この家の長男で一人息子の経広(木村了)の許嫁である。おれいによると、朱雀家の当主が結婚すると守り神である弁天様が嫉妬して、妻が早死にするのだという。目の前の着物は、現当主、朱雀経隆(國村隼)の妻が婚姻の儀のときに身につけたもので、一年ほどのち経広が生まれてまもなくこの若い妻は亡くなったのだ。
朱雀家は、弁天様に縁があるとおり、宮中で琵琶、音曲を司る家柄で、当主の経隆は、天皇のそば近くに仕える侯爵である。国民の声、ひいては陛下の御心を察して田淵首相の退陣を工作し苦労の末に成功させるが、分を超えた行動だったと辞表を出し、陛下にお伺いを立てると一瞬お悲しみの色が見え、その目が「なにもするな。なにもせずにおれ。」といっているように感じられる。そのまま退出、屋敷に戻って仕事から身を引いた。
その前、田淵退陣の先触れのようにして現れた経隆の実弟で宍戸家に養子に入った宍戸光康(近藤芳正)とおれいや経広たちの間で、朱雀家のまわりで様子を探るものたちがうろうろしていたという話のなかで「田淵は、朱雀家の男どもを根絶やしにしたかっただろう。」というせりふがあるのは、田淵がテーバイの僣王リュコスにあたると言うことであろう。首相と一侯爵の敵対というのではなんだかスケールが違いすぎてがっかりのような気もするが、それはまあいい。
朱雀家を狙う者がいなくなり、当主の経隆は「遠くからお上にお仕えする」ことになる。ヘラクレスが帰ってきて家族に平和が訪れるといったところである。
そうしたなか、息子の経広が学習院の生徒でありながら、海軍予備学生に志願したことを父親に話すと「お上に仕える方法はいろいろあっていい」と琵琶音曲で仕えてきた家にはじめて武人が出ることをよろこび、賛意を表す。すると、許嫁の璃津子は当然のことながら不満である。
しかし、国難のとき陛下のためにという経広の決意は固く、ほどなく海軍士官となって家族の前に現れる。
秋になって、今や経広は海軍少尉として出征の時を迎えている。宍戸光康におれい、璃津子、当主の経隆を前に、近く戦地に赴く旨を報告するのであるが、俄作りの少尉でしかも侯爵家の跡取りと言うこともあって、戦地と言っても命の危険があるようなところではないだろうと一同は高をくくっていた。しかし、父親だけに指で書いて見せたその場所は、行けば玉砕覚悟の、ある「島」の名前であった。
経広が璃津子を庭に連れ出して別れを惜しんでいる間に、居間ではその島の名前を聞き出した宍戸光康が、何としてもそこへ行かせてはならないと騒ぎ出す。宍戸は今から知り合いの大臣に、出征先を変えてもらうよう頼んでみようというが、経隆は黙して語らない。自分の息子をむざむざ死地に追いやる親があるかと激昂する宍戸の声をおれいが聞いている。おれいも懇願するが、経隆はそれをしてはならないと宍戸を制する。朱雀家の名を汚すことになるというのだ。
おれいが、庭にいる経広のもとにいって、理由はともかくただ「おじさまの言うとおりにする。」と言ってくれと頼んで居間に連れ戻す。ところが話しているうちに事情を飲み込んだ経広が、女中の分際に危うく名誉を汚されそうになったと、あらんかぎりの言葉を尽くして、 卑怯未練な女のあさはかさを糾弾する。
ここの異様にしつこいほど(脂っこいと言ってもいい)長い台詞は、やはりギリシャ悲劇を意識してのことだろう。
おれいは、ただ泣きながらこれを聞いているが、最後に「我が子にこんなにも罵られる母親が、世界のどこにいよう。」とつぶやく。ここで観客は、経広がおれいの産んだ子であることを知るのだが、経隆は「ここにいる誰もが知っていること」を口にしてはいけないとたしなめて、おれいもまたそれを謝るのである。
となると、経広は自分の母親と知りながら、女中風情が差し出がましいと罵倒したわけで、なんだか変である。家の名誉とかお国のためと言っても人間の情というものが働かないのか、いくら学習院でもやりすぎだろうと観客としては釈然としない。しかし、まあ、そんな庶民の情などと言うものを三島はもっとも軽蔑していたし、しかもギリシャ悲劇だから有り得ることなのだ。
気まずい空気を一掃するように、璃津子がこの門出の席を自分と経広の結婚の祝いの席にしようと言いだす。璃津子は、朱雀家の正妻は弁天様の嫉妬をかって早死にするというが、自分がその犠牲になるかわりに経広の命を守るよう願をかけたというのである。経広が海軍で訓練を受けている間、この家のお社に毎日お詣りしていたのであった。経広は、若い娘の未来を思って自分が無事に帰還してからでも遅くないという。しかし、経隆は、璃津子の気持ちを汲んで、今夜は仮祝言の宵にして、経広の出征を祝おうとワイングラスを掲げる。ここはなかなかうまい始末のつけようであった。
さて、第三幕は休憩を挟んではじまるが、明かりが入ると、蝉時雨の中、経隆が舞台奥の庭で草いじりをしている。おれいは、手前のテーブルの上の大きな灰皿を前に、だらしなく足を投げ出して肘掛け椅子でたばこを吹かしている。
経隆がたばこをくれというと、自分で取りにこいという。何という変わり様だ。女中が主人にたてついているのである。
東京は空襲で焼け野原になっている。弟の宍戸が疎開するよう勧めても、経隆はお上が東京にいる以上自分も離れるわけにいかないと、食糧もものもなくなった屋敷にとどまっている。
経広が向かった「島」はすでに陥落していた。戦死公報の電報が届いていることを経隆が隠しているが、おれいはそれを知っている。
あなたは何故、むざむざ息子を死地に追いやったのかとおれいが責め立てる。「あの子が臆病な性格だったことは母親である私がよく知っていた。あの子は死にたくなかったのです。」あの夜、おれいを罵ったのはその恐怖を隠すためだったというのである。それに対して、経隆は「あれは、母親を母と呼ばせずに育てた自分にたいする抗議であった。むしろ母にたいする優しさがあのようにさせたのだ。」というのである。
そして、あの若さでもっとも苦しい死を強要されて経広は不幸であったというおれいにたいして、経隆は、
「お上が行けとお命じになった。お上が死ねとお命じになった。仰せの通りにしたという喜びがあったはずだ。」と反論する。
続く経隆の台詞が、どう考えても意味がよくとれない。
経隆:経広はおそらく知っていたろう。自分の小さな死は無益であり、たとえその死を何万と積み重ねても、狂乱を既倒に回らす由もないことを。しかしまた知っていたろう。このような御代に生き御代に死んで、すでに閉じられようとしている大きな金色の環へ鋳込まれて、永遠に歴史の中を輝かしく廻転してゆくその環の一つの粒子になることを。身をもって空にかけた悲しみの虹の、一つの微粒子になることを。
・・・・・・どんな苦しい戦況であろうと、経広は男として満ち足りて死んだはずだ。
経広は、悪化した戦況を押し戻すすべもないと知っていたが、滅び行く歴史、それはまもなく閉じられて永遠に輝く環となり、自分というものがその中の微粒子となることをも知っていた、とでも言えばいいか。経隆の考えたとおりに息子もまた同じ心境であったはずだという。しかし、このような歴史観、世界観を舞台上で聞かされても俄には同意しかねるのであるが、はて、演出家は訳が分かっているのであろうかとふと心配になる。
こうした心境の裏にあるのは、お上の大御心、お上の悲しみを理解するという思いである。
経隆:我が子を失ってから、私はもう一歩、大御心に近づき得たような気がしている。恐れながら以前は拝察できなかった、お上のお心の奥のほんとうのお悲しみが、今ひとつありありと分かってきたような気がしている。
それに対して、「そのお上が自分のお子を一人も失っていない。」とおれいが言うと、「不敬である!」と経隆の怒りが爆発する。「お前が死んでも経広には会えない。」呪われた存在だというのである。(実際「お子」はふたりいたが、まだ幼かった。ここで言いたいのはいずれも成人した軍人であった三人の弟君のことだが、直截な言い方を遠慮したのだろう。)
こうなるとお上にたいする絶対的帰依というか、一種の宗教的境地というべきものであって、経隆の思いは余人の計り知れぬところのものである。
このような現実離れした台詞よりも、そんなに言うなら、死んで中尉に昇進した経広の供養のために「私たちは結婚しよう。今すぐ籍を入れよう。」と迫るおれいの言い分の方が、はるかに説得力がある。
ところが、経隆は「それはできん。」と朱雀家の掟を楯に取る。
おれいは、子を産み、その子も死に、弁天様の怒りを怖れるほど若くもなくなった。自分は、はれて朱雀家の嫁になるこの日を待っていた、といって経隆に迫る。
ちょうどそのとき、空襲警報が鳴って、おれいの攻撃は中断する。
一緒に防空壕に行こうとする経隆にたいして、おれいは、「なにもしないといったあなたが来るんですか?」といって追い返す。
茫然と立ち止まる経隆。
防空壕に向かうおれい。
暗転の後、大音響。
第四幕、大きなテーブルの手前が下に入り込んで、持ち上がった向こう側が防空壕の入り口に見立てられている。テーブルの上に大きな朱雀の紋。
すでに戦争は終わり、冬を迎えている。
あの空襲の日に、外に取り残された経隆が助かり、防空壕で直撃弾をうけたおれいが亡くなっていた。
あたりが薄暗くなってきた夕暮れ、一人屋敷に取り残された経隆を探して、弟宍戸光康がやってくる。敗戦によって華族制度がなくなり、それぞれの家が自活しなければならなくなった。朱雀家と経隆の心配をした宍戸が、事業を興すという知人の会社の役員になるよう勧めに来たのだが、それをきっぱりとことわる。
宍戸ががっかりして帰り、外套の襟をあげてたき火に当たっていると、琵琶の音が聞こえてくる。雪がちらほら舞う中を、鳥居の方から、亡き妻の婚儀の衣装、開幕の時におれいが手にしていたあの衣装を身につけた女が現れる。かざした檜扇を取ると璃津子であった。
璃津子はその衣装を身にまとい琵琶を弾いているとき、なき経広の花嫁になることができるという。さらに、若くして死んだ夫を持って朱雀家の妻は不死になり、嫉妬にさいなまれてきた女神が、もっとも恋しい人を殺すことによって、永遠に嫉妬から解放されたという。いまこそ朱雀家にとって、決して嫉妬しない女神の新しい時代が来たのである。
そして、昔の女神を慕っている経隆を新しい女神は滅ぼそうとするのだと告げる。
新しい女神の化身である璃津子は、何故あなたは、なにもしなかったのか?何故、あなたは、自分の「夢見る誠」を貫くために息子や妻同然の人を見殺しにしたのか?と経隆に迫る。経隆は、何一つ応えようとしない。
璃津子は、自分は決して死なない朱雀家の花嫁だという。花嫁が女神になり、女神が花嫁になったことによって、朱雀家は新しい時を迎えたのである。三十七代続いた朱雀家の最後の男であるあなたが滅び、朱雀家が永遠に滅んで、不死となった花嫁が水辺で琵琶を奏でる、それでよいのだという。
話が混沌として、なんだか論理が通らない言い方だが、朱雀家がなくなって、女たちは天上の、涅槃の境地を獲得するのだとでも言っているのだろう。
そして、最後の台詞は、三島の戯曲らしい締めくくりである。
璃津子:滅びなさい。滅びなさい。今すぐこの場で滅びておしまいなさい。
経隆:(ゆっくり顔を上げ、璃津子を注視する。__間。
どうして私が滅びることができる。夙(とう)の昔に滅んでいる私が。
歌舞伎の決めぜりふのように決まっている。
といっても、実際何を言っているのか俄には判然としないものがある。
まず、「滅びなさい。」という言葉も奇妙な日本語である。「死んでしまえ。」と言う意味なら「わたしは、とうの昔に(精神的に)死んでいる。」と応えるので筋は通るが、「滅びる」という言葉を選んだのは、あきらかに「わたし=経隆」だけでなく朱雀家を二重に込めようとしたものと思われる。
息子経広が戦死した時点で、すでに放っておいても朱雀家は絶えてしまうことが確実になっていて、璃津子が「今すぐ」と急ぐ必要もないことである。
それに対して、わたし(=朱雀家)はとうの昔に滅んでいる。」という「とうの昔」とは一体いつの時点のことを言っているのか?
この第四幕の、女神か亡霊のようにして登場した璃津子とのやりとりは、言葉は流麗だが、きわめて非論理的で、何のことやらぼんくら頭には分からない。
最後の台詞「・・・夙(とう)の昔に滅んでいる私」を言いたいために、弁天様と若妻についてさんざん理屈にならない理屈を璃津子にこねさせて、「滅びよ」などと言う無理無体な日本語を導き出したのではないかとさえ思えるのである。
ここはしかし、昭和四十二年当時の三島の心境を重ねてみると見えてくるものがある。
それについては、後回しにして、さきにいった第三幕のおれいの豹変について述べよう。
三十七代の朱雀家の当主のうち正妻をめとったのはわずかに五代だったという。こう言うのはめずらしいが、ないこともない。腹は借り物とはよく言ったもので、当主の種ならば畑はどこに蒔いても子さえできれば後を継ぐことができる、とは昔から我が国で行われてきたことで、めずらしくもないことである。
幼児死亡率が今よりはるかに高い時代であったから、あちこちに保険をかけておかねばならなかったのだろう。
こうした場合、子供に母親と呼ばせないこともままあることで、おれいの場合は、出自がはっきりしないことはあるが、女中として,家の中の用事を切り盛りしていたのだから、立場は奉公人である。
第二幕では、経広に罵られて、思わず母親といってしまうが、それをたしなめられると、素直に謝ってしまう。そこまでは、いまからみれば随分不自然だが、あの時代の侯爵家としてはごくありふれた光景だっただろうと納得できる。
ところが、第三幕では、経広が戦死したことを知って、女中であり奉公人であることをかなぐり捨てて、子を産み育てた母であり妻である一人の女 に代わってしまう。人間には自然に備わった情というものがあり、理にかなった人間関係があると、経隆の不実を責める態度は、近代そのものであり、西欧的な合理主義であり現代的な民主主義である。ここは、女たちが言いたかったことを思いっきりはき出しているところだから世の女性にとってはすじこぶる気持ちのいいところかも知れない。しかし、ようやく婦人参政権が行使されるのは敗戦三年後のことであり、この時点ではおれいの態度としてはきわめて不自然に思えるのである。
さらにいえば、経広の出征のことでうろたえるのはまだしも、戦死を嘆くふるまい方がこれも当時としては異常に感情的なのだ。我が子を戦場で失い悲嘆に暮れる母親といっても、あの当時の母親も父親も子供を国に捧げたと自分を納得させ、その悲しみを耐え忍んだ。たとえば、僕が生まれる少し前に叔父が中国戦線で戦死しているが、祖父母はそのことを一切口にしなかった。本音はともかく誇りを持って我が子を兵士として送り出し「名誉」の戦死とした当時の世相に反して、 おれいは、ありのままの感情を隠しもせず「あなたのせいで、息子はむざむざと無意味な戦死をしたのだ」と鋭い言葉で経隆を攻撃する。 これもまた、日本の文化とは対極にある直接的な感情表現と言わねばならない。
昭和二十年の時点で、こんな価値観が存在しなかったことは三島は百も承知であっただろう。ここには嘘がある。この嘘は、エウリピデスの「ヘラクレス」を典拠にしていると宣言することによって許されている文学的虚構なのである。
何故そんなことをしたのか。
それは、経隆の「なにもしない」という態度が、合理主義の精神から見た場合、一種の「狂気」に見えるという演出を施したかったからである。つまり、尋常の理解を超えた狂えるヘラクレスが「なにもしな」かったことで,妻おれいたる合理精神をほろぼすというパラドクスを描いて見せたかったのである。
しかしここでは、経隆自身も狂気に犯されていることを怖れている。つまり、おれいの言い分にも一理あると思っている。
三島は、高級官僚であった父親から意に染まない法学部への進学を半ば強制されたが、そのことを結果としては為になったと述懐している。西欧の文化的所産であり合理的な精神の集大成たる法の体系を学んだものが、それとは対極にある超越的な存在への絶対的帰依というふるまいを見せるアンビバレンツにゆれている様が、この第三幕に投影されていると理解してもよいのではないか。
それが、第四幕になると,敗戦によって怖れていた事態が確実なものとなり、もはや回復は不能になっている。しかし、時の流れにかかわらず、変わらぬものを見つめている自分の狂気こそが大義なのだという確信にかわり、璃津子のくりだす一方的な攻撃にほとんど抵抗することもなく身を預けてしまう。
「ああ、お上。尊いお上。気高い、あらたかな、神さびてましますお上。今やお上も異人の泥靴に瀆されようとしておいでになる。民のため、甘んじてその忍びがたい恥を忍ぼうとしておいでになる。何のえにしで、同じ学友のお上と私が、こうして焼き尽くされた国に生き延びたのか。私にはわかっている。私こそは、お上のおん悲しみ、そのおん苦しみ、いやまさるおん苦しみを、遠くからじっとお支えする役をつとめるために生まれたのだ。 かつて瑞穂の国、日出ずる国であったこの国は、今や涙の国になった。お上こそはこの国の涙の泉だ。遠く苔むした山の頂で、限りもなくあふれるおん涙の泉を、私ははるか山裾にいて川へ伝える一本の筧だったのだ。
ああ、ここにいてもお上のお苦しみが、おん涙の滴瀝、篠竹の身にありありと感じられる。経広よ。帰ってくるがいい。現身はあらわさずとも、せめて御霊の耳をすまして、お前の父親の目に伝わる、おん涙の余瀝の忍び音を聞くがよい。
すべては去った。偉大な輝かしい力も、誉れも、矜りも、人をして人たらしめる大義も失われた。この国のもっとも善いものは、焼けた樹々のように、黒く枯れ朽ちて、死んでしまった。」
この台詞は、おそらく三島自身の本音である。
先に取り上げた「後記」の締めくくりに次のように書かれている。
「この芝居の主題は、『承詔必謹』の精神の実存的分析ともいえるであろう。すなわち、完全な受け身の誠忠が、しらずしらず一種の同一化としての忠義へ移ってゆくところに、ドラマの軸がある。ヘラクレスを襲う狂気に該当するものは、すなわち狂気としての孤忠であり、また、滅びとしての忠節なのである。」
『承詔必謹』とは、聖徳太子の十七条憲法の第三条にある言葉だが、「天皇の発した詔(みことのり)を承りては必ず謹めよ。」 ということで、 これは、『臣』すなわち天皇の周辺にいた官僚や豪族に向かっていったもので、文字通りに受け止めれば「やれといったことはその通りに実行しなさい。」といっているに過ぎない。しかしこれは戦時中、「陛下の命令は絶対である。」とあたかも天皇が『民』に向かっていったかのように曲解され、軍部に利用されたという経緯がある問題の言葉である。
三島は当然その経緯を知っていてなお、『承詔必謹』の意味を問おうとする。
しかし、なんといおうとそれは、想像上の「お上の御心」を絶対の「大義」として、いかにすればそれと同化できるかという「不可能性」に、身をよじるようにして挑戦することである。すなわちそれは必然的に狂気を帯びる。しかも、不可能性によってそれは滅び、滅びることによって永遠を獲得することができるという道だけがみえているということである。
この場合の「お上」とは言うまでもないが、昭和天皇のことである。
しかし、三島は二・二六事件における天皇の裁断と戦後に行った「人間宣言」に違和感を覚えていることを公言していた。昭和十一年の青年将校は「憂国の士」として遇されるべきであり、「開かれた皇室」などは愚劣な政策だといった。したがって、この芝居における「お上」とは三島の想像上の天皇であることに留意しておく必要があると、パンフレットのコラムで大笹吉雄が書いている。
「宮田慶子は確か二度目の演出になる。お気に入りなのだろう。」(レパートリーを読む9「『人間天皇制』から遠く」P28)と控えめな皮肉ではじめたこの文章は、昭和天皇の実像はまさに理性の人だったということを印象づけるために書かれている。
三島のつくり出した「気高い、あらたかな、神さびてましますお上」などフィクションにすぎないのであり、いたずらな神格化には与すべきではないと言いたいのであろう。
立憲君主制とはどういうものかを若くして英国に学んだ昭和天皇が、二・二六事件の首謀者たちを直ちに反乱軍と断じたのは、天皇が下した欽定憲法に違反するものであり、法治国家の元首として当然のことであった。また、『現人神』などは戦中の一時期に軍部や右翼によって喧伝された言葉で、天皇がそのように考えたことは一度もなかったことを「人間宣言」にわざわざ書き加えていた(上記、大笹吉雄)のもうなづけることであった。
何故、三島由紀夫は自分だけの内なる天皇の像を作り上げ、それを至上絶対のものとあがめ、できれば「同化」したいと思うようになったのだろう。
この芝居に直接かかわることでもないので、手短に二つのことを言っておこう。
まず、西欧列強がアジアの国々を次々に征服して日本に迫ってきている頃、我が国は六十余州に三百諸侯のそれぞれが領土を治めていた。弱肉強食の列強に互して生き延びるには、それを一つにまとめて近代国家としての陣容を整える必要があった。京都の片隅にひっそりとながらえていた天皇を歴史の表舞台に引き出して、近代国家の象徴的存在とすることによって、歴史上はじめて統一国家としての日本が誕生し、はじめて「日本人」が出現したのであった。これが天皇でなければ国民の合意形成はきわめて困難(内戦)だったに違いない。この時点で、天皇はこれもまた歴史上はじめて顕現した日本ナショナリズムの原点なのである。
外が敵だらけで内が貧しい頃は、モラルが機能する。いや、天皇というたがをはめて内部を引き締めなければ富国強兵は成立しなかった。極東に浮かぶ寄る辺ない小島に過ぎない日本国とそれと一体になった天皇。三島が見つめていたものは、この時点の日本である。そして、三島にとって、時は進んでも、日本を取り巻く情況は少しも変わらずむしろ悪化する一方に見えた。一つは、共産主義「革命」の脅威である。もう一つは日本国民のモラルの低下である。
三島が、自決する直前市ヶ谷でまいた檄文から引こう。
「・・・われわれは戦後の日本が、経済的繁栄にうつつを抜かし、国の大本を忘れ、国民精神を失い、本を正さずして末に走り、その場しのぎと偽善に陥り、自ら魂の空白状態へ落ち込んでゆくのを見た。政治は矛盾の糊塗、自己の保身、権力欲、偽善にのみ捧げられ、国家百年の大計は外国に委ね、敗戦の汚辱は払拭されずにただごまかされ、日本人自ら日本の歴史と伝統を涜してゆくのを、歯噛みをしながら見ていなければならなかった。・・・」
三島は、人は生きるために大義がなければならないといったが、近代日本が誕生する地点へ回帰すべきという思いが三島にとっての大義になっていた。とはいえその実現は困難であり、あまりに文学的な夢想に過ぎないこともよく知っていただろう。その一方で、大義のために命をかけるというのは、人の生き方として当然のこととも考えていた。
このとき、自分が滅び、日本国も滅ぶことによって自分の中にある理想の日本が永遠の輝きを取り戻すという光景をすでに見てしまっていた。
この戯曲が書かれた時点で、「夙(とう)の昔に滅んでいる私。」とは経隆に託した作者自身のことであった。
もう一つは、こうした三島のファナティシズムに誰もまともに異を唱えなかったことである。それは三島にとっては不幸なことであった。二代続いた高級官僚の家に生まれ、自らもエリートとして天才の名を恣にしてきた流行作家だが、酒も飲まず、文壇とのつきあいもなく、熱狂的な取り巻きはいても、孤高の小説家であり文学者であった。晩年の作品には、この芝居に見られるモチーフが頻繁にあらわれ、批評家は真意を測りかねて困惑するばかりであった。
日本の政治的文化的情況をあれだけ鋭く批判しながら、自決によってそれが中断されたことは日本の文化にとっても不幸な出来事であったというよりほかない。
それにしても、「大義」を唯一のものとしてそれに命をかけねばならなかった二十世紀と言う時代の、三島由紀夫は犠牲者だったのではないだろうか?
そのことについてもう一言。
明治維新の頃の日本の人口は約三千三百万人である。それが、約八十年後の終戦時には七千五百万人に増加している。そして維新から百五十年後の現在はそれが四倍弱と、江戸期が終わるまでの増加率に比べれば驚異的に増えている。(これをGDPの伸びにすれば、さらに数値は大きくなるだろう。)
ということは、日本の資本主義がそれだけ多くの人口を養うことができるほどに発展したことになる。
マックス・ウェーバーはご案内の通り、欧州の初期資本主義の発展にプロテスタンティズムの倫理がうまく機能したことを指摘した。それは資本の規模が小さい段階では勤勉や禁欲などの宗教的倫理の抑制が働いてより発展するためのエネルギーを蓄積することができたということであった。しかし、いったん資本の運動が自律して廻転しだし風をはらんで離陸するようになると、宗教や倫理といった規制はかえって邪魔になり、放埒ともいえる自由競争の時代に入る。これを規制するには、ルールを決め、法で管理する以外にないが、自由が資本の原理であってみれば過度な規制は自由を束縛することになるという危ういコントロールが必要になる。とりあえずこのモデルが、日本にもあてはまるとすれば、すでに、モラルや素朴な道徳,あるいは宗教的な観念によって社会に影響力を行使することは難しい時代になっていると言うことである。
石原慎太郎が、三・一一は日本人のおごり高ぶり、天罰だといって物議を醸したが、この言葉をまともに受け止めるほどナイーブな日本人がいなくなった。それを草葉の陰で三島が「俺の言ったとおりになっただろう。」というかも知れないが、あのかつて「美しく輝いていた日本」はもうどこにもないという覚悟を僕らは持たねばならない。
大義がなければ生きていけないとは一面の真実ではあるが、「大義」が「単一ではない」、つまり多様な価値観が混在する社会を認証し、命をかけてなくても丹念に同意を形成しようとする以外に、大義の実現はあり得ないと考えるのが、僕らの時代を生き抜く知恵ではないかと思うのである。
木村了と柴本幸の若い二人には、この役は少々重すぎた。
三島の台詞は、黙読するようにできあがっている小説の言葉である。とりわけこの芝居は冗長で格調高く歌いあげるような言葉の連続で、発語の調子と気分の起伏、息継ぎのコンビネーションが難しい。それに、学習院の育ちの良さとはどこかに天衣無縫な明るさがあってしかるべきだが、声を絞って一本調子になってしまった。これについては、三島のファナティックな気分に規制された演出に問題があったとは思うが。
國村隼は、感情表現に乏しく、台詞の技巧に走りすぎた。あれではラジオドラマである。「とうの昔に滅んでいる私が。」のあと暗転して終幕となるが、しばらくして明かりが戻ると、終幕の姿勢のまま顔を上げてにやりと笑った。「やってやったぜ。」という気持ちの表れかも知れないが、ぶちこわしであった。いや、それよりも、侯爵としての品格に乏しいのは仕方ないとしても、男としての色気が出せないようでは國村隼の名が廃るのではないか?
これだけ書きながら、芸術監督としての宮田慶子、演出家としての宮田慶子のふたりが何故この戯曲を取り上げて、観客に何を伝えようとしたのか、今に至るも僕にはまったく理解できない。
