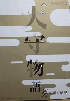
「天守物語」
中劇場の客席に張り出した舞台。下は奈落の底に暗く落ちていて、三尺ほど低く舞台を取り巻いた回廊が、一段高くなった奥舞台の下に潜り込んでいる。この奥の舞台は、幅一間ほどの長い板が二重三重に上下して、人物の登場に合わせたり,場面によって高さが自在に変化する。美術の小竹信節が中劇場の仕掛けをうまく引き出して、ここが五層の最上階であることを表現しようとした。上手手前に舞台に登る四、五段の階段。奥にホリゾントはなく暗闇である。
その闇に稲妻が光り、ひとしきり激しい雷鳴が轟き渡るとやがて驟雨の気配。
一条の光が舞台に差し込んで、白いシャツに白ズボンをはいた男が伸ばした片手を枕に横たわっているのが浮かび上がる。側らに立って、それをのぞき込んでいるジャケット姿の老人と腰を落として見守っている若者がいる。
雷鳴の中、しばらくそのまま動かないが、やがてつと頭をもたげると半身を起こし、静に立ち上がる。そのまま歩いて闇に消え、みていた男二人もあとに続く。
若い女たちの「ここはどこの細道じゃ・・・細道じゃ・・・」と歌う賑やかな声で明かりが入る。
最初の短いプロローグは、むろん原作にはない。 白井晃が演出の都合上付け加えたものであろう。この幻想的で怪奇趣味あふれるけったいな物語をそのまま上演して、果たして新国立劇場の観客の知性は納得するであろうか?破天荒な構成は、劇画とも漫画ともつかない奇想天外な展開で、まともな神経で理解できる物語ではない。
そこで、この幽玄の世界は、ひとりの男の夢枕に現れた不可思議な光景なのだという前置きをこしらえた。
漱石に、「夢十夜」という幻想的な小説があるが、それは「こんな夢を見た。」というフレーズではじまる短文十個で構成されている。夢に現れた何とも説明のつかない「お話」を集めたオムニバスで、あのプロローグは、白井晃にとっての「こんな夢を見た。」の一つだったのであろう。(ちなみに、黒澤明の映画「夢」は「夢十夜」を下敷きにしているが、なんとなく似たような発想か?・・・・・・)
「天神様の細道じゃ・・・細道じゃ・・・」と歌いながら遊んでいるのは三人の女の童( 冠野智美、淺場万矢、飛鳥井みや)。その脇で桔梗(村岡希美)、萩(小見美幸)、葛(栗田麗)、女郎花(岡野真那美)、撫子(鳴海由子)の五人の侍女が、立ったり腰掛けたりの姿勢で、五色の糸巻きに付けた細い竿から釣り糸をたれている。
舞台の端を低く細い柱で囲ってあるのは天守の欄干のつもりであったろうが、これは腰高で華奢すぎて感心しなかった。
ここは、播州赤穂の城の五重の上に立つ天守。秀吉の頃からというから百年以上もの余、人も寄りつかない妖怪の住まう魔界として怖れられている。主は年の頃二十七八の美女、天守夫人富姫(篠井英介)だが、今は出かけて留守である。
留守を取り仕切っているのは、奥女中の薄(江波杏子)。なかなかのしっかり者である。今日は遠来の客があるから気が気ではない。
釣り糸が引き上げられるとそこには秋の草花を描いた半透明の布がついている。女童が歌い、侍女らが釣り糸をたれてゆらゆらと動き回る。何とも典雅な幕開けである。
舞台下手奥には、「金色の眼、白銀の牙、色は藍のごとき獅子頭」,それは幅が1メートル以上はある巨大なものだが、「萌黄錦の母衣、朱の渦まきたる尾」の上に据えられている。この獅子頭の由来は後に明らかにされるが、今はまだ何ものでもない。
釣り上げられた草花は、その前に供えられるのだ。
折しも蓑を着けた富姫が帰還すると、女たちの遊びも収まり雨もやんだ様子である。富姫は、越前の国大野郡夜叉が池の主、お雪様のところに頼み事があって、行ってきたという。
それというのも、ここ姫路の城の「長屋の主」(ほんとうは城主であるが、富姫にとっては城内の長屋に住んでいる人間にすぎない)、播磨守が大勢の従者を連れて鷹狩りに出かけたのを見届けたので、百姓の難儀もかまわず田畑を駆け回る連中の大騒ぎは、今日はるばるやってくる客人、猪苗代の亀姫様の道中に失礼になると、ここは大風と雷雨で邪魔してやろうと思いたったのだ。
夜叉が池のお雪様の巻き起こした嵐はすさまじく、高台で見ていた富姫も少しは雨に濡れたが、鷹狩りの連中ときたら、雷に打たれ、洪水に襲われて散り散りさんざんな目に遭って城に追い返されていた。
百姓に借りた蓑を返してくれるよう頼んだところに、亀姫一行の先達が現れる。
岩代国麻耶郡、猪苗代の城、千畳敷の主、亀姫の供頭、朱の盤坊(坂元健児)である。頭に犀のような角が一つ、 額には頭襟(ときん)を載せ袈裟をまとった山伏の扮装。手足は青く、まん丸眼に朱を差したような赤ラ顔に黒い隈取りがあり、白布で包まれた桶を小脇に抱えている。
そこへ亀姫(奥村佳恵)が到着。
年の頃二十歳ばかり,振り袖姿で手には手鞠を持っている。年の割には顔が赤く,眉も太くて妙なメークだと思った。この世のものならぬと言うことを強調していたのかも知れない。うしろに袴をはいた白髪の老婆、茅野ヶ原の舌長姥(田根楽子)が従っている。
亀姫は、今日は鞠をつきにはるばる五百里(というが猪苗代、姫路間が二千キロもあるわけがない)を富姫の元へやってきた。二人は姉妹のようでもありレズビアンを思わせるあやしげな挨拶を交わす。
亀姫は、たばこを一服すると、手土産を持ってきたという。
朱の盤坊が、抱えていた小桶を差し出し、蓋を開ける。現れたのは若い男の生首である。道中汁がこぼれたと言って盤坊、舌長姥にそれを掃除するよう頼むと、富姫は、血だらけなのはなおおいしかろうと意にも介していない様子。姥がそれを抱えて口から一尺は飛び出す長い舌でぺろぺろ。(田根楽子が玩具の「吹き戻し」をうまく使って長い舌を表現したのは、おかしかった)
何と彼らは人の生肉を食らう妖怪であることがいよいよ明らかになるのである。
薄が生首を見て、この姫路の城の殿様に瓜二つと驚くと、亀姫がこれは自分が「庇を貸す」猪苗代亀が城の主、武田衛門之介の首だという。誰あろう衛門之介は,この城の主、播磨守の血を分けた兄弟であった。
二人の姫は、自分たちが住まう城の主を兄弟ながら徹底的にコケにしているというわけである。
亀姫によると、衛門之介は、いまお妾の膝に手をやって酒を飲んでいる頃だが、まもなく鯉こくを口にするはずで、その腸の中には針があり、それがのどに突き刺さって死ぬことになっている。
と、そこまで言って、もし富姫がこれを食べては、生首の喉に刺さった針を口にすることになると気づいて、「どれ、それを取り除いておこう」と手を伸ばすと、富姫は慌てて止める。針を除いては甦るやも知れないというのだ。
なるほど、その通りである。
生首は、ひとまず獅子頭に供えることにするが、これが男を独り占めする行為に思えたのか、二人は「こんな男が欲しいのう。」と目配せして完爾と笑う。
このあたりのディテールは、なかなか手が込んでいて、これこそ泉鏡花の芸の見せ所なのだろうと感心した。
富姫は、亀姫訪問の返礼として、播磨守先祖代々の家宝の兜を蔵の奥の奥からとりだしておいた。ところが、こんな結構な土産をもらった上は、恥ずかしくて差し上げるわけにいかない、そのうち何か適当なものを選ぶ故、見せるだけといって獅子頭の脇に置く。
亀姫は意にも介さないで、約束の手鞠を遊びましょと誘い、ここからは一同華やかな大宴会になる。
女好きの朱の盤坊は、童女、侍女らをからかい、愛想を振りまき、「勧進帳」の弁慶と富樫の掛け合いを下敷きにしたようなせりふで思わせぶりな問答。酒も入って案外お調子者である。姫たちは手鞠歌を歌い、それに侍女も加わってしばし遊びに興じる。
宴もたけなわ、ちょうどそのとき、富姫の目に鷹狩りの一行が嵐から逃れて帰り着いたのが見える。それをながめていた亀姫が、鷹匠の持つ白鷹に興味を示すと、富姫があの鷹は姫路の富、あれを土産にしようと、脇にあった蓑を被って両手を翼のようにひろげ、ばたばたする。それを鶴と見紛うた白鷹が富姫めがけて飛んでくるのを手で捕らえ、亀姫に「たんと、お遊び」といって渡す。と、同時に下から驚きの歓声が上がり、ばらばらと矢が射掛けられてくる。続いて、銃声が響くので、天守に火がつくと見せかけようと花火線香を焚くようにいいつけると、やがて銃声がやみ、この騒ぎのうちに亀姫は挨拶もそこそこに城を去っていくのであった。
薄も侍女たちも去り、暗がりのなかに富姫一人が獅子頭に向き合ってすわり、なにかしている。遠くから童女が歌う「ここはどこの細道じゃ・・・細道じゃ・・・」が聞こえてくる他は、先ほどの喧噪が嘘のように静である。
小さな明かりが一つ、下手奥の回廊に見えたと思うと、それがゆらゆらと正面に近づいてくる。舞台に上がる階段まで達したところで明かりに照らし出されたのは、黒羽二重の紋付きに萌黄の袴、臘鞘の大小を腰にした美丈夫、姫川図書之助(平岡祐太)である。
富姫が気づいて、なに用かと訊ねる。
殿様の鷹が天守のあたりに隠れたから見てこいといわれただけだという。それなら無事に帰してあげるが、誰もここへは二度と来てはいけないと富姫。命が惜しいものばかりだから誰も来ないだろうというのを聞きとがめて富姫は、ならばお前は平気なのかとたずねる。図書之助は、殿様の不興を買って蟄居していたところ、鷹が逃げたといって呼び出されたのだ。この仕事をやり果せたら切腹を賜る約束になっているという。
人の生死はどうでもいいが、武士の切腹は嫌いだから、させたくないと富姫。それにしても、今夜は死ぬ運命のものの命を助けたと感慨にふける。
図書之助は、帰るまえに律儀にも問いかけて、富姫に会ったことを主人に話して構わないと言う了承を得ると,その場を立ち去った。
暗がりの中を戻る図書之助のまえに、なにやら黒い姿が立ちはだかり,その場から押し戻される。そこへ,鉢巻き襷掛けも凜として、手に薙刀や懐剣を構えた侍女たちが現れ、応戦するも、そのさ中に手にしていた明かりが消えて、いつしか図書之助一人が取り残される。
再び、天守に至る階段を登ると、富姫が二度と来るなと言ったはずと言う。図書之助は三階ほどまで降りたとき蝙蝠に襲われて明かりを消され、進退窮まったという。上にかすかな光が見えたので、おとがめによって命を召されようとも、怪我して不具になっては武士の面目が立たないと思い、 明かりをいただきに再度登って来たと申し開きする。
富姫はいたく感じ入って、図書之助の顔をうっとりとながめ、もう帰したくなくなったとつぶやく。
ところで何故切腹なのかと問うと、鷹匠である自分が鷹を逃がしたからだという。しかし、播磨守が世にも美しい鳥を天守に見つけ、それに鷹を合わせた結果、それてどこかへいってしまったことをお前の落ち度にするのは間違っていると富姫。第一、鷹はもともと自由に大空を飛ぶもの。大名などが独り占めしようとするのは思い上がっている。人間の命と鷹を引き替えにするとはつけあがりも甚だしいと怒る。
図書之助が返答に窮しているのを見て、富姫は、この道理が少しでもわかるなら、命を奪おうとしている下界へ帰るのはよして、ここへとどまるように勧める。
図書之助が自分の一存では図りかねるというので、迷っているなら是非もないと帰すことにする。天守で私に会った証拠の品を与えようと、傍らに置いてあった兜を差し出すとこれぞ家宝の青龍の御兜と驚き、それを捧げて図書之助、急ぎ階段を下りて回廊を闇の中に進んで消える。
薄が現れ、あの人こそ富姫の理想にかなう方、無理にも引きとどめるべきだったのではないかという。力尽くは、播磨の守なぞがやることで、「真の恋は、心と心・・・」と妖怪らしからぬ風情である。
薄が下をながめていうには、図書之助が播磨守に兜を捧げ見せている様子。ところが、図書之助の手柄になるどころか疑惑を呼んでしまったらしく、捕らえられようとしている。図書之助が刀を抜いて抵抗すると、斬り合いになり、次第に天守の建物の方に追い詰められているらしい。
まもなく図書之助は,天守に登ってくる。富姫の前に三度立ち現れたことをわび、逆賊の汚名を着せられて討たれるより、富姫の手にかかって死にたいと願うと、富姫は、私と一緒にいつまでも活きなさいとかくまうそぶり。
取りあえず、獅子頭の母衣をかぶせ、自らも中に潜り込む。すると、獅子頭の大きさに見合う二メートルを超える高さの勇壮な獅子が立ち上がった。
ちょうどそこへ討手の小田原修理(関戸将志)、山隅九平(関秀人)はじめ大勢の侍が刀、槍を構えてやってくる。獅子を見た小田原修理によると、この獅子頭には曰く因縁があった。城の二代の頃のこと、鷹狩りから帰る途中、都人と思われる艶麗な女の一行に出くわした。いずれ戦に負けた国の上﨟、貴女、貴婦人であろう、意のままにしようと捕らえると舌をかみ切って死んだ。そのときそばにあったこの獅子頭をじっと見て、自分に獅子ほどの力があったら・・・とつぶやいた。その獅子頭が女の血を舐め舐め涙を流したという話が伝わっている。それから洪水が頻発して・・・・・・という物語が続いて獅子頭はこの天守に打ち上げられ、そこは魔所のようになったのであった。
続く立ち回りは、勇壮な獅子の動きと、討手の繰り出す刀と槍のやりとりが、歌舞伎の優雅さとはほど遠く、新国劇のシリアスさとも違う、すさまじくリアリティがあるみごとな殺陣であった。殺陣は、渥美博。名のあるスタントマンであり俳優である。これを要求した白井晃の感性も高く評価していい。
荒れ狂う獅子のふるまいに難儀した小田原修理が、木彫りの精である目を狙えと号令をかけると一同が一斉に刀槍を突き上げる。たまらず、獅子頭どうと倒れ、目が見えぬと図書之助、母衣より這い出るや討手と一太刀交わしてその場に倒れる。すると獅子頭の脇にすっくと立った富姫の手に、元結いをつかまれた生首。
それを討手の前に投げつけると播磨守の首と見た小田原、山隅が自分の首はあるかと声を掛け、こんな恐ろしいところに長居は無用とあとずさりしながら引き上げる。
目をやられた富姫と図書之助は、互いに居場所を探る内、はたと抱き合い、目の見えないのを嘆く。持ち帰った首はまもなく消えてなくなり、討手は再びとって返すだろうと富姫。自分はどうにでもなるが、目が見えなくなってはあなたを助けることが出来ない。すると、図書之助はその手で殺してほしい、それがかなわねば自分で腹を切るという。富姫は、それでは私が介錯し,その手でわたしも死のうと、二人で抱き合いさめざめと泣く。
と、そこへ突然六十ばかりの優しそうな老人が現れ、「泣くな、泣くな」と言いながら腰の袋から鑿を取り出し、目をあけてやろうとかがみ込んだと思ったら、獅子頭の目のあたりを二三度打った。すると、抱き合ったままの二人の目があく。 決まり悪そうにしている二人を前に、自分は、近江之丞桃六(小林勝也)というもの、獅子頭を彫った工人、楊枝削りだと名乗る。
そして、気苦労の末は一寝入りしなさいと二人を獅子頭の母衣の下に隠し、もう少し涼しい目にして進ぜようと鑿を打つ中、月明かりもさえて溶暗。
白井晃の「こんな夢」は、唐突に現れた工人によってハッピーエンドになるが、図書之助が人間界から魔界に入ることは、果たしてほんとうにハッピーかどうかはわからないではないか。と言う理性が、おそらくプロローグの意味だったのだろう。
大正六年、泉鏡花四十四才、円熟期に書かれた作品である。
この戯曲を上演するなら自分が費用を負担してもいいと発言していたが、昭和十四年になくなるまで、その望みは叶わなかった。
初演は、戦後になって昭和二十六年の新派である。富姫はむろん花柳章太郎、水谷八重子の亀姫に、伊志井寛の図書之助、しかし、演出はなんと千田是也である。(兄の伊藤道郎と共同演出、美術は弟の伊藤熹朔)須永朝彦氏によれば「音楽はドビュッシー(「雲」だったらしい:註、中村)を用いるなどして、新派悲劇の呪縛を斷ち切つてゐる。戯曲の發掘者は、おそらく千田是也である。主宰する俳優座の上演予定演目に『天守物語』を挙げてゐたし、獨逸の演劇に詳しい彼は、この作品に、たぶん獨逸浪曼派の理想主義に通ずるものを見出だしたのであらう。」(オペラ「天守物語」パンフレット)と推察している。
これは意外だった。ブレヒト劇に怪奇譚があったかどうか覚えていないが、新劇の旗手とも言うべき千田是也が目を止めたのは、どうにも不思議なことである。バリバリの左翼と泉鏡花の取り合わせは不似合いだからだ。
僕の記憶では、六十年代末か七十年代に入ってすぐの頃か、澁澤龍彦が泉鏡花の再評価を言い出したのではなかったかと思う。同じころ、三島由紀夫や谷崎潤一郎が取り上げて賞賛していたのも覚えている。三島は、わざわざ澁澤を呼んで鏡花の戯曲について対談をして大いに宣伝しているくらいであった。(実際歴史的にどうだったのかは知らない。)
その頃僕は、耽美派が何か古くさいものを取り上げて騒いでいると感じて、何の興味もわかなかった。実際、世の中は澁澤の反社会的な嗜好に惹かれながらも(ただし、僕自身の趣味には合わなかった)それどころではない政治の季節だったのである。
その後、新派は言うまでもなく歌舞伎でも泉鏡花は取り上げられているのを知っていたが、いつだったか蜷川幸雄が「夜叉が池」をやるというのを知って、ほう、時代も変わったものだと思った。
しかし、おどろおどろしい妖怪変化の話などにつきあっているほど暇ではないとして、依然として関心はなかった。
そして、この度はじめて泉鏡花がどういうものであるかを体験したというわけである。
率直に言って、戸惑いとともに、なつかしさも感じ、なるほどこれを評価したいという気持ちがわからないでもないという気がした。
これが天守夫人、富姫の色恋沙汰を主題とした物語だということにおそらく誰も異論はないはずである。ところが、近代文学の発想から言えば、どう考えてもおかしなところが少なくとも二つはある。
まずひとつは、芝居の構成である。色恋沙汰といっても、姫川図書之助が登場するのは、芝居が半分は進行して後のことである。最初の半分は、亀姫訪問の露払い(のための不在)からはじまり、亀姫との生首賞翫と手鞠遊び、土産にする鷹を誘ういたずらまで、後半とはほぼ何の関係もない話が続く。
亀姫が帰って、いったん話は途切れたかに見える。それからようやく図書之助が現れ、その男っぷりに一目惚れして,いよいよ色恋沙汰の話である。前半の最後、鷹を捕らえるのがそれの伏線だといっていえないこともないが、全体の半分ではあまりにもバランスが悪い。
もうひとつは、妖怪と人間の恋というものが成立するのか,成就するとしてそれはどういう形になるのかという点について結論が曖昧なことである。
図書之助はどうせ切腹になるなら、天守に居続けよという富姫の誘いに最後まで迷っている。目が見えなくなって、こうなったら以上死ぬ以外にないと覚悟するが、人間はそれでいいとして、妖怪が死ぬとはどういうことか? 心中のように見えて、そこには互いに熱に犯されたような感情の燃焼がない。
どうも二人の色恋沙汰は、すれ違っているように思えるのだ。
この曖昧さを一挙に解決するのが、 近江之丞桃六の登場であった。「まあ、まあ、そんな細かいことはいいではないか。若いふたりが幸せならば。」といってなんだか無理矢理ハッピーエンドにしてしまうのである。
これもまた近代文学の文法から言えば、あまりにもご都合主義が過ぎるというものだ。
ところが、この終幕は高く評価されるべきだというものもいる。
渋澤龍彦によると、
「迷宮のアナロジーで言えば、大団円に近江之丞桃六と呼ばれる工人が突然現れて、獅子頭の目が傷つけられたために失明する二人の恋人同士を、その鑿によって救ってやるところは、まさにダイダロスがデウス・エクス・マキーナのごとく闇から躍り出たという感じで、間然するところのない作劇術の冴えを示している。この桃六の出現によって、劇全体が一挙に高い批評性を獲得したといえるからだ。」(瀧澤龍彦、岩波文庫「夜叉が池・天守物語」解説)
これには少し説明がいるだろう。
「迷宮のアナロジー」といっているのは、鏡花の作品に見える化け物と人間が織りなす非現実的な物語のことを指している。また、「ダイダロスがデウス・エクス・マキーナのごとく闇から躍り出た」というのは、まずダイダロスがギリシャ神話における大工、工人の神であること。そして、デウス・エクス・マキーナは直訳すれば、「機械仕掛けの神」だが、特にギリシャ悲劇において、もつれた筋立てを一挙に解決するために天から降りてくる神のような役者のことをいう。
泉鏡花は、明らかにギリシャ劇のこの手法を知っていて、この芝居に応用しているのである。
「桃六の出現によって、劇全体が一挙に高い批評性を獲得した」というのは、ギリシャ悲劇のような「格調ある」構造を持ったという意味なのかも知れないが、それが「批評性」とどう関わりがあるのか僕には理解が不能であった。渋澤龍彦独特の価値観が働いているのだろう。
とはいえ、このご都合主義が案外、劇の締めくくり方として、安心し納得できるというのは、なにもギリシャの方法論に遡らなくても、単にハッピーエンドであり、どうなるのかと心配したことが「めでたし。めでたし」で終わったからである。芝居見物のカタルシスというものは徹頭徹尾理屈でできあがっているわけではない。感動とは実に厄介な人間の業のようなもので、合理性を超えてなお発生することがままあるものなのだ。
このいびつでアンバランスな構造や非合理的な大団円は、近代文学あるいは自然主義の立場から見れば、ばかばかしく低劣なことになるが、考えてみれば、江戸期以前の物語には、説話にしても、謡曲にしてもこの手のことが数多く見いだされるのである。特に歌舞伎の出し物には、構成や脈絡など無視したものや、妖怪、化身、憑依等々を登場させるファンタスティックな筋立てに仕上げられているものが少なくない。
この芝居は、江戸期の戯作の雰囲気を色濃く備えているために、そういうものとしていったん了解してしまえば、大して違和感なく受け入れられると言うことではなかったかという気がするのである。
もっとも、猪苗代亀が城の主、武田衛門之介の生首をもてあそんだり、播磨守の鷹狩りを邪魔し、その家中の高官を揶揄したりする権力への「批判精神」は、もし江戸期ならまったくNGだったに違いない。そこだけには大正期の価値観が紛れ込んでいるといっていいだろう。
泉鏡花の師である尾崎紅葉が、山田美妙らと作った文学結社「硯友社」の精神は、古典回帰を目指し、専ら、通俗的で娯楽性を追求、政治むきのことは「命に替えてもお断り」するというものであり、紅葉の忠実な弟子であった泉鏡花の文学も、「偉大なるマンネリ」とか何とか言われながらもこの延長上にあったのである。
初演が新派で、しかも千田是也演出だった(さらに、俳優座の上演演目候補だった)ことから考えると、歌舞伎とは一線を画した芝居として、千田がどこかに現代批判の精神を見いだした可能性があったと思われる。しかしその後、主として歌舞伎の演目として上演されてきたのは、千田の思惑とは違って、おそらく歌舞伎ともっとも相性がよかったせいに違いない。
歌衛門の富姫に守田勘弥の図書之助が最初であったらしいが、いまでは坂東玉三郎がまだそこに活きているかのように「泉鏡花センセイ」と呼んで、鏡花の作品は専ら彼が演出まで一手に引き受けている。
さて、これが「【美×劇】─滅びゆくものに託した美意識」シリーズの掉尾を飾る作品であった。この言葉に一体何の意味があるのかよくわからないが、この作品だけは「朱雀家の滅亡」「イロアセル」という前の二つに比べて「滅びゆくもの」がはっきりしていると言う気がする。
「滅びゆくもの」とは、上に述べてきた近代以前の物語の自由な構造であり、人間と魔界の間の距離感である。それは我が国が西欧と出会う前に育んできた伝統文化であり、独自の完成された形式を持つ世界であった。それが、近代化あるいは近代自然主義文学の影響のもとで滅んでしまった。その残滓が、「硯友社」であり、泉鏡花だと言ってもいい。
この物語の背景には、姫路城の天守にまつわる妖怪伝説があり、戦国の落人伝説や自然災害についてのあるいはまた起源不明の祭りのようなものの土俗的な伝承がある。いわば、日本人が言い伝えてきた怪奇譚や昔語りや信仰にまつわる物語など広くいってしまえば古い日本人の世界観とも言うべきものの上に、そのもっとも洗練された形として成立しているのがこの芝居だと言える。
その「滅びゆくもの」に「美意識」を発見して、現代に再現して見せようというのが、新国立劇場の上演意図だったと解釈できるが、それは、古典回帰を標榜した「硯友社」の精神とどう違うのだろう。その中から見いだされる「美しさ」が、時空を超えた普遍的な「美」だと考えたいのかもしれないが、その「美しさ」を成立させている環境、時代あるいは前提というものが、変わってしまったとしたら一体普遍性はどのようにして保証されるのか。
それでもなお、絶対的な「美」は存在するとなどと言う想念が、未来に向けて何かを生み出す(Feed Forward)とは思えないのである。
「逝きし世の面影」(渡辺京二、平凡社ライブラリー、2005年)と言うロングセラーがある。幕末から明治初年に掛けて日本を訪れた外国人の見聞録を広く集め,そこから見えてくる日本の原風景を検討したもので、かつて我が国には「日本文明」と呼ぶべき生活様式があったと言う仮説を述べたものといってよい。それは、日本の近代化によってすでに「逝ってしまった」もので、もはや取り戻すことは出来ない。しかし、その逝ってしまったものがあまりに愛しくて,思わずその残り香を探してみるという思いがタイトルに込められている。
その「文明」がどのように変容していったかは、日本の近代史を見れば明らかであるが、「逝きし世」と今日に至る日本の近代のもっとも大きな違いを端的に表している(と僕が考えている)文章があるので紹介しよう。
それは、梅竿忠夫が、1984年にコレージュ・ドゥ・フランスで行った講義の中にある。彼は、日本の歴史に言及しながら「日本学」とも言うべき学問を世界に提唱するという大胆な試みをしたのであるが、その背後には上のような「日本人が独自に創りあげた」とする文明論が存在している。
「日本は、1638年の島原の乱の鎮圧後、200年間の平和を享受していたため、江戸時代の終わり頃には、戦争の哲学も近代的軍事技術も有してはおらず、そこでそれらをヨーロッパ文明にまなばねばなりませんでした。ある歴史家が、1480年から1941年までの460年間に行われた戦争の数を次のように報告しています。イギリス78回、フランス71回、スペイン64回、ロシア61回、ドイツ23回、そして日本は9回です。
これらの数字はヨーロッパ文明の発達が戦争の遂行といかに緊密に結びついていたかを、はっきりと示しています。
西洋文明がアジアの諸国をうちまかしたとき、アジア諸国の平和はふかくゆるがされたのです。
ペリー提督の艦隊の到来と開国の後、日本は、新しい戦争の考え方を、次第にとるようになりました。新しく習得された戦争の技術や哲学が、少しづつ国の性格をかえていったのです。・・・・・・」(「近代日本文明の形成と発展」1984年)
戦争の哲学も技術もない社会が、いきなり食うか食われるか弱肉強食の世界に投げ出され、それまで考える必要もなかった他国との軋轢という難題を突きつけられたのである。そして、1945年の大東亜戦争敗戦によって、直接的な戦争はなくなったが、競争にさらされ、常に他国が脅威であるという構造は今日に至るも変わりはない。世界とはもともとそれが常態であったのだ。
尾崎紅葉や泉鏡花が見ていたものは、二百年以上にわたって平和だった我が国が、そのもとで練り上げてきた「美学」であり、それが消えつつあるという強い懸念によって、その文学運動が動機づけられていると言っていい。
あれはまだ手を伸ばせば届きそうな時代であった。しかし、それから百五十年経って、僕らが見ているものは、異質で、密度の違ういくつもの層を透過してすでに屈折している光景である。
ユーロ危機もリーマンショックも、円高や財政・年金問題,震災復興もみな括弧に入れた時に成立する「美学」だからこそ現代の歌舞伎と相性がいいと言ってしまえば身も蓋もないことになるが、歌舞伎というものが幕の内弁当のおかずを肴にぬる燗をちびりちびりやりながら半日掛けて見物するものであった平和で牧歌的な時代のものであってみれば、「滅びゆくものに託した美意識」などという想念も随分と浮世離れしたテーマに見えてくるのである。
ただ、そうした新国立劇場の思惑に抗して、白井晃の演出は「滅びゆくもの」を描いたわけでも、「美意識」などと言う気取った思い込みにとらわれてもいなかった。
それは、魔界の住人といえども登場人物にことさらそれらしい意匠を施してはいなかったことに端的に表れている。亀姫の着物は泉鏡花がもっとも得意とする生地や柄の記述に忠実ではあるが格別のものではなく、メークに至っては田舎娘のそれのようにリアリズムであった。薄にしても、侍女たちにしても「滅び」すなわちある種の退廃を感じさせる異様なところを描こうとはしていなかった。
富姫に至っては、篠井英介のキャラクターもあっただろうが、実にあっさりとした下界の観察者に終始した。
そうしたことからうかがえる白井の演出意図はおそらくこうである。
魔物の住む幽玄の世界が、ダイダロスの作ったラビリンス=迷宮のようなどこか官能の誘いを匂わせる妖しい光を放つものと描くよりは、そこが好きなように遊び、自由に行き来できる束縛のない楽園と強調することによって、 図書之助の生きている社会(時代あるいは現実といってもいい)を支配している倫理の理不尽さや不合理、残酷さが際だって見えるようにしたのである。
この魔界と人間界を逆転させるという大胆な解釈によって、むしろこの芝居は渋澤龍彦の言う「高い批評性」を獲得したのではないかと僕は思う。
篠井の女形ははじめて見たが、見事な台詞回しであった。ただし、所作ふるまいについては、我が国伝統の女形に備わった踊りの素養やしなやかさを感じさせるものに乏しく、芝居が中劇場の大きさを支配するスケールに至っていなかった。
凛とした女の気っ風、辰巳芸者のような心意気、臈長けた女の気品などというものが一朝一夕に出来るものではない。こればかりは歌舞伎に任せざるをえないところで、どうも無い物ねだりなのかも知れない。
それにしても、白井晃の冷静で理性的な解釈と演出が、新国立劇場の意図を凌駕したことはもっとも愉快なところであった。ひょっとしたら、千田是也がつくったイメージに近いものだったかも知れない。と言うのも、あの千田是也がまともに泉鏡花をやろうとは思えないからだ。ということは、白井もまた一筋縄ではいかない男ということか?
