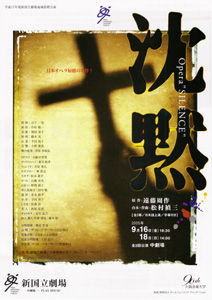
|
題名: |
沈黙 |
|
観劇日: |
05/9/16 |
|
劇場: |
新国立劇場 |
|
主催: |
新国立劇場 |
|
期間: |
2005年9月16日〜9月17日 |
|
原作:
|
遠藤 周作 |
|
作: |
松村 禎三 |
|
指揮:
|
山下 一史 |
|
演出: |
中村 敬一 |
|
美術: |
増田 寿子 |
|
照明: |
木段木 実 |
|
衣装: |
半田 悦子 |
|
音楽・音響: |
小野 隆浩 |
|
出演者: |
小餅谷哲男 新川和孝 井原 秀人 桝 貴志 松本 薫平 石橋栄実 野間直子 田中勉 青木耕平 寺内智子 松森治 西尾岳史 安川忠之 雁木悟 |
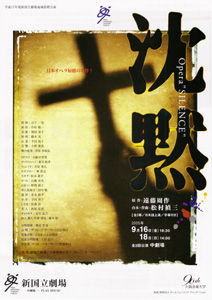
「沈黙」
オペラを見たのは初めてだ。嫌いなわけではないが機会がなかった。イタリアオペラもドイツオペラも言葉がわからなくては面白くないだろうと思ってわざわざ行く気にならなかったのだ。もう何年も前になるが「アリア」というオムニバス映画があった。いくつかのオペラをテーマに数人の監督がオリジナルの映像を作って曲を重ねるというやや趣味的な映画で、僕はこれを試写会で見たのだが、劇場に客が入ったかどうかは知らない。この中の、ラスベガスの夜の極彩色のネオンをバックに若い男女がオープンカーに乗っているスローモーションの画面に「トリスタンとイゾルデ」のアリアがついていたのを見て感激した。翌日フィリップスのCDを買って、しばらく聴いていたがそのうちに厭きて、今どこにあるかわからない。
「沈黙」がオペラになったのは話題になったから知っていた。しかしこれをどうすればオペラ=歌劇に出来るのか不思議であった。このオペラはよくある色恋沙汰を扱ったものではなくて「信仰」の問題がテーマである。キリシタン弾圧の辛気臭い話と神の存在を問う深刻な宗教的苦悩が歌われるのでは見ているほうもしんどいに違いない。と思っていたが、実際は、案に相違して骨格のはっきりした、極めて完成度の高い劇として成立していた。スコアを書いた松村禎三が「渾身の力を込め、十三年の歳月を費やして」完成させたというだけあって、曲の出来もそうだが、何よりもテーマの深さと構成の明快さによって、観劇後の満足感が大きい。ちょっと変な言い方だが「松村さんは頭がいいなあ。」というのが率直な感想である。
ザビエルが日本にやってきたのは16世紀半ばで、秀吉がバテレン追放令を布告するまで約40年あったが、信長が奨励したこともあってこの間に大名をはじめ西日本の庶民に燎原の火のように広まった。文明の生態史観で宗教は伝染病にたとえられる。なるほど相当強い伝染性の有る教義だったのだ。
秀吉が突然これを禁じた理由は、歴史の教科書では習わなかったような気がする。最近は「カソリックは領土に野心があった。」とはっきり書くようになっているらしい。実際日本に来る宣教師は中国沿岸に作った占領地を拠点にしていたし、まもなくフィリピンを植民地にしたスペインは、教会を中心に国中でひどい収奪と圧制を繰り広げた。こういうことが日本に伝わらないはずがない。任務のことを「ミッション」といってしゃれたつもりの若者がいるが、権力者の手先になって侵略と虐殺の露払いをした坊主の「仕事」のことをさしているわけで、それを思えば、僕の場合はとても口にする気にならない。
しかしまあ、突然禁止された方は迷惑な話で、すでに伝染したものは、心の問題だからおいそれと元には戻れない。なぜ信仰がダメかといえば理屈もくそもない、一大勢力になりそうだったから権力が恐れただけのことである。信長が一向宗に手を焼いた記憶は家康ム家光にとってもまだ鮮明だった。
この歌劇の舞台は、江戸初期の長崎の周辺である。島原の乱にはまだ遠い。あれだけの弾圧をしたのだから当然転向者、信仰を捨てるものも多数いたはずである。その転向の話である。
マカオにいるポルトガルの若い宣教師ロドリゴ(小餅谷哲男)は、音信が途絶えた恩師フェレイラ(井原秀人)の安否が気になり、神父ヴァリニャーノ(新川和孝)に申し出て、日本人のキチジロー(枡貴志)を案内人に長崎に向かう。
この第一場のテーマの措定の仕方が物語の起点として極めて論理的であり、惹きつけるものがある。まだ見ぬ日本への期待と不安、尊敬する恩師の行方がわかるかどうか、この揺れる心を歌う船の上での独唱が美しい。
うまくトモギ村に潜り込んだロドリゴは、しばし村のキリシタンとともに神に祈りを捧げる幸福な日々を送る。その中には若い茂吉(松本薫平)と許嫁のオハル(石橋栄実)がいた。愛し合う二人の周囲には笑いが絶えず、未来は明るく輝いているように見えた。
この起承転結の「承」に当たる部分がつかの間の平和を歌っていて、解放感がある。次にやって来る災厄によって、この平穏な日々の幸せがいっそう際立って見えるように構成されているのは、演劇的で説得力がある。
やがて、長崎奉行井上筑後守(田中勉)の手が迫りキチジロー、茂吉を含む4人が捕らえられる。踏み絵の前につれ出され、取り手に促されるが、茂吉はこれをついに踏めない。転向を迫る拷問にかけられるが、それにも応じなかった。キチジローは、躊躇した揚げ句、聖像に足をかけ許される。茂吉と後の二人は、水磔にされるべく十字架に縛りつけられ海に立てられるが、それを見ていたオハルが半狂乱になり、「マリア様はおらんと?デウス様はおんなっとやろか?」と天に呼びかける。茂吉は「参ろうやな。参ろう。ハライソの寺に・・・」と歌いながら満ちてきた海に飲み込まれていく。
キチジローの密告によって、ロドリゴはとらえられる。まもなく井上筑後守がやってきて、フェレイラはすでに信仰を捨てたと告げ、ロドリゴにも転向を迫る。ある夜、牢にフェレイラがやってきた。まげを結い、着物を着ている。それには驚いた。さらにフェレイラは「日本人にキリストの教えは根付かない。神の存在を理解することが出来ないのだ。」という。もはやあの信仰篤い恩師の姿ではなかった。ロドリゴは裏切りを許すことが出来ない。そして、転向を拒むロドリゴは独房に閉じこめられる。その獄のどこからか低いうなりのようなものが絶えず聞こえて来る。そこへフェレイラが現れ、「あの声は、逆さ吊りにされた日本のキリシタンのものだ。この獄の下で、耳を切られ、少しづつ血を流して死んでいこうとしているもののうめき声だ。お前が聖像を踏めば、直ちにこれは中止される。」と迫る。
何という拷問だ。ロドリゴは神に呼びかける。「あなたは、どこにおいでなのだ。あなたはほんとうにおられるのか?」有らん限りの声で問いかけるが、かえって穴吊りにされたキリシタンのうめき声がロドリゴの耳に迫ってくる。
ロドリゴは、苦悩の中で「これはキリストの愛と同じ行為ではないか?」と気付く。これは究極の愛を実行することなのだと納得し、おのれの信仰と引き換えに聖象に足をかけるのであった。
物語はここで終末を迎える。これ以上何を描くことが出来るか。ロドリゴは抜け殻となってこの先を生きていくのである。
キチジローの裏切りは、ユダにたとえられるともいわれるが、そんなことよりもロドリゴが捕らえられ、フェレイラがすでに棄教していたという驚くべき事実が明らかになるという展開から、いっきに大勢の信者の命と信仰を引き換えにする、という究極の選択を迫る大団円に登り詰めていく構成が実にドラマチックで、物語の悲惨さはともかく、見ていて気持ちがいいくらいである。そして、ロドリゴの苦悩(歌うことによって、より深く心情を表現することができて、観客は感情移入しやすくなる。)と誰もが納得の出来る彼の翻意によって、物語は「すとん」と終わるのである。
ここでロドリゴとともに悩み苦しんできた観客は、カタルシスの余韻を十分に味わうことが出来る。
松村禎三は、この歌劇のために原作になかった「オハル」を創作した。なるほどこの若い無垢な女を登場させたことによって、殉教者茂吉の存在は、より悲劇性を帯びた。さらに村人の群れに、唯一の華やかさを添えた効果は極めて高いというべきであろう。
また、原作は、この劇が終わった後の章を長く書いているらしいが、それを省略した。遠藤周作は、ロドリゴがあの後の日々の中で、自分はなぜ転向したか、それが正しい行為だったか否かを反芻させているという。(遠藤の抹香臭さというか宗教臭さが嫌いで、エッセー以外はまったく読んでいない。) 遠藤周作にとって、それこそがテーマだったのだからむしろ後半に力が入っていて当然だろう。
しかし、松村禎三はそれを無視した。信仰を持っているものともっていないものの違いである。
遠藤周作は、十一歳で洗礼を受けた。物心ついている年代とはいえない。大人になっていろいろと知恵がついても子供の頃宗教に染まったものにはいつでも「神」がそばにいる。(長く生きていると、気配でわかるものである。) 振り払ってもなお、神はついて回るのである。遠藤は慶応の仏文で、パリに留学したくらいだから「実存主義」を知らぬはずはない。一方で、そういう思想に迫られながら、しかし神の存在を否定しきれないというのが、十一歳洗礼の後遺症であろう。
実存主義で思い出したが、ジャン・ポール・サルトル「悪魔と神」の中でも似たようなことが出てくる。確かゲッツ・フォン・ベルリッヒンゲンがこう叫ぶ場面である。
「おれは天に向かってしるしを求めた。しかし、神にはなんの応えもない。・・・」サルトルにとっては神がいようがいまいが俺には関係ないというのだから、こういう言い方は当たり前だったろう。それが近代というものである。
つまり欧州近代化とは、近代科学の発展と同時に、せんじ詰めれば神の不在を証明する思想的営為であったわけで、松村禎三はこのことを十分承知していた。
神が存在しようがしまいが、ロドリゴのような究極の選択を迫られる場面は、生きていれば必ず、何回かはあるだろう。ロドリゴは苦悩の末に最も人間的な結論を選択した。それでよかったかどうかはくどくど悩む必要はないというのである。いや、だからといって超越的なものを否定しているわけではない。それへの畏れを十分認めながら究極的には己がおのれの人生を選択しなければならない、というのが作者の世界観ではなかったか。僕らが深く共感したのはそのことだったに違いない。
オペラにもプロンプターがいたので少し驚いた。袖から大きな声が聞こえた。メロディはさすがに全部入っているだろうが、歌詞まではなかなか・・・。
最初に見たオペラがこれで本当によかった。
カーテンコールで、松村さんがステージに上がっていた。小柄で少し足下がおぼつかなかった。高齢だから心配だが、世界に誇れる作品を残してくれたと思う。
2005年11月3日
