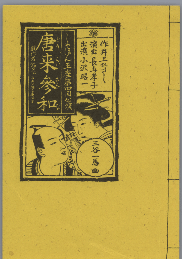
|
題名: |
唐来参和 |
|
観劇日: |
00/10/20 |
|
劇場: |
紀伊国屋ホール |
|
主催: |
シャボン玉座 |
|
期間: |
2000年10月2日〜 |
|
作: |
井上ひさし |
|
演出: |
長与孝子・木村隆 |
|
美術: |
石井強司 |
|
照明: |
服部基 |
|
衣装: |
|
|
音楽・音響: |
深川定次 |
|
出演者: |
小沢昭一 |
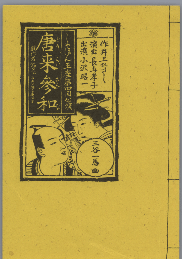
「唐来参和」
十年以上も前にはじめてみたときは、感激して友人知人に触れ回ったものだ。だから、いまでも印象は鮮明に残っている。 あの時の演出はこうだった。
舞台の上には、吉原大門の向かいにあるというお信の住むしもた屋がしつらえてあって、まだ照明りは入っていない。舞台中央が明るくなると、上手の袖幕から、額に手ぬぐいを載せた小沢昭一が顔だけのぞかせて、客席をぐるりと見回す、と、いい客入りだといわんばかりに「へへ、へえー」と澁声で笑い、一呼吸置いて、出てくる。出ばやしこそないが、どんな名人でもかなわない、見事な間合いであり粋な出である。
天気の話、世相の移り変わり、時事放談から艶話、そして得意の江戸物売りの声色とすすんで、話が浅草、吉原大門にさしかかるころになると、急に闇が迫った空から白いものがちらほら舞ってきて、明りが落ちると思うと、くるりと向こう向きになり、着物の裾を下ろして、襟を抜く。白が頭に団子を乗せたかぶり物を素早く被ってこちらを向くと、もう六十にはなろうという婆さんに早変わりだ。手ぬぐいの端を銜えて、姉さんかぶりをつくりながら、家の中に向かうと、そこではじめてお信の長家に明りが入る。
上がり框に三つ指をついて身体を二つに折り曲げ、「御奉行所のご紋所のある黒の丸羽織に着流し、御腰にはお刀と緋房の十手、そしてバラ緒の雪駄・・・、八丁堀の定廻りの同心(だんな)でございますね。この婆が、しん粉指のお信でございます・・・ハア? さすがは昔、吉原〈なか〉の扇屋で鳴らした花魁だけあって、とても婆には見えない? いやですよ、冷やかしちゃあ。・・・」と小説「唐来参和」のものがたりが始まるのである。
小沢昭一は、この小一時間の「まくら」で芸の限りを尽くして楽しませてくれた。落語家のまくらはその時の思いつきや気分次第のところがあって善し悪しがでるが、小沢昭一はおそらく何度も吟味して磨いた一言一句を、稽古に稽古を重ねて完成させ、寸分たがわず舞台にのせている。しかも、そういう緊張感はみじんも見せない、珠玉の話芸というべきであった。
井上ひさしは、原稿用紙わずか四十八枚に足りない短編を舞台にかけると聞いて、唖然としたようである。小説と劇作、二足のわらじを履く自分は、この素材は一人称の小説という形式を求めていると判断したというのだ。
小沢昭一は、この天の邪鬼、ひねくれ者の黄表紙作家唐来参和の一代記を既にラジオドラマとして演じていたが、これにこっけいで、やがて悲しい落語の人情ばなしの要素を重ねていたのであろう。この本編にまくらをつければ十分舞台は成立すると思った。本編は既に出来ている。まくらの重要さはいうまでもない。
この幕開けから早変わりまでの語りは、何度みてもいいと思っていた。それが、意外なことに今度はすっかり様変わりしていた。
唐来参和は、赤穂浪士討入りの時に、吉良の息子が養子に入った上杉家の用人だった。その元禄のころの江戸はどうだったのか?吉原はどんなところだったのか?唐来参和が生きた時代を、話の背景として、まず分かっていただきたいというつもりの、まくらというよりは解説ではじまった。
装置は多分同じものだと思うが、違いといえば長屋の入口に、幅七、八寸長さ六尺ほどの板が何枚も立て掛けてあるのが新しい。 話が肝心なところにさしかかると、この板を手に取りすばやく裏に返えして、客席に示す。それにはたとえば「傾城」とか「猪牙船」と立て看板の様にかかれていて、傾城は花魁のこと、猪牙船は柳橋など大川を通って吉原のある日本堤通称土手まで漕いでゆく非常に小型の船などと蘊蓄が語られるのである。
無論話芸は申し分ないが、江戸の風俗や吉原の様子など承知の事柄なので、このまくらには少々落胆した。
早変わりはそのままだが、長屋の家の壁にも、何枚も板が立て掛けてあって、「どうさびき」と語られると同時に自然に手が動いて板を裏返して「礬水引き」を見せるという演出が加わった。つまりまくらの延長である。これが何枚も用意されていて、とうとう最後まで途絶えることなく「解説」が繰り返されたのであった。全部で百枚はあったように思う。
井上ひさしは、読み手あるいは観客の心理をよくわかって書く作家である。どう書けばどういう疑問が湧き、それを解消するにはこう書けばいい、というルールを外した小説も戯曲も僕はみたことがない。 礬水引きのような常識にない言葉は、膠と明礬水を混ぜたものを和紙に塗って、版刷りの顔料の滲みを押さえるものだということを極く自然に文章に埋め込んでおくものだ。「起請文」や「蔦屋重三郎」しかりである。
はじめてみたあとで、地方廻りをやっていると聞いたので、東京に近いところならいこうと思っていたが、十年の間その機会はなかった。 そうして、このとき目まぐるしく立て看板を見せられて「どさ回りから帰ってきたらこんなにも野暮になっていた!」と思わず愚痴ってしまいそうだった。 「江戸時代の言葉が難しい」とか「時代背景が分からないと、面白さが伝わらない」とか「しゃべっている言葉にどんな漢字があてはまるのか」とかいろんなことをいう人が現れて、とうとう解説付きになってしまったのだろう。文部省の指導要領みたいなものだ。
僕らは、志ん生も文楽も先代の金馬も知っている。宝井馬琴だって聞いたことがある。〈先代の虎造には間に合わなかったが、テープは持っている。〉あえていうと日本人なら山本周五郎や池波正太郎、藤沢周平あたりを読むのは当たり前でしょう。
井上ひさしの「唐来参和」を解説されたい野暮は、豆腐の角に頭をぶつけて死んじまえ!である。 と書いて、暗然とする思いもある。
当節、落語家はテレビで座布団を奪い合っているばかりだし、いい年の大人が電車で読んでいるのは漫画ばかりである。若者にとっては、人情ばなしこそ野暮の骨頂ということになっているのかもしれない。
だからこそ小沢昭一の話芸を聞いてもらいたいと切実に思うのだ。この おかしくてやがて悲しいものがたりは、あなたの中の深い深いところにしみ込んで、生きるとは?という根源的なテーマと響きあうはずだ。ところが、もったいないことに「唐来参和」はこの公演をもっておしまい、なのだそうである。
日本はどうなるのだろうか?
何だか非常に不安になってきたので大急ぎで筆をおいて、よく思案してみることにする。
(1/28/2003)
