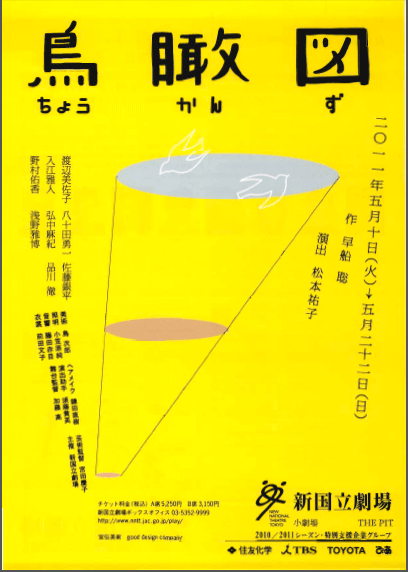
「鳥瞰図」
忘れないうちに書いておくが、入江雅人の髪はなんだ! 僕が演出なら「さっさと前髪を切ってこい!」と言ってやるんだが・・・・・・。あれでは学生か、職業不詳の遊び人か、売れない小説家である。仮に船長としても、客が釣りをしている間、操舵室にいて文庫本でも読んでいそうな風体で、とてもつきあう気になれないタイプである。
2008年の初演を見て書いた劇評は、隔靴掻痒。言いたいことをもっと直裁に明確に書くべきだった。
「同じ時代を生きる、新しい世代の劇作家と異世代の演出家によるコラボレーション企画」「シリーズ・同時代」と銘打った若手三人による書き下ろしのひとつであったこの芝居が、はたしてどのような「同時代」を描いたのか?ということを問うべきだった。そして、この再演が三月の地震による「浦安、液状化」の影響を受けたのか、それとも、実はしっかりとした土台の上に立っていて、びくともしなかったのか、それを論じる必要がある。
まず前回、島次郎の舞台美術が真に迫っていてすばらしいと書いたが、それもそのはず、浦安にある釣り宿「吉野屋」をそっくりそのまま写したものだと分かった。前回は、島次郎の守備範囲が広いとほめたが、半分くらい減額しなくてはならない。
さて、物語は2008年の劇評で要約してあるが、読み返したら、ほぼそのまま使えるので再録をお許し願う。
舞台は、遊漁船をやっている釣宿の店先。上手半分が安物のパイプ製テーブル椅子がいくつかおかれた場末の食堂風。鴨居の上に昔の東京湾の風景と思しき古い写真が一枚、大物の魚拓数枚の間にならんでいる。端に流しがあり、その横に釣り竿が何本も立てかけてある。舞台奥が通りに面した出入り口でそこにも釣りの道具がぶら下げてあったり、脇にアイスキャンディの冷凍ボックスが置いてある。
下手半分は上がり框から上が畳敷きの居間になっていて、ちゃぶ台やいまはなつかしい茶箪笥、テレビに仏壇まで置かれている。奥には台所の流しと、洗面台、二階に通じる階段があり、一家の生活があからさまに見えている。
東京湾の古い写真は、この辺りがまだ埋め立てられる前の風景であり、かろうじて干潟が残っていた手つかずの自然と、同時に三代に渡って続けられてきたこの釣宿のひとびとの過去を物語るものである。
かつて海であったところには、いま道路ができて高層ビルやいわゆるタワーマンションが建ち並んでいる。游漁船が係留できて海に出られる水路は確保されているが、街の様子は一変し、それが人々の心にも微妙な変化を及ぼしているという予感が、この劇の背景にある。
釣宿升本の女主人佐和子(渡辺美佐子)は既に七年前、連れ合いをなくして、いまは息子の茂雄(入江雅人)に三代目の船長をまかせている。茂雄は四十代半ば、子供がないために近所に住む勇太(佐藤銀平)を雇ってゆくゆくは店を任せようと考えている。勇太も船舶操縦免許をとろうと勉強しているのはそのつもりがあるからだろう。
常連の客は皆近所に住むものばかりで店はいわば彼らのたまり場になっている。医薬品の問屋に勤めるサラリーマンでそばの高層マンションに住んでいる杉田(八十田勇一)は、浮気が見つかって目下のところ妻と冷戦状態にある。家を追い出され車で寝たこともしばしば。釣りが唯一の息抜きで緊張から解放されるときという。子供もいないので出て行かれても仕方がないと思っているが、なぜか別れようとはいわないのだそうだ。お盆は妻の実家で過ごすのが習慣になっていて、そのたびに早く子供を!といわれるのがつらいという。妻はその期に及んでも曖昧な態度でごまかしているというから、杉田としてもそれに合わせていざるを得ない。じつは三年もセックスレスなのだ。別れ話に発展しない宙ぶらりんの状態を存外楽しんでいる様子も見える。杉田は、これらのことをあけすけに語って聞かせる。
朝子(弘中麻紀)と照之(浅野雅博)の姉弟は小さい頃から家族ぐるみの付き合いがあった。最近母親が亡くなったが亭主、つまり姉弟の父親と一緒の墓に入るのは嫌だといっていたのを朝子が覚えていてまだ納骨をすませていない。朝子も照之も釣り好きで、しょっちゅうこの店に出入りしている。
朝子は地元のカーディーラーでセールスの仕事をしているが、話し振りによるとなかなかのやり手らしい。しかし、夫とは別居中で、大阪の夫の実家に小学生の一人息子を預けている。子供を取り戻して別れようと思っているが、息子はいまの生活にすっかりなじんでしまっているという。上辺の元気のよさの裏にはキャリアウーマンらしい苦悩が潜んでいた。
弟の照之はそういう姉を心配して同居しているが、サラリーマンの身の上で、転勤話が持ち上がっており、どこになるかはともかくそれを機会にいまの恋人と結婚しようかと思っている。
もう一人、峰島(品川徹)という老人がぽつねんと店の椅子に腰掛けている。いたと思ったら、ふらふらとどこかへ消えている。茂雄は、佐和子がこの老人から乗船代をとっていないことに気づいている。佐和子はそのことを責められて、峰島が元漁師だったから海に出たいのはしようがないではないかと理屈にならないことを言う。
この辺り一帯が埋め立てられることになった二十年ほど前に、峰島は反対派の急先鋒だったという。周りが切り崩されても最後まで抵抗していた。そこで孤立して近所の評判も悪くなったらしい。抵抗しても勝てる戦ではない。いくらか保証金を手にして、以来行方がわからなくなっていたが、二三年前にすっかり年老いた姿でこの街に現れたのであった。
佐和子はいきさつを知っている。漁師が働く場所を奪われたと思って同情しているのだ。だからせめて海に出たいなら出してあげようと思ったのである。茂雄はそれ以上追求しようとしない。
これらの人々の日常の中に、ある日突然一人の若い娘が飛び込んでくる。劇の主筋はここから始まる。
佐和子はとたんにそわそわと落ち着きがなくなり、仏壇の前で何かし始めたり急に台所に立ったり、外出したりしはじめる。
娘は二十歳、ミオ(野村佑香)といって、佐和子の長女波子の子であった。波子と茂雄の父親は彼らがまだ幼い頃家を出たまま帰ってこなかった。佐和子はしばらく待ったが、自分の不安と寂しさ、さらに子供の将来のことを思って、釣宿に入ったのであった。茂雄は小さかったので父親の記憶は全くない。しかし、物心ついていた波子は風景写真家だった父親を慕っていた。子供ながら佐和子の裏切りを心の底で許していなかったのだ。
波子は学校を出ると家を出て、消息を絶った。それがつい二三ヶ月前に車を運転中に事故でなくなったという知らせが入ったのだ。脇にミオが同乗していて怪我を負った。その傷が癒えると、にわかに思い立って母親の育ったところに初めて訪れたのである。ミオは母親の中に潜んでいる、あるかたくなな部分に違和感を覚えていた。そのために自分たち親子の間には溝があると思ってきた。いつか確かめようと思っていたが、事故でそれはかなわなくなった。そこで、手がかりを求めるつもりで祖母佐和子のもとを訪れたのである。
ミオは波子の父親と同じ風景写真家の道を歩もうとしていた。おそらく母親はミオに、幼い頃この辺りの風景を撮影する父親の姿を語ったに違いない。蛤やアサリがたくさん採れた干潟のことやおびただしい数の野鳥の群れがそこで羽を休めていたことなど。ミオは、毎日カメラを手に出かけていった。そんな風景はどこにも見つからないのに、である。
ミオが来ていることを茂雄が気を利かせて父親の片岡に知らせていた。そこからミオがなかなか自分の家に帰らない理由がわかる。事故から何か月もたたないうちに片岡が女を家に引き入れたというのである。ミオにしてみれば父親に裏切られた思いである。
一方、茂雄はこのまま釣宿を続けるのは困難と判断したので、とりあえず二艘ある舟のうち新しい方を処分して、勇太には跡継ぎをあきらめてもらうといいだした。唐突な言い分に佐和子は驚くが、これには何か裏がありそうだ。それでなくても、ディズニーランドで小さな女の子をつれているところを朝子に見られていたり、パチンコにいくといっては頻繁にどこかへ出かけていくので皆に変だと思われていた。そのうちに杉田に、近所のある病院にいるところを見とがめられる。
佐和子が問いただすと、六年前に別れた妻の良美が子供を連れて戻ってきたが、末期がんで入院しているというのであった。子供はフランス人とのハーフで自分の子ではない。茂雄が面倒を見るいわれはなかったが、入院費やら保険のきかない薬代などを負担してやっていた。足りなくなったために舟を売って充当しようとしたのである。しかし、それももはや手遅れで手の施しようがなくなったようだ。
佐和子はそのことも波子のこともみんな自分のせいだと過去の自分の選択を否定するように嘆く。茂雄はそれをきいて、俺の父親はあっちだよと仏壇をさして、佐和子の選択は必ずしも間違っていなかったことを告げる。このとき、いなくなった佐和子の連れ合いには、元々妻がいたことが明らかにされる。
峰島がアパートでなくなっているのが発見される。一週間たっていた。すでになくなっていたと思われる日に峰島が現れて、昔の思い出を語って帰るということがあった。(この場面は、今回挿入されたもののようだ。)
夕方、ミオが外出から帰ってきた。
峰島から聞いた昔の風景のかけらもなかったという。夕飯の支度をしようという佐和子に、突然ミオはふたりで写真を撮ろうと言い出す。戸惑う佐和子をよそにカメラの準備をするミオ。そして、二人は並んで一つの画面に収まった。
突然告げられた娘の死、唐突にやってきた初めて目にする孫にどう対処していいかうろたえるばかりであったが、ここに来てようやく肉親としての情がわいてきたのである。家族あるいは血のつながりということが、どうしようもない事実として、ある種の幸福感を伴いながら、突きつけられる終幕であった。
当時の芸術監督である鵜山仁が提案した「シリーズ・同時代」とは、どういうコンセプトであったかもう一度確認すると、「同じ時代を生きる、新しい世代の劇作家と異世代の演出家によるコラボレーション企画」ということであった。
有り体に言ってしまえば、若い作家の作品を年長者が演出するとどうなるかということなのだろう。しかし、それが何故「同時代」なのかは、理解できない。僕がバカだからかもしれないが、鵜山仁には理解できないことが多い。この際そういうことを言っても始まらないから、勝手に解釈して進めることにする。
「同時代」とは世代にかかわらず、文字通り「現在」を対象化して「考現学」的に批評を試みることによって見えてくるある表象=イメージと言うものだといえる。
そうはいっても、このシリーズ三作品(他に「まほろば」「混じり合うこと、消えること」)に共通しているテーマは具体的に「家族」である。従って、「同時代」などと大上段に振りかぶらなくても、「家族」というものの「現在」はどういうものか?というのが企画の意図だと言っても不都合はあるまい。
早船聡によると、プロデューサーの鵜山から本を書くに当たっていわれたのは「伝承」とか「民話」という言葉だったので、「遠野物語」のような田舎に伝わる物語を題材にしようとしたらしい。これは、「まほろば」に反映されていることだから、同じことを蓬莱竜太にも言ったとわかる。何故こんなことを言ったのか、推量するしかないが、おそらく「家族」の「現在」を浮き彫りにするには「過去」と比較してその「変化」を描かなければならないという判断だったのだろう。つまり、「通時的」にはどうなんだと言うことを検証しようとしたのだと考えられる。
早船は、遠いところでは取材しにくいことがあったため、検討しているうちにだんだん東京に近づいて、多少の土地勘があった浦安に決めたといきさつを話している。(シアタートーク)
浦安は、山本周五郎(好きな作家)が住んだところで「青べか物語」も読んでいたから、埋め立てられる前の様子がイメージできる。また、干潟は渡り鳥の中継地だったという消えた「過去」を「伝承」として使える。それらのことがあって「鳥瞰図」というタイトルも決まったのだそうである。
前回劇評で、何故「鳥瞰図」なのかということに、こだわったのかといえば、何を隠そう鵜山仁が書いた文章が意味ありげだったからである。
「空の高みから見下ろした時、人間の喜怒哀楽は一体どんな色や形に見えるのだろう。われわれ一人ひとりの心の中で起こっている葛藤とはちょっと質の違う、群れて、離れて、また集まって、ちりぢりになってを繰り返す、まるで干潟に集う鳥たちの生態を観察するような視点、世界を何万分の一の縮尺で見るような醍醐味、それはすなわち人生を一人の一生の単位ではなく、「人類の歴史」的な長さで一望する面白さに通じるのだと思う。
宇宙から見た地球には国境線がないと、言われてみれば当たり前のそんな話を聞くと、われわれはなんだか神様の目を持ったような気分になって、ついつい神々しい、超越的なものの見方をしたくなる。お天気も、環境汚染も国境線を超越しているから、これはこれで確かに大切な、それこそユニヴァーサルな視点なのだろう。ただし、鳥たちは、宇宙船と違って空気のない高さを飛ぶことはできない。奴らは神様と人との間にいて、良くも悪くもわれわれと同じ空気を吸っている。だからこそ心は地上にあって、うごめきぶつかり合う一人ひとり、一羽一羽と同じ高さの目線を保つことができる。
鳥瞰することによって初めて見えるものに、一方そのことによって見過ごしてしまいがちな小さなもの、ささやかなもの、隠されたものにも同時に心を配り続けたいものだ。」(初演パンフレット「鳥瞰する」全文)
この文を読んで、何が書いてあるかを解説してくれる人がいたらお目にかかりたい。
鳥の目になって、人間を空からながめたらどんな風に見えるかということを書いていることは分かる。
当然、人間は地上をうごめく点のような大きさにしか見えないだろう。それを「人の群れ」と言おうと「人類」と言おうと、一人ひとりに帰属している喜怒哀楽が何色にも見えるはずがないのである。ひとりひとりにどんな人生があるかなど見えない視点が、つまりは「鳥瞰」ということで、そこから見たら、ただ、人は男も女もなく、ちっぽけな虫のようにうごめいているだけに決まっている。
こういう解読不能の文章にこだわって、前回はこの劇と「鳥瞰する」ことの意味を考えたのだが、全くの徒労であった。タイトルは、せいぜいが渡り鳥の中継地であったことから来る連想に過ぎないのである。
これが目くらましになって、この劇に対する不満を十分に書けなかったことを反省して、今度は感じたままを述べることにする。
まず、この劇には、浦安が干潟を埋め立てた土地であることに対する文明批判のような視点がある。
鳥が群れる広大な干潟の航空写真が梁にかけられていて、おそらくそれが昔の浦安なのだろう。それが人の手で埋め立てられた。もう二度とその自然は帰らない。ラムサール条約違反ではないか?これはひどい、ひどすぎる。なんてことをしてしまったのだ!
と、人は思っただろうか?
もしも干潟を埋め立ててできた浦安の土地が、人類(文明)の愚かさを象徴しているとしたら、高層マンション群も、整然と区画整理された(高級と言われている)宅地、それにディズニーランドとホテル群も負の遺産として批判の対象にならないといけない。
「あれは、渡り鳥の死骸の上にそびえ立っている豊かさという名の虚構に過ぎない!」
そして、この再演に当たって、液状化は気の毒だが、「天罰だ」と峰島に言わせたらどうだったか?
しかし、そこまでの徹底した文明批判は早船聡にはない。
それもそのはず、その手の狂信的な自然崇拝主義は、工業化産業化社会には有効に作用したが、現在のような情報化消費化社会にはトゥマッチといわざるをえない。環境アセスメントを徹底しなければ、世界中に非難される時代である。守るべき自然は守るというのが世界の一応のコンセンサスであろう。
さすがにそういう認識はあったと見える。
確かに、「かつて」浦安には海があり漁民がいて干潟もあった。
峰島の存在は、その「かつて」を象徴するものとして登場させたに違いない。
では、一体それがどうしたと言いたいのか?この劇のいわば「芯」に当たるところかもしれないのに、その「思想」が抜け落ちている。
魚がとれなくなり、海によって暮らしが立たなくなったから、漁業権を売ったのではなかったのか?その結果、何倍も造成された土地にやってきたのは、全く別の町の人々であった。今の浦安に、旧浦安市民など一握りもいないだろう。そういう新しい町に「伝承」などあるはずがない。かつて干潟があったという「記憶」も存在しない。「記憶」を掘り起こして懐かしむ人さえいない。
峰島老人が亡くなって、ここが海だったことを証言するものはいなくなった。そしてその記憶は忘れ去られていく。峰島がぶつぶつ言っても、歴史は一区切りついたのだ。「伝承」すべき何ものもなかった。それは「新しくはじめる以外にない」ということなのではないか。
液状化が「天罰」であろうがなかろうが、ひとはふきだした泥を片付けて、傾いた家屋を直し、どうにか生きていかねばならない。それを高みの見物と決め込んで見ている鳥がいようといまいと、ひとは明日も足元を見て生きていかねばならないのである。
その「鳥瞰図」を見ている神がいようといまいと、そんなことには全く関係なく人は生きていくのである。
かつて海であった記憶を背景に置こうとしたことは理解できるが、浦安とは、いかにも筋が悪い選択であった。
この劇は、一つ一つのエピソードがきわめて詳細に描かれ、そのディテールの面白さで観客の興味をかき立てていくところが高く評価され、再演につながったと考えられる。
たとえば、杉田の結婚が破綻しているように見えるのに、何故か別れないという事情について、どうでもいいことが恐ろしく詳細に描き込まれている。その妻については、登場しないのに、語りから性格や態度、実家の人間関係などかなりくわしく分かって、杉田の苦労に同情したくもなる。
また、朝子が、なくなった自分の母親が言い残した「連れ合いと同じ墓に入りたくない」という遺言に振り回され、お骨を持って右往左往する挿話など、いかにもありそうで笑える場面もある。
一体に、この常連客のエピソードを描くときは肩の力が抜けていて、それがどうと言うこともないが、そうした積み重ねが劇にリアリティを与えて説得力を持つのである。
ところが、升本の家族の話になると、とたんに腑に落ちないところが目立ってくる。初演の時は、「意地悪じじい」と言われそうで遠慮したが、僕の感覚がおかしいのかためしに書いておこうと思う。
まず、ミオの母親波子、つまり佐和子の娘である。
佐和子が升本と再婚したことを許せないと思っていたことはわかる。実の父親と仲がよくて、一緒に干潟を撮影しにいったというのだから母親の再婚はショックだっただろう。高校を卒業したら姿をくらましたというのも無理はないと思う。
しかし、それからずっと何の連絡もなかったというのは、有り得ることなのか?
それが疑問だと言ったらYが、「ないとはいえない。」というので、女はそれほどまでに「かたくな」になれるものなのかと半ば納得した。はっきり言えば「縁切り」ではないか。茂雄と連絡をとっていたというなら納得できるがそういう説明もない。
ミオの出現に、佐和子がうろたえるのも変ではないか?
むしろ、波子が自分のことを孫のミオにどう話していたか聞き出そうとするのではないのかと思うのである。ミオが何しに現れたのか聞き出そうともしないで、まるで腫れ物に触るような態度はおかしいと思う。自分の再婚が「後ろめたかった」ということだろうが、子供に対して、どうあれ親は毅然としているべきである。
この点は、演出でどうにでもなる問題だから、松本祐子の解釈だろう。しかし、その解釈は僕には不満であった。人は「後ろめたい」思いを抱えて生きて行くことには耐えられないものである。
茂雄の元妻良美が浦安の病院に入院したことにも何の説明もなかった。
このもとスッチーの妻は、遊漁船の店を手伝うのがいやで出ていったのである。茂雄は早くから店を継ぐつもりでいたから、結婚に当たって、良美が店のかみさんになることは決まっていた。それなのに、何故結婚したのだろう。
いかにもハイカラ好きの女らしく、すぐにフランスに行って、子供を産んでいる。茂雄の子供が腹に入っているのではないかと言われるぐらいそれは素早く行われている。それから六年の間何があったか分からないが、末期ガンになって子供と二人帰ってきた。よりによって別れた亭主のいるところに戻ってくる理由が解せない。
茂雄がそれを知って、高額の薬を買ってやるのは、まあ、お人好しの男のことだから有り得るが、商売道具の船(一千万円ぐらいはする)まで売って直る見込みもない病気に金をかけるのは、どう考えても間尺に合わない。大人のやることではないだろう。
結局、順当な判断をしたからそれはよかった。
ついでながら、この女は、自分が死んだら、フランス人との間に生まれた子供をどうしようと考えていたのだろう。茂雄は女の子をディズニーランドに連れて行くなどこまめに面倒を見ている。「ついでだから、あんたが育ててよ。」とでも言うつもりだったのか?
不思議だ!
この一連の騒ぎの結末は描かれていないが、もしも再々演があるとしたら、良美が浦安の病院に来た理由を説明していただきたい。
それから、茂雄たちの父親は風景カメラマンで、他に家族がいたことになっている。そして、どこかで死んだというのだが、これほど影の薄い存在もない。
ミオは、母親からこの祖父のことを聞かされて昔の風景を写真に撮ろうとしたのであった。この一家にとっては重要人物のはずだが、何ものかほとんど分かっていない。もう少し書き込む必要があった。
第一、風景カメラマンという職業が(特に若かったはずだから)成り立つはずがないのは常識である。一体何で収入を得て妻子を養っていたのか?しかもあっちもこっとも、である。
この芝居には所々こうした設定の甘さが見られる。
僕に言わせるとこれは戯曲の瑕疵である。
瑕疵だと気づかない、あるいは思わない人も大勢いるはずだから、無理にとは言わない。なにしろ、それを通り越してディテールが面白く書き込まれているのは確かだといってよい。そこを評価しての再演だったのだろう。
しかし、以上のことは指摘しておかなければならなかった。
渡辺美佐子は、再演を楽しんでいるようだった。松本祐子が「うろたえる」のを要求したから、後ろめたさが出るのはしようがなかった。「子供のくせに大人のやることを批判すんじゃない」と波子には言い聞かせるべきであった。それならそれで、渡辺美佐子らしい凛としたというか個性的演技が見られたはずで、残念だった。
前回、茂雄は浅野和之がやって、僕は演技賞ものだと書いた。日程がかち合ったらしいのは残念だった。入江雅人の茂雄も悪くはないが、何せ、あの髪型である。遊漁船の船長というものがどういうタイプなのか、松本祐子には再度取材をお願いしたい。
杉田の八十田勇一もあいかわらずきっちりと笑いを取る演技で達者なところを見せた。
野村佑香は、前回非常に固くなっていて、見ているこっちがつらくなるほどであったが、今度は少し余裕が感じられた。自分のやっていることの意味がかなり分かってきたという印象だった。
弘中麻紀と浅野雅博の姉弟は安定したうまさ。佐藤銀平も若者らしいはつらつさで好感が持てた。品川 徹は適役という他ない。
早船聡は、役者もやっていた。昔の資料を見ていたら、新国立劇場の「マテリアル・ママ」(岩松了 作・演出)に出ていた。劇作は多いというわけでもなさそうだ。
道理で、ディテールにこだわるあまり、劇の骨格をしっかりさせることをおろそかにしたように見受けられる。骨組みさえしっかりしたら、細かいところは、あとからいくらでもついてくるものなのに。
題名: |
鳥瞰図 |
観劇日: |
2011/5/13 |
劇場: |
新国立劇場 |
主催: |
新国立劇場 |
期間: |
2011年 5月10日 ~ 5月22日 |
作: |
早船 聡 |
演出: |
松本祐子 |
美術: |
島 次郎 |
照明: |
小笠原 純 |
衣装: |
前田文子 |
音楽・音響: |
藤田赤目 |
出演者: |
渡辺美佐子 入江雅人 野村佑香 八十田勇一 弘中麻紀 浅野雅博 佐藤銀平 品川 徹 |
