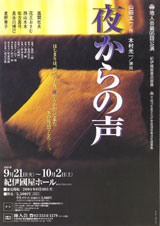
|
題名: |
夜からの声 |
|
観劇日: |
04/10/1 |
|
劇場: |
紀伊国屋ホール |
|
主催: |
地人会 |
|
期間: |
2004年9月21日〜10月2日 |
|
作: |
山田太一 |
|
演出: |
木村光一 |
|
美術: |
高田一郎 |
|
照明: |
室伏生大 |
|
衣装: |
宮本宣子 |
|
音楽・音響: |
山崎純一 |
|
出演者: |
風間杜夫 花王おさむ 西山水木 佐古真弓 長谷川博己 倉野章子 |
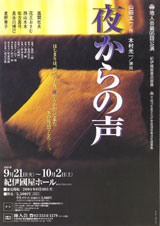
「夜からの声」
山崎正和が「社交する人間」(2003年中央公論社)の冒頭で1960年に書かれたエドワード=オルビーの戯曲「動物園物語」のあらすじを引用して、現代人の孤独について述べている。
セントラルパークで無頼の青年ジェリーに「動物園で何が起きたか知っていますか?」と話しかけられた男、篤実で平凡な市民ピーターが、心ならずもこの見知らぬ若者を殺してしまう話だ。ジェリーは自らのつまらぬたいくつな日常を語り、自分がいかに淋しく孤独かを延々としゃべり続ける。ピーターは礼儀正しく辛抱強く聞いているがついに立ち上がって帰ろうとする。ジェリーは怒りだして飛び出しナイフを挿頭すがピーターももはや逆上している。これを取り上げて前に構えた瞬間、ジェリーは「こうなるのを待っていたんだ」とつぶやき、あろう事かその刃先に体当たりするとナイフは深々と彼の胸に突き刺さるのである。「ありがとうピーター。これでよかった。ありがとう。とても心配だったんだ、あんたが俺をすてていってしまうんじゃないかと思って。」瀕死の息のなか不思議な微笑を残して「なあ、わかっただろう。これがあの動物園で起こったという出来事だったんだよ。」とささやいて幕が下りる。
この戯曲が書かれてから既に40年以上がたつが、内容はいささかも古びておらず、青年の孤独はまさしく現代の問題だという。
山崎正和は、この序章「社交への飢餓」で「一方に都市の無関心の砂漠が広がり、他方に無数の小市民の排他的な家庭が貝のように閉じているのが、現代である。かたや砂粒に似た孤独な個人が散らばり、かたや鉄の組織が生きた人間の絆を押し潰す様な時代が長く続いた。両者の中間に社交というもうひとつの関わり方があり、それは命を賭するに値するものだということを人々が忘れ去って久しい。」と書いて人と人との関係の未来についてその可能性を論じるこの本の背景を説明した。
山田太一はこうした状況を十分知りながらむしろ「貝のように閉じている排他的な家庭」も内側からのぞいてみれば時によっては死と引き換えにするような淋しさが存在することを見せようとするのである。
この芝居の主人公、本宮真司(風間杜夫)は「話し相手」と言うボランティア活動に参加している。誰にも聞かれたくない話を親身に聞いてやると言うものらしいが、相手になるには多少のレクチャーと訓練が必要と言うから、それなりの覚悟がいったに違いない。定年にはまだ間があるがサラリーマンとしては先行きが見えている。匿名の相手とは言え他人の人生に多少ともコミットするのは気の重いことだが、なにかせずにいられなかったのだろう。格別世話好きとも思えない本宮があえて参加した理由を推量すると、「話し相手」は他者を慰めながら実は共犯者のように自分の孤独をも癒してくれると感じたからではないか。
9月のある日曜の朝、パート先の居酒屋チェーンで店員教育係に抜擢された妻加代(西山水木)が新規開店訓練のために迎えに来た若い社長のポルシェに乗って出かけるのをマンションのベランダから見送る。6階という設定のベランダは舞台中央の奥にあって本宮が下を覗き見するような態度なのは多少嫉妬の気持ちがあるのかもしれない。会社勤めの一人娘、本宮亜弥(佐古真弓)は既に外出していて本宮はひとり取り残される。
このマンションの装置(高田一郎)は真ん中にリビング、上手にダイニングテーブルを置いたモデルルームのようなしつらえで、都会で暮らす市民の典型的な住まいになっている。山田太一ということもあって、極めてリアルな作りにどこかテレビドラマのにおいが漂ってくる。自分がテレビからやって来て「新劇の味を薄めている」と思われていると言っているのはこんなところに現れるのかもしれない。
程なくチャイムがなってタウン誌の記者と名のる藤井頼子(倉野章子)が訪ねて来る。ボランティアの仕事を取材したいと言ってきたが挙動が怪しい。問い詰めると何かに憑かれたように訪ねた本当の理由を話しだす。この春自分の夫は自殺した。日記を読んで、最後に話をした相手が本宮だったことを突き止めたのだが、何を話したか聞かせて欲しいというのである。当然のことだが半年前に話した男が自殺したのは知る由もなかった。前触れもなく遺書もないままある夜ベッドから抜け出したかと思うとマンションの下からどすんと言う物音が聞こえたというのである。藤井頼子は「話し相手」が原因だったのではないかと疑っている。本宮に心当たりはなかったが、嘘を言って上がり込んだことが気に入らない。話の内容はだれにも公開できないことになっていると最後まで突っぱねて追い返すことになると言うのが話の発端である。
倉野章子は、始めこそ普通の主婦のようだったが、次第に押しつけがましく難詰するようになるとこれはどこか精神を病んでるに違いないと思わせて鬼気迫るものがあった。夫の自殺の原因は、自分にあったのではないかと悶々と悩んだあげく責任転嫁できる「話し相手」を発見したのだが、それが解決の糸口ではないことを知っているようだった。出口を失った孤独が身体の中で毒になってまわっていたのである。
数日後、藤井と名のる男から電話があった。藤井柾(長谷川博己)、頼子のひとり息子で、製鉄会社の傍系に勤めている。母親が迷惑を掛けたので伺って謝りたいと言うのである。やって来たのはなかなかの好青年で、事情に通じていない加代は亜弥の相手になどと勝手な想像を巡らせたりしている。このとき加代の父、森沢郁夫(花王おさむ)が来ていて、頼子が何故か森沢の家を訪ねたことがわかる。狂気が生んだ行動力であろう。森沢は娘の結婚以来、本宮とは打ち解けない間柄である事を不満に思っていたが、この事件をきっかけにこだわりを捨てることが出来たと喜んだ。
藤井頼子は結局鬱病とわかって入院する。この鬱病の背景には夫の突然のわけのわからない自殺の他に、実は痛ましいできごとがあった。
山田太一が提示して見せるのは痴呆と介護と言う高齢化社会が抱える厄介な課題である。誰もがそうなるかもしれない恐怖の中を生きているという意味ではもっとも身近な問題といえる。あまり大ピらに語られることはないが、家族や人間関係あるいは人間の尊厳への破壊力はいうまでもない。
頼子の舅は「夕食はまだか?」と言うボケの症状に始まり、ついには息子の顔も嫁の顔もわからぬまで進行した。夫は工作機械メーカーの技師で長期間家を開けることもあった。その間頼子はひとりで舅の面倒を見ていた。次第に人格を失っていく舅をむしろいとおしく思っていたが、あるとき苛立って頬を張った。その時目に生気が蘇ったことに気づいて頼子は時々それをした。舅の身体にはその痕跡が残り、夫は虐待を疑っているようだった。ついに夫は決心して費用のかかる養護施設に預けるのだが、不幸なことに一ヶ月後火事で焼け出されてしまう。再び家に連れ帰った舅の寝顔を見ているうちに、頼子はこのまま眠りから覚めないでと手で顔をふさぐ。そこから惑乱のうちに記憶がなくなり、翌朝気がつくと舅の息はなかった。自宅でなくなると警察に届けるものらしい。死因は心不全ということだった。寝ているうちに心臓マヒを起こしたものだろう。六年という歳月が流れていた。その二ヶ月後である。物も言わず何も書き残さず夜中に起きだした夫はベランダから飛び降りた。
第二幕は、鬱病の治療で一ヶ月も入院していた頼子が息子を連れて本宮家に挨拶に訪れるシーンである。頼子は普通に見えるが、本宮の目からは何もかも封じ込んだだけで心の傷が癒されたとは見えない。もうすんだことだという頼子に、本宮は禁を犯して「話し相手」で何が話されたのか教えようという。克明に記録したメモがあったのだ。本宮がそれを元に夫の話を再現すると、頼子がそれに応じ、いつの間にか本宮に夫が乗り移ったように会話が進行するのを一同が驚きの表情で見守る。このクライマックスのいわば次元の移動はテレビではやりにくいところかもしれない。それまで平凡な勤め人と見えた本宮がこのボランティアに生き甲斐を見つけたことを家族は理解しただろう。
頼子には夫が何を思っていたかよくわかった。しかし、何故自殺したのか?本宮は、それは分からないと答える。少なくとも亡くなった父親のことをめぐってその理由を探すのは困難だと本宮は思う。「奥さん、人は理由もなく死ぬものですよ。」
頼子はようやく心の雲が晴れたように生き生きとした表情を取り戻す。森沢にけしかけられた藤井柾と亜弥も互いに好意を持っていることがわかり、これ以上もないハッピーエンドである。
最初は倉野章子の独り舞台のようなものだった。憑かれたように本宮に迫る様子や、本人にボケが始まっているようなあるいは鬱病特有の気が抜けたようなところ、退院してきて躁鬱がまだ抜けていないと思わせるところなど適度に演じわけていて、先行きそれらの狂気がどうなるのかはらはらさせた。クライマックスで風間杜夫が俄然精気を発揮していいところを見せてくれたのでうまくバランスしたが、やはり倉野の達者な演技が目立った。花王おさむの老人もいよいよ味が出てきた。ただし老け込むにはまだ早い気もする。木村光一の演出は手堅く、山田太一の世界を平明に創りだした。客席はめずらしく中高年の男性が多く、これは木村光一あるいは地人会のファンに違いない。これからこの層は益々大事な観客になると確信しているのだが・・・。
痴呆と介護は日常的でしかも重いテーマである。痴呆はようやくその原因が突き止められようとしている。ウイルスか何かの外因性の因子が関係しているともいう。これは治療法が見つかるかもしれない。介護は家族の負担を地域全体で分け持とうという思想が実現した。現実的な対応策に一応の見通しが出来たと言ってもいい。
むしろ、この劇を観ながら山崎正和の「社交する人間」を思っていたのは、本宮真司や藤井頼子、その自殺した夫らの孤独である。我々の社会では自分が何ものであるかを自分で選択して自分で決めなければならない。家族と言えども父親らしさや娘らした妻らしさなど誰も要求しなくなった。バラバラの個がつながっているだけである。この厳しい実存の様態に耐えていかねばならないのは分かるが、この時代にあった新たな絆を構築する可能性として「社交する人間」があるのではないかと思ったからだ。
頼子の夫が何故自殺したかは永遠の謎である。ただ深いところに絶望的な孤独があって、その飢餓に耐えきれなくなったのではないかという気がする。
(2004年10月8日)
