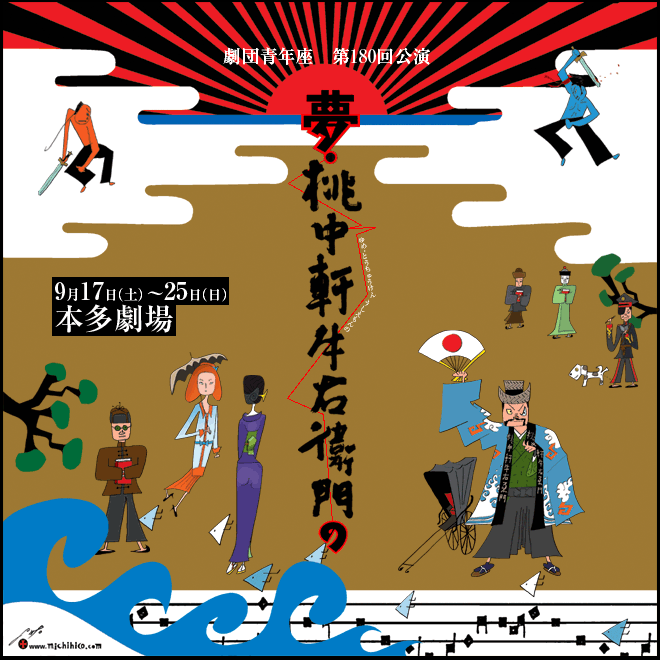
| 題名: | 夢・桃中軒牛衛門の |
|
観劇日: |
05/9/22 |
|
劇場: |
本多劇場 |
|
主催: |
青年座 |
|
期間: |
2005年9月17日〜9月25日 |
|
作: |
宮本研 |
|
演出: |
鈴木完一郎 |
|
美術: |
柴田秀子 |
|
照明: |
中川隆一 |
|
衣装: |
岸井克巳 |
|
音楽・音響: |
高橋巌 |
|
出演者: |
山本龍二 那須佐代子 山野史人 今井和子 村田則男 松熊明子 大家仁志 屋中宏 小柳洋子 佐藤祐四 豊田茂 小豆畑雅一 井上智之 青葉剛 青木鉄仁 永幡洋 平尾仁 太田佳伸 石井淳 高松潤 中村大輔 高橋幸子 |
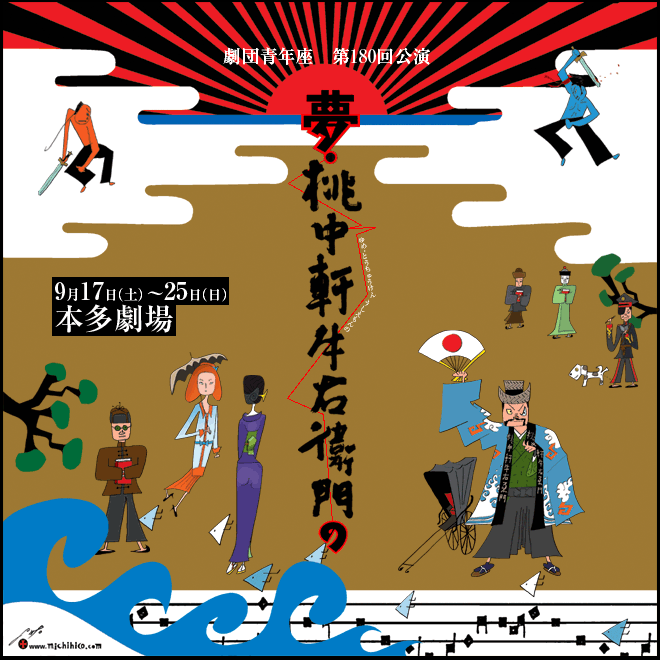
「夢・桃中軒牛衛門の」
宮本研の作品を見たのは「美しきものの伝説」(新国立劇場ユ99年11月)が最初だった。今はなくなった友人が学生時代に「宮本研はいいぞ。」といっていたのだが、それはおそらく「美しき・・・」(ユ68年文学座か?)の初演を見てのことだった。そのころは政治の季節であり、彼から芝居の批評を聞くのは意外だった。気になっていたが、その後会社員になったから三十年も見る機会がなかった。翌年は青年座の「明治の棺」を見た。そしてこの芝居である。「宮本研はいいぞ。」といっていた意味を友人の思い出とともに今味わっている。
手元にある東洋文庫「三十三年の夢」は以前、神田で手に入れた復刻版である。その元になった本も大正十五年、滔天が亡くなってから再出版されたもので、民本主義の吉野作造が解題を書いている。復刻版は宮崎龍介と衛藤瀋吉によって校注がなされ、彼らが寄せた一文も面白い。中でも長男宮崎龍介が、昭和四年の孫文慰霊祭に母、槌とともに招かれたときに新聞に連載された槌の口述筆記「支那革命の思い出」を全文紹介しているのが興味深い。宮本研はこれを多いに参考にしたものと思われる。それによると、
明治三十五年三月二十三日、滔天は芝愛宕下町寄席八方亭を訪ね、桃中軒雲右衛門に弟子入りを申し込む。雲右衛門は薮から棒に飛び込んできた見知らぬ男に驚くが、滔天は幸い楽屋にあった新聞に自らのコラム「三十三年の夢」が載っているのを示して、自己紹介を済ませた。翌日、雲右衛門は妻をともなって滔天の寓居(といっても元芸者の愛人留香の家)にやってくる。本気かどうかを確かめようとしたのだという。滔天はすでに弟子としての礼を尽くしてこれを迎える。愛人にとっては、収入のない滔天が浪花節の弟子になるのではこの先見込みがないということでもあり、同居していた愛人の親兄弟に迫られすったもんだの揚げ句、滔天は留香と別れて雲右衛門の家へ転がり込むことになる。革命に失敗した恵州事件のあと、失意のなかで、浪花節語りに転身を決意するところで「三十三年の夢」は終わっている。辛亥革命まであと八年である。
芝居は、この夢が終わったところ、滔天が桃中軒牛衛門になって、傍から見れば新たな「夢」を紡ぎ出そうとする場面から始まる。
妻槌(那須佐代子)が雨の中を舞台に現れる。夫宮崎寅蔵(山本龍二)の消息がようやくわかって訪ねてきたという口上。明かりが入ると横浜本牧座の高座だが、客はわずかに三四人という有り様である。桃中軒雲右衛門(山野史人)がもう今日はやめたから帰ってくれというと、ひとりだけ残ったものがいる。額に包帯を当てた宮崎滔天寅蔵であった。弟子にしてくれと頭を下げる滔天に何をしたいと問うと、恥ずかしながら高座で革命を語りたいという。芸名も決めてある、亭号はそのまま桃中軒をいただいて、名を牛右衛門とする。牛飲馬食、日に三升酒をたしなむからだという。滔天の柄の大きさを示すネーミングである。
雲右衛門の妻浜(今井和子)は、もとは三河屋梅車の女房をかどわかして一緒になったもの、三味線の名手で欠かせない存在だが、そのため不義だ密通だといわれて東京にはいられなくなっていた。そこで、一緒に熊本へ向かい美当一調という軍談語りの節を盗んで新たな節回しを創造し、捲土重来を期すというのが滔天の提案だった。革命家というものは戦略家でもある。雲右衛門の才能を見込んで、彼に天下を取らせるマーケティング戦略を考えていたのであった。
そこへ妻槌が現れ、うしろに高野さん、実は孫文(村田則男)がついてくる。清国政府から多額の懸賞金がかかっているお尋ね者だが、恵州事件のあと、次の準備のために奔走していた。恵州での失敗の一因は滔天にあると仲間に責められた時に負ったのが実は額の傷だった。それで嫌気が差したのだったが、孫文はまたやりましょう、機会はいくらもあると滔天を慰める。孫文はハノイに向けて発っていく。というのが第一幕の第一場。
ところで、滔天の山本龍二のことだが、この役はもともと津嘉山正種がやるはずだったのを彼が脳梗塞で倒れたために急きょ変わったものだと聞いた。どうなることやらと思って出かけたが、これはかえって山本でよかったと思う。津嘉山の滔天を想像すると、少し線が細いような気がする。初演は、文学座の北村和夫だったらしいが、これが当て書きのような適役だったという評判である。山本龍二は例の語尾をあげる癖もすっかりとれて、破天荒な主人公をけれん見なく演じた。北村和夫のアナーキーさはないが、野太いスケールの大きな人物像を創り出して、彼の代表作になりそうである。
さて、弟子になって下手な語りでもアジ演説のようなものは案外受けていたのだが、相変わらず声がかかれば名古屋だ、大阪だと走り回っているうち、顧みなかった家族の生活も行き詰まり、明治三十八年の正月とうとう槌と三人の子供は東京へ出てくることになった。
舞台はこの年の初夏、内藤新宿、番衆町の借家である。主が留守にもかかわらず、清からの官費留学生が出入りし、浙江省と呼ばれる実は革命の女傑、秋瑾(小柳洋子)、湖南省というあだ名の実は後に、革命政府の要人となって袁世凱に暗殺される宋教仁(家中宏)が孫文とともに寄宿していた。革命の準備をしていたのである。そしてもうひとり、槌の姉で出戻りの波(松熊明子)がなぜか一緒に住んでいる。この波が滔天に似た奔放な生き方をしていて愉快であり、最後まで一家に付添い狂言回しのような役割を果たした。若い頃、はしごを掛けて槌の部屋に忍んでくる滔天を見過ごしてやった度量の持ち主である。
この波をやった松熊信子は儲け役だとはいえ、存在感を示してうまかった。
それから武器の調達や爆弾の製造やら、てんやわんやのところに北輝次郎(青木鉄仁)すなわち北一輝が現れ、革命を手伝うと申し出る場面や、番衆町の借家の庭先に猫を抱いた夏目先生(青羽剛)すなわち夏目漱石がなぜか出没するところがでてくる。孫文と夏目漱石はここで出会うことになっているが、さて本当だったか?このサービスのような挿話は、「美しきものの伝説」など群像を描く宮本研独特の手法だといえるが、この劇の最後の場に、もうひとり、革命なった中国の師範学校の学生が登場する。日本からの賓客に講演を頼みに来る学生は別れ際に毛沢東と名乗って帰る。宮本研は、中国で生まれ育った。だから格別の思いがあったろう。この若いまじめそうな学生が後の国家主席だったのだというさりげないスケッチを挟み込んで敬意を示したかったのだと思う。
ところが初演当時は、文化大革命のさなかである。これは中国共産党の内部抗争が表に現れたもので、報道はほとんどされていないが、このために一千万人余の人民が命を落としたといわれている。時の中国政府は極めてナーバスになっていたらしく、中国大使館は、毛沢東の文字をいっさい使ってはならないと強硬に申し入れてきた。思わぬ反応に対応は大変だったし、書いた本人にとってはショックだったようだ。
孫文の革命は清国を倒したが、袁世凱の横暴を許し、これを制した蒋介石の中華民国政府に直結する。上海で生まれた中国共産党は蒋介石に弾圧され、いったん内陸深く撤退する。いわゆる長征である。孫文の流れを組む滔天の劇にはおそらく複雑な思いがあったのだろう。
しかし、今日の日本と中国のぎくしゃくした関係を改善する意味で、日本側から辛亥革命のいきさつを両国民に啓蒙して、しすぎることはない。
なぜ滔天をはじめ、多くの日本人が孫文を支援したのか?この謎を解くのが劇の基底をなしているテーマである。
先に上げた槌の口述筆記はこう始まっている。
「滔天が支那革命運動に志したのは明治二十年ごろからのことと記憶します。その頃滔天は兄の彌蔵とともに、世界の現状の不合理をあらためるには、まず支那の革命を実行して、その力で世界を理想的に改革することが一番自然であり、最も実現可能だと考えたのでした。それで兄の彌蔵と滔天とは、その頃誰でも希っていた栄達や安逸を終生捨てる覚悟を決め、将来支那に永住して、その運動に没頭する考えを決めました。その時は、私は二人を助けて飯炊きをする約束でした。・・・」
熊本民権党を率いて西郷軍に合流し、獅子奮迅の働きをして戦死した長兄八郎の影響が兄弟にはあっただろうが、妻となった槌までがその覚悟であったとは。なるほど、あれだけ夫に家を空けられて、貧乏生活を強いられても凛としていられたのは「飯炊きをする約束があった。」からだった。
また、東洋文庫の解説を書いた衛藤瀋吉は、冒頭、清末革命運動研究家で、イスラエルのシフリン教授との雑談を紹介している。かれはこういった。
「どうしてこうもたくさんの日本人が中国革命に夢中になったのか。中にはミヤザキみたいに兄弟そろって私財まで持ち出して情熱を注ぎ、しかもなんら報いるところを求めていない・・・」外国人から見てもこれは不思議な光景に映ったであろう。衛藤瀋吉自身も「明治の人たちの異常なほどの大陸問題に関する情熱と行動力をいったいどう歴史学の中に組み入れたらよいのであろうか。」とやや戸惑い気味である。
いずれにしても、これらの運動の中に欲得ずくのところがまったく見えない、純粋に大義と理想を追い求めた若い情熱だけが今日から見れば奇跡のように輝いて見えるのである。坂本龍馬の人気があるのも、変革に当たってこの無私という態度が、いまだに日本人の心の琴線を揺さぶるところがあるからなのだ。
「民族の若返り(Re-generation)ともいうべき明治のエネルギーは一つの驚異である。」(衛藤瀋吉、前述の解説)といえるが、これはおそらく長い封建社会が醸成し磨き上げた「武士」というものの倫理がその土台になって出来たものだろう。
劇のせりふにも出てくるが、滔天が支那革命を志した根本的な願望は「天下の乞食に錦を着せ、車夫や馬丁を馬車に乗せ、水飲み百姓を玉の輿、四海兄弟無我自由」であり、このような社会の到来を求めたのであった。今日、世界を見渡してこの「志」が実現したとは到底いえるものではない。僕らも若い頃、それを考えて、一敗地にまみれた。・・・ような気がする。だからいうわけでもないが、堀江もんが「宇宙旅行を売り出す」などと聞くにつけ、「何用あって宇宙へ行く?」他にやることは山ほどあるではないかと、まるでいじけた古老にでもなった気分になる。
芝居は、桃中軒雲右衛門が大成功を納め東京に帰ることが出来るが、人気におぼれ、妻を顧みなくなるもう一つの筋を追う。しかし、頂点にいられた時期は短かった。駆け落ちまでして奪った女房に先立たれ、今は名古屋に引っ込んで、病の床にふせっている。栄枯盛衰、諸行無常というべきか。大正六年春、槌と波を伴ってこれを見舞った足で、夫婦は革命が成就した上海へ向かう。
終幕近く、滔天がなぜこの年まで中国のことばかりにかまけてきたかと自問する場面がある。ジャン・ジャック・ルソーを読んで人となり、兄八郎の民権思想の影響を受け、中国革命こそ全アジア解放の要と考えた、といってもその理由はへ理屈に過ぎないと独白する。槌は誰かに尋ねられたのでしょうと合いの手を入れる。つまりその人は、なぜあなたは自分の国、日本のためにこそ働かなかったのか?と尋ねたのではないか。
この後のせりふがいい。
滔天 ・・・だって、俺はあの国が好きじゃなかった。憎んだ。だから、二十歳いくつの時からこの年まで、あの国にずっと背を向けて生きてきた。それを今さら。
槌 そうなんです。あなたは日本という羽織を長い間、ずっと・・・裏返しに着て生きていらっしゃった。
滔天 裏返しに?
槌 ええ、裏返しに。・・・でも、生きていらっしゃったんです。日本というお国を。そう、羽織でも着るみたいに、わざと裏返しにして。
尋ねた本人はむろん宮本研に決まっている。
そして、とびきりしゃれたたとえで、真実に肉薄した応えを用意したのも宮本研その人に違いない。
滔天が浪花節の下手なのは仕方がない。山野史人の桃中軒雲右衛門がもうすこし浪花節になっていたら万点あげられたのに、惜しかったなあ。
(2005年11月13日)
