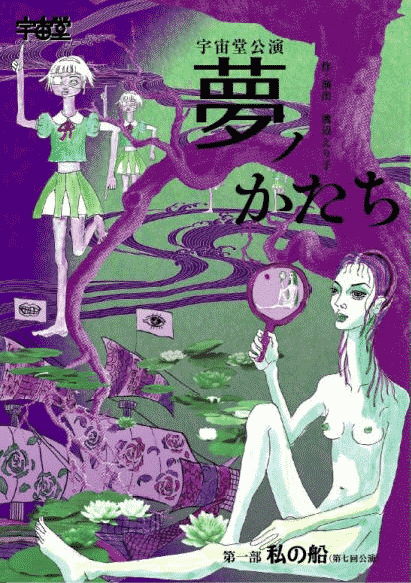 }
}
「夢ノかたち 〜私の船〜(第一部)」
渡辺えり子の芝居を初めてみた。昔の赤テントのようにアナーキーでにぎやかな歌劇であるが、唐十郎が下町の少年時代への論理を越えた郷愁をてこにしているのに比べると、存外まじめで律義、理屈っぽいテーマ性を抱え込んでいる。人は見かけによらぬものとはこのことだ。
ただし1955年生まれの渡辺が、どうしてこんなにも戦中や戦後の生活・風俗にこだわるのかじつに不思議である。当然ながら今の戦争、これからの戦争が気になっているのだろうが、戦後60年も経つうちに世の中はすっかり変ってしまったことをあまり見ようとしていない節がある。ようやく高度成長までの戦後史をなぞって見せたが、それから先は判断停止の具合。戦争への漠然とした不安は理解出来るが、自分の「夢」の中から出てこない自閉症気味の「カタチ」になってしまって、振り出した問題の射程は「現在」まで届いていない。
戦中の学徒動員で被服工廠のようなところでミシンを踏んでいた娘福子(大下美歩)は、戦後も洋裁で弟縞男(吉田裕貴)を養い、今や決して完成することのない洋服を縫い続けていた。母親の角子(杉嶋美智子)は、福子と縞男の姉弟は戦時中七つの海を渡り歩く船乗りの男との間にできた子供と称しているが、中田(土屋良太)という夫がいる。中田は、洋裁学校の校長で経営者である。ここは、洋裁学校の図書室兼休憩室で、姉弟の居室であり作業部屋でもある。角子には、戦時中の「生めよ増やせよ」の掛け声で産まれた子供が戦争にとられて死んだとの記憶が強迫観念になっているようで、時々発作を起こす。戦時中の輸送船で子供を産み落とし、敵艦の攻撃でその子を海に流したと言う遠い記憶があるようだ。洋裁学校の経営に支障がないよう気遣いする中田は、それをなだめすかして今や戦後なのだといいきかせ、一方生徒には何事もなかったかのように振る舞おうとする。
生徒は手に職をつけようという若い女が多いが、中には戦争未亡人富士子(奥山隆)のように、ミシン一つで立派に遺児を育てているが、まだ腕に自信がないと学校に踏みとどまっているものもいる。この富士子をやった奥山隆は、和服に割烹着、髪を後ろになで付けて、きれいに化粧をした顔がなかなかの女っぷりで、別に男がやらなくてもすみそうなものだが、劇団の層の厚さを見せてくれた。
この洋裁学校という設定は、劇場となった「白萩ホール」と重なる。つまり、「白萩ホール」とは新宿・白萩服飾専門学校の校内にある教室二つ分くらいの広さの「ホール」なのだ。鉄筋二階建ての古い建物だが、入り口から階段を上っていくつかある教室の前を通って二階の一番奥にあるこのホールへたどり着く。まるでこの学校そのものが舞台という錯覚を狙ったもののようである。どういういきさつがあったかは知らないが、これはテーマと密接な関係がありそうだ。
「白萩の歴史」という短文がパンフレットに載っている。「大正13年の萩原まきが日本で初めての手編み機(萩原手編み機)を発明し、創立された学園です。女性が編み物の技術をもとに自立し、社会で活躍していくことを目的に、戦時中は戦災で全施設を失ってしまいましたが、戦後復興、今日へと続いています。現在は、進展するファッション社会への正しい理解、そして技術と理論からなる立体教育により、優秀な卒業生を数多く社会へ送り出しています。」
戦中から戦後の貧しい時代、戦災孤児やら、傷痍軍人が登場して戦争の記憶をかき立てる場面があったかと思ったら、まもなく「もはや戦後ではない」と言う掛け声が聞こえて来る。渡辺えり子の世代は、戦災孤児も傷痍軍人も見たことはないはずだが、そのあたりの研究は確かなもののようで、作り方のリアリティにはなかなか感心した。
ともかく戦後は終わったかと思ったら、戦前との関連で「バウハウス」がスライドで登場する。たぶんシカゴに移ったバウハウスではなかったかと思うが、米国のファッションをリードしたエピソードがしばらく語られる。
そこで、実業家の滝沢(新井和之)?がやくざっぽい男成本(戸沢俊啓)をともなって登場。校長の中田とどうやって儲けるかという話になる。戦後の暴力やくざが経済やくざになるというエピソードかと思ったらこれが案外まじめなマーケティングの話で、ファッションのブランドを形成する戦略は勿論、製品開発の手法に至るさまざまな考え方を一挙に披瀝する。なるほどこうして戦後が「終わったあと」の高度成長は始まったのだという高揚した気分が舞台には満ちあふれる。
そうした中に、祭り半纏を羽織ったテキ屋の男田岡(梅原晶太)が紛れ込んできて、ここは図書館なのに本がないではないかと言い出す。ところが、勢いに気圧されていつの間にかこの騒ぎの中に巻き込まれ、次第に我を忘れていく。自分は誰なのか?田岡安治であることが、曖昧になり別人に仕立て上げられることに抗することが出来ない。それにしても何故、本棚に一冊も本がないのだろう。
滝沢が去って、何かが送られてくる。風呂敷に包まれた四角い大きな包みである。急いで開けてみると、そこから浮浪児が出てくる。背中にぜんまいを巻くハンドルがくっついているところを見ると、これはおもちゃのつもりなのだろう。角子にすり寄って母親だというが、角子は知らないという。いったい誰の子、いやおもちゃなのか?
角子が再び戦中の世界に戻って遠い記憶を語り始める。輸送船、航跡の残る海、産み落とした子供、しかも夥しい子供。息子の縞男が母親の狂気に励起されたように舞台前方の廊下にはいつくばり、床板をはぎ取るとそこにはあふれるばかりの無数の水ヨウヨウが水に浮かび、その一部は糸に引かれるように母親角子の股につながっている。「殺されるくらいなら、生まないほうがましだ。」と呪文のように言い続ける角子。
この狂気が乗り移ったかのように次第に一同の振るまいから精気が抜け、あるものはしまりのない口元を見せて笑い、あるものは震え、まるで世界が変ったかのように見える。
田岡が私は誰と校長に聞くと、いつの間にか校長は髪形が変り、白衣を着て椅子に腰掛けている。ここは精神病院らしい。気がつくと、富士子の奥山隆のメイクは無残に壊れ、もはや尋常の表情ではない。角子を始めみんな狂っていたのだ。
舞台の壁についていた本棚が動き出し、棚には裸の人間が胎児の格好ではまっている。棚の後ろから緑色の手首が多数突出され、誘っているような不気味な動きを見せている。
この緑の手首を見せて終わるところは、たぶん次回作の「夢のかたち第二部緑の指」に続くことを示していたのだろう。
最後を精神病院にしてしまうところはずるいやり方で、あまり感心しない。かといって他の始末の付け方があったかといえば、にわかに思い浮かばないからあれでよかったとも言えるが、下手をすると狂人の戯言になりかねない。何度も使える手ではないといっておこう。
最初と最後の挿入歌は歌詞が難解すぎて理解出来なかったが、劇中二回入るシャンソンの替え歌には感心した。第一選曲がいい。「La Foule 群衆」は長い曲のあいだに何度か転調が入り、群衆の中の孤独を歌った味わい深い旋律の名曲である。これを前半と後半ちょうどいいタイミングでいれてくれた。
シャンソンを選んだ感覚もそうだと思うが、渡辺えり子にはフェミニズムへのこだわりが見える。
まず、戦争に駆り出される若者を母親の立場から考えるという視点である。あの戦争の時代、何故母親は無力であったのか?戦中戦後の時代にこだわる物語にはこういうテーマが深くかかわっていたと考えられる。むろんそれがまともに議論されたことはほとんどない。戦後の一時期、母親の子を思う気持ち、それが子供を戦場に送らない、ひいては母性愛が戦争を抑止する力になるのではないかと言い出すものがなかったわけではない。しかし、その議論は根拠があまりにも薄弱すぎた。
それがこれからの戦争に機能するかも知れないという議論は当然あってもよい。しかし、たとえばイラク戦争に参戦する米国の若者たちを見ていると、その根底には経済的な問題が横たわっているように感じるのだが、それと母性愛にどうやって折り合いをつければいいのか僕には到底見えてこない。
そして、渡辺には「女の自立」ということも気掛かりなテーマとしてあるようだ。
白萩服装専門学校とは格好の舞台を取り上げたものだ。大正時代に女が職業を持って自立出来る教育装置を作り上げた萩原まさに対する敬愛の念があったのだろう。戦後の高度成長期をあのような形でとりあげて言及しようとしたのも、女性にはそこから事業として成長させていくという視点もなければならないと思ったのかも知れない。
さて、今回渡辺えり子ワールドなるものがあると初めて聞いたが、確かにはまってしまえば、それなりに楽しい世界かも知れないと思った。実にさまざまなイメージが次々に差し出され、考えている暇など与えない。言葉も程よく洗練されていて違和感がない。しかも考えていることの根底には世界に向き合うまじめさと律義で粘り強い東北人らしい気質があると感じられる。まあ、好感は持てるが、女性性が強すぎてはまりこむほどにはなれないのが正直なところだ。
夫君の土屋良太は、それなりにやっていたと思う。しかし、いかんせんここは彼が「住むべき世界」ではない。若い連中がわあわあやっているようなところでは彼のうまさは生きてこない。宇宙堂という劇団がこの傾向を続けるなら彼は居場所に困るのではないか。題名: |
夢ノかたち 〜私の船〜(第一部) |
観劇日: |
06/8/23 |
劇場: |
新宿・白萩ホール |
主催: |
おふぃす3○○宇宙堂 |
期間: |
2006年8月16日〜8月27日 |
作: |
渡辺えり子 |
演出: |
渡辺えり子 |
美術: |
加藤ちか |
照明: |
宮野和夫 |
衣装: |
Dress |
音楽・音響: |
鶴岡泰三 |
出演者: |
土屋良太 杉嶋美智子 奥山隆 木村絵里木村真弓 野笹由紀子 吉田裕貴 梅原晶太 多賀健祐 田辺愛美 谷口幸穂 藤沢太郎 加藤記生 川崎侑芽子 東澤有香 戸沢俊啓 草谷夏枝 加藤亜依 新井和之 梅野渚 大下美歩 |