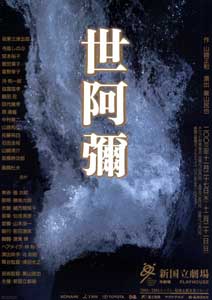
|
題名: |
世阿彌 |
|
観劇日: |
03/12/5 |
|
劇場: |
新国立劇場 |
|
主催: |
新国立劇場 |
|
期間: |
2003年11月27日〜12月21日 |
|
作: |
山崎正和 |
|
演出: |
栗山民也 |
|
美術: |
島 次郎 |
|
照明: |
勝柴次朗 |
|
衣装: |
緒方規矩子 |
|
音楽・音響: |
仙波清彦 |
|
出演者: |
坂東三津五郎
寺島しのぶ 宮本裕子 観世葉子 倉野章子 沖恂一郎 益富信孝 鶴田 忍 田代隆秀 原 康義 中村育二 山路和弘 佐藤祐四 石田圭祐 山崎清介高橋耕次郎 風間杜夫 |
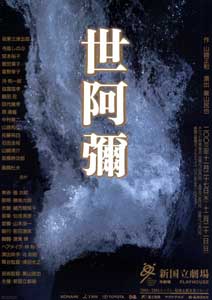
「世阿彌」
将軍義満の愛妾、葛野の前(寺島しのぶ)に懸想して世阿彌(坂東三津五郎)は、これを許される。このとき義満からと言って葛野が差しだした鼓、手に取るとこれが皮の代わりに綾織を張ったもの。打てと命ぜられるが、音が出るはずもない。うって響かぬならば世阿彌、満天下に恥をさらすことになる。天の声は、今を時めく世阿彌が打てば聞こえぬものでもない、とけしかける。苦悶し躊躇する世阿彌。しかし、ついに意を決して・・・鼓は打たれた。天から義満の声、「葛野、お前には聞こえたか?」
一幕、中盤に現れる場面だが、芸術家とパトロンの関係を思い知らされた世阿彌は、所詮自分は義満の影にすぎぬ、義満という強い光、その「影」として生きるより他ないと心に刻む。
能は、舞なのか芝居なのかと今さら馬鹿なことを言うが、しぐさに「型」と言う非常に抽象性の高い構えがあるのは事実で、民衆芸能からこの高みに達するには、一種の止揚が行われていることは確かである。その過程を追うのは誰かに任せるとして、結局すべての芸術が見物を必要としているとするなら、能もまた能にふさわしい観客によって、能になったのである。ふさわしい観客が15世紀の日本に多くいたとは考えにくい。商品経済が発展段階に達していたから一部の富裕層は能舞台を見ただろうが、やはり貴族やら時の権力者が支えなければ成立しなかった。同じような関係は、茶の湯の千利休と秀吉にあった。こちらは商人文化は成熟をみていたが、戦国時代を戦い抜いた武家が贔屓にした。
山崎正和はこの関係が気になると見えて、どちらも戯曲に書いている。その事情に触れたエッセーをたまたま読んでいた「世紀を読む」(朝日新聞社)の中に見つけたので引用しよう。
「振り返ると、これまで私は芸術家の登場する戯曲を書くことを意識的に好んできたような気がする。世阿彌の『世阿彌』を初めとして、源実朝の『実朝出帆』、千利休の『獅子を飼う』はいずれも芸術家が主人公であったし、、『野望と夏草』の『今様』の芸人達も主役にかかわる重要な役柄であった。
ひとつには、私はすべての人間を本質的に表現する存在だと信じていて、芸術家の人生に人間性の運命が凝縮されたいると感じていたからであったらしい。もうひとつには芸術家は他人の目に見られる職業であるから、これを劇場の観客の前に立たせることは、いわば表現の構造を二重にすることになる。芸術家は人生の中で既に役者であるから、これを主役にすれば登場人物が自分を『演じる人間』として意識し、劇中で劇中の人物であることを自覚して生きることになる。私は戯曲のこの『入れ子』構造、いわゆる『メタシアトリカル』な仕掛けが生来好きだったようである。」(「二人のマーガレット・バークホワイト−ある演劇的実験について」より)
人間は、いつでも何ものかである。家では夫であり父である。会社では課長であり、財務担当の中堅社員である。フェミニズムの文脈で言えば、男というジェンダーを生きている。そのようなものとして振る舞っていることを客観的に眺めるとそれは「そのつど割り振られた役割を演じている」ともみえる。芸術家の場合、日常的に既に何ものかであるうえに舞台上の役割を演じることによって、自己同一性が危うく揺らぐ(多分)、その構造が好きだということらしい。
いかにも「柔らかい個人主義の誕生」の著者らしい言い方だが、少しからかい気味に言うと、葛野の前の寺島しのぶの元気がない様子を見て、僕は彼女が長く付き合っていた市川染五郎が最近他の女性と結婚したことをきっかけにいわゆる暴露本を出そうとして騒ぎになっていることを思い出した。世阿彌の坂東三津五郎は、いわゆる女子アナと恋愛して、すったもんだのあげく元宝ジェンヌの妻を離縁し、この不倫相手と一緒になったが、姑だか家族だかと折り合いが悪く、あっという間に別れてしまった。家を出た元女子アナにすぐに相手ができたとかで、三津五郎は大いに男を下げたのだが、世阿彌をみながらこれがその恋愛に不器用なしかも不運な男かと余計なことに気遣いしたのである。
こんなものは大いに邪魔である。感興を阻害することおびただしい。だが、僕がそう思うくらいだから観客のうちどのくらいがこんな目で見ていたか知れはしない。
もちろん山崎正和の言いたいことがそこにあるのではない。芸術家と言う表現者を主人公にすると、「演じる」と言う行為にある自己対象化の構造を舞台の上でもう一度対象化することになり、そこに生まれるアイデンティティの混乱とも言うべき「仕掛け」が面白いと言うのだろう。
しかし、こういう見方が果たして実際的かといえば、せいぜい僕の頭に浮かんだような下世話な興味と役柄との間の「分裂的自己同一」が関の山で、高邁な存在論を楽しむところまで到達する様な気はしない。
それよりも芸術家の登場する戯曲を好んで書いてきた理由として「芸術家の人生に人間性の運命が凝縮されていると感じていた」というさりげない一行に本音が表れているような気がする。
世阿彌は全霊をかたむけて能をひとつの体系にまで磨き上げようとしているが、義満にとっては所詮道楽のひとつである。それは利休と秀吉の関係にも当てはまる。一方にとって命懸けの事柄が一方にとっては愉楽、愛玩の対象であり、その素人がいわば生殺与奪権を握っているというインバランスの関係が人間社会を象徴しているというのであろう。芸術家の場合、自ら追及する技能や「道」がある一点を突き抜けたとき社会的価値を生み共有資産になりうるという点で、初めて関係が均衡するのである。
山崎正和は、劇作家である。劇作家で劇団を主宰している例はあまたある。劇団の経営は難しい。彼が劇団をもちたいと思っている様には見えないが、芸術家としてのみ身を立てることからある意味では開放されている。劇作家でありながら大学に席を置く研究者であり教育者であるという立場によって、はじめて芸術家とスポンサーとの関係に目配りが行くのではないかと思う。つまり、芸術家にとって二項対立あるいは一方的な関係のように見えるものが、もう一方の立場に立てば実は相互補完的存在なのだととらえているのである。おそらく、その間をいかに有効に効率よくつないでいくかといういわばプロデューサー的な指向がこの人の中にあって、それが芸術家を中心に置く劇作の動因ではなかったかと考えるのだ。少し強引かもしれないが、このように考えられる演劇人は、極めて少なく、演劇に限らず芸術一般の発展のためには貴重な存在だと言える。
ところで、僕は能についてあれこれ言うほど知識はないが、最近、五十六世梅若六郎が中学生に教えているのを見て感心したことがあった。
気をつけ!の姿勢で、前に後ろに歩けというと身体が緊張しているからその動作は実にぎこちない。次に左右に歩けといえば、何と全員よろけてしまうのである。梅若六郎は、人間が立つというのはどこにも力が入っていない状態、肩が下がり腰の辺りで身体を支えているような気分をいい、その自然の立ち姿が昔から日本人の動作の基本だったというのである。つまり、この状態からからだと、苦もなくどの方向へも歩き出せ、しかも自然に例の「摺り足」になるのだ。こういう日本古来の身体感覚を下敷きに能の形式が作られたことを目のあたりにしてみると、山崎正和の言葉で書かれた「世阿彌」は急にバタ臭く見えてくる。
世阿彌の演劇論について、パンフレットで松岡心平(東大教授・表象文化論−こういう学問があったとは知らなかった。)はこう書いている。
「世阿彌は世界で初めて観客についてまともに考えた演劇人であった。演劇とは観客問題以外の何ものでもない、ということを世界でもっとも早くに自覚し、透徹した思考を展開した演劇人であった。
そのことにもっとも早く気づき、観客問題が、実は、人が人と人との間に生きるという人間の本質的な在り方や意味を問うことにまで深まる問題であることを、現代人のアイデンティティ危機にからめて問いかけ直したのが山崎正和氏の『世阿彌』である。
・・・俳優は演じている自分とそれを客観的に認識している自分を常に合わせ持たなければならない。演技や役に没入する自分と、それを覚めた目で見つめる自分との二重性を生きることが、優れた役者の要件だと(世阿彌は)いうのである。自分を醒めた目で見つめる、もう一つの自分に、世阿彌は、観客の目を重ね合わせる。観客が俳優としての自分を見つめているその目に同化させるようにして、もう一つの醒めた自分の目をもて、というのだ。」
この後、美空ひばりを例に引いて、彼女が「悲しい酒」を歌うとき必ず流す一筋の泪こそ、「没入する自分とそれを醒めた目で見る自分との二重性」を表す好例であると述べていて、実に分かりやすい。
世阿彌に対する世界の評価はここにあるように確かに高い。しかし、このことならば、いやしくも舞台に立って何かを演じるものなら常々感じるものと推量できる。それを突き詰めて行くとやがて、世阿彌のいう「幽玄」という境地に到達するのであろう。
僕がいぶかしく思うのは、松岡教授が「世阿彌は世界で初めて観客についてまともに考えた演劇人であった。」ということである。つまり、役者であれば誰でも感じているはずのものを対象化して分析し、文書化した功績は世阿彌にあるというのはいいが、「世界で初めて」とはどういう意味があるのか?このことは、西欧の演劇にはこういう視点がなかったということであり、なくても構わなかったということである。
世阿彌が生きた15世紀、パリには常設の劇場がようやくいくつか出来たばかりだったと思う。そこで何が演じられていたかはよく知らないが、宗教色の強い何かであったろう。デカルトがスコラ哲学への刺激を巧妙に避けて「我=コギト」という概念を思想の基準として提示するまで、フランスはその時代から約2世紀を要した。更にいえば、対岸のロンドンでシェークスピアがグローブ座を観客で一杯にし、歓呼の声で迎えられるまで、200年の歳月を待たなければならなかったのである。
世阿彌のいうように主観でありながら他者あるいは世界と呼応することによって変容する主観、いわば間主観性(あるいは共同主観性)の様な概念をヨーロッパが承知するのはようやく20世紀にはいってからではないか?
「世界でもっとも早く」とは西欧に先駆けてという意味だろうが、世阿彌が残したことは、本当はヨーロッパ辺境とはまったく無関係に、極東の辺境ではぐくまれた独自の思想的営為である。従って早いかどうかよりも、そのような観想をもたらした歴史的社会的あるいは思想史的背景がなんであるか、また、とりわけ梅若六郎が教えるように「日本古来の身体感覚」が基本にあるとするなら、その先に見えている能の自然観とはなにか、ひいては日本古来の世界観とはなにかという課題が正しく評価されなければならない。西欧の思想体系にすり寄って、その文脈に世阿彌をいれて解釈しようとしても所詮かみ合わない議論である。
話があらぬ方へいってしまったが、山崎正和の「世阿彌」が現代人のアイデンティティの危機を視野に入れているといっても、その自己同一性の概念すら今は他者のそれと、あの「入れ子」になっているという実感によってのり超えられてしまっている。それはどう解釈しても世阿彌の演劇論に帰結するのであり、それ以上でも以下でもない。結局、「野望と夏草」もそうであったが、その底に流れるのは「時間」である。義満が逝き、その子義嗣が追われ義持の世が義教に変わるまで世阿彌は生きた。義教に疎んじられ、自らの芸に殉じると覚悟したとき、息子達を始め皆側を離れていった。権力者は滅びやがて自分もこの世から去る。時にあらがうことは出来ないが、せめて自分は一巻の書物を残して行けることに満足していると述懐する世阿彌。日本的な時間意識、ある種の諦念といった叙情を西欧的な教養を背景に書ける作家としても、山崎正和は希有な存在だと言える。
三津五郎はずいぶんエンジンの掛かりが遅かったが、鼓を打つあたりから次第に魂が入ってきて、終盤は一人で舞台を切り盛りしているようだった。新劇の俳優たちの中にあって歌舞伎役者らしい所作も違和感がなく、かえって好もしかった。ただし、この難しい役どころを捕まえきっていたとは言い難く、演出との更なる議論が必要と見た。代表作にしてもらいたいとも思うが、何とももどかしい。
目立ってよかったのは、大江望房卿役の山崎清介であった。自ら演出も手がけるシェークスピア大好き俳優?がなよなよしながら一癖ありそうな公家のある種の典型を造形して柄の大きさとうまさを見せてくれた。僕の印象では、これがあの山崎清介かと驚いてしまったほどである。
宮本裕子もまた存在感のある俳優だと思った。目に力がある。小柄なのは少し損かもしれないが、広い役どころをこなせそうで、これからが期待される。
寺島しのぶは、最初にも書いたがあまり元気がなかった。宮本裕子とは対称的にやや大柄な身体を持て余している印象があって、この人にはいつも感じることだが、決断力、この役はこのように演じるという決断力、没入しながら醒めているという態度が欲しいところである。そうすれば全身がひとつにまとまって見えるはずだ。
僕は、この芝居を最前列で見ていた。終幕近く、一人は死を覚悟して砦へ加勢に向かう、一人は新たな芸を探しに民衆の中に向かう、二人の息子たちに「行くな!」と手を差し伸べ、呼び止める世阿彌元清=坂東三津五郎の頬に涙があふれ出ているのを見た。あの場面ではきっといつも泣きながら一方で醒めて演じる自分を見ているのだろう。
(12/19/03)
