
新国立劇場
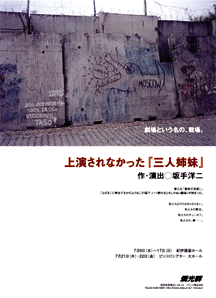
|
題名: |
上演されなかった三人姉妹 |
|
観劇日: |
{day}2005年7月12日 |
|
劇場: |
{ theatre}紀伊国屋ホール |
|
主催: |
燐光群 |
|
期間: |
{term}2005年7月6日〜17日 |
|
作: |
{auther}坂手洋二 |
|
演出: |
{director}坂手洋二 |
|
美術: |
じょん万次郎 |
|
照明: |
竹林功 |
|
衣装: |
{dress}宮本宣子 |
|
音楽・音響: |
{music}島猛 |
|
出演者: |
中山マリ 立石凉子 神野三鈴 鴨川てんし 猪熊恒和 久保島隆 大西孝洋 杉山英之 江口敦子 下総源太朗 JOHN OGLEVEE川中健次郎宇賀神範子 裴優宇 向井孝成 樋尾麻衣子 宇賀神範子 内海常葉 工藤清美 阿諏訪麻子 安仁屋美峰 市川実令 尾形聡子 坂田恵 椙本貴子 塚田弥与以 中川稔朗 樋口史 樋口美恵 松山美雪 |
「上演されなかった『三人姉妹』」
紀伊国屋ホールの客席半分を舞台に見立てて、テロリストに占拠された劇場という空間を作り出した。その分、切符は売れなくなるが、そういう設定ならば致し方あるまい。何とも贅沢なことをしたものだ。おかげで、開幕と同時に銃をうちながら入ってきた連中にこちらも人質に取られたような気になった。効果は絶大だったというべきだろう。
いうまでもなく数年前に起きたモスクワでの事件を下敷きにしたものである。チェチェン共和国の独立を巡ってプーチンが独立派を弾圧したために、二十万人もの同胞が殺されたと抗議して、100人ものゲリラが劇場の観客を人質に立てこもった事件である。結果は、記憶に残っていると思うが、何日か膠着状態の後、プーチンが突撃を命じたために観客に多数の死者が出て、ゲリラも一人残らず殺されてしまった。降参したらしい若い男女にもご丁寧に頭に一発づつ撃たれたあとがあったというから、恨み骨髄だったのかあとに続くものへの警告だったのか、観客が死のうが誰が死のうが知ったことではないという、やることはどうにも凄まじいものであった。チェチェンで何が起きているかよくわからなかったが、あの辺りはボスニアもそうだったように民族と宗教の対立、それに石油の利権が絡んで複雑な利害関係になっているようだ。日本人が理解しようとしても、テレビのコメンテーターのようにとかく耳触りのいいヒューマニズムやら民主主義を唱えることになりそうだが、それですむなら話は簡単だ。胸が痛むけれどとりあえず訳が分からんというしかあるまい。
この事件の後、劇場関係者として山崎正和が黙っていられないという面持ちで発言していたが、梅竿忠夫が書いた『文明の生態史観』を援用してロシアという国は何百年も「帝国」のままではないかと嘆いていた。このことはあとでまた書くことにして、いまは坂手洋二である。
こっちは何ともおっとりしたもので、その夜上演されるはずだった「上演されなかった『三人姉妹』」はもちろん中止される。はずであった。銃で武装した集団がやってきて観客を人質に立てこもったのだから、芝居どころの話ではないだろう。僕のようなリアリストは、まず何百人入っている観客かわからないが、この人数を仕切るのはロシアの事件が示す通り、数十人いたって間に合うものではないと思ってしまう。そこに役者というなんとも厄介な人種(普通じゃないという意味で)を抱えたら、一部屋に押し込めておくのがせいぜいではないか?
この連中は、どうやら戦争をしている自分の国から軍隊を引き揚げろとこの劇場のある国の政府に要求しているらしい。イラクに入っているアメリカの同盟国つまりは日本もそうだが、そういう背景を想像させるものだ。要求が通らなければ観客を皆殺しにして自分たちも死ぬといっている。しかしまあ、何という大ざっぱな要求ではないか。軍隊を引き揚げたら問題は解決するのか?それとも自爆テロのつもりなのか?どういうそろばん勘定でこういう暴挙に及んだのか、よくわからない。プーチンのような人間なら少し迷ったような顔をして「どうぞ、観客を殺して、あなた方もさっさと自爆してくれ。」といいかねない。
坂手が書いたようなテロリストのイメージなら、イラクの戦争報道で耳にタコが出来るほど聞いていたから、『君もテレビ見てたね』という程度のもので、このわけのわからんテロリストの正体をもう少し書き込むべきだった。これをコロンビアにいたときに考えたといっているようだが、南米だろうが中東だろうが、だって、命がけでやってきたはずなのにのんきに芝居に付き合うという神経はやっぱりヘンである。どっかの大学でシェイクスピアを読んだとか、カール・マルクスの唯物論は得意だとか、フッサールを研究したとか、あるいはポケットに毛沢東語録英訳本を忍ばせているとかというなら、チェーホフが何者であるか知らないはずはない。興味はあるだろう。しかし、そういう連中だったとしてもねえ。
つまり「上演されなかった『三人姉妹』」は、この緊迫した状況の中でほとんど「なし崩し」に上演されてしまうのである。これがまあ、第1の蹉跌である。
蹉跌だといっているのは、いくら劇でもそんなはずはないだろうという意味である。
占拠されてまもなく怒号が収まると、どこからともなく女が現れて何やらぶつぶついっている。ちょっと気掛かりなことがあって(何しろこの芝居を観た頃はずいぶん忙しかった)他に考え事をしていたが、どうやら「三人姉妹」のせりふを言っていると気がついた。
えっ!やるの。と思って見ていると、オーリガ(中山マリ)が舞台奥を歩いている。そしてイリーナ(神野三鈴)がぞろりと長いドレスで登場すると、そこがテロリストに占拠された劇場であることを忘れてしまいそうだ。むろんマーシャ(立石涼子)だって出てこないはずはない。
テロリストがごちゃごちゃいってくるが、私たちは役者で、今日上演するはずだった芝居の稽古を休むわけにいかないなどと抗弁して、舞台は続くのである。
僕は、まあ女三人だから、心優しいテロリストも稽古くらい許してやろうと考えたのだろうと思った。ところが、あろうことかマーシャの夫のクルイギン(鴨川てんし)、兄貴のアンドレイ(猪熊恒和)、マーシャとただならぬ仲になるベルシーニン(大西孝洋)、イリーナを巡って決闘することになるソリョウヌイ(下総源太郎)とトーゼンパフ(John Oglevee)も登場して、いよいよ本格的な「三人姉妹」になるではないか。これだけの騒ぎ?になるとテロリストも黙ってはいられないとばかり間に割って入ろうとするが、これがなかなかうまく仕掛けられていて、邪魔立てはすっかり芝居の中に吸収されるという妙な(このあたりの運びはなかなか見せてくれる)展開になる。さすがにあの延々と続く哲学談義のようなものは省いてあったからよかったが、のんきにサロン風の芝居を見せられでもしたら、いったいテロリストは何しに来たのかいよいよ首をかしげるところだった。
イリーナ(神野三鈴は燐光群で始めて見たが、適役を得たと思う。よかった。)が舞台前面にきて、例の最後の長ぜりふをはいて、姉妹三人が身を寄せあうところで芝居は終わる。都合のいいことにここでどうやら堪忍袋の緒が切れたとばかりに政府軍だか警察だかが突撃してくる。テロリストたちはそっちに(舞台裏)対応するためにいなくなり、何だかあっけなく舞台上はからっぽ、暗転の中銃声が響きわたる。
どうも全員殺されたということらしいが、それについてはなんの感慨も沸かない幕切れだった。動機がよくわからないものに同情の仕様がない。これが第二の最大の蹉跌というか、謎である。
いったい、坂手洋二は何を書こうとしたのか?
劇場占拠という実際にあった事件に触発されたことは間違いないだろう。しかし、そこで上演される芝居が、なぜ、チェーホフで、しかも「三人姉妹」でなければならなかったのか?
あの事件はモスクワで起きた。この芝居の場所について坂手はいっさい書いていないが、コロンビア滞在中にこれを考えたといって、関連性をはぐらかすような言い方をしている。コロンビアは、反政府ゲリラが麻薬を軍資金にして勢いを持つ政情不安定の国である。同じような事件があったとしてもおかしくはない。コロンビアの反政府ゲリラなら、芝居の稽古くらい多目に見てくれるに違いない、なぜなら、彼らは素朴なカソリックだから、と考えたのだろうか。
一方、「三人姉妹」についてもなぜこれを選んだのかよくわからない。チェーホフ没後100年のブームに乗ったわけでもあるまい。
一つだけ意識したのかと思われることは「三人姉妹」の家族の思考のベクトルがモスクワを向いているということだが、それとてもこのような芝居を書く動因になったと言い切る自信はない。
なんとも評価の仕様がない芝居だった。
何だか仕事が立て込んでいたので、後から見ることになった印刷物にはこう書いてあった。
「劇場という名の、戦場。
新たな「戦争の世紀」。
「はざま」に寄生するかのようなこの国で、いつ終わるともしれぬ<籠城>が始まった。私たちは守らなきゃならない。
私たちの舞台。
私たちのチェーホフ。
私たちの、夢ノノ。」
一行目はゲリラが劇場を占拠したのだから、その通りである。二行目は「戦争の世紀」と言われた二十世紀が終わったと思ったら、「9.11」以降、一つの国とはくくれないものとの争いが新たに生まれたという意味だろう。これはアラブ人のアタに出し抜かれたと怒りに震えるカウボーイ、ブッシュが定義づけた。戦争の実態は、アメリカがアフガンを攻め、次いでイラクを攻める国家間の戦争のようになった。とはいえ、この両国が近代国民国家などというしろものではなかったために、終わりようのない戦争になったのは事実である。新たな形態の戦争の世紀が始まったというなんともくらい予感が生まれたのは否定できない。
「私たちは守らなきゃならない。」以下は、まあ芸術一般をいっていると解釈してもいい。
問題は、「はざまに寄生するかのようなこの国で・・・・」という一行である。「寄生するかのような」とはどの国か?三つしか考えられない。ゲリラの母国か、劇場のある国か、坂手が「この国」と呼べる日本のことか、である。前の二つなら、「寄生」の具合を説明しないのでは、そもそも劇自体が成り立たない。では、それは我が国、日本のことだったのか?どうもそういう解釈が最も自然のような気がする。すると、日本は世界に寄生していて、どこで戦争が起きようが、ゲリラに襲われようがじっとろう城するかのように身を潜めていなければならない、という覚悟を語っているのだろうか?いや、そういったのでは消極的すぎる。何があっても芝居、芸術は守り抜くべきもの、たとえ世界に寄生するといわれようともそれが我が国の役割だ、ということになるのか。何だか芸術至上主義みたいだね。
詮索しても仕様がないが、とりあえず僕たちは異常なプレッシャーの中で上演される「三人姉妹」を目の前にしたのであった。
しかし、「はざまに寄生する」という言い方には坂手の現代日本およびそれを取り巻く世界の解釈がかなり色濃く反映されていると思う。
つまり、はざまというのは憲法9条が存在するために世界で紛争があっても武力でこれに介入することは出来ない、したがって、世界平和の一翼を担っている実感を持てないということなのだろう。たとえ国連が決議してもPKFには参加できないのである。この世代の人間たちには世界に貢献できなくて、つまり「金は出しても汗はかかない」という批判(誰がそれを責めているのかさっぱり見えないが。)に応えられないことが、恥のように思っているものが多い。坂手も多分そのひとりなのだろう。
こういう考え方の土台には世界は均質であるという、見えにくいが確実なテーゼが存在する。この迷信は、西洋の考え方の基本をなしているところで、日本人も近代化と称して懸命にこれを取り入れたのだから今や堅固な思想的根拠となっている。わかりやすくいえば、マルクスの唯物史観は時間が一方向に流れていくことを前提に社会の発展段階を区分して最終的には共産社会という理想に到達する。それが歴史的必然だといった。いまでもそれを信じているものは少なくないが、こういう考え方に従うと、どんな社会もそれぞれ発展段階は違うが、同じような時代を経験し、結果としては同じ歴史をたどっていることになる。
これが大きな誤解のもとなのだ。最初に書いた山崎正和の「ロシアは帝国のままだ」と嘆いたのはそのことに関係する。何百人も入っている劇場に100人以上の武装したゲリラが入ったら、そのことですでに何人か犠牲者が出るにきまっているが、そういう想像力が働かない。人権という言葉の根拠をたどればフランス革命に至るが、チェチェン人やロシア人にジャン・ジャック・ルソーはおそらく歴史上まだ登場していないのだ。こういうやり方は日本でいえば江戸時代の百姓一揆とそれを弾圧する悪徳領主のようなものである。
山崎正和は、ロシア(とその周辺地域)がまだ江戸時代いや室町時代をやっているといいたいのである。
この「文明の生態史観」という観点に立てば、日本の歴史がいかにごく自然に発展してきたか、つまり生態学でいうオートジェニックサクセション(自成的遷移)を行ってきた歴史だったかを認めることが出来る。偶然、西ヨーロッパも同じような発展をした。一方ユーラシア大陸の中央では帝国の興亡が何度も繰り返された。それは生態学にたとえれば、アロジェニックサクセション(他成的遷移)ということになる。
このようなパースペクティブをおいて考えるとまず、世界は均質ではない。その上で日本は特殊であると認めるべきだ。
僕らは、世界の「はざま」にはいない。まして世界に寄生してはいない。日本が特殊であることにいくぶんかの恥じらいを見せてもいいが、はざまに寄生しているなどという認識は改めるべきだ。ばかな政治家の口車に乗って「大義」もないことに命を懸けるのは愚の骨頂である。
こういう時代だから、テロに屈せず芝居を続けるぞ!と叫ぶのもいいが、ここまでリアリティがなければ、「単なる芸術的夢想」としてひとまず倉庫に預けておいたらどうだ。
(2005年9月29日)
Since Jan. 2003